栚丂師
堦丂晄摦摪偺椺嵳
擇丂幁搰恄幮偺椺嵳
嶰丂峅朄條偺椺嵳
巐丂瀽揤曭擺嵳
屲丂愺崄擖忛愓偲愺崄擖偲偄偆抧柤
榋丂栻巘摪偲偦偺廃曈
幍丂愇媨丒愇憸暔偺懚嵼
敧丂愺崄擖晹棊偺晽廗
嬨丂愺崄擖敧栘愡曐懚夛偺曕傒
廫丂偦偺懠奺庬揱彸榖
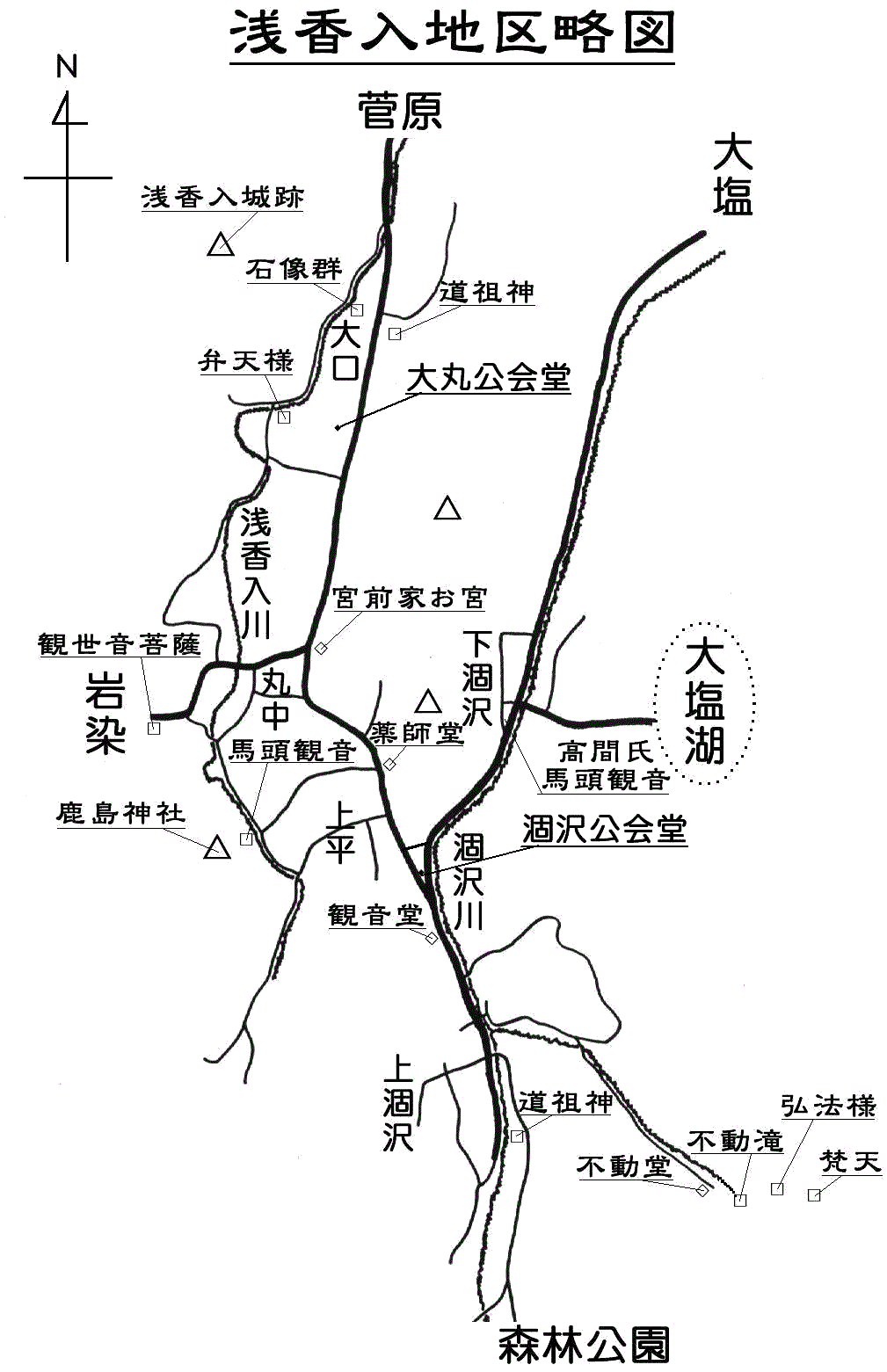 |
愺崄擖偺楌巎偲揱彸
曇幰丂釼摗挬抝丂丂丂丂丂 彉
彉
丂愺崄擖抧嬫偵偍偗傞丄楌巎傗暥壔側偳偵偮偄偰丄夁嫀偵偳偺傛偆側宱夁偑偁傝丄尰嵼偵帄偭偰偄傞偺偐尒媶傔側偑傜丄昅傪恑傔偰傒偨偄偲巚偄傑偡丅
丂嵟弶偵丄妟晹抧堟慡懱偺堚愓側偳偵偮偄偰峫偊偰傒傑偡偲丒丒丒
丂崱偐傜栺巐乑乑乑擭慜崰偺堚愓丄偡側傢偪乽撽暥帪戙乿拞婜偐傜乽栱惗帪戙乿乽屆暛帪戙乿傑偱偺堚愓偑丄敪孈挷嵏偵傛傝敾柧偟偰偄傑偡丅摿偵丄嶁幵偺搶媢椝抧偺娤壒嶳堚愓偼丄愴崙帪戙傑偱偺孈傝妱傝側偳偺嵀愓偑丄崙偺廳梫暥壔嵿偺巜掕傪庴偗偰偄傑偡丅傑偨丄栰忋抧嬫偺搶媢椝抧偵傕丄搚抧夵椙帠嬈偺愜丄乽栱惗帪戙乿偺廤抍惗妶偺愓抧偑敪尒偝傟傑偟偨丅偙傟偼嶍屗丒惣暯堚愓偲偟偰巎愓偵巆傞偲巚偄傑偡丅摉帪棙梡偝傟偨愇婍傗搚婍傕懡悢敪尒偝傟偰偄傑偡丅偦偺懠乽杒嶳拑塒嶳屆暛乿傗乽杒嶳拑塒嶳惣屆暛乿側偳偼丄屆暛帪戙弶婜偺庱挿偺暛曟偲偟偰憿塩偝傟偨丄幚偵婱廳側暥壔堚嶻偱偼側偄偱偟傚偆偐丅
丂偙偺條偵丄妟晹偺庡側媢椝抧偐傜偼丄條乆側堚愓偑敪尒偝傟偰偄傑偡丅摉帪偺恖乆偑丄尩偟偄帺慠娐嫬偺拞偱廤抍惗妶傪塩傓偵偼丄戝曄側嬯楯偑偁偭偨偲巚偄傑偡丅奜揋偐傜恎傪庣傝側偑傜偺乽怘椘偺妉摼乿乽暔帒偺挷払乿乽幮夛揑暥壔揑妶摦乿側偳丄廤棊偺庡傪拞怱偵嵳婭側偳偱寢懇傪寁傝丄惗妶埨掕偺偨傔偺嫟摨嶌嬈傪峴偭偰丄惉傝棫偭偰偄偨偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅
丂偙偙偱嶲峫傑偱偵丄摉帪偺恖乆偺庻柦偵偮偄偰愢柧偟偰偍偒傑偡丅
丂乽撽暥帪戙乿偼恖惗巐乑擭偲尵傢傟丄擔杮慡崙偱偺恖岥偼屲乑枩恖偲尵偄傑偡丅乽栱惗帪戙乿偼恖惗巐屲擭偱丄恖岥偼擇乑乑枩乣嶰乑乑枩恖偲丄媫寖側憹壛偑偁偭偨偲尵傢傟偰偄傑偡丅偙偺恖岥憹壛偺尨場偵偮偄偰偼丄乽栱惗帪戙乿偵帄偭偰暷傗敒側偳偺嶌暔偺嵧攟偑壜擻偲側傝惗妶偑埨掕偟偨偙偲偲丄奜崙偐傜偺廤抍堏廧側偳偵傛傞丄偲屆暥彂偵婰偝傟偰偄傑偡丅乽愴崙帪戙乿偼恖惗屲乑擭偲尵傢傟偰偄傑偡丅偙偺帪戙偺擔杮慡崙偺恖岥偼傛偔傢偐傝傑偣傫偑丄峕屗帪戙偺峕屗乮尰搶嫗乯偺恖岥偼堦乑乑枩恖偲暥專偵婰偝傟偰偄傑偡丅
丂慜抲偒偑挿偔側傝傑偟偨丅愺崄擖抧嬫偺暥壔堚嶻偵偮偄偰偼丄屻掱徻偟偔徯夘抳偟傑偡偑丄峕屗帪戙拞婜乮堦幍乑乑擭戙乯崰偐傜偺乽愇暓乿傗乽愇憸暔乿乽愇旇乿側偳丄懡偔偺婩婅曭婅偑偁傞偺偱丄偙偺揰偵偮偄偰怗傟偰傒偨偄偲巚偄傑偡丅
 丂揤柧嶰擭乮堦幍敧嶰擭乯偵愺娫嶳偺戝暚壩偑偁傝丄擾嶌暔偺戝嫢嶌偺偨傔偵暷壙偼崅摣偟丄暷憅偺懪偪夡偟傗暔昳偺棯扗側偳偺悽憡晄埨丄嵭奞偵傛傞塽昦偺敪惗側偳丄廧柉惗妶偼戝曄側崲擄偵捈柺偟傑偟偨丅偙偺婋婡埲屻丄暓嫵偺晍嫵偑惙傫偵側偭偨偲峫偊傜傟傑偡丅偲偄偆偺偼丄愺崄擖抧嬫偺愇媨丄愇憸摍偼丄偦偺杦偳偑姲惌擭娫乮堦幍敧嬨擭乯傛傝嫕榓擭娫乮堦敧乑堦擭乯偵偐偗偰寶棫傪尒偰偄傞偐傜偱偡丅
丂揤柧嶰擭乮堦幍敧嶰擭乯偵愺娫嶳偺戝暚壩偑偁傝丄擾嶌暔偺戝嫢嶌偺偨傔偵暷壙偼崅摣偟丄暷憅偺懪偪夡偟傗暔昳偺棯扗側偳偺悽憡晄埨丄嵭奞偵傛傞塽昦偺敪惗側偳丄廧柉惗妶偼戝曄側崲擄偵捈柺偟傑偟偨丅偙偺婋婡埲屻丄暓嫵偺晍嫵偑惙傫偵側偭偨偲峫偊傜傟傑偡丅偲偄偆偺偼丄愺崄擖抧嬫偺愇媨丄愇憸摍偼丄偦偺杦偳偑姲惌擭娫乮堦幍敧嬨擭乯傛傝嫕榓擭娫乮堦敧乑堦擭乯偵偐偗偰寶棫傪尒偰偄傞偐傜偱偡丅
丂偙偺搙丄埲忋偺娤揰偐傜丄偝偐偺傏傞偙偲擇屲乑擭偵媦傇奺庬嵜帠傗揱婰側偳丄楌巎揑偵壙抣偁傞暥壔堚嶻傪丄愺崄擖抧嬫偺奆條偵棟夝偲嫤椡傪捀偒丄傑偲傔傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅
丂側偍丄暥專偑朢偟偔丄撪梕摍偵偮偄偰惓妋偵攃埇偱偒偢偵丄庡娤傗巹尒偱幏昅偟偨晹暘傕懡乆偛偞偄傑偡偑丄偛梕幫偄偨偩偒丄偙偺帒椏傪奆條偺嶲峫彂偲偟偰丄暥壔偺摂傪徚偝偸條丄愗偵婅偆師戞偱偡丅
乮拲乯崱夞幏昅偵摉偨傝丄愇憸暔偺恖柤傗暥帤偺帺慠晽壔乮徚偊傞乯尰徾偑偁傞偨傔丄堚嶻偲偟偰偺曐懚栚揑偺堊偵柫婰偝偣偰捀偒傑偟偨丅
丂嵟屻偵丄幏昅偺嫤椡幰偱偍悽榖偵側偭偨壓婰偺曽乆偵丄怱偐傜岤偔偍楃怽偟忋偘傑偡丅
嵵摗埳惃梇丂崅娫恀懢榊丂崅嫶廏晇丂嵵摗拤梇丂嵵摗柧怣偺彅巵
暯惉嬨擭嬨寧媑擔丂丂丂丂幏昅幰丂釼摗挬抝
栚丂師 堦丂晄摦摪偺椺嵳 擇丂幁搰恄幮偺椺嵳 嶰丂峅朄條偺椺嵳 巐丂瀽揤曭擺嵳 屲丂愺崄擖忛愓偲愺崄擖偲偄偆抧柤 榋丂栻巘摪偲偦偺廃曈 幍丂愇媨丒愇憸暔偺懚嵼 敧丂愺崄擖晹棊偺晽廗 嬨丂愺崄擖敧栘愡曐懚夛偺曕傒 廫丂偦偺懠奺庬揱彸榖 |
|
堦丂晄摦摪偺椺嵳
 丂熆戲晹棊偺撿搶栺屲乑乑倣丄戧戲扟捗偺墱偵晄摦摪偑偁傝傑偡丅偙偺偍摪偼棤嶳偺帺慠娾嶳偵書偐傟丄慜曽偵偼崅偝擇乑倣偺偍戧傕偁傞偲偄偆岲忦審偺応強偵偁傝傑偡丅晄摦摪椬抧偵嫕榓尦撗擭乮堦敧乑堦擭乯堦擇寧媑擔偲柫婰偺乽姦擮樑嫙梡搩乿偑偁傝丄怣嬄幰偑擬怱偵擮暓傪彞偊側偑傜嶲偭偨傕偺偲巚傢傟傑偡丅偙偺晄摦摪偺嵳楃偼枅擭惓寧擇廫敧擔偲寛傑偭偰偄傑偡丅偙偺釱偺楌巎偼掕偐偱偁傝傑偣傫偑丄晄摦摪庤慜堦屲倣抧揰偵丄擇乑乑擭埲忋宱偨屼恄栘偺戝悪偑擇杮偁傝丄戝懱偺擭悢偼暘偐傞偺偱偼側偄偐偲峫偊傜傟傑偡丅釱偺拞偺晄摦柧墹杮懱偼寴幙偵傛傞愇宆偑堦懱乮崅偝榋乑噋乯丄偦偺懠栘宆偑擇懱丄崌寁嶰懱偑廂傔傜傟偰偄傑偡丅
丂熆戲晹棊偺撿搶栺屲乑乑倣丄戧戲扟捗偺墱偵晄摦摪偑偁傝傑偡丅偙偺偍摪偼棤嶳偺帺慠娾嶳偵書偐傟丄慜曽偵偼崅偝擇乑倣偺偍戧傕偁傞偲偄偆岲忦審偺応強偵偁傝傑偡丅晄摦摪椬抧偵嫕榓尦撗擭乮堦敧乑堦擭乯堦擇寧媑擔偲柫婰偺乽姦擮樑嫙梡搩乿偑偁傝丄怣嬄幰偑擬怱偵擮暓傪彞偊側偑傜嶲偭偨傕偺偲巚傢傟傑偡丅偙偺晄摦摪偺嵳楃偼枅擭惓寧擇廫敧擔偲寛傑偭偰偄傑偡丅偙偺釱偺楌巎偼掕偐偱偁傝傑偣傫偑丄晄摦摪庤慜堦屲倣抧揰偵丄擇乑乑擭埲忋宱偨屼恄栘偺戝悪偑擇杮偁傝丄戝懱偺擭悢偼暘偐傞偺偱偼側偄偐偲峫偊傜傟傑偡丅釱偺拞偺晄摦柧墹杮懱偼寴幙偵傛傞愇宆偑堦懱乮崅偝榋乑噋乯丄偦偺懠栘宆偑擇懱丄崌寁嶰懱偑廂傔傜傟偰偄傑偡丅
丂偄偭偨偄晄摦柧墹偲偼壗傪堄枴偟偰偄傞偺偱偟傚偆偐丅暓偑屽傝傪奐偄偨帪丄埆杺傪崀暁偝偣偨偲尵偄傑偡丅柧墹杮懱偼乽擮搟憡乿偱塃庤偵崀杺偺棙寱傪埇傝丄嵍庤偵乽埆媡柍摴乿傪曔敍偡傞峧傪帩偪丄壩墜傪攚晧偄恖傪埿埑偟丄暓朄偵摫偔巔偱乽墔揋戅嶶乿乽抧堟捔岇乿丄摿偵屄恖偺庣岇偲偟偰偺怣嬄傪堦怱偵庴偗偰偒偨偲暦偄偰偄傑偡丅丂晄摦條偺屼嶥偼乽壩嵭彍乿乽壠撪埨慡乿乽岎捠埨慡乿側偳偑偁傝傑偡丅愄偼丄擾嬈廂擖偺拞偱嵟傕崅偐偭偨乽梴嶾乿偺屼嶥傕偁偭偨偲暦偒傑偡丅
丂尰嵼偱傕丄愺崄擖慡抧堟偺庣岇恄偲偟偰釰傜傟丄揱摑揑峴帠偲偟偰庴偗宲偑傟偰偄傑偡丅
丂側偤嵳擔偺曄峏偑側偔丄枅擭堦寧擇廫敧擔側偺偐丄暥專傕側偔晄柧偱偡偑丄廔偄惓寧偺嵟屻偵抧堟偺堦擭娫偺嵭奞彍偲朙嶌婩婅偑娷傑傟偰偄傞傕偺偲巚傢傟傑偡丅
丂
 仢瀽忇偵偮偄偰乮瀽忇偵偼婅庡柤偲婑婅擭寧偑婰偝傟偰偄傑偡丅乯
仢瀽忇偵偮偄偰乮瀽忇偵偼婅庡柤偲婑婅擭寧偑婰偝傟偰偄傑偡丅乯
丂
忋栰偺崙娒妝孲屻働懞丂棿戲晄摦摪摪庡丂嶳丂嵟屻偵丄嵳楃偵捈愙嶲壛偡傞曽払傪徯夘偟傑偟傚偆丅
仢嵳傝悽榖恖
丒愄偼奺晹棊偛偲偵擇柤偺栶堳傪慖弌丄戙昞悽榖恖傪屳丂丂慖偟塣塩偵摉偨傝傑偟偨丅尰嵼偼嬫挿偝傫傪拞怱偵丄奺慻挿偝傫偑悽榖恖偲側傝傑偡丅
仢媨斣惂搙
丒枅擭廃傝斣偱丄巐柤偺恖払偑嵳擔偺摉斣偵偁偨傝傑偡丅
擇丂幁搰恄幮偺椺嵳
 丂幁搰恄幮偺幮釱偼丄愺崄擖抧堟偑堦朷偱偒傞撿惣晹偺彫崅偄嶳乮幁搰嶳乯偺捀忋偵捔嵗偟丄忢偵抧堟慡廧柉傪捔庣偟偰偄傞偐偺傛偆偱偡丅幁搰恄幮偺曭幮楌偼掕偐偱偁傝傑偣傫偑丄恄慜偵偁傞摂饽偵偼師偺條偵柫婰偝傟偰偄傑偡丅
丂幁搰恄幮偺幮釱偼丄愺崄擖抧堟偑堦朷偱偒傞撿惣晹偺彫崅偄嶳乮幁搰嶳乯偺捀忋偵捔嵗偟丄忢偵抧堟慡廧柉傪捔庣偟偰偄傞偐偺傛偆偱偡丅幁搰恄幮偺曭幮楌偼掕偐偱偁傝傑偣傫偑丄恄慜偵偁傞摂饽偵偼師偺條偵柫婰偝傟偰偄傑偡丅
乽曭擺屼摪慜乿丂曮楌嬨枻櫱乮堦幍屲嬨擭乯廫寧媑擔
丂丂丂丂丂丂丂丂巤庡丂巐嬫拞
丂椺嵳偼枅擭巐寧廫屲擔偵寛傑偭偰偄傑偡丅嶲攓幰偼丄妟晹岞柉娰娰挿丄妟晹恄幮憤戙巐柤偺曽乆丄抧尦偺嬫挿偝傫偲慻挿丒奺庬抍懱戙昞幰側偳偱偡丅
丂幁搰恄幮偼丄愺崄擖抧嬫偺暥壔堚嶻偲偟偰偼屆偔丄彫敠斔庡怐揷怣塃偺帪戙丄晲巑偺弌恮傪婩婅偟偰偄偨偲偺愢傕偁傝傑偡丅
丂偐偮偰偺恄幮崌暪帪丄幁搰恄幮傕妟晹恄幮偵堦帪崌幮偟傑偡偑丄偦偺屻愺崄擖抧嬫撪偵偍偄偰塽昦偑敪惗偟丄摉帪偺嬫挿偝傫側偳偺寁傜偄偱丄杮壠婣傝偲側傝丄愄捠傝偺嵳幮條偲側傝傑偟偨丅尰嵼偺搊傝岥偺愇抜偼丄幮釱堏摦帪偵愺崄擖抧嬫慡堳偺楯椡曭巇偵傛傝丄愊傒廳偹偨偲暦偄偰偄傑偡丅偄偢傟偵偟偰傕丄幁搰恄幮偑愺崄擖抧嬫偺捔庣偺恄條偲偟偰釰傜傟丄廧柉偑偄偮傑偱傕埨怱偟偰惗妶偱偒傞條丄婅偭偰巭傒傑偣傫丅
丂側偍丄幁搰恄幮偺幮楌偼丄愺崄擖抧嬫偲偟偰堦斣屆偔丄懠偺愇憸暔傗晄摦摪傛傝傕巐廫擭埵慜偵寶棫偝傟偨傛偆偱偡丅
丂
嶰丂峅朄條偺椺嵳
 丂晄摦摪慜偺戧忋偐傜旜崻偮偨偄偵嶰乑倣掱搊傝暯抧偵払偡傞傑偱偺丄媫嶁偺奺僐乕僫枅丄戜愇擇屄偺忋偵丄傢傜偠偲峅朄條偺愇憸偑嬨屄抲偐傟丄暯抧偵偼戜愇偵屄恖柤丒抍懱柤側偳婰偝傟丄摨偠偔峅朄條偺愇憸偑墶偵攝楍傛偔暲傫偱偄傑偡丅
丂晄摦摪慜偺戧忋偐傜旜崻偮偨偄偵嶰乑倣掱搊傝暯抧偵払偡傞傑偱偺丄媫嶁偺奺僐乕僫枅丄戜愇擇屄偺忋偵丄傢傜偠偲峅朄條偺愇憸偑嬨屄抲偐傟丄暯抧偵偼戜愇偵屄恖柤丒抍懱柤側偳婰偝傟丄摨偠偔峅朄條偺愇憸偑墶偵攝楍傛偔暲傫偱偄傑偡丅
丂媫嶁偺晹暘偵婑憽幰柤偑崗傫偱偁傝傑偡丅敾暿偺曽払偵偮偄偰戞堦斣偐傜婰柤偟偰偄偒傑偡偲丄
丂戞堦懞丂丂丂嵵摗惔懢榊
丂戞擇懞丂丂丂嵵摗棙憼
丂戞嶰懞丂丂丂媨慜嬥栱
丂戞巐懞楢柤丂壓嶳恟彆 壓嶳惔屲榊丂壓嶳暯暫塹
丂丂丂丂丂丂丂壓嶳暯嵅僄栧丂壓嶳尮幍
丂戞屲戝懞丂丂巵柤晄柧
丂戞榋彫敠丂丂崅嫶尃幍
丂戞幍懞丂丂丂媨慜暫擵彆
丂戞敧壀杮懞楢柤丂嶰揷婌戝晇丂嶰揷斏敧
丂戞嬨丂丂丂丂巵柤晄柧
丂師偵暯抧偺愇憸暔偺婑憽幰柤傪婰柤偟傑偡丅
楢柤偺曽乆傕偁傝傑偡偑丄塃懁傛傝弴師彂偄偰偄偒傑偡丅
丂懞丂丂丂崅娫敧暫塹丂崅娫敧擵彆丂崅娫敿擵彆丂栁栘敧廫彆丂尨揷徧嵍栧
丂丂丂丂丂尨揷摽帯榊丂尨揷栱屲榊
丂撪彔懞丂搾愺怴嵍栧
丂懞楢柤丂栁栘恟暫塹丂栁栘尮懢榊丂栁栘徏擵彆丂媨慜帯徏丂媨慜枓憼
丂戝懞丂丂尨揷巗屲榊丂尨揷掑嶰丂嵵摗乮晄柧乯
丂拞懞丂丂崅嫶愬帯
丂懞丂丂丂媨慜梌嵍僄栧
丂戝懞丂丂恵尨旻彆丂丂崙曱懞丂娭岥姩幍
丂懞丂丂丂栁栘側偐丂丂丂懞丂丂媨慜壝暯帯
丂懞偺抧柤偵偮偄偰丄峕屗帪戙偼屻働懞偲徧偟丄懞偲偟偰偼愺崄擖抧嬫撪偺恖払丄戝懞偲偼尰嵼偺撿屻売嬫乮愺崄擖傪彍偔乯偺恖払偲嶡偟傑偡丅懠抧嬫偺恖払偼崅悾偺撪彔丄娒妝挰偺彫敠丄崙曱丄側偳偱丄拞懞偲偁傞偺偼丄撿屻売嬫偺拞杒抧嬫偲峫偊傜傟傑偡丅
丂偙偺峅朄條偺椺嵳偼丄巐寧擇廫堦擔偲暦偒傑偡偑丄師偺條側揱愢偑偁傝傑偡丅嵳楃擔偵抋惗偺巕偳傕偼丄妛椡桪廏偱寬傗偐偵堢偮偲尵傢傟偰偄傑偡丅傑偨摉擔偼丄抧堟偺恖払偑婑傝崌偭偰峅朄條偵場傫偱嬪壧夛傪嵜偟丄栭娫偵偼愇憸暔偺愇忋偵摂柧傪棫偰丄妝偟傒側偑傜妛傫偩偲暦偒傑偡丅側偍丄堦偮偺愇媨偺戜愇偵偼丄姲惌廫滫擭廫堦寧媑擔乮堦幍嬨榋擭乯偺擔晅偑崗傒崬傑傟偰偄傑偡丅
 丂偱偼丄側偤偙偺抧偵峅朄條側偺偐丄屆榁傗怣嬄幰偐傜暦偄偨榖偵傛傞偲丄峅朄揱愢偼丄妛栤偲悈偲偵娭學偑怺偐偭偨傛偆偱偡丅
丂偱偼丄側偤偙偺抧偵峅朄條側偺偐丄屆榁傗怣嬄幰偐傜暦偄偨榖偵傛傞偲丄峅朄揱愢偼丄妛栤偲悈偲偵娭學偑怺偐偭偨傛偆偱偡丅
丂愄丄嬻奀乮峅朄戝巘乯偲偄偆偍朧偝傫偑丄斾塨嶳墑楋帥偵廋峴拞丄揤峜偵擣傔傜傟柦偵傛傝巟撨乮尰拞崙乯偱廫擭娫丄暥昅側偳傪妛傃丄婣崙屻擔杮奺抧傪弰夞偟側偑傜丄悈栤戣傗妛栤偵偮偄偰丄柉廜嫵壔偺偨傔擬怱偵峴媟偟偨偲偄偆偙偲偱丄愺崄擖偵傕悈傗妛栤偵娭偡傞峅朄揱愢偑堦偮偁傝傑偡丅
丂峅朄條偑愢朄偺搑拞丄熆戲抧撪偺偁傞壠偵棫偪婑偭偰悈岊偄傪偟偨偲偙傠丄乽帺暘偺壠偺堸傒悈偵傕帠寚偔偺偵丄懠恖條傪弫偡悈偼側偄丅乿偲抐傢傜傟偨偲尵偄傑偡丅峅朄條偼巇曽側偔丄嶳墇偊偺偨傔愺崄擖嶳偺曯忛壓偲偄偆偲偙傠偱媥傒丄熆戲曽柺傪怳傝曉傝側偑傜帩嶲偺忨偱戝抧傪堦撍偒偟偨偲偙傠丄悈偑桸偒弌偰岮傪弫偟丄棫偪嫀偭偨偲偄偆愢偑巆偭偰偄傑偡丅崱偱傕曯忛壓偺堦攖悈偲偟偰棙梡幰偑懡偔丄姶幱偝傟偰偄傑偡丅偙偺堦攖悈偺桸偒悈傗抧壓悈傪棙梡偟偰丄徍榓擇擭偵孮攏導嵟屆偺娙堈悈摴偑奐愝偝傟丄熆戲抧嬫傪拞怱偵拞暯抧嬫傑偱屲廫悢屗偺惗妶梡悈偲偟偰壎宐傪偆偗丄崱偱傕戝愗偵娗棟曐懚偝傟偰偄傑偡丅
丂偙偺條側峅朄揱愢偑偁傝傑偡丅峕屗帪戙拞婜崰偺愭廧柉偺曽乆偺怣嬄怱偺嫮偝偵丄崱峏側偑傜姶摦偡傞傕偺偱偡丅
丂 巐丂瀽揤曭擺嵳
巐丂瀽揤曭擺嵳
丂瀽揤忋擺応強偲偟偰丄晄摦摪慜偺戧忋偐傜峅朄條偺愇憸抧揰傪旜崻偮偨偄偵堦屲乑倣偺強偵丄愄偐傜屲杮徏偺屆栘偑偁傝丄曭擺栘偲偟偰棙梡偟偰偄傑偟偨丅嬤擭偼丄屲杮徏偺屚巰偺偨傔丄椬抧偺庽栘偵曄峏偲側偭偰偄傑偡丅
丂瀽揤曭擺嵳偼廫寧廫榋擔偲寛傔偰偄傑偟偨偑丄嬤擭偼廫榋擔慜屻偺擔梛擔偵峴偭偰偄傑偡丅
丂柧帯偺弶傔偙傠丄愺崄擖抧嬫偵娒妝挰嶚抧嬫傛傝恄妝晳傪摫擖偟丄廐偺嵳楃偵旛偊丄堦儢寧慜偐傜抧堟撪奺屗傪弰傝側偑傜惉壥傪斺業偟丄恊杛傪恾偭偨偲尵偄傑偡丅
丂戝惓帪戙偵堏偭偰偐傜偼丄敧栘愡傕摫擖偝傟丄恄妝晳偲嫟墘偟堦憌壴傪揧偊偨偲暦偒傑偡丅廫榋擔偺屵慜拞乽恄妝乿乽敧栘愡乿偺暔懙傪幚峴偟丄屵屻晳戜偺屻曅晅偗偲瀽揤曭擺慻偲偵暿傟丄嶌嬈傪幚巤偟偨偲暦偄偰偄傑偡丅
丂瀽揤曭擺嵳偺偄傢傟傗丄栚揑偵偮偄偰丄屆暥彂傗暥專傕側偔晄柧偱偡偑丄愭戙偐傜暦偄偨偲偙傠偱偼丄乽瀽揤墹乿乮暓嫵偺庣岇恄偱懎奅傪棧傟偨惔忩偺悽奅傪巌傞乯傊偺怣嬄偲乽埆昦彍偗乿偲乽屲崚朙忰乿偺婩婅偩偲偄偄傑偡丅
丂瀽揤憿傝偺庡側弨旛傪丄嶲峫傑偱偵婰偟傑偡丅挿偝堦屲倣偺抾娖堦杮丄巻堦愗挘丄屼暭懇巐廫杮埵丅抾娖偺愭抂偵敒傢傜傪懇偹庢傝晅偗丄懇偹偨屄強偵屼暭懇傪嵎偟崬傒廔椆丅偦偟偰尰抧偵塣傃庽栘偵捈棫偲偟偰峳撽偱寢懇乮悢屄強乯偡傞偺偑曭擺偱偡丅
丂曭擺抧晅嬤偐傜偼丄柇媊丒怸柤丒愒忛偺忋栄嶰嶳偑墦朷偱偒丄惤偵慺惏傜偟偄宨娤偱偡丅
丂傑偨丄埨拞巗傗柇媊挰曽柺偐傜傕曭擺嵳偺屼暭懇偑尒偊傞偲暦偒傑偡丅墦曽偵廧傫偱偄傞懞撪弌恎幰偼丄偙偺屘嫿偺峴帠傪夰偐偟偔挱傔側偑傜丄乽偄傛偄傛廐偺廂妌婫偲側傝朲偟偔側傞傫偩側偀乿偲尵偭偰偄偨偲暦偄偨偙偲偑偁傝傑偡丅
丂
丂屲丂愺崄擖忛愓偲愺崄擖偲偄偆抧柤
 丂妟晹恄幮偺幮釰偐傜撿曽岦偺旜崻偮偨偄偵搊傞偙偲屲乑乑倣傎偳丄戝岥廤棊惣曽偺昗崅嶰乑乑倣偺崅戜偵愺崄擖忛愓偑偁傝傑偟偨丅偙偺忛愓偼丄崱偐傜屲乑乑擭慜崰偺愴崙帪戙偺傕偺偱丄嵲偱偼側偄偐偲悇掕偝傟偰偄傑偡丅愴棯揑偵旕忢偵廳梫帇偝傟偨応強偱丄惣曽偵惣暯忛丄墫柤揷忛丄搶杒曽柺偵偼撪彔忛丄撿搶曽柺偵曱忛丄偦偟偰搶曽柺偵偼摉帪惣忋廈嵟崅偺尃椡傪帩偭偰偄偨崙曱忛偑偁傝丄愺崄擖忛偼嬤嵼偺忛偲忢偵楢學偺曐偰傞埵抲偵偁偭偨傢偗偱偡丅
丂妟晹恄幮偺幮釰偐傜撿曽岦偺旜崻偮偨偄偵搊傞偙偲屲乑乑倣傎偳丄戝岥廤棊惣曽偺昗崅嶰乑乑倣偺崅戜偵愺崄擖忛愓偑偁傝傑偟偨丅偙偺忛愓偼丄崱偐傜屲乑乑擭慜崰偺愴崙帪戙偺傕偺偱丄嵲偱偼側偄偐偲悇掕偝傟偰偄傑偡丅愴棯揑偵旕忢偵廳梫帇偝傟偨応強偱丄惣曽偵惣暯忛丄墫柤揷忛丄搶杒曽柺偵偼撪彔忛丄撿搶曽柺偵曱忛丄偦偟偰搶曽柺偵偼摉帪惣忋廈嵟崅偺尃椡傪帩偭偰偄偨崙曱忛偑偁傝丄愺崄擖忛偼嬤嵼偺忛偲忢偵楢學偺曐偰傞埵抲偵偁偭偨傢偗偱偡丅
丂偙偙偱崙曱忛偺惉棫偵偮偄偰婰弎偟偰偍偒偨偄偲巚偄傑偡丅楌巎帒椏偵傛傞偲丄彫敠堦懓偼姍憅帪戙慜婜乮堦擇敧乑擭乯崰偺崑懓偱丄弶戙偺娒妝孲巌偱偁偭偨偲尵偄傑偡丅偦偺屻崙曱忛庡偲側傝丄愴崙帪戙枛婜偵偼惣忋廈抧堟偺庱椞偲偟偰尃椡傪怳傞偄丄嵲傗弌忛傪娷傔榋廫梋廈傪庤拞偵廂傔偨偲尵偄傑偡丅屻偵崙曱忛庡乽彫敠旜挘庣寷廳乿偺拕抝偱乽忋憤夘怣恀乿帪戙偵偼峛斻偺崙晲揷怣尯岞偺捈宯丄晲揷擇廫桬巑偺堦晲彨偲偟偰妶桇偟偨偲偁傝傑偡丅
丂愺崄擖忛傕丄摉慠崙曱忛偺巟攝壓偵偁傝丄戙乆偵榡偭偰嵲偲偟偰栶妱傪壥偨偟偰偄偨偲巚偄傑偡丅
 丂偙偙偱愺崄擖偲偄偆抧柤偵偮偄偰峫偊偰傒偨偄偲巚偄傑偡偑丄側偤崙曱忛偵怗傟偨偐偲偄偄傑偡偲丄師偺條側娭學偑偁偭偨偲巚偆偐傜偱偡丅愴崙帪戙傕廔傢傝偵嬤偯偒丄峛斻偺晲揷堦懓偑柵傃丄悽偼怐揷怣挿丄朙恇廏媑帪戙丅偙偺楢崌孯偑惣忋廈偵恑峌偟丄崙曱忛傪嶰枩偺戝孯傪棪偄偰峌傔棊偲偟偨偲尵偄傑偡丅偙偺愜偵楢崌孯偺堦枩屲愮恖偑妟晹抧堟傪捠夁偟丄屻働懞偐傜戝墫傪宱偰崙曱懞偵峌傔擖傝丄巆傞堦枩屲愮恖偺楢崌孯偼揷幝曽柺偐傜慞宑帥傪宱偰崙曱偵峌傔擖偭偨偲偺揱愢偑偁傝傑偡丅
丂偙偙偱愺崄擖偲偄偆抧柤偵偮偄偰峫偊偰傒偨偄偲巚偄傑偡偑丄側偤崙曱忛偵怗傟偨偐偲偄偄傑偡偲丄師偺條側娭學偑偁偭偨偲巚偆偐傜偱偡丅愴崙帪戙傕廔傢傝偵嬤偯偒丄峛斻偺晲揷堦懓偑柵傃丄悽偼怐揷怣挿丄朙恇廏媑帪戙丅偙偺楢崌孯偑惣忋廈偵恑峌偟丄崙曱忛傪嶰枩偺戝孯傪棪偄偰峌傔棊偲偟偨偲尵偄傑偡丅偙偺愜偵楢崌孯偺堦枩屲愮恖偑妟晹抧堟傪捠夁偟丄屻働懞偐傜戝墫傪宱偰崙曱懞偵峌傔擖傝丄巆傞堦枩屲愮恖偺楢崌孯偼揷幝曽柺偐傜慞宑帥傪宱偰崙曱偵峌傔擖偭偨偲偺揱愢偑偁傝傑偡丅
丂摉帪偺愺崄擖忛庡乮愺崄抏惓庣乯偼愴嫷晄棙偲嶡抦偟慺憗偔撡憱傪峫偊丄熆戲廤棊傪宱偰廐敤懞偺撨恵抧嬫偵棊偪墑傃偨偲尵偄傑偡丅偙偺帪戝岥廤棊偐傜娵拞丒熆戲扟捗傪捠夁偟偨愺崄條偵場傫偱愺崄擖傪柦柤偟偨偲暦偒傑偡丅
丂懠偺揱愢偵傛傞偲丄愄丄暯壠偺棊恖偑摉抧偵廧傒丄愺崄惄傪柤忔偭偰偄傑偟偨偑丄帠忣偑偁偭偰傗偼傝廐敤偺撨恵偵廧嫃傪堏揮偟偨偲尵偄傑偡丅偦偺愜丄熆戲扟捗偵擖偭偨偲偺榖偱丄愺崄擖偲屇傇傛偆偵側偭偨偲偺抧柤愢傕偁傝傑偡丅
丂榋丂栻巘摪偲偦偺廃曈
 丂栻巘摪丄尰嵼偼熆戲晹棊偺忋偺暯抧撪偺摴楬増偄偵埨抲偝傟偰偄傑偡丅栻巘摪寶棫偼峕屗帪戙偲巚偄傑偡偑丄傛偔暘偐偭偰偄傑偣傫丅桼棃偵偮偄偰偼丄師偺傛偆側揱愢偁傝傑偡丅
丂栻巘摪丄尰嵼偼熆戲晹棊偺忋偺暯抧撪偺摴楬増偄偵埨抲偝傟偰偄傑偡丅栻巘摪寶棫偼峕屗帪戙偲巚偄傑偡偑丄傛偔暘偐偭偰偄傑偣傫丅桼棃偵偮偄偰偼丄師偺傛偆側揱愢偁傝傑偡丅
丂栻巘偲偼堛巘偲摨偠堄枴偱丄栻巘擛棃偺棯偱偁傝丄惗暔偺嵭栵昦婥傪媬偆暓偱偁傞偲偄偄傑偡丅偦偺懠丄栻巘條偵偼丄娽昦偺恖偑偍寃傝偡傞偲偄偄傑偡丅愄丄栚偺埆偄恖偑婅偐偗傪偟偨嵺丄擭楊偺悢偩偗乽傔乿偺庣傪偐偄偰偁偘偨傝丄婅傪壥偨偣傞傛偆偵徏偙偛傝傪擭楊偺悢偩偗巺偱偔偖偭偰偁偘偨偲尵偄傑偡丅偍摪偺拞偺扞忋偵丄栻巘擛棃憸乮嬧敁乯栘憸杮懱偑抲偐傟偰偄傑偡丅
丂搚娫偵偼丄愄搚憭梡偲偟偰巊梡偟偨嫽偑堦婎旛昳偲偟偰巆偟偰偁傝丄懠偵彫摴嬶偑屲揰掱偁傝傑偡偑丄尰嵼偼壩憭応偱恄楈偲側傞偨傔丄棙梡偝傟偰偄傑偣傫丅側偍丄栻巘摪惣懁摴楬増偄偵丄愇憸傗愇旇偑偁傝傑偡偑丄帺慠晽壔偑挊偟偄偺偱擭昞傗婑憽幰柤偑敾暿偟偵偔偔側偭偰偄傑偡丅岦偐偭偰塃懁偐傜弴師婰弎偟偰傒傑偡丅
仢峂怽搩丂
丂姲惌堦擇擭乮堦敧乑乑擭乯曭乮杮婅庡乯丂峂怽搩偲偼丄暓朄傪嫮偔偟丄寴偔庣傞擇怢偺恄丅
丂廫擇巟偺峂怽乮偐偺偊偝傞乯偺栭偵峴偆柉娫偺怣嬄偺堦偮丅偙傫側愢傕偁傝傑偡丅榋廫擔偵堦夞弰偭偰偔傞丄懱撪偵憙偔偆乽梸朷乿乽偝傫偟偺傓偟乿偑丄峂怽偺栭偵徃揤偡傞偲晄岾偵側傞偲怣偠傜傟偨帠偐傜丄恖乆偼拵偑弌傞偺傪朩偘傞偨傔揙栭偟偨偲偄偄傑偡丅抧尦偺奆條偺婑憽傜偟偄偱偡丅
仢娤壒條
丂
昞懁偼暥帤偼偁傝傑偣傫丅棤懁偵乽栧昳擇枩姫乿偲偁傝傑偡丅丂昞懁偐傜尒傞偲丄戝偒側戜愇偺忋偵僴僗偺壴柾條偑偁傝丄偦偺忋偵娤壒條偑埨抲偝傟偰偄傑偡丅偙偺條側戝偒側娤壒條偼怣廈崅墦偺愇岺偵傛傞嶌昳偲尵傢傟丄幚偵棫攈側嵶岺偲姶怱偟傑偡丅
丂側偍丄偙偺娤壒條偼丄抦宐丒桬婥丒帨斶偲嶰偮偺摽偺徾挜偱偁傝丄帺暘帺恎偺恀幚偺巔偲尵偄傑偡丅
丂崗擭帤側偟
仢擮樑嫙梡搩乮崗帤側偟乯
丂擮樑偲偼丄暓傪怣嬄偟偰暓柤乮撿柍垻栱懮暓乯傪彞偊傞偙偲偱丄堦怱偵擮樑傪彞偊偰嬌妝墲惗傪媮傔傛偆偲偡傞廆攈偺堄枴偁偄傜偟偄偱偡丅
仢曭擺幯鉙炓孠嫙梴搩
丂
揤壓懽暯埨塱俋乮堦幍敧乑擭乯峂巕擭丂幯鉙炓孠偲偼丄抧忋悽奅偡側傢偪悽偺拞偺暯榓傊偺婅偄偲尵偆堄枴偱偡丅
仢愇旇
丂
曮塱撔擭屲寧媑擔丂宧敀偲偁傝丂愇旇偺忋憌晹偵乽
儃儞帤乿偑婰偝傟丄偦偺壓偵撿柍垻栱懮暓偲偁傝傑偡偑丄偙偺愇旇偺堄枴偼恎柦傪曺偘偰暓偺嫵偊偵廬偄傑偡丄偲偺偙偲偲尵偄傑偡丅仢偦偺懠偺愇憸暔偑擇丄嶰懱偁傝丄摴慶恄傜偟偄偱偡丅
丂摴慶恄偼丄懞偺擖岥側偳偵偨偨偢傒丄椃恖偺埨慡傪庣傝丄奜晹偐傜怤擖偡傞塽昦傗埆楈傪杊偓丄懞恖偺埨慡傪庣偭偨偲尵偄傑偡丅惓寧偺峴帠偲偟偰丄摴慶恄偺廃曈偱忺傝暔側偳偺僪儞僪從傪峴偄乮徍榓嶰廫幍擭崰傑偱乯丄堦擭娫偺壠撪埨慡丄朙嶌偲柍昦懅嵭傪婩偭偨偲偺偙偲偱偡丅
丂抝彈憃懱憸偼丄抝彈偺塩傒傪昞尰偟丄榓崌偺戝愗偝傪屻悽偺恖乆偵嫵偊偰偄傞偲偺愢傕偁傝傑偡丅摉慠丄巕曮偑庼偐傞傛偆偵偲偄偆婅偄偱傕偁偭偨偲尵偄傑偡丅
丂幍丂愇媨丒愇憸暔偺懚嵼
 仢戝岥晹棊偺媽摴乮揷戲乣娾愼慄乯偺摴増偄偵師偺屲屄偺愇憸暔偑埨抲偝傟偰偄傑偡丅
仢戝岥晹棊偺媽摴乮揷戲乣娾愼慄乯偺摴増偄偵師偺屲屄偺愇憸暔偑埨抲偝傟偰偄傑偡丅
丂丂姦擮樑嫙梡搩丂丂摴慶恄丂丂峂怽搩丂丂娤悽壒丂丂嫙梡搩
丂偄偢傟偺愇憸偵傕崗擭偼尒偮偐傝傑偣傫丅偙偺愇憸暔傕丄愺崄擖抧嬫撪偵偁傞懠偺傕偺偲摨擭戙乮峕屗帪戙乯偺傕偺偲巚傢傟傑偡丅
丂摉帪暓嫵偺晍峴偑惙傫偲側傝丄廤棊偺恖乆偑暓嫵傪捠偠偰恖娫偺媬嵪傪婩婅偟丄偦偟偰憤懱揑側埨慡傪擮偠傞栚揑偺傕偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅
仢巗摴丂揷戲乕愺崄擖慄偱娵拞晹棊偺摴増偄偵愇憸偑嶰屄偁傝傑偡丅
丂擇偮偺憸偼丄摴慶恄傜偟偄偺偱偡偑丄崗擭偼晄柧偱偡丅巆傞堦憸偼娤悽壒曥嶧偱丄婅庡媨慜屲榊塹偲偁傝傑偡偑丄崗擭偼晄柧偱偡丅娤悽壒曥嶧偼丄恖娫偺婄偲惡偺偡傋偰傪尒暘偗丄帺嵼偵媬嵪偟偰偔傟傞偲尵偄傑偡丅摨帪偵暓摴傪峀傔巹払傪慞摫偡傞栶妱傪偵側偭偰偄傞偲尵偄傑偡丅
仢撿柍娤悽壒曥嶧
丂娵拞晹棊偐傜曢戲摶墇偊偺巗摴撿懁偺愇奯忋偺愇旇偱偡丅
丂丂
姲惌廫敧擭乮堦幍嬨敧擭乯嬨寧媑擔丂偲偁傝傑偡丅丂丂婑憽幰晄柧
丂嵍壓曽偵擮暓嫙梡搩偑偁傝傑偡丅
丂撿柍娤悽壒曥嶧偲偼丄恖娫偑偄傠偄傠偺嬯擸傪庴偗偨偲偒丄偙偺娤悽壒曥嶧偺柤傪暦偄偰堦怱偵偦偺柤傪彞偊傞偲丄娤悽壒曥嶧偼偡偖偦偺壒惡傪暦偒暘偗偰夝扙偝偣偰壓偝傞偲尵偄傑偡丅
仢攏摢娤悽壒旇
 丂幁搰恄幮搊傝岥偺愇抜壓偵偁傝傑偡
丂幁搰恄幮搊傝岥偺愇抜壓偵偁傝傑偡
丂丂
柧帯擇廫幍擭怽擭廫擇寧媑擔丂醕強攏楢幰寶棫丂偲偁傝傑偡丅丂丂乮攏楢幰偺婑憽偱丄壗柤偐偺恖乆偵傛傝寶棫偟偨嫙梴搩乯
丂攏摢娤悽壒偲偼丄媿攏偺埨慡婩婅傪尒庣傞丄戝愗側娤壒條偲偄偄傑偡丅
丂攏摢娤壒偲彂偄偰偁傞傕偺傕偁傝傑偡偑丄摉帪媿攏偼擾峩梡丒岎捠庤抜偲偟偰傕弾柉偺枴曽偱丄廳梫側栶妱傪壥偨偟偰偄偰丄懠抧嬫偵偍偄偰傕尒庴偗傜傟傑偡丅攏側偳偑帠屘偵偁偄丄巰朣偟偨応崌偺尰応偵寶棫旇側偳傕尒偐偗傑偡丅
 仢摴慶恄乮愇旇乯
仢摴慶恄乮愇旇乯
丂惣熆戲晹棊偺熆戲愳嵍懁忋晹乮媽摴忋乯偵偁傝傑偡丅
丂
丂暥媣擇擭乮堦敧榋嶰擭乯惓寧媑擔醕強巵巕丂偲偁傝傑偡丅丂偙偺摴慶恄偼懠偺摴慶恄偲暥帤偺堘偄偑偁傝傑偡偑丄栚揑偼摨堦偲巚偄傑偡丅椃恖偺埨慡丄摴埬撪偺傎偐丄壆晘恄丄杺彍偺恄丄嶌恄偺懳徾偱丄埆偄巕傪摫偄偰偔傟傞怣嬄偲傕暦偒傑偡丅尰嵼偺岎捠埨慡婩婅偱傕偁傝傑偡丅
仢攏摢娤悽壒
丂壓熆戲晹棊偺摴増偄偵偁傝丄師偺傛偆偵婰偝傟偰偄傑偡丅崅娫壠屄恖偺嫙梴搩偲巚傢傟傑偡丅
丂丂徍榓幍恜怽擭幍寧媑擔丂攏摢娤悽壒丂崅娫巵 丂敧丂愺崄擖晹棊偺晽廗
仢媨慜壠偺愭慶嵳傝
丂娵拞晹棊偺巗摴増偄偵屼媨偑寶偭偰偄傑偡丅
丂丂摂饽偵
丂姲惌廫擭乮堦敧乑乑擭乯丂峕屗帪戙丄媨慜壠偺愭慶偑懡栰孲枩応挰偐傜摉抧偵堏廧偝傟偨偲暦偒傑偡丅
丂偙偺屼媨偺嵳楃偼堦擭偵堦搙丄娭學堦懓偵傛傝丄庰傗嫙暔傪偟偰嶲攓偟丄寢懇傪寁偭偨偲偄偄傑偡丅偦偺懠丄媨慜壠偺愭戙偺恖偱丄柧帯弶婜偵摉抧曽偱弶婜僉儕僗僩嫵傪妛傃揱摴偟偨偲偄偆帒椏傕偁傝傑偡丅
仢熆戲偺娤壒摪
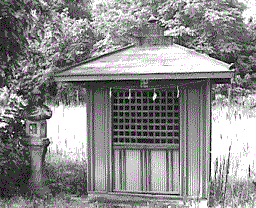 丂熆戲岞夛摪慜曽偵櫬報偱僩僞儞傇偒壆崻偺娤壒摪偑寶偭偰偄傑偡丅愇摂饽偵丄
丂熆戲岞夛摪慜曽偵櫬報偱僩僞儞傇偒壆崻偺娤壒摪偑寶偭偰偄傑偡丅愇摂饽偵丄
丂丂
姲惌敧乮堦幍嬨榋乯暩扖丂偙偺娤壒摪偺拞偵偼丄堖傪傑偲偭偨暓憸偑擇懱埨抲偝傟偰偄傑偡丅傑偨丄抝彈偺昞尰偲巚傢傟傞愇傕擇屄掱抲偄偰偁傝傑偡丅
丂娤壒條偵偼怓乆側揱愢偑偁傝傑偡偑丄摉娤壒摪偼抦宐偲帨斶偲桬婥偺嶰偮偺摽偺徾挜偲偄傢傟傑偡丅摿偵帨斶怺偝偑嫮偔丄彈惈娤壒偱偼偲偄偆愢傕偁傝丄傑偨丄娤壒條偑嵍庤偵孠偺梩傪帩偭偰偄傞巔偱埨抲偝傟偰偄傞偨傔丄梴嶾偺恄條偲傕偄偄傑偡丅
丂嵳擔偼丄敧寧廫擔偱丄偙偺嵳恄偵傛傝嶾偑摉偨傞偲偄偄丄墢擔偼旕忢偵擌傗偐偱丄徍榓弶婜傑偱偼懡悢偺栭揦偑暲傫偱偄偨偲偄偄傑偡丅
丂傑偨嵳擔偵偼丄庒偄抝彈偑嬤懞偐傜婑偭偰偒偰丄愺崄擖偺恖払偼柊傟側偄掱偱偁偭偨偲尵偄傑偡丅偙偙偱寢偽傟偰晇晈偵側傝傑偡偲丄嶾偑摉偨傞偲傕尵傢傟傑偟偨丅
仢敧敠條偺嵳楃
丂愺崄擖偱傕壗儢強偐丄敧敠條偺嵳楃傪峴偭偰偄傑偡偑丄偙傟偼帺暘偨偪偺壠宯傪戝愗偵廳傫偢傞偨傔丄廐偺枮寧偺栭傪嵳楃擔偲掕傔偨偲暦偒傑偡丅
丂熆戲偺嵵摗壠偱偼懢屰偑偁偭偰丄嵵摗儅働偩偗偱偨偨偔晽廗偑偁傝傑偟偨偑丄廋棟旓傪晹棊偱弌旓偟丄埲崀傒側偱梡偄傞條偵側偭偨偲暦偒傑偡丅
丂乽媩栴偺恄乿丒丒丒孯偺恄偱丄敧敠戝恄偵惥偭偰偆偦偼怽偝偸偲偄偆愢傕偁傝傑偡丅
仢戝岥晹棊偺嵳帠
丂戝岥晹棊偵偼丄愄偐傜師偺嶰幮恄嵳偑枅擭偺峴帠偲偟偰幏傝峴傢傟偰偄傑偡丅
丂丂嶳偺恄丂丂嬥斾梾條丂丂曎揤條
丂巐寧敧擔傪嵳楃擔偲掕傔峴傢傟偰偒傑偟偨偑丄嬑傔恖側偳偺娭學偱丄嵟嬤偼巐寧敧擔慜屻偺擔梛擔偲側偭偨偲暦偒傑偡丅
愄偺奺嵳楃擔傗応強桼棃偵偮偄偰愢柧偟傑偡丅
仦曎揤條
 丂晹棊撪撿惣晹偺桸悈抧偵捔嵗偝傟偰偄傑偡丅愄偼棫攈側偍媨偑偁偭偨偲偺偙偲偱偡偑丄柧帯巐廫嶰擭偺戝悈偱棳偝傟偰偟傑偄丄栘釱傪嶌偭偨傕偺偺嵞傃棳偝傟丄尰嵼偺愇媨偲側偭偨偦偆偱偡丅悈恄條傪釰偭偨傕偺偲巚偄傑偡丅
丂晹棊撪撿惣晹偺桸悈抧偵捔嵗偝傟偰偄傑偡丅愄偼棫攈側偍媨偑偁偭偨偲偺偙偲偱偡偑丄柧帯巐廫嶰擭偺戝悈偱棳偝傟偰偟傑偄丄栘釱傪嶌偭偨傕偺偺嵞傃棳偝傟丄尰嵼偺愇媨偲側偭偨偦偆偱偡丅悈恄條傪釰偭偨傕偺偲巚偄傑偡丅
丂愄丄彫敠斔偐傜拑搾偺悈傪媯傒偵棃偨偲偄偄傑偡丅堦擭拞悈偑愨偊偨偙偲側偔丄偳傫側姳偽偮偱傕悈熆傟偼偁傝傑偣傫丅擭堦夞彈廜偑枻懸偪傪偟傑偡丅廐偺枻偺擔偺慜擔偵峴偄傑偡丅愄偼彫摛傪備偱偰偄偨偺偑丄栞傪偮偔傛偆偵側傝傑偟偨丅廻偼夞傝斣偱僆僐儌儕偼偟傑偣傫丅曎揤條偼彈偺恄條偱偟偨丅偙偺悈岥乮悈尮抧乯偼梡悈偲偟偰擇榋挰曕傪弫偟偰偄偨偲偄偄傑偡丅搤偱傕搥偭偨偙偲側偔棙梡偝傟偰偄偨傛偆偱偡丅崗柤偼晄柧偱偡丅
仦嶳偺恄
丂応強偼戝岥晹棊偺愺崄擖忛愓偺拞暊偱丄娾偺娫偵捔嵗偝傟偰偄傑偡丅愇媨偑偁傝傑偡丅崗柤偼晄柧偱偡丅
丂嶳巇帠傪偟偰夦変傪偟側偄傛偆偵庣偭偰偔傟傞恄條偱丄愄偼悪偺戝栘偑愇媨偺嬤偔偵偁偭偨偲偄偄傑偡丅偦偟偰堦寧屲擔偺嶳擖偺擔偵丄懞恖奺恖偑僉儕僴僊偍摢偮偒傪偟傫偤傑偡丅抾偱偍扢傪嶌傝丄庰傪擖傟丄悈堷偱擇偮偟傏傝崌傢偣偰偮傞偟傑偡丅偙偺條偵偟偰嶳偺恄傪釰偭偨偲尵偄傑偡丅
丒嶳巇帠偲偼丄徍榓嶰廫屲擭崰傑偱丄擱椏偲偟偰巊傢傟偰偒偨儅僉丒僗儈丒儃儎側偳偺嶨栘傪敯嵦偡傞嶌嬈偺偙偲偱偡丅
仦嬥斾梾條
丂愺崄擖忛愓嬤偔偺奟忋偵捔嵗偡傞愇媨偱偡丅崗柤偼偁傝傑偣傫丅偦偽偵偍揤嬬條偺愇媨偑擇婎偁傝傑偡丅偙偺嵳楃偼巐寧敧擔偱屼暭懇丒僔儊傪忺傝丄晹棊慡堳偱嵳傝嫟斞怘傪偟傑偡丅
丂嬨丂愺崄擖敧栘愡曐懚夛偺曕傒
丂摉愺崄擖敧栘愡偼丄戝惓枛婜偵巗撪拞崅悾抧嬫偺曽乆偐傜巜摫傪庴偗偰晛媦偟傑偟偨丅摉帪偺悽憡偼屸妝偑彮側偔丄敧栘愡偑媫懍偵抧堟偺庒偄恖払偺娭怱傪屇傃丄栆楙廗傪廳偹偨偲暦偒傑偡丅偦偟偰孮攏導惣栄抧嬫敧栘愡戝夛偵嶲壛偟丄尒帠桪彑偺塰梍偵婸偒傑偟偨丅偦偺屻愴憟側偳偺塭嬁偱堦帪拞抐偟丄徍榓擇廫擇擭崰傛傝暅妶丅愴屻偺崿棎婜偵暥壔岎棳偲偟偰恄妝晳偲嫟偵墘寍夛摍偵弌墘丅傑偨丄徍榓擇廫嬨擭偵偼巗惌崌暪帪偺峴帠偵嶲壛丅徍榓屲廫嬨擭偵偼丄巗惌嶰廫廃擭偵墬偄偰丄嫵堢埾堳夛偺埶棅傪庴偗恄妝晳偲嫟偵曐懚斉價僨僆僥乕僾偵廂傔傜傟傑偟偨丅偦偺屻傕愺崄擖敧栘愡曐懚夛偲偟偰丄戝墫屛偺旇偺媢僼僃僗僥傿僶儖傗抧嬫暥壔嵳側偳丄巗撪奜偺弌墘偺埶棅傪庴偗丄愊嬌揑偵弌墘偟暥壔岎棳偵椼傫偱偄傑偡丅偙傟偐傜傕偙偺揱摑偁傞愺崄擖偺敧栘愡傪宲彸偡傋偔搘椡偟偰捀偒偨偄偲巚偭偰偄傑偡丅
 丂乽墘栚乿偲偟偰丄師偺屲庬栚偺梮傝傪揱彸偟偰偄傑偡丅
丂乽墘栚乿偲偟偰丄師偺屲庬栚偺梮傝傪揱彸偟偰偄傑偡丅
丂丂崙掕拤帯偱丂堦丄擔嶱丂擇丄悰妢丂嶰丄愵巕丂巐丄壴梮傝丂屲丄庤梮傝
丂側偍丄壒摢丒揓丒屰丒忁丒梮側偳丄抧嬫偺恖払偩偗偱偼恖堳偑懌傝偢丄妟晹偺懠抧嬫偺曽乆偺嫤椡傪摼偰愺崄擖敧栘愡曐懚夛偺堦堳偲偟偰弌墘偟偰捀偄偰偄傑偡丅偛嫤椡傪偟偰捀偄偰偄傞奆條偵怱偐傜姶幱怽偟忋偘傞偲嫟偵丄崱屻偲傕傛傠偟偔偍婅偄偟偨偄偲巚偄傑偡丅崱屻偺寬摤傪偍婩傝偟傑偡丅
丂弶戙曐懚夛挿偼丄嵵摗摽梇偝傫丅尰嵼偺夛挿偼丄嵵摗桭帯偝傫偱偡丅
丂廫丂偦偺懠奺庬揱彸榖
丂愭戙偺曽乆偐傜怓乆偺尵偄揱偊傪暦偄偰偄傞偺偱丄偄偔偮偐徯夘偟偰傒傑偡丅
仢偦偺愄丄熆戲愳壓棳偺壓壨尨偺峀応偵偍偄偰丄暥壔岎棳偲偟偰壴壩戝夛傗憪嫞攏丄憡杘戝夛側偳惙傫偵奐嵜偝傟丄堦帪婜戝曄偵擌傗偐偱偁偭偨偲暦偒傑偡丅尰嵼偼壨愳夵廋偱椉娸偑愇愊傒偱偡偑丄摉帪偼帺慠傑偐偣偱偐側傝偺峀応偑偁偭偨偦偆偱偡丅
仢晄摦摪偺釱偺晄摦柧墹偑嶰懱偁傝傑偡丅偦偺愄丄徖揷巗墶捤挰偺墑柦帥偐傜丄壀杮偺惣曽帥偺朧偝傫偑庁傝庴偗擺傔丄杮摪偼愺崄擖抧嬫偺恖払偑寶憿偟丄娗棟曐懚傪嵳傝悽榖恖偑峴偭偰偄偨偲偄偄傑偡丅傑偨妋偐側偙偲偼傢偐傝傑偣傫偑丄屲廫擭傎偳慜傑偱偼丄嵳傝偺慜擔乮擇廫幍擔乯偺栭丄偍偙傕傝傪偟側偑傜攷懪傪偟偰偄偨偲偄偆榖傕暦偄偰偄傑偡丅
仢偍帥偺懚嵼丅
丂峕屗帪戙屻婜崰偺抧恾傪尒傑偡偲丄嶰僣嵆偺墱抧偵丄摉帪帥堾偑偁偭偨偲偼偭偒傝帵偟偰偁傝傑偡丅帥柤偼敾柧偟偰偄傑偣傫偑丄嶰僣嵆抧撪偺敤偺偁偪偙偪偵柍墢暓偲巚傢傟傞曟愇偑偁傝丄娭學偑偁傞偺偐傕偟傟傑偣傫丅
仢峅朄堜屗愢丅
丂愄峅朄條偵場傫偱慡崙奺抧偺桸悈抧偵峅朄堜屗偲婰偝傟偨応強偑偁傝傑偡偑丄摉抧熆戲晹棊偺捠徧忋偺嶳乮嵵摗壠乯偺擖摴偱桍戲摴偺捠増偄偵傕丄峅朄堜屗偲屇偽傟偨堜屗偑偁傝傑偟偨丅崱偼杦偳柺塭偼偁傝傑偣傫丅扟捗偺桸偒悈傪堷偒崬傒壆崻傪嶌偭偰塉悈傪偝偗丄椬抧偺曽乆偑棙曋傪摼偰偄偨偲暦偄偨偙偲偑偁傝傑偡丅
丂
偁偲偑偒偵戙偊偰
丂崱夞丄偙偺尨峞偺幏昅偵偁偨傝丄懡彮偺暥專帒椏偺懠偵丄愺崄擖抧嬫偺尦榁傗愭攜偺曽乆偺揱尵丄揱愢丄偝傜偵巹偺愘偄峫偊偱嶌惉抳偟傑偟偨丅暥拞丄幐楃側暥柺偱偛柪榝傪偍偐偗偟偨偲巚偄傑偡偑丄偛梕幫偺傎偳偍婅偄偄偨偟傑偡丅
丂側偍丄愺崄擖抧堟偼暥復傪彂偄偰偄傞偆偪偵丄斾妑揑怴偟偄懞憿傝偑峴傢傟偰偒偨抧嬫偱偁傞偲姶偠偰偄傑偡偑丄崱屻偵偍偄偰傕丄愄偐傜偺嵜帠側偳丄楌巎傗暥壔偺摂傪偄偮傑偱傕徚偡偙偲側偔丄暥壔堚嶻偲偟偰娗棟曐懚傪婅偊傟偽丄嵟忋偺娊傃偱偁傝傑偡丅
丂嵟屻偵丄奆條偺偛垽撉丄怱傛傝姶幱怽偟忋偘傑偡丅
乮嶲峫暥專乯 晉壀巗巎丄晉壀偺楌巎丄娒妝孲巎丂懠
丂