
�������A�������ɂ����@�I���q�͐������ŁA���{�̐����Ƃ̋����n�܂�I�i��҂҂̌Z�j
��k�Ђ���Q�T�Ԃ��o�߂����B��k�Ђ̑�Ôg�Ŕ�������������ꌴ�����̂͂��܂���i��ނ̕�����Ƃ������Ă���B�Ƃ���ł��̎��̂ł��邪�A����̓��{�o�ρA���S�ۏ�ʂɏd��Ȋ�@�������炷���ƂɂȂ肻�����B���������Ƃ����ƁA���˔\�������肪�N���[�Y�A�b�v����邪�A���ƒP�ʂōl����ƌo�ρA���S�ۏ�ʂł̖��̕����͂邩�ɑ傫���B�����炱���A�����J�̃X���[�}�C�������̂̑S�e�́A���܂��ɃA�����J�̍��Ƌ@���Ȃ̂ł���B
1986�N�Ƀ`�F���m�u�C���������̂��N���������ƁA3�N��Ƀx�������̕ǂ�����A����2�N��Ƀ\�A����̂������Ƃ��l����ƁA���Ƃ��ƈ������Ă����\�A�o�ςɃ`�F���m�u�C���������̂��Ƃǂ߂��h�����\���������B���ꂾ���d�͂Ƃ����͍̂��ƌo�ς̗v�Ȃ̂��B
����̓��{�̌��q�͐���͕�����ꌴ�����̂ɂ���āA�}�u���[�L��������\���������B�������i�h�̒n���c���͌����ݗ��I�B�����̐V�݂͂��납�A�����錴���̑��݂����Ԃ܂��B�����͊댯�ł���B�����炱���n�k�ɑ���������K�v�Ȃ̂��B�������h�̐l�Ԃ͕�����ꌴ���̎��̂�����ɂ��邪�A����̐k�ЂŖ������������쌴�����X���[����͕̂Ў藎���łȂ��̂��B
��
�w�����A���Õ������Ôg��@����͔��Ɂx
�����{��k�Ђ̔�Q�ł́A�������k�̑����m���݂ɗ��n���铌���d�͂̕�����P�����Ɠ��k�d�͂̏��쌴�������Â����B������P�����������̏Z�����̋�����������������ʂŁA���쌴���ɂ͉�œI��Q�ƂȂ������쒬�������Ƃ��Đg���Ă���B�Q�̌����̖��Â������ꂽ�͕̂�����P�����ł͑z�肳�ꂽ�Ôg�̍�������T�E�U���[�g���������̂ɑ��ď��쌴���͂X�E�P���[�g���ɐݒ肵�����n�̂킸���ȈႢ�������B�k�Ќ�̒�d�͂Ȃ��A���̔��~�����������߁A���쌴���͒Ôg�ʼn�œI��Q�������쒬���̋~���̏ꏊ�ɂȂ����B���q�F���K���@�ň�ʏZ���͋��Ȃ������~�n���ɂ͓���Ȃ����A�l����̔z������J������A�ő�łR�R�O�l�����������̕ʊقƑ̈�قɔ����B�i�Y�o�V���j
������ꌴ���͓��{�̌��q�͐���̊ϓ_����A���쌴�����Q�l�ɂ��蒼���ׂ��ł���B
�d�͂̋����s������A���łɘV�������Ă���Η͔��d�̍ĉғ����n�܂��Ă���B�Η͔��d�͍�����������Ζ����ʂɏ���A���ݖ��ɂȂ��Ă����_���Y�f���ʂɔr�o����B������肩���{�̓d�͋����\�͂�30�N�`40�N�O�ɋt�߂肳����B��ƌo�c�҂͑O�����̎��ƌv����l���邱�Ƃ͂����Ă��A�������̎��ƌv����l���邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��B���{�̌o�c�҂����{�ň��肵���d�͂̋����������Ȃ��Ȃ�A�����ɍŐV���̌����i���������{�l�̐ŋ��Łj�������āA�����ɓ��{�̍Ő�[�̍H����ڐ݁B���{��Ƃ����������_�ɃO���[�o���o�ςɑł��ďo��Ƃ������Ƃ��l���Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B
�u����ł�������ł����H�v�Ƃ����b�ł���B���̂��Ƃ������A����̌������̂̐^�̊�@�Ȃ̂ł���B
�����c���̍��۔�r�i�t�B���s���ݏZ�̓��{�l�j
���̐}�͓��{�̍��������������Ƃ��ɂ悭�p������A�����Ȃ̃T�C�g�Ɍf�ڂ���Ă���O���t�ł���B���{�A�A�����J�A�J�i�_�A�C�^���A�A�h�C�c�A�t�����X�A�C�M���X�̐�i7�J���iG7�j�̍��c���̑�GDP�䗦��\���Ă���B

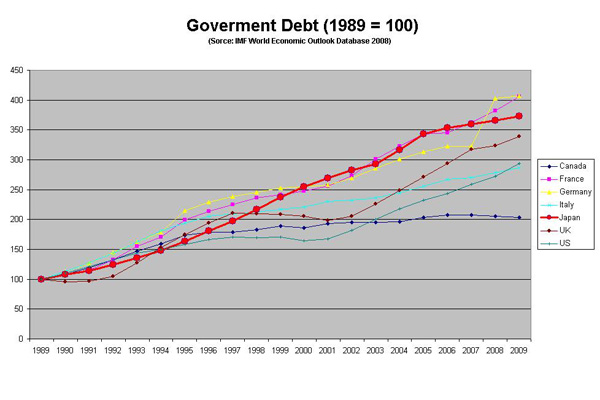
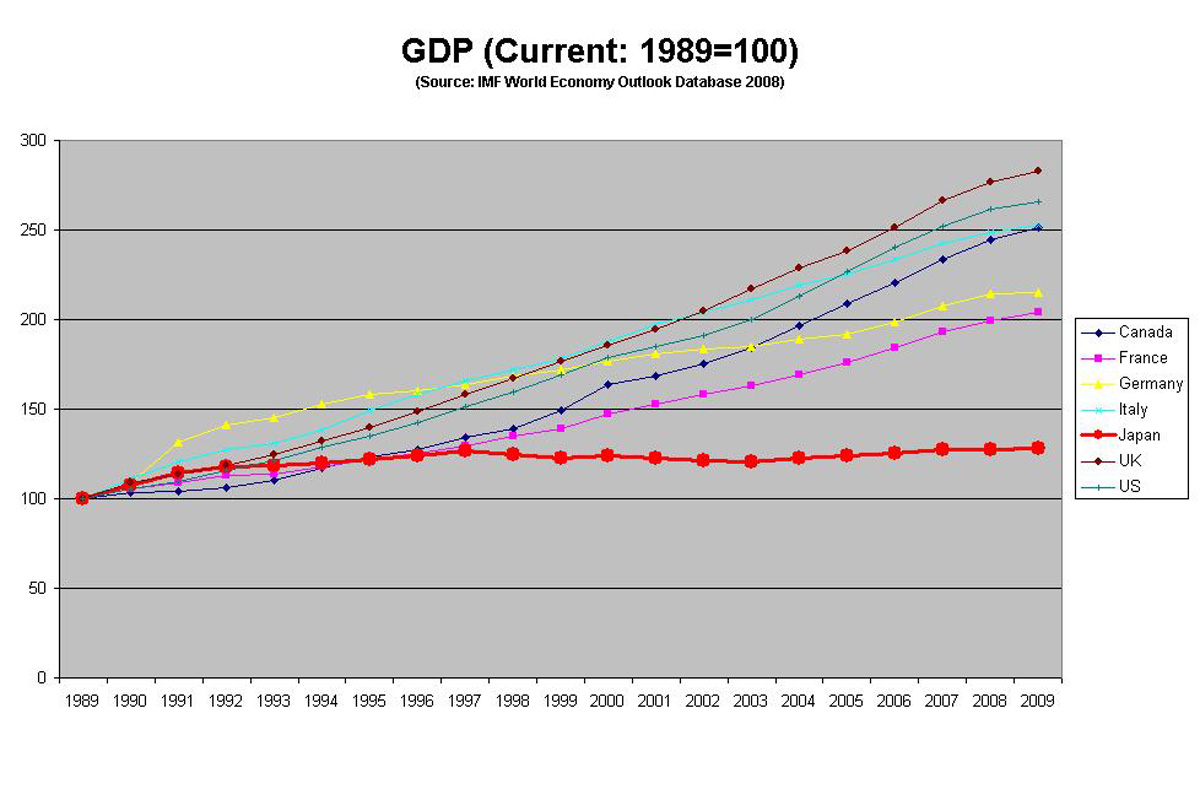
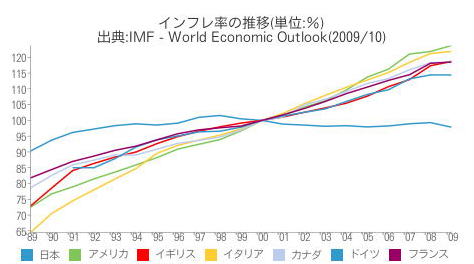
�����{��Ɠ��{�̃��f�B�A�i�O���M���j
��Ύ��̒����w���y�w�čl�x�ōł���ۂɎc���Ă���̂́A���������̏d�v���̌������邱�ƂȂ���A���{�������u���R�ЊQ�j�ρv�Ɩ��Â��A�嗤�i���B�⒆���j�Ƃ͌���̈Ӌ`���炵�āA�S���قȂ镶���Ƃ��Ĉʒu�Â��Ă��镔���ł���B��Ύ��͉��B�⒆���Ȃǂ̃��[���V�A�e���̕������A�u�������j�ρv�ƒ�`���Ă���B�������j�ςƂ́A���B�⒆���ł͐��S�N�A���\�N�A���ɂ͐��N���ƂɁu�Z�����F�E���ɂ����K�́v�̑�ʎE�C���������A�X�⌾�ꂪ����ɑΉ����i�����Ă������Ƃ��Ӗ����Ă���B
�Ⴆ�A���B�̓s�s�́A���̑�������������ǂɈ͂܂�Ă���B����ɑ��A���{�́u�鉺���v�Ƃ������t�̒ʂ�A����͂ނ悤�Ɏs�X�n�����W�����B�X�Ɓu�O�v�Ƃ̋��E�́A����قǖ��m�ł͂Ȃ��̂ł���B���B�͈ٖ�����A���ɂ͓�����������L����l�X���A���m�̏W�c�Ƃ��ĉ����A�X�̏Z���͋��͂��Ă���ɑ��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���ʁA�X����ǂň͂ނƂƂ��ɁA�Z�������͂��ꂼ�ꂪ�u���m�v�Ƃ��āA�P���҂Ɛ��Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł���B���̂��߁A���B�̌��t�͒P���t���[�Y�́u��`�v�����m�ŁA�N��������Ȃ������ł���悤�ɐi�������B�N�������ߕ��̉��߂���������ʁA�X�̏Z�����댯�Ȗڂɉ�\�����炠�����ȏ�A���������Ɋ�Â����W������Ȃ������킯�ł���B
����ɑ��A�u�ٖ����P���Ƌs�E�v�Ƃ������j�������Ȃ����{�ł́A���t���u�e�P��̈Ӗ����`�����L���v�X�^�C���ŁA���R�C�܂܂ɔ��W���Ă������B�ى����`�ꂪ�ɒ[�ɑ����i�p��́uI�v�̓��{���̐��𐔂��ė~�����j��ɁA�P��̈Ӗ�������قnj����ɒ�߂��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�ǂސl�╷���l�ɂ��A�l�X�ȉ��߂��\�Ȃ̂��B���̌���I�B�����̂ɁA���{�ł͋��낵���قǂɉ����[���A���ՐF�������Ǝ��̕��������W�����̂��B���݂̓��{�������A���E�̗l�X�ȍ��X�ōL��������A�y���܂�Ă���̂́A���̓��{�ꂪ���X�����͂��ɂ߂đ傫���ƍl����B
�������A���́u��`���B���v�ȓ��{��́A��̓_�ō��������������N�����B��ڂ́A�_��@���ȂǁA�u�N�����������߂����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�����ł����Ă��A�l�ɂ����߂��قȂ��Ă��܂��Ƃ����_�ł���B������A���̍�������@���ł���u���@�v�ł����A���ߘ_�����������Ă��܂����炢�ł���B��ڂ́A��`���B���̂ɁA�Z���Z�[�V���i���ȁu���o���v�̉e�����傫���Ȃ��Ă��܂��_�ł���B���Ƃ��u�����j�]�v�Ƃ������t���T�^�����A�V���̌��o���ȂǂŁA�u���{���{�̍����j�]�A�b�ǂݒi�K�ɁI�v�ȂǂƏ������ƁA���ʂ̐l�͋����邾�낤�B���̍ۂɁu�����j�]�v�̒�`�͉��Ȃ̂��A�u�b�ǂݒi�K�v�Ƃ͋�̓I�ɂǂ�قǂ̊��ԂȂ̂��Ȃǂ́A�ǂސl�͓��ɐ[���͍l���Ȃ��B���ꂼ�ꂪ�u�����j�]�v��u�b�ǂݒi�K�v�Ȃǂ̌��t�������炷��ۂɊ�Â��A�Ӗ�������ɉ��߂��Ă��܂��̂ł���B���ʁA�e�l�������ɂ��ăC���[�W�Ɋ�Â����������d�ˁA��B���Ȃ܂ܗ��z���Ă��܂��B
���f�B�A���Z���Z�[�V���i���Y�������߂�̂́A�m���ɐ��E�I�ȌX�����B�������A���{�̏ꍇ�́A�V����ǂޑw�̊������i���ĂȂǂƔ�ׂāj���X�������Ƃɉ����A���{����L�̞B�����Ƃ�����������B��ۘ_�Ɋ�Â����~�X���[�h���A���ΓI�ɍs���₷�����ɂ���\���������̂ł���B
���A�����J�̓��������e����������J�����Q�P���I�̐V���Ȃ钪���i��҂҂̌Z�j
�A�����J�̓��������e����������T�N�ɂȂ�B���̎����͋߂��Ƃ���ł́u�x�������̕Ǖ���v�u�\�A��́v�ɕC�G���鐢�E�j�̓]���_�ł���B���R�Ȃ��炱�̂T�N�̊Ԃɗl�X�Ȑ��ƁA���҂ɂ�錟���s���Ă����B�����͂ЂƂ�҂҂̌Z��������Đ��Ƃɂ͂Ȃ����_�ł��̎�����傢�Ɍ����Ă݂����B
�܂����̎��������O�ɁA�l�ނ̗L�j�ȗ������Ƒ����Ă����u�푈�v�ɂ��Č��Ȃ��Ă͂����Ȃ��B����͉����ƌ����Ɛl�Ԃ�����Ɛ푈��������悤�ɂȂ��Ă����Ƃ������Ƃ��B�Q�P���I�ɓ����Ă�������ς�炸���E�̊e�n�Ő푈�������Ă���B����������͐푈�ƌ��������A�����ƌ`�e���������������悤�ȏ��K�͂Ȃ��̂���ł���B���Ă̑�ꎟ�A����E���̂悤�ȃX�P�[���̑傫�Ȑ푈�͂߂����茸�����B�����炭���̂悤�Ȑ푈�̓x�g�i���푈�����肪�Ō�ł͂Ȃ����낤���B
���{���푈�����Ȃ��Ȃ��ĂU�O�N�ɂȂ�B���[���b�p���ߔN�ł̓��[�S�X���r�A�̖������������������炢�ŁA�������ĕ����ł���B���t�����X�ƃC�M���X�̊ԂŐ푈�ɂȂ邾�낤���B���h�C�c�R���|�[�����h�ɐN�U���邾�낤���B���Ă͓�����O�̂悤�ɍs���Ă������̂悤�Ȑ푈���A���݂ł́A�قƂ�NjN����\�����Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B�P�X�X�O�N�O��Ƀ\�A�A�����ŋN�������v���������v���ł������B���[�}�j�A�Ń`���E�V�F�X�N�哝�̂��E���ꂽ���炢�Ȃ��̂ł���B�푈��D���̃A�����J������Ɛ푈�����ɂ����Ȃ��Ă��Ă���B�푈���������āA�������ɑ�ʂ̎��҂��o��A�哝�̂̎x�������}�����āA�����I���S�͂������Ă��܂����炾�B
���푈��M�S�ɂ���Ă��鍑�́A���E�̌x�@�����F����A�����J�Ƃ��̎q���ł���C�X���G���A�����Ċe�X�̌�i�����炢�Ȃ��̂ł���B���̂����A�����J�͔��������߂āA���u����ɂ�郍�{�b�g��ɐ芷���悤�Ƃ��Ă���B����قǐ��E���܂��ɂ����Đ푈�����A�l���E���܂����Ă����l�ނ��Ȃ������ɂȂ��Đ푈��������悤�ɂȂ��Ă����̂��낤���B
�ЂƂ����������サ�āA�R�j�i�����A�����A�댯�j�Ȃ��Ƃ���肽����Ȃ��Ȃ��Ă����Ƃ����̂�����B�P�O�N�ȏ�O�ɓ��{�̎�҂��R�j�d������肽����Ȃ��Ȃ������Ƃ���莋���ꂽ���A���̌X���͓��{�Ɍ��炸���E�I�Ȃ��̂ł���B������x���������������A����ǂ����Ƃ͂�肽���Ȃ��B�y���������B���ɐ푈�Ȃ͂R�j�̍ł�������́B�N���D���D��ł�肽���Ȃ��i�R���}�j�A�͂̂����j�B��قǂ̃n���O���[���_���Ȃ��Ɩ��܂�Ȃ��B�A�����J�̊C�������n�����K�w�̏o�g�҂��肾�Ƃ����B
�����ЂƂ��푈���f���ɂ���ċL�^�����悤�ɂȂ������Ƃ��傫���B�̂͐푈�̌��̂Ȃ��l�Ԃ��푈��m��ɂ͌��`�������Ȃ������B���R����́u�p�Y�k�v�u���E�`�v�ƂȂ��Č���A�������ꂽ�푈���C���v�b�g���ꑱ���Ă����̂ł���B�������Q�O���I�ɓ���Ɖf���Z�p�����B���Ă���̂܂܂̐푈���L�^����邱�ƂɂȂ����B���R�푈��̌����������Ƃ̂Ȃ��l�Ԃ��A�푈�̎��Ԃ��ǂ��������̂��A����̂܂܂�m�邱�Ƃ��ł���B��������Đ푈����肽���Ɩڂ��M��������l�͏����i�R���}�j�A�����j���낤�B
�l�ނ������ԑ����Ă����푈���A���������̍�����i���𒆐S�ɏk���X���ɂ���B����͎����ł���B�Ȃ��������������̒��ŋN�������A�����J�̓��������e�������͂��������ǂ������ʒu�Â��ɂȂ�̂ł��낤���B���x�͎��_�������ƕς��Ď�����S���u�x�@�v�ɂ��čl���Ă݂����B
�A�����J�̓��������e���������N���������ƁA���炭���āA���{�ł͖k���N�ɂ��f�v����������݂ɂȂ����B�������{�̗��j�I�]���_�Ƃ��āu���{�̂X�P�P�v�ƌĂԐl������B���������̖�肪���o���ĂS�N���Ȃ�̂ɂ��܂��ɉ������Ă��Ȃ��B�Ȃ����낤�B���̂��Ƃ��݂ȕs�v�c�Ɏv��Ȃ��̂��낤���B������҂҂̌Z���k���N�Ɠ����悤�Ȕƍ߂�Ƃ��ǂ��Ȃ邩�B������f�v���A���O�֘A�ꋎ��A�U�D�����A����𖧔�����B�����炭���ꂼ�ꂪ�d��ƍ߂ł��邱�Ƃ���x�@�ɕ߂܂��Ď��Y�ɂȂ�͂��ł���B
�������k���N�̝f�v�����ŁA�N�����߂܂�����A���Y�ɂȂ����Ƃ����b�������Ƃ��Ȃ��B���₻��ǂ��납��Q�҂̐����⎖���̑S�e����킩��Ȃ��̂ł���B�����̎����ł���Ȃ��Ƃ͂��蓾�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�P�P�O�Ԃ���Όx�@�����āA�����̉����ɂ������Ă���邩��ł���B���������ꂪ�ЂƂ��э����̂Ȃ��O�������ގ����ɂȂ�ƁA�����̌x�@�ł͑Ή�������Ȃ��B�ł͂ǂ���������̂��B���͂ǂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł���B�Ȃ��Ȃ����{�̍����ɂ͌x�@�����Ă��A���E�ɂ͌x�@�����Ȃ�����ł���B�P�P�O�Ԃ��Ă��N�����Ă���Ȃ��B����P�P�O�Ԃ���Ȃ��̂ł���B
���E�ɂ͈ꉞ���A�Ƃ����g�D������B�����ڂ͐��E�̕��a�����x�@�̂悤�Ɍ����邪���Ԃ͈Ⴄ�B�Ȃ��Ȃ牽�̗͂��Ȃ�����ł���B�x�@�̖�����S���Ȃ狭���͂����\�͂��s�����B���{�̌x�@�ł��A�Ɛl�ɑ��Čx�_���ӂ邢�A����������A�����ƂȂ����甭�C����B����������Ȃ��Ƃ̂ł���g�D�͐��E�ɂ͂Ȃ��B���̏؋��ɝf�v�����̎�d�҂ł�������������܂��ɑߕ߂���Ă��Ȃ��B���A�͋����͂�Ȃ����悾���̑g�D�ł���B���A�Ƃ͕ʂɃA�����J�����E�x�@�݂����Ȃ��Ƃ�����Ă��邪�A����͎����̗��Q�����œ����Ă���̂ŁA����x�@�Ƃ͌ĂׂȂ��B�����Č����Ȃ��\�͒c�ł���B���{�̍����ɗႦ��A���{�̎������R���g���d���Ă���悤�Ȃ��̂Ȃ̂��B
�������A�����͌��������E�̕��a�����x�@�����낻��K�v�ɂȂ��Ă��Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃɂ݂ȋC�Â��n�߂Ă���B������������낤�Ǝv���Ƃ��ꂪ�Ȃ��Ȃ�����B�Ȃ��Ȃ����E�e���̗��Q����v���Ȃ������ł���B�Ⴆ�Β����ɃC�X���G���Ƃ������\�҂�����B�����𗐂��Ď��͂ɑ�ςȖ��f�������Ă���B�������e���ł���A�����J�͎q���̃C�X���G������ʈ������āA�\�͍s�ׂ���C���Ă���B�A���u�͂���ɑ��Ė\�͂ʼn��V����B���[���b�p�A���V�A�͗��҂Ƃ͋�����u���Ă����������������������ߓ��낤�Ƃ���B����ł͌����̗��v�����x�@�Ȃǂł������Ȃ��̂ł���B
���E�x�@�����낤�Ǝv�����琢�E�̗��Q����v���Ȃ��Ƒʖڂ��B��Ԏ����葁���̂́A�n���ɉF���l���U�߂Ă��邱�Ƃ��B����Ȃ琢�E�̗��Q����v���邵�A�c�����ł���B�������n���ɉF���l���U�߂Ă��邱�Ƃ͂����������肦�Ȃ��B�ł͂ǂ�����������낤���B
���{�����Ă͌���̐��E�̂悤�ɍ����o���o���������B�����č����m�Ő푈���J��Ԃ��Ă����B�퍑���オ���̂����Ⴞ�B���ꂪ�����ȍ~���ꂳ��A�x�@���a�����A���E�Ɋ����镽�a�ȍ��ɂȂ����B���̂悤�ȓ��{�̉ߒ��߂A���E�ɂ��x�@�����܂�A���E���a����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�ł͂Ȃ��o���o�����������{������ł����̂ł��낤���B��������ĂɐN������邩������Ȃ��Ƃ�����@������������ł���B
���ĂƂ����G�����āA���߂ē��{�͍���ł����A�x�@���ł����A���a�ɂȂ����B�Ȃ�ΐ��E���l�ދ��ʂ̓G�����K�v������B����͒N���ǂ����B�F���l�͗��Ȃ��B�~���[�^���g������Ȃ��B����҂Ă�B�����e���ɂ���āA���̍߂��Ȃ��l�X��吨�E���܂������q��Ȃ炴��ُ�ȏW�c������B�e�����X�g�B�������e�����X�g���I�e�����X�g��l�ދ��ʂ̓G�Ƃ��āA����X�P�[�v�S�[�h�ɂ��āA���E�ꂵ�A���E�x�@������A���E���a���������邩������Ȃ��B���ۂ����l���ē����Ă���l�Ԃ�����B
�����Ő�́u�l�Ԃ��푈��������悤�ɂȂ��Ă��Ă���v���Ƃƌ��т��Ă��Ă���B���E�x�@���������Ȃ�����A���E�͖\�͂��x�z���閳�@�n�тł���B����ȏ��Őg�̈��S����낤�Ǝv������A�����̐g�͎����Ŏ��Ȃ��Ă͂����Ȃ��B���Ȃ킿���h�ł���B���ݓ��{�ł����h���������肵�悤�Ƃ����C�^�����܂��Ă��Ă���̂́A�������������������邽�߂��B�����������̐g�������Ŏ��ɂ͂R�j�i�����A�����A�댯�j�ł���푈�����Ȃ��Ă͂����Ȃ��B����͂��������B�����ō��h�����Ȃ��Ă��g�̈��S���ۏႳ���u���E�x�@�v�̑Җ]�ɂȂ���킯���B
�A�����J�̓��������e�����������E�j�̓]���_�ƂȂ����B����́A�ЂƂɂ��l�ޗL�j�ȗ����߂Đl�ދ��ʂ̓G�����ꂽ���Ƃł���A�����ЂƂ��l�ޗL�j�ȗ������s�\�Ƃ���Ă������E�x�@�a���̕z�����������Ƃ���ɂ���ƒf���ł���B
���u�P�T�O�l�v�����傤�ǂ����i�ēc�����j
���Ȃ��̌g�тɂ́A���l�̓d�b�ԍ����o�^����Ă��邾�낤���B����̊���v�������ׂ邱�Ƃ��ł��āA���ꂩ����d�b��������W���A�Ǝv����l�̐��́A�P�O�O�`�Q�O�O�l���炢���ƌ����Ă���B
�p���̐l�ފw�҂q�E�_���o�[�́A�l�X�ȋ����́A�R���A��ƁA�@���g�D�Ȃǂ̏W�c�̑傫���ׂ��B���̌��ʁA�ړI�����L���A�S��ʂ킹�Ȃ����̂ƂȂ��Ċ������郆�j�b�g�i�R���̒����A��Ƃ̋@�\�P�ʁA�P����̐M�k���Ȃǁj�̋K�͂́A�قƂ�ǂP�O�O�`�Q�O�O�l�͈̔͂ŁA���̕��ς͂P�T�O�l�������B�R���́A�݂��ɖ���a���������ɂ̉^�������̂����A���j���Ȃ��s���P�ʂł��钆���̋K�͂͗m�̓����A������ĂP�T�O�l�قǂ������B�Ñネ�[�}�R�̕��������͂P�Q�O�`�P�R�O�l�B��Q����펞�̊e���R���A�P�R�O�`�Q�Q�O�l�ƂقƂ�Ǖς���Ă��Ȃ������B���̌��ʁA�_���o�[�́A�@�\�W�c�̈ێ��ɂ̓����o�[�Ԃ̒��ړI�A�l�I�Ȃ��肪�s���ŁA���̍œK�K�͂��u�P�T�O�l�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����ƍl�����B���̐����ɂ́A�ǂ�ȈӖ����B��Ă���̂��낤�B
�`���p���W�[��S�����A�l�ԂȂǂ̗쒷�ނł́A�]�i��]�V�玿�j�̑傫���ƁA���������𑗂�Q��̑傫���̊Ԃɔ��W�����邱�Ƃ��킩���Ă���B�l�Ԃ̔]���琄�肳���Љ�W�c�̋K�͂��Z�肷��ƁA��͂�P�T�O�l�ƂȂ�B�l�Ԃ͔]�����剻�����邱�ƂŌ�����l�����A������g�����Ȃ��A���G�Ȑl�ԊW�������ł���悤�ɐi�����Ă����B�l�Ԃ̔]�́A�P�T�O�l���炢�̏W�c�ŕ�炷�̂ɍœK�����Ă���Ƃ������Ƃ��ł���B�l�Ԃ͑���̐S�̒���ǂݎ��A�l�ԊW��ǍD�ɒz�����ƐS���ӂ��Љ�I�������B�l�Ԃ��R�l����ꍇ�̊W�́A�`�Ƃa�A�`�Ƃb�A�a�Ƃb�̎O�ƒP�������A�R�O�l�̏W�c�ł͂S�R�T�̑��p�W�ɂȂ�B�K�͂͂P�O�{�����A�W�͂P�T�O�{�ɂȂ�B���ꂪ�P�T�O�l�̏W�c�ɂȂ�ƁA�W�͂P���P�P�V�T�ʂ�B�l�Ԃ͂��̕��G�ȊW�ɔz�����Ȃ���A�����������ێ����Ă����\�͂�����Ă���̂��B
�u�P�T�O�l�v�Ƃ��������́A����ɋ����ׂ��Ƃ���ɂ�����o���B
����U�U���܂ő������l�ނ����A���ڂ̑c��ƂȂ����W�c�͖�P�T�O�l���������Ƃ��A�ŐV�̈�`�q��͂ł킩�����̂��B��V���N�O�ɃA�t���J���o�������ȏW�c�́A���m�̊��ɓK�����A���E�̋��X�܂Ő��͂��L���Ă������B���̑c��W�c�����\�l�̏�������������A���������R�Ƃ����~�L�T�[�ɂ���Ԃ���A���ł��Ă������낤�B�Q�O�O�l��葽��������A�h���R�����N�����ĕ��A���|��őS�ł��Ă�����������Ȃ��B�������̑c��́A�▭�̃X�^�[�g������̂������B
���u���w�҂̖��_�_�v�]�i�����L��j
���钘���ȃA�����J�̉Ȋw�҂��������r�e�����Ɏ��̂悤�Ȗ��V�[��������B�R�D�P�S�E�E�E�Ɖ~�������Ɍv�Z���Ă����ƁA���鎞�_�łP�ƂO�����o�����Ȃ��Ȃ�ӏ�������B�R���s���[�^�[���͂����o������́A�f�B�X�v���[��ɂP�ƂO�@�I�ɕ��ׂĂ����B�ڂ��蒭�߂Ă�����l���̊�͓ˑR�A�B�t���ɂȂ����B��ʏ�̂P��w�i�ɁA�O�����o�����}�`�������т����������炾�B����͐��m�ɉ~�̌`�����Ă����E�E�E�B
���̏�ʂ��Ӑ}������͖̂��炩���B���R�̒��ɐ_�͎���̑��݂��������b�Z�[�W�𖧂��Ɏd�g��ł���B�ނقǂ̉Ȋw�҂ł����Ă��A��������͂ւ̃i�C�[�u�Ȑڋ߂����邱�Ƃ�m��A���͋����߂����B������ւ��Ă����Ȋw�҂ł͂Ȃ��̂��B���̓_�A�{���̒��҂͂��������U�f�����₷��p�����I�n�������Ă���B
���̐��E�́A�P�Ȃ���R���琶�܂ꂽ�ɂ��Ă͂��܂�ɕ��G�Ŋ������B����͉��炩�̑�����̂Ȃ���킴�Ƃ��邵���Ȃ��B�䂦�ɑ����傽��_�͑��݂���B���̘_���͐��������낤���H�����͔ۂł���B
�X���P�P���͂P�N�̑�Q�T�S���ڂł���B�Q�A�T�A�S�̘a�͂P�P�ƂȂ�A�X�A�P�A�P�̘a���P�P�B�X���P�P���ȍ~�̂P�N�̎c������͂P�P�P���B�|�����E�f�ՃZ���^�[�r���̂Q���͂P�P�Ɍ����A�Փ˂����ŏ��̗��q�@�͂P�P�ւ������B�e���Ɋ֘A����New York City, Afghanistan, The Pentagon�̂R��͂��ׂĂP�P�����B���̓��M���ׂ������ɂ͉����Ӗ�������̂��낤���H�����͔ۂł���B
�P�Ȃ���R�ɓ��ʂȈӖ���t�^�������B����͎������̔]�̐����ł���B�i���̉ߒ��Ŋl�������D�ꂽ�p�^�[�����o�\�͂́A�����Ɏ������̑������������F���̊��v�ɂ��Ȃ肤��B
���u�c�m�`�ł��ǂ���{�l�P�O���N�̗��v�]�i�����L��j
���悻�P�O���N�O�A�A�t���J�̓��A�ł��̏����͐��܂�A�����u�ĂĎʖ{�����ꂽ�B�ʖ{�͂悻�̓y�n�։^��A�s����X�ŕʂ̎ʖ{�����܂ꂽ�B�ʖ{�͑S���E�ɎU����č��Ɏ���B�ʖ{�Ǝʖ{���ׂ��ׂ̍��ȍ��قׂ�ƁA�ʖ{�̌n�����������A����炪���ǂ̎}���番���̂����킩��B
���������Ŏʖ{�Ƃ����Ă���̂́A�j���^���x���F���̂��Ƃł���B��n�Ŏp�����~�g�R���h���A�̉�͂́A�l�ނ��ׂĂ̑c�悪�A�t���J�Ő��܂ꂽ�ЂƂ�̃C�u�ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B����A�x���F�̂̑��^��͂́A���̌�̐l�ނ̋O�Ղ�N�₩�ɏƂ炵�������B����܂ł̏펯�͂��Ƃ��Ƃ��h��ς���ꂽ�B
�C�u�̎q�������́A�O��ɂ킽���ďo�A�t���J���ʂ����A���[���b�p�A�C���h�A�A�W�A�A�����Ėk�āA��Ăւƈړ������B���̓r��A������̂����͂����ɗ��܂�A������̂����͂���ɐi�B�ォ�痈�����̂����Ƃ̊Ԃ��y�����������B�A�t���J�ɗ��܂������̂������܂߁A���݁A�l�ނ̂x���F�̂̎ʖ{�́A�P�W�̃^�C�v�ɕ��ނ����B���E�̊e�n�悲�Ƃɑ��^��͂�����ƁA���̂����ǂ̌n�����D�����ɂ���āA�o�A�t���J����ڂ̂ǂ̎}�̎q��������������B�����锒�F�l��A�L�F�l��Ƃ��������ނ͌���I�Ȍ��ł���A���̓����̑��l�������ɈӖ�������B
�����Ƃ������[���͓̂��{�l�̉�͂ł���B�c�m�`���猩��ƁA�o�A�t���J���ʂ������O�̌n�������ꗬ��ĕ������ƁA������x�������������ʂȏꏊ�Ƃ��ē��{�������B���{�������u�l��v�̂�ڂȂ̂��B
���݂�Ȓ��̂����`�퍑����̈㏑�����i�n�ӒB���j
�u����̒��Ɍ����v�u���̋����������v�E�E�E�B����ȕ\���������悤�ɁA���{�l�͌×��A�a�Ȃǂ������N�������̎p��z�����Ă����B�����̒��̃J���[�C���X�g�Ƒގ��@�Ȃǂ��L�����퍑����̌È㏑�w�j�����x���߂��A�����o�ł����B
�P�U���I���A�����{��؎s�t�߂ɏZ��ł����j�̍��V���J�c�A��،��s���҂��������ŁA�c�Q�S�Z���`�A���Q�P�Z���`�A��P�S�O�y�[�W�B�ޗ�̂Ȃ���ŁA��Îj�̎����Ƃ��Ă��M�d�����A�ߔN�܂ő��݂��m��ꂸ�A�Q�O�O�R�N�ɌÏ��s��Ŕ�������A�ȍ~��������̎�œlj����i�߂�ꂽ�B�����A����ƐM�����Ă����U�R��ނ̒��ɂ��āA�C���X�g��Y���A�֘A�̕a�A���̎��Ö@���q�ׂĂ���B
�������荘���N�����Ƃ������́A�����̃g���{�̂悤�Ȏp�ŁA���đ̂ɐN�����A�w���Ɋ����t���ĂƂ��Ŏh���A�Ƃ���B�Ñ��Ȃǂp����Ύ���Ə����Ă���B�u�x�ρv�Ƃ������́A�l�ʂ��t���������ȉ_�̌`�����A���̒��Ŕ�剻���ċC����J�T�ɂ���B�j�������Ƃ����B���̂ق��A������݂̌����ƂȂ邫�Ⴍ�`�̒��⍂�M���o������Ԃ��w�r�̂悤�Ȓ����o�Ă���B
�����́A�퍑���̐l�X�̑z���͂ƁA�����̂ɂɂ����̃C���[�W�Ȃǂ��d�Ȃ荇���A���ݏo���ꂽ�ƍl������B�������́u���̎d�ƂƂ��āA�a�̏�Ԃ���̓I�ɂ��݁A���Â������Ƃ��킩��B�����`���̐j���ÂȂǂ��A�ߐ����{�œƎ��̔��W�𐋂������A����͂��̌����ɂ�����v�Ɛ�������B
���̏����Ɍ���Ă��銴���́A�����\�h�|�X�^�[�Ŏ����ӂ��������`����錻����{�ɂ��ʂ��镔�������肻�����B
�����̐��ݗ́i�ЎR�P���j
�M�҂����挧�m���߂Ă������A���悩��������Ă��ĂȂ�Ƃ������䂭�A���ɂ͂��炾�����o���邱�Ƃ����������B
���͂Ȃ�Ƃ����Ă������{�̒��S�ł���B�R�A�Ɍ��炸�k���ł��l���ł����������A�_�Y���̍ő�̎s��͑��ł���B�܂��A�ό��q�̑�������������ł͂Ȃ��A�����͂��߂Ƃ�����������ł���B�����̒n��̐l�����͏�ɑ��ɊS�������A���̓����ɒ��ӂ��Ă���B
�Ƃ��낪�A���̊S�⒍�ӂ͈���ʍs�ł����Ȃ��B���ɁA���̐����E�s���Ɍg���l�����̎��Ӓn��ɑ���S�͋ɒ[�ɒႢ�B���̂��Ƃ́A�����̒n��ɂƂ��ĐȂ����Ƃł͂��邪�A����ȏ�ɑ��ɂƂ��Ă����ɂ��������Ȃ��B���̊S�̔������A��㎩�g�̐��ݔ\�͂������E���Ă��邩��ł���B
�Ⴆ�A��ʑ̌n�𓌋����Ɣ�r����Ƒ��̃E�C�[�N�|�C���g���悭�����ł���B�������͓����𒆐S�ɍ������H���l�ʔ��B���Ă���B�S�ē������N�_�ɁA�����̊S�ɏ]���Đ�������Ă���B
������͂ǂ����B�Ⴆ�A���挧�̌������ݓs�s�ł�������s���獂�����H�Œ��ڑ��֍s�����Ƃ͂ł��Ȃ��B���ݒ���s���畺�Ɍ��̍��p�܂ł̋�Ԃ��H�����ł���B���N�O�̍������H�̌������̍ہA���̍H�����r����߂ɂȂ�\�������������߁A���{����s�ɗ͓Y���𗊂��Ƃ�����B�������A�c�ɂ̍������H�ɂ͖w�NJS�������Ȃ��悤�������B���̓��H�̖ړI���u���ɏ����ł��������B���邱�Ɓv�ɂ���A���̌�w�n�������I�Ɋg�傷�邱�ƂɂȂ���ɂ�������炸�A�ł���B
���̊S�����̋����ɏI�n����̂ł���A���F���̗͂͒m��Ă���B���{�ɂ��Ă����s�ɂ��Ă������Ȗʐςł����Ȃ����炾�B�����s�����ł����Ώ����Ȏ����̂ł��邪�A�֓��ߌ��͂��Ƃ�蓌�k�A���C�A�M�z�Ȃǎ��ӂ̍L��ȋ��Ƃ��̐l���������t���A���������́u�h�{�v�ɂ��Ĕ삦�����Ă���B���ɂȂ��炦��Γ��R�R�A��k���A�l�����u�h�{���v�����A���͖��������̒n�����������Ɏ����Ă��Ȃ��B
�����ߋE���̎����̂Ƃ͒���I�ɉ���J���ȂǁA�A�g����낤�Ƃ��Ă���B�������A�T�炩�猩�Ă���ƁA���̒��ő�オ�g�b�v���[�_�[�Ƃ��ĐU�镑���Ă���悤�ɂ͂ƂĂ������Ȃ��B�ނ���A�_�˂⋞�s�Ƃ̍j�����⌡���̕����ڂɂ��悤���B
���͂��̓_�ł��A�g�̘g�g�݂��g�債�������������낤�B�����Łu�����ߐ���v����ɐ����A�ߗב�s�s�Ƃ̊Ԃɔg���𗧂Ă邱�ƂɂȂ邩�犸���Ď����o���܂��B�����A�傫�����قǒ��S�Ɍ������d�͂��傫���Ȃ�̂Ɠ����悤�ɁA��オ�S�ƘA�g�̑Ώۂ��g�傷��A���ꂾ�����Ɍ������G�l���M�[�͑�������B
�Ƃ�����A���͎��牟���E���Ă�����ݔ\�͂����܂�ɂ������B����͎���̍L�����[�_�[�V�b�v�����Ă��炢�����B
���o�y�����u�̍��v����킩��A�q�g�̐i���i���{�����j
�ꕶ����P�U�O�Z���`�A�퐶����P�U�R�Z���`�A�]�ˎ���P�T�T�Z���`�A����̂P�V�P�V�O�E�X�Z���`�B
�]�ˎ���ȑO�̎���ʂ̒j�����ϐg���́A�퐶���ゾ�����ʂ��č����B���̗��R�𐼖{�����̌������ɂ����ƕ����퐶�̍������������Ă����B�ꕶ����̉ƒ{�͌��������������A�퐶����ɂȂ��āA���c�̈��ƂƂ��ɏ��߂ē��嗤�������Ă����B�L�x�Ȃ���ς�����ێ�ł���悤�ɂȂ�A���{�l�̕��ϐg��������ƐL�т��B
�������A�ޗǎ���̂W���I�ɂȂ��āA�E�������߂镧����Ă��M���������V�c�̖��߂ŁA�͖�ɕ����ꂽ�B�ȍ~�A���{�l�̐H�삩��A�Ȃǂ̏b�����j���[�������Ă������B����ɔ����A���{�l�̔w�͍ĂђႭ�Ȃ����B���쐶�����ăC�m�V�V�ւƖ߂��Ă����P�Q�O�O�N�B���{�l�͂悤�₭�퐶����̐g����ǂ��������̂��B
���͂Q�O�N�قǑO�܂ŁA�퐶����̈�Ղ���o�y�����̍��͖쐶�̃C�m�V�V���ƍl�����Ă����B�@�������A�ꌩ����ƌ���̃C�m�V�V�Ɏ��Ă��邩�炾�B�������A�ꕶ�l���l���Ƃ����C�m�V�V�ƃV�J�̔䗦�͔��X�Ȃ̂ɁA�퐶����ɂ̓C�m�V�V���W�Q�ƁA���|�I�ɑ����Ȃ�B���{�����́A���̕s���R���ɒ��ڂ����B
�ƃC�m�V�V����ʂ���|�C���g�́A�㓪�����ۂ��_�≺�����̍��̌����ȂǁB�������A���̍��͔������B���ɂ߂�ڂ�{�����߁A�R�N�ԁA�C�m�V�V��̋Ǝ҂̂��Ƃɒʂ��l�߂��B�������ĂP�X�W�X�N�A�啪�s�̉��S�K�c��Ղŏo�y�����O�̃C�m�V�V�Ƃ݂��铪���͂��A�ł���Ǝ��ʂ��邱�Ƃɐ��������B�퐶����ɓ͂��Ȃ������Ƃ�������������ꂽ�̂��B���\��͊Ӓ�˗����������A�ƒ{�����ꂽ���S���ɐZ�����Ă������Ԃ������яオ�����B
����A�����Ȃ��Ȃ�����̓��{�ɂ��Ă͂��������ł���B�]�ˎ���̊G�ɂ�����{�l�݂͂ȏ���ŏo�����ł���B���������������ς��������܂�H�ׂȂ��Ȃ������ƂŁA��ƃA�S���������Ȃ�A�����o�Ă��������Ȃ̂ł���B�����邩�A���Ȃ����ŁA�l�Ԃ̊�̌`�܂ł��ς���Ă��܂��B��������������j�ւ����ɉe����^���Ă����̂���T�������l�Êw�Ȃ�ł͂̋����[�����_���B
���e���r�ԑg�Ɛ��Ɓi�_���B���j
���e���r�́u���@�I���邠��厖�T�U�v�ɂ��u�[���_�C�G�b�g�����v���_�@�ɁA�e���r�Ƃ������f�B�A�̂�����ɑ���c�_������ɂȂ����B�����ł͔ԑg�������芪���l�X�Ȗ�肪�w�E����Ă���B�����A����ɋ��͂��Ă����u���Ɓv�̂��Ƃ��A�Y���ׂ��ł͂Ȃ��B������ς���A���ꂱ�������̖{����������Ȃ����炾�B
���{�w�p��c�́A�ߔN�̉Ȋw�҂̕s���s�ב������āA��N�u�Ȋw�҂̍s���K�́v�����肵���B����̖��ɑ��Ă��A�e���r�ԑg�ɂ�����u�����v���Ȋw�̊����̈�ƂƂ炦�A�Ȋw�҂̗ϗ��I�K�͂����炷�ׂ��Ƃ̉�k�b���o�����B����͕\�ʏ�́A�Ȋw�̐E�\�W�c���烁�f�B�A�ւ̃��b�Z�[�W�ł���B�����A���̎�̔ԑg���Ȋw�҂��t�Ȃǂ��u���Ɓv�̋��͂̏�ɐ������Ă������Ƃ��l����ƁA���f�B�A�ɓo�ꂷ����Ƃւ́u���ӊ��N�v�̈Ӗ�������͂����B���Ȃ��Ƃ��A�e���r�ԑg�ɂ����āu���Ɓv�Ƃ��ăR�����g���邱�ƂɁA���̎Љ�I�ӔC���͎̂��ɓ��R���B������Ƃ����Đ��Ƃ��u�N�q�A�낤���ɋߊ�炸�v�I�ȑԓx����邱�Ƃ́A���̉����ɂȂ���Ȃ��B����͌��ʓI�ɓK�łȂ��u���Ɓv�̓o����������ƂɂȂ邩�炾�B
�����Ŏw�E�������̂́A������l�I���v�̒Nj���_���悤�ȁu�C���`�L���Ɓv�̂��Ƃ����ł͂Ȃ��B�������ӂ��Ȃ��ꍇ�ł��A���ƂȂ肤��B����͂Ȃ����B
����́A������w�p�̐�啪�����������A�^�����ȁu���Ɓv�ł����Ă��A�������삪�قȂ�Ƌ}���ɗ���������ɂȂ�Ƃ������ۂ��N�����Ă���B������u�^�R�c�{���v�̖�肾�B����ŁA���f�B�A���K�Ȑ��Ƃ�T���ɂ��A���Ԃƒm�����K�v���B�������A��\�Z�Ŏ����������ɒǂ��鐻�쌻��ł́A���̂悤�ȗ]�T�͏��Ȃ����낤�B�����ƌ����A�t���I�����A���̐�含�̔����ȍ��ق́A���Y����̐��ƂłȂ��Ɩ{���͕�����Ȃ��̂��B
���̌��ʁA�u���Ƃ̎g���v����������B���f�B�A�ɓo�ꂷ��l���̐������́A���f�B�A�ւ̘I�o�x���̂��̂ŒS�ۂ�����Ƃ����A�z�_�@�Ɋׂ�̂��B�����K�Ȑ��Ƃ��A����̎������u���P�v�Ƀ��f�B�A�Ƌ��������悤�ɂȂ�A���̌X���͍X�ɉ�������A���݂��lj݂��쒀���Ă��܂����낤�B
���j�̃R���N�V�����A���̃R���N�V�����i�|�F�����Y�j
���ԓI�ɂ��u�R���N�^�[�v�Ƃ����ƁA��͂�u�j�������́v�̃C���[�W�������̂ł͂Ȃ����낤���B�m���ɐl���̂��ׂĂ�q����悤�ȁA�C�����̓������R���N�V������z���̂͒j���������B�ł́A���ɃR���N�^�[�͂��Ȃ��̂��B����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B���C�ɓ���̏������W�߂���A�����m�����W�߂���A�f�G�ȃe�B�[�J�b�v��k�C�O���~���W�߂Ă��鏗���͌����ɑ����ł͂Ȃ����B�Â���ŋ��k�����A�V�O�N��O���̃A�C�h�����D����������F�I�̓X�k�[�s�[�̑�t�@���ŁA�L�����N�^�[�O�b�Y����t�ɏW�߂Ă������A�����O�q�͂S�O�N���̃p���_�E�t���[�N�ł���A�p���_�̂ʂ�����݂�p���_�G�̓������������W�߂Ă���Ƃ����B��ʓI�ɒj���͌Ö{��\�t�r���b�A�G���t�B�M���A�͏W�߂Ă��A�m����f�G�ȃe�B�[�J�b�v���W�߂�l�͏��Ȃ��B�܂����̒m�����ł͊F�����B�������R���N�V�����Ƃ��čD�ޕ���ƒj�����D�ޕ���ɂ́A�W�������̈Ⴂ������̂͊m���ł���B
���������������̂́A�u�W�߂�Ώہv�̍��قɂ��Ăł͂Ȃ��B�ǂ��炩�Ƃ����u�W�߂�s�ׁv���̂��́A���̍s���p�^�[���ɂ����A�j�Ə��ɂ͗e�Ղɒʂ������ʁA�����I�ȈႢ������̂��ƍl���Ă���B����͂�����������������������B���ۓI�ɂȂ邪�A���������������͂ǂ����B���̃R���N�V�������u�����̍D���ȃ��m�v�������W�߂�̂ɑ��āA�j�̃R���N�V�������u���E�v���A���邢���u�F���v���W�߂�s�ׂ��ƌ����邩������Ȃ��̂��ƁB���̂��߂ɒj�́A�����āu�D���łȂ����m�v�ł����W�߂邱�Ƃ�����̂��ƁB�u���E�v�u�F���v���W�߂�Ƃ͂ǂ������Ӗ��Ȃ̂��H����Ɂu�D���ȃ��m�v���W�߂邱�Ƃ̓R���N�^�[�Ƃ��ē��R�ł͂Ȃ����H���Ɂu�D���łȂ����m�v���W�߂�R���N�^�[�ȂǁA���݂���̂��Ƃ����^������낤�B�ȏ��������邱�Ƃ́A��ϓ���̂����A�d�v�ȃ|�C���g�Ȃ̂Ŕ�����킯�ɂ͂����Ȃ��B
���Ƃ��R���N�V�����̉��l�ƌĂ��u�؎���W�v���l���Ă݂悤�B���̎q���̍��͏��N�G���ɕK���؎�R�[�i�[�������āA�����܂����u�[���ł������B�؎�ɂ͒���ȗ��j������A���|�I�ɖL�x�ȃo���G�[�V����������B�l�i�������Ȃ��̂���z�ʒʂ�ɔ�����荠�Ȃ��̂܂ő����Ă��āA�����[���Ɠ����Ɏq���ɂ��肪�o���₷���荠�ȃR���N�V�����ł������B�؎�ɂ́u�ʏ�؎�v�Ɓu�L�O�؎�v������B�ʏ�؎�͂������t���╕�����o�����ɓ\����̂ŁA����̋L�O�؎���ʏ�؎�Ɠ��l�Ɏg�����Ƃ��ł��邪�A���ʂ́u�R���N�V�����p�v�Ƃ��Ĉ����邱�Ƃ������B���E�̍��̒��ɂ́A�O�ݖړI�ő����Ɍ����ċL�O�؎�s���Ă��鏬��������B�����ċL�O�؎�͂����Ă��̏ꍇ�A�u�V���[�Y�v�Ƃ��ĉ����g���Ŕ��s�����B�R���N�^�[�̐S���Ƃ��āA�ł���V���[�Y��S�����������Ƃ����Փ��ɋ����̂����ʂ��B�u���������R���v���[�g�v�̗U�f�ł���B�L�O�؎�Ɍ��炸�A�H�߂ȂǁA���Ƃ���u�V���[�Y�v�Ŕ�������邱�Ƃ��������̂́A�}�j�A�̃R���v���[�g�~���h�����邽�߁A�킴�Ƃ������Ă����肷��킯�ł���B���́u�R���v���[�g�~�v�͒j���ɑ����A�����ɂ͂��܂茩���Ȃ��Ǝv���̂����A�ǂ����낤���B
�������ĂU�O�N�㖖�́u���N�}�K�W���v�o�b�N�i���o�[���W�߂Ă����Ƃ��ɂ́A����N�̂��鍆�������ǂ����Ă������炸�A�s���̌Ö{�����قړ��j�������Ƃ��������B�������A���̓��e�����ɓǂ݂��������킯�ł͂Ȃ��̂��B�w�\�����Y�����ƕ��ׂ��Ƃ��ɁA���̍����������Ă���̂��u�C�������������v����ł���B���͂◝���������Ȃ��B�ǂ�ȂɃJ�l�⎞�Ԃ������낤�Ƃ��A�u����v���W�߂��ɂ͂����Ȃ��̂��B�����́A�Q�Ă��o�߂Ă����̍��̂��Ƃ������l���Ă����B���e�́u�ǂ��ł������v�̂ɁA�ł���B���ꂪ���������u�D���łȂ����m�ł��W�߂�v�Ƃ������Ƃł���B��萳�m�Ɍ����Ȃ�A�����́u�}�K�W���v�͂������u�D���v�Ȃ̂����A�u�����߂遁�R���v���[�g����v���Ƃɓ������S�Ɏx�z����Ă��܂��A�u���g�v�̂ق��͂����ǂ��ł��悭�Ȃ��Ă���Ƃ������Ƃł���B
�p���_�}�j�A�̏����������Ƃ��āA�{���Ɂu�p���_�Ȃ�Ȃ�ł��v�W�߂鏗�����ǂ̂��炢����̂��낤���B�����̃p���_�O�b�Y�̒��ɂ́A�����u�����Ȃ��v���̂�����̂ł͂Ȃ����B����ł��u�~�����v�������ǂ̂��炢������̂Ȃ̂��A���ɂ͂悭�킩��Ȃ��B�j�R���N�^�[�̏ꍇ�A�u����Ȃ����ăR���v���[�g�ł��Ȃ��v�ƂȂ�����A�����낤�������łȂ��낤���A�l�I�ȋ����Ȃǂǂ��ł��悭�Ȃ�͂����B�u�R���v���[�g���邱�ƂŁA���E������������v���Ƃ��A���d�v�ȖړI�ɂȂ邩��ł���B�����R���N�V�������l���邤���ŁA�u���E�v���u�F���v�Ƃ������t���g�����̂͂��������Ӗ��ɂ����Ăł���B�j�ɂƂ��ăR���N�V�����Ƃ́A�R���v���[�g���邱�Ƃ��u�̌n�v������������A�v������u���E�v�Ȃ��u�F���v�����������邱�Ƃł͂Ȃ����Ǝv���̂��B�ނ̓R���N�V�������邱�Ƃős��ȊϔO�̃W�O�\�[�E�p�Y�������������悤�Ƃ��Ă���̂ł���B�����ɂ��������l���܂��������Ȃ��Ƃ܂ł͌���Ȃ����A���Ȃ����Ƃ͊m�����Ǝv���B�����̏����ɂƂ��ẴR���N�V�����́A�ǂ��܂ł��u�D���ȃ��m�v�������̎茳�Ɋ�s�ׂ��Ǝv������ł���B
����A�W�߂邱�Ƃɂ���āu���E�̖͌^�v����炴������Ȃ��u�j�v�ɑ��āA���͂������u�����݁v��������������Ȃ��̂��B����͌l�I�ȉ����Ȃ̂����A�j�ɂƂ��ẴR���N�V�����Ƃ́A�u�q�����Y�ނ��Ƃ��ł��Ȃ��v���Ƃւ́u�㏞�s�ׁv�ł͂Ȃ����Ƃ����v���̂ł���B���͎q�����Y�ށA������̐���������̑̓��Ɍ`�����邱�Ƃ��ł���B�j�͎q���Ɂu���́v���邱�Ƃ͂ł��Ă��A���琶���ݏo�����Ƃ͂ł��Ȃ��B�����ł��̑ւ��Ƃ��āu�R���N�V�����v������̂ł͂Ȃ����B�R���N�V�����Ƃ́A�{���I���������@�\���A���m�ɂ���ĕ⊮����s���Ȃ̂ł͂Ȃ����B���������m�͂ǂ��܂ŏW�߂Ă����m�Ȃ̂ł���A��������������a������킯�ł͂Ȃ��B���ꂪ�j�ɂƂ��Ă̖{���I���u�����݁v�łȂ����ĂȂ�ł��낤�B
���̃R���N�^�[�́A�D���ȃ��m�Ɉ͂܂�čK���������B����A�����j�̃R���N�^�[�Ɋ�����̂͂����u�Ɓv�̐[���ł���A���̂����ʂ����߂Ă��u�Q���߁v�ł���B���͈ȑO�A�u�b�N�R���N�^�[�Ƃ��Ă������ȍr���O���ɂ͂��߂Ă�������Ƃ��A��b�̒��Ŏ������x���u�Ȃ�Ŗ{�Ȃ��W�߂Ă��܂����낤�E�E�E�v�ƒQ���Ă������Ƃ��v���o���B�u�Q�O�`�R�O�N��̃A�����J�̃p���v�}�K�W���ȂA�ςݏグ��ΐ����[�g���ɒB���邭�炢�W�߂���ł����ǂˁB����Ƃ��A�����J�̌Ï��X�ɔ������āA���J�Ƀp�b�N���ꂽ���̂��͂�����ł����A�r�j�[���̕����������u�ԁA�G�������݂���ɂȂ��Ĕ�юU������ł��B����Ȃ��Ƃ������ł��ˁB���Ƃ��Ǝ�����������ɁA���\�N������Ă������̂ł�����A�}���ɊO�C�ɂ��炵���{�N���o�J��������ł��B���s����Ƃ����܂��傤���A���̂Ƃ��{�N�́A����Ȃ��̂��W�߂���Ȃ������̏h�����܂�����E�E�E�v
�r�����̏q�����āA�v�킸�g���������܂�v���ɂ���ꂽ�B����ȍr�����ł��邪�A�W�O�N�㖖�ɏ����w��s����x����q�b�g���āA�����Ȃ�Q���Ƃ��R���Ƃ������鋐�z�̈�ł��]���荞�Ƃ��A���͂����S���Ö{�w���Ɏg���Ă��܂��������ł���B���̒��ɂ͈����疜������P�V���I���[���b�p�̎�ʐF���̉�̐}�ӂ�����A���ꂪ���̑咘�w���E�唎���}�Ӂx�i���}�Ёj�̃l�^�{�ɂ��Ȃ����B���������N�̊m��\���ŁA�����w�����u�K�v�o��v�Ƃ��Đ\�������Ƃ���A�Ŗ����͍Ō�܂ŔF�߂Ă���Ȃ����������ł���B�u�����疜������悤�Ȗ{�́A�o��Ƃ͔F�߂��Ȃ��A��Ɠ��������Y�����ɂȂ�Ƃ�����ł���B�{�N�ɂƂ��Ă͕K�v�o��Ȃ̂ɁE�E�E�v���������čr������́u�{�ȂW�߂���Ⴀ��܂����B�s�K�ɂȂ邾���Ȃ̂ɁE�E�E�v�ƁA�[�����ߑ��������B���̊�́A�s���̓�a��鍐���ꂽ���҂̂���ł������B
���E�}�����n�ԂƁA��Ɖ��i�N���p���_�j
���R�[����A�f�q�f�W�^���Ƃ����J���������\����܂����B����P�C�^�C�ł�������O��"�Y�[���@�\"�̖����A"�P�œ_"�̃����Y���A��^�̈��t�Ȃ݂̉掿�ݏo���A�v����}�j�A�����̍����J�����ł��B���̓��R�[�̃f�W�J�����A�g���₷���čD���Ȃ̂ŁA���̐V���i�ɂ�����������̂ł����A����ȏ�Ɋ��S�[���̂́A���̃j���[�X�̌��o����"�≖����"�Ƃ����\�������������Ƃł��B"�f�q"�Ƃ����l�[�~���O���A�f�W�^���ȑO�̖��@�������p�����̂�����ł��B
�����t�B�����́A��������������������������ƁA"������"�������č����Ȃ�܂��B���ꂪ"�≖"�̌ꌹ�ł��B
���A�J�����Ƃ����A�f�W�J���̂��Ƃ������A�t�B�������g���J��������ʂ���Ƃ���"�≖�J����"��"�t�B�����̃J����"�ƌĂ�܂��B�P�O�N���炢�O�A�f�W�J�����o�Ă����Ƃ��́A�������J�����Ƃ����≖�̂��ƂŁA�f�W�J����"�f�W�^���J����"�ƁA��ɂ����Ă��܂����B
�f�W�J����"�≖"�̔���s����ǂ��������̂́A�����R�N�O�̂��ƂȂ̂ŁA�J�������f�W�^���Ƃ����\���Ɉ�a���������̂����R�̂��Ƃł��B�����āA�Â����̂ɂ́A�Â�����"�≖"��������킯�ł��B
���m�ɂ́A���O������A���t���^�����܂��B�p���car�Ƃ����A�N�ł������Ԃ̂��Ƃ��v�������ׂ܂��B�������A�����Ԃ��������ꂽ����̍��A�����"�E�}�Ȃ��n��"(horseless carriage)�ƌĂ�܂����B�N���}�ɂ͔n�������̂���������ɂ́A�����\������̂����ʂ���������ł��B
"�≖"�J�����Ƃ������t�ɂ́A���Ă�"�n��"�̂悤�ɁA�s�ւł͂�����̂́A�m�X�^���W�b�N�ŗD��ȋ������t���������悤�Ƃ��Ă��܂��B
���o�����͂Ȃ�������̂��i��҂҂̌Z�j
���{�̏o�����������葱���Ă���B���q��������ɂȂ��đ���\�N�B����ɉ��P����C�z���Ȃ��B���{����@�����点�ėl�X�Ȏ{���ł��Ă͂��邪�A���ʂ͔����悤���B�o�����ቺ�͓��{�����łȂ���i�����ʂ̔Y�݁B��i���ł��x�T�w�𒆐S�ɏo�����͒ቺ�X���ɂ���B�o�����ቺ�͎Љ�I�Ȗ���o�ϓI�Ȗ��ȂǁA���낢�댾���Ă��邪�A��ʓI�ɐ��������������Ȃ�Ȃ�قǏo�����͒ቺ����悤�ł���B
�Ȃ����������シ��Əo�������ቺ����̂��H����͐l�Ԃ������ł���A�����ł��邱�ƂƖ��ڂȊW������B���Ƃ��Ɛl�Ԃ��܂ޚM���ނ͑��̐����ɔ�ׂďo�������Ⴂ�B�Ȃ��Ȃ��q���̐������������̂ŁA��������̎q���ޕK�v���Ȃ������ł���B�M���ނ̎q���̐������������͎̂q������̂̒��ň��S�Ɉ�Ă��邽�߂ŁA�t�ɚM���ވȊO�̓����͎��R�E�ɒ��ڗ����Y�ݕt���邽�߁A�q���̎��S���͋ɂ߂č����B�����牺��ȓS�C�������Ⴀ��������ĂȊ����ł�������̗����Y�ނ킯���B
�l�Ԃł���̑��Y�������͕̂n�����H�����A�Ȉ�ÁA�V�Ђ̒����A�����̐푈�ɂ��q��������������ŁA�q������������Y�ޕK�v�����������߂��B��i���̏o�����������̂��قړ������R���B���ꂩ�炢���Əo�������グ�悤�Ǝv������A�����̃��x���������āA�q�������ɂ₷����������Ƃ������ƂɂȂ�B�����Ĉ�ʂɏ��̎q���j�̎q�̕������S�����������Ƃ���A���̊��䂦�u��P�Y�v�u�j�n�j�q�v�Ƃ������푰�ۑ���j�̎q���S�ɍl����X��������B
�܂��o�����̒ቺ�͎q���̐������Ƃ̑��֊W�����������ł͂Ȃ��B�v�́u���������̂͌���v�u���������̂͑�����v�u�オ�������͉̂�����v�u�����������̂͏オ��v�Ƃ��������R�@�����W���Ă���B���������o�������l�Ԃ̓s���̂����悤�Ɉ�{���q�ŏオ���Ă����ƍl����������������B���ʂ͐l�Ԃ̑̏d�⌌���̂悤�ɁA�܂��I�V���O���t�A�����`���[�g�A�n�k�g�`�̂悤�ɏオ������A���������肷��̂����R�ł���B�o�������܂�������B�o�����̒ቺ�͒P���u���܂ő����Ă������̂������������v�ƌ��_�t���邱�Ƃ��ł���̂��B
�o�����ቺ�����R�@���Ɋ�Â��Ă���B�������������R�E�̎��Ԃ����āA���q���͓��{�̊�@���Ƃ��A���{�͂������I�����Ƃ��s�������ɐ���R�����e�[�^�[�����͐��^�����̋����҂Ȃ̂ł���B�o�����ቺ��ڂ̓�����ɂ��āA��X���Ƃ�ׂ��ԓx�Ƃ́A��������ɕs������̂ł͂Ȃ��A����������̂܂~�߁A���X���邪�܂܂ɐ�����B�������ꂾ�����B�����ɏo�����������グ��̂ł͂Ȃ��A�l����������Ɍ��������������̐�������T��Ηǂ��̂ł���B
�����͓x���A�j�͈��g�i�����S�j�j
�j�Ə��Ƃǂ����������̂��낤���B�Ȃ�ł����_�̂��̂܂����_����X�^�[�g���Ȃ��Ƃ��̂��Ƃ��l�����Ȃ��M�҂̓A���[�o�ɂ܂łƂ�ł��܂��̂ł���B�A���[�o�ɂ̓I�X�����X���Ȃ��B����͓���O���B���n�I�Ȑ����͕��Ăӂ�����A�肪�o�Ăӂ����肷��B���ꂪ�i������ƁA�~�~�Y�̂悤�Ȏ��Y���̂̐������o�ꂷ��B��̊����^�ł͂Ȃ��A�Q�C�ő��݂ɐ��q����������̂ŁA�i���̉\�����傫���Ȃ�B���̃^�C�v�ɂ��Ă̓��X���I�X�̋@�\�������Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���B���X����̂ł���B����ɐi������ƃI�X�ƃ��X���������ĕʂ̌̂ɂȂ�B�Ƃ����Ă��ˑR���X������ł����āA�I�X�͎��̍�A�h�g�̂܂��B�������A�キ�A�������Z���B���̎�̐����͊T���ė��̐��������A�S�����������A�A�b�Ƃ����Ԃɑ�ɐB���āA�H�Ɗ�@�őS�ł���͂������A���ۂ͌̂̔\�́i�U���́A�h�q�́A�K���́A�m�\�j���Ⴂ�̂ŁA�����c��̂͂����킸���A����Ńo�����X���Ƃ�Ă���B�̂̔\�͂����サ�������ł͗��̐�������B�����łȂ��ƃo�����X���Ƃ�Ȃ��Ȃ�B�����c��̂̓o�����X�̂Ƃꂽ���̂Ɍ���̂��B
����͚M���ނ̂悤�ȍ����Ȑ����ł��ς��͂Ȃ��B�\�͂͒Ⴂ���q�����������A�q���͏��Ȃ����\�͂��������������c������B�܂��ǂ̏ꍇ�ł����X�͊��ւ̓K���͂������A�̗͓I�ɂ͏u���͂͂Ȃ��������͂͂����Ƃ����̂��ӂ��ł���B�I�X�͏u���͂͂��邪�����͂͂Ȃ��B���̓T�^�����C�I�����B�m�~�̕v�w�ȂǂƂ����A�����Ȑ����ł͓��R���X����������A�I�X�����h�Ɍ����钹�ނ�M���ނł����̓��X��������B�I�X�̓A�N�Z�T���[�ł���A�p�S�_�ł����Ȃ��B�ω����܂Ɛm�����܁A���͊ω����܂�����Ȃ̂��B�Ȃ�Ƃ����Ă������̐��E�ł́A�q����ň�ĂāA�H���B��������Ȃ̂ł���B
�ł͐l�Ԃ͂ǂ��Ȃ̂��H�l�ނ��a����������̍��͎ア���݂ŁA�ҏb�A�V�ЁA�ۓ��ɂ���Đ����̂т�̂������ւ����ɂ������Ȃ��B�ƂȂ�Ə�������ł���A�j�͂�͂�A�N�Z�T���[�ł���A�p�S�_�������낤�ɂ������Ȃ��B�����A���H�ƍؐH�ł͂����Ԃ����B��͐��N�j�q�̎d�������A�_�k��̏E�i�̎����E���A���̍���x��A�L��������j�͏��q���ł��ł���̂ŁA�܂��܂������D�ʂɂȂ�B�����A�H���ĐQ�邾���̃T���Ȃ݂̐����𑲋Ƃ��ĕ����Ɩ��̂����̂����悤�ɂȂ�ƁA�j���̂���o���B�Ί�����A�|������A���������A�D�����A�e��̓y�؍H�����s���B��������͎d���Ȃ̂Œj������ɂȂ�B����ɐl�Ԃ��ӂ��Ă���ƁA���݂̑������Ђ�ς�ɋN����̂ŁA����܂��j�̏o�ԂƂȂ�B����ɕ������i��ŁA�@�B�����̎���A����܂��j�̓ƒd��A�@�B�����ɂ͗͂����邵�A���̂ɂ���Ă͏u���͂��K�v�B�܂��A���w���A�͊w���A�d�C���ƁA���ۓI�Ȋw����K�v�A������j�������ł���B�I�X�Ƃ������̂͂��Ƃ��Ƃ����X�̗H�̂̂悤�Ȍ`�ŕ������ꂽ���ۓI�ȑ����ł���A��̕ۑ��ɂ��Ă����X�͗���q����ň�Ă�̂�����ɂ߂ċ�̓I�����A�I�X�̖����͋ɂ߂Ē��ۓI�A�{���ɃI���͎�̕ۑ��ɖ𗧂��Ă���̂��ȂƁA�^�S�ËS�̃I�X�������ɂ������Ȃ��B�]���ē��̒��g�����ۓI�v�l�Ɍ����Ă���̂��Ƃ��߂��Ă��܂����B
�����̂ЂƂA�Z�p�̃A�N�Z�T���[�I���݂Ƃ��Č|�p������B�Ƃ�ł��Ȃ��A�|�p���������ׂĂł���A�Z�p�͌|�p�ɕ�d����A�N�Z�T���[�ɂ����Ȃ��A�Ƃ����咣������Ǝv�����A����Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł���낵���B�Ƃɂ����|�p�Ƃ����X�p�C�X�A�n�D�i������B�����ɂ͊W�̂Ȃ������ɏ�M��R�₷�Ƃ����_���炷��ƁA�|�p���g�[�^���ł͒��ۓI���B�|�p�̒��ł���̐��̋������w�A���p�ł͏��������\������Ă��邪�A���ې��̋������y�i��ȁj�ɂ͏����͏��Ȃ��B
���āA������̔��l�ƁA�_�k�����̓��{�l�Ƃł͂���ς肿�����������āA���Ăł͐̂���j�������B�̊i�����Ēj���������ɑ傫���B���f�B�t�@�[�X�g�Ƃ����̂͒P�ɏ����������̒��ӂƂ��Ĉ����Ă���ɂ����Ȃ��B���Ăł͍��ł���l����Ƃ��x�z���Ă���A�����P���̐������v���Ȃɓn���B�����ɂ��v������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�v����̑��蕨�ōȂ��L���V�ɂȂ�B���Ă̕v�͂܂��Ɏ�l�ƌĂԂɂӂ��킵���B���{�ł͐̂���j�������ŁA�j���̑̊i�������Ȃ��B�������̕������������������B���{�ł͍Ȃ���Ƃ��x�z���Ă���A�v�͍Ȃ���P���̂���������������ďo�Ă������̓���炵�̐����B�Ȃ͂ق������̂�����ɔ����B���{�ł͖{���̎�l�͍ȂȂ̂����A�\�ʏ�͕v����l�Ƃ��ĕ���Ă���B���Ẵ��f�B�t�@�[�X�g�Ɠ����悤�ȈӖ��ł̃W�F���g���}���E�t�@�[�X�g�Ȃ̂ł���B
���E�̂ǂ��ł��n���_��A�i���o�[�����̐_���܂͒j�����B�v�w�_�Ƃ����̂��ꕔ�ɂ͂��邪�A�Ɛg�����Ńi���o�[�����ɂȂ����͓̂V�Ƒ�_���炢�̂��̂��낤�B�����ČÑ�ɂ͏����q�~�R�����āA����Ɏ����I�ȏ���Ƃ��Đ_���c�@�o��A�����I�ɂ�����ƂȂ����̂͐��ÓV�c�i�݈ʂT�X�Q�`�U�Q�W�j�ŁA���̌���c�Ɂi��ɍēo�ꂵ�ĐĖ��j�A�V���A�����A�F���i��ɍēo�ꂵ�ď̓��j�Ə��邪�����A�F���̕�̌����c�@�������I�ȏ��邾�����B�C�M���X�ɏ������o�ꂷ��̂͂P�T�T�R�N������P�O�O�O�N����̘b�ł���B���ɑ��A�R�k�𐭎q�ɂ��Ă��P�R���I�̏��߂ł���B������Ǝ��������P�O���I������P�P���I���߂ɂ����Ċ���A���`���ɏ]���āA�Q����G�����������ƂȂ��|���A�a��|���A���ߎE�����Ƃ��������ҁA�b��O�i�P�Q���I�j�Ȃ�Ă����̂����Ăɂ͂��Ȃ��B�W�����k�_���N�i�P�T���I�j�ɂ��Ă��w�����ł����ĕ��҂ł͂Ȃ��B���݂̏��q�v�����X�𗽂��l�C���W�߂��Ƃ��������o���P�V�T�O�N���̗��s���Ƃ�������A���Ăł̓W�����E�W���b�N�E���\�[�A�q���[���A���H���e�[���̎��ゾ�B���{�̏��͐̂��狭�������B�풆���̐H�Ɠ��ł����͋��������B�푈���A��������ăC�J�_�ŕY�����ď��������A�Ƃ������A�Y���҂̃��[�_�[�ƂȂ������w���̏��̎q�̘b�B�A�i�^�n���Ƃ������l���łT�l�̒j���]���ČN�ՁA�f��ɂ܂łȂ����A�i�^�n���̏����A���ŋ߂͓��q�@���̂Ő����c�����S�l�̏����B��q�͒j���̕������������̂ɁA�����c�����̂͏��������Ƃ����̂̓V���b�L���O�������B
�Ƃ���ŁA���ꂩ���͂ǂ��Ȃ邩�Ƃ����ƁA������������܂��܂������D�ʂ��������Ă���B�����Ԃ������Ⴞ���A���ׂĂ̋@�B���}�C�R���E�I�[�g�ɂȂ�A�ؓ��^�����s�v�ɂȂ�̂ŁA�ؗ͂��キ�Ă������͂̂��鏗�����L���B���]�J���̕����������B���ꂩ��̓R���s���[�^�[�̎���A�V�˓I�ȑM���͕K�v�Ȃ��B�ǂ����Ă��K�v�Ȃ�R���s���[�^�[�ɂ��̂悤�ȋ@�\���������邱�Ƃ��ł���͂����B�������Ȃ̂̓R���s���[�^�[�Ƃ̍��C�̂悢�������B����̓^�C�s�X�g�̎d���ɂ����Ă���A�����ɗL�����B�L�[�{�[�h�̑���͎w���ׂ����Ȃ₩�ȏ��������B������p�Ƃ���L�[�{�[�h���̂��̂����^���ł���B����ɉ������͂̃R���s���[�^�[�ƂȂ��Ă��A���ēx�̓_�Œj����菗�����L�����B�����Љ�̓R���s���[�^�[���x�z���邪�A�R���s���[�^�[���x�z����̂͏����ł���B�R���s���[�^�[�J���҂͏������S�A�͎d���̓��{�b�g�����B�j���̓��{�b�g�ɕs�����ȗ͎d���A���邢�̓��{�b�g�ɂ�点��ƃR�X�g�A�b�v�ɂȂ�̂Ől�Ԃɂ�点���������オ��Ƃ����悤�ȎG�p���B�����炭�Ǝ��玙���j����ȂƂȂ�A�v�͈�Ƃ̎�v�Ƃ��āA���邢�̓A�N�Z�T���[�A�p�S�_�I���݂Ƃ��Đ�����ۏ���邱�ƂɂȂ邾�낤�B���̑��A�|�p�͒j���̂��̂ɂȂ�\�����o�Ă���B�Ǝ��A�玙�ɂ���قǂ̎��Ԃ��Ƃ��邱�Ƃ͂Ȃ��̂ŁA�]�������Ԃ��|�p�ɐU�������B����̔_�k���S�̖��J�����̊Ԃł́A�����Ђ����瓭���A�j�͂������ƁA������ׂ�ƁA�x��ƁA�|�p�i���ɖ�������B�����Љ�͓����悤�ɂȂ�ɂ������Ȃ��B
���n��Փ��ƈ��̑r���̊W�i�g�����j
�]��c�m�`�Ɋւ���ŐV�������Љ��o���G�e�B���Ȋw�ԑg�i�u�T�C�G���X�E�~�X�e���[�v�t�W�e���r�j�ŁA�u������ˑR�|�p�Փ��ɋ����悤�ɂȂ�A���̂����Ɉ����������j���ɂ��Ă̘b�v�Ƃ����̂�����A�����[�������̂Ō��Ă݂��B
��l���̓A�����J�̂Ƃ���U�O��̒j���B�]�����œ|��A��p�����ĉ��Ă���A�i����܂ł͑S���A�[�g�Ƃ͖��W�̈�J���҂̐����������̂Ɂj�킯�̕�����Ȃ��n��Փ��ɋ����悤�ɂȂ�A�~�܂�Ȃ��Ȃ����ƌ����̂��B�����̕Lj�ʂɊ�ȊG��`���A�S�y�����˂ĕs�C���Ȓ��������A���ɂ͎�����������B�����ʂ�Q�H��Y��A�Ђ�����ǓƂ��ǖقɑ��葱����B���̎p�͊����Ɂu�|�p�Ɓv�Ȃ̂����A��肪�ЂƂB���ꂪ�u�|�p���[���v���Ƃ������ƁE�E�E�B
���̔ԑg�ł́A�����]�́u��Q�v�Ƒ����A�n��Փ����肪��ɗ����āA������ւ̈����A�F�B�Ƃ̕t���������A�q���ւ̋��������S�Ɏ����A�ǓƂ�����D�݁A���������藎��������N�ƟT���ڂ܂��邵������ւ��A�Ƃɂ����������̎Љ�I�s�K���҂ɂȂ��Ă��܂������Ƃ��A��p�ɂ��]�̈ꕔ�̌������h�[�p�~���̉ߏ���o���n��Փ��̖\�����}���̕s�S�����i��Q�E�E�E�Ɖ������B
�@
���[��B�ł��A������Č|�p�ƂƂ��Ă͂������ʁi�H�j�̐�������Ȃ��낤���B�ǂ�����Q�Ȃ̂��T�b�p��������Ȃ��B�����قڂP�O�O�����̒ʂ肾���i�j�B
�����A�ꌩ�u�v���X�v�̐��i�v�f�̂悤�Ɍ�����u�n��i�|�p�j�Փ��v�Ƃ������̂��A�i���͔]�̃V�X�e���s�S�ɂ���āj�ǓƕȂ�l�Ԍ����E�N�ƟT�̌��⑽�d�l�i�E�Љ�I�s�K���Ƃ������u�}�C�i�X�v�̐��i�v�f�ƕ\����̂̂悤�Ɍ����E�E�E�ƌ����̂́A�b�Ƃ��Ă͂�����Ɩʔ����B���Ԃ�q�˔\�r�Ƃ����̂́A���ʂ̔]�Ƀv���X�Ƃ��đg�ݍ��܂��lj��@�\�ł͂Ȃ��A�}�C�i�X�̌���������₤���߂ɔ�������⏕�@�\�Ȃ̂��B������A�ڂ������Ȃ��Ɗ����s���Ȃ�A���t�������ƕ\���͂͌������܂���A�]�݂��Ȃ��قǖ��͍L����A��������Ȃ��قLj��͐[���Ȃ�B
�u���������q�|�p�r���q���r�������Ƃ���ɂ��悤�Ȃ�āA����ł͂���܂蒎���ǂ������Ȃ����ˁv�E�E�E�ƁA���������Ĕ��ސ_�̐�����������i�j�B
�����j�͊C�ł���ꂽ�i��҂҂̌Z�j
�s�s������������O�ɂȂ��Ă�������B�������𒆐S�ɕ������l���Ă��܂��B�������������ˈȗ��B���j�̒��S�͊C�������B���ɊC�Ɉ͂܂�A�ʐς̑啔�����R����߂���{�́A�嗤�̂悤�ɕ��암�ő�K�͂Ȕ_�Ƃ�q�{���c�ނ̂���������B�Â�������{�l�͂��̋��菊���C�ɋ��߂Đ����Ă����̂ł���B
�ŋ߁u���H�v�̖�肪�N���[�Y�A�b�v����Ă���B���ʂȓ��H����������B���≢�Ăɔ�ׂ�Ɠ��H�̐������x��Ă���ƁB���H�̐��������Ă��x��Ă���͎̂����ŁA����͐����I�Ȗ��ł͂Ȃ��A���{�͒��炭�^�A�E��ʂ̒��S�͊C����������ł���B���[���b�p�̂悤�ɂȂ��炩�Ȓn�`�����X�Ƒ����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�R����J����̒n�`�ɓ��H������Ƃ����͎̂���̋Ƃ������B�܊X���ƌ����Ă��������ɖт̐������悤�Ȃ��̂ŁA�ƂĂ����H�ƌĂׂ�悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ������B
�^�A�E��ʂ̒��S�͊C�Ƃ��������ゾ�����͉̂������{�����ł͂Ȃ��B�l��͕�������͂̂قƂ�ɕ�����z�����̂́A�������̊m�ۂ�_�Ɨp���̒��B�ȊO�ɐ���g���ĉ^�A�E��ʂ��X���[�Y�ɂ���_�����������B����̉^�A�E��ʂ������Ƀn�[�h�Ȃ��̂ł��邩�͗V�q���̐���������Έ�ڗđR�B�Ђ邪�����Đ���ł��u�d�����́v���u��ʂɁv�������u�����ցv�u�����v�u�����I�Ɂv�A���E�^�����邱�Ƃɒ����Ă����B�Ȃ��Ȃ����́A�����A�����Ƃ��������R�̕����I�G�l���M�[�ɂ���āA�ŏ����̃G�l���M�[�ōő���̗A���E�^�����\����������ł���B
�V���N���[�h���m�g�j�̃h�L�������g�ȂǂŗL���ɂȂ����������ŁA�����̌𗬂������������㒆�S�������悤�Ȉ�ۂ�^���邪�A���͓����̌𗬂��C�����S�������̂ł���B���D�Z�p�ƍq�C�p�͍��̔ɉh�Ɍ������Ȃ����̂ƂȂ����B����͋�𐧂�����̂��A���E�𐧂��邪�A�̂͊C�𐧂�����̂����E�𐧂����̂ł���B�k������{������ɂ����Ă���i���Ȃ̂͑��D�Z�p�ƍq�C�p�����B�����������ł���B
�k������{�łȂ����D�Z�p��q�C�p�����B�����̂��B����͊C��̂���������n�悾��������ł���B���{�̗�Ō����ƃ����X�[���ŊC�オ�����₷���A�C�������G�i���{�̊C�͂��傤�ǒg���Ɗ������Ԃ���n�_�j�B�����Ő_���������āA�G�̑D�����Ƃ��邪�A���D�Z�p�A�q�C�p�������ł����ƁA���{�̊C�̍q�s�͋ɂ߂Ċ댯�ł��邱�Ƃ��ے��I�ɕ�����Ă���B
����l�����j�𗤏㒆�S�ɍl����悤�ɂȂ����̂��ߑ㉻���āA�s�s�����i��ŁA�����̒��ɂ�����C�̖������������������B�������ŋ߂̗��j�w�͈�Ք��@�ɂ��Ȋw�I���Ŕ��B�����o�܂�����A��ՂƂ����Ă������c��Ȃ��C���A���j�̋L�����牓������͖̂������Ȃ����ƂȂ̂ł���B
���C�͂Ǝ��́i�ʍ�r���j
���́A��\�㔼����Â������ɋ����������n�߁A������ʂ����u����v�Ƃ������Ƃ̊y������m�����B
�Ⴆ�A�㓙�̖��̕z���u��z�v�Ƃ������A��z�ɂ����낢��Ȏ�ނ�����B�{�ÁA�z��A�\�o��z�ɋߍ]��z�ȂǁB�����͐D��ꂽ�Y�n�ɂ���ē���������B���͂��Ƃ��A�ŏI�I�Ȃ��̂̌��ɂ߂́A���ׂ̍������r��̈Ⴂ�A���Ȃ킿�@�ۂ̃��x���B���[�y�̐��E�ł���B
���ꂪ�����Ȃ���̂ł���̂����u�������v���߂ɂ́A�m���⊴���͂��Ă����A�܂��͂悭���Ȃ���Ύn�܂�Ȃ��B������u�C�́v���u���́v�̂��邱�Ƃł�����B
���̂̍ו��܂ł�����Ƃ������Ƃ́A�������炳��ɐ[�����E��m�������ɂ����Ƃł�����B�������A����͋C�͂Ǝ��͂��[�����Ă���Ⴂ�����ɕȂ����Ă����˂A���������ł��邱�Ƃł͂Ȃ��B�Ⴂ���Ɉ�̂��̂Ɏ������A�����̖ڂł悭���A�G�������G�̋L���͋M�d�ł���B�����ނ����������Ƃł͂Ȃ��B������߂܂���đ�Ɍ����B���̂�����Ƃ����̂́A�q���̍��̂��������o������n�܂���̂�������Ȃ��B
���̂��Ƃ́A���t�ɂ����Ă��u�����v�ɂ����ʂ���B���t�Ƃ��߂����Ȃ�A�����̉����ו��܂Œ��J�ɒ����Ƃ������Ƃ��A�����s���A�����Ď��Ԃ̂����Ղ肠��Ⴂ�����ɐg�ɒ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�����́A�Ⴂ�ƌ�����N����߂������ɁA�����������Ƃł�����B
�����ʂɂ��Ă̎��R�Ȋw�I�l�@�i��҂҂̌Z�j
���ʂƂ͉����H�Ɩ��ꂽ�ꍇ�ԓ�����̂͂ƂĂ�����B����͐l�ԎЉ�ɋN������L�̌��ۂł���A�Ȃ�����ʂɎЉ�Ȋw�I�Ȏ��_�ŋc�_���邽�߁A�q�ϓI�ɕ��͂��邱�Ƃ�������߂��B�����Ŏ����Ɏ��R�Ȋw�I�Ȏ��_�ō��ʂ��l�@���Ă݂Ă͂ǂ����B�Ƃ������Ƃ���Ă݂����B
���ʂ͐l�ނ������W�����A�ߑ㉻���i�ނ��Ƃɐ[�܂��Ă����B�Ⴆ�Ύ��Y���s�l�͂��Ƃ́u���Y�v�Ƃ������̏@���I�s�����i��Վi�ł������B���ꂪ�ߑ㉻����ɂ���˖��ƂȂ����B�u�q���v�����Ƃ͌��P���������q�����菜���E�\�ł������B���ꂪ�ߑ㉻���Đg�����Œ肳��A���ʂ̑ΏۂƂȂ����B
��ʂɐl�Ԃ̂��������������ɂȂ�E�ƂقǍ��ʂ̑ΏۂƂȂ�B�Ⴆ�Δ��t�i���j�A�H�����H�i�H�j�A���Y���s�l�i�E�l�j�A���|��ƈ��i�r�A�A�r�ցj�B�����Љ����l�Ԃ́A�l�Ԃ��{�������Ă��铮�����������ɂȂ邱�Ƃ����Ƃ���������B�u���v�͂���炵���A�p���������A�j���p���ƕ��A�\�͎͂c���A����A�l���N�Q���Ƃ��ċ��e����B�����̔��˂͐l�Ԃ����������̔ے肩��n�܂��Ă���A�������i�߂ΐi�ނقǓ������̔ے肪�i�ށB�������l�Ԃ������ł��邱�Ƃ͂ǂ�Ȃɕ������i��ł��ς�肪�Ȃ��B���̂��Ƃ̘������������ʂɂȂ���̂ł���B
���ʂɂ��čl����Ƃ������Ƃ́A�����ɂ��čl����Ƃ������Ƃ��B���̏ꍇ�̕����Ƃ͉����Ƃ����ƁA����͕����̏ے��Ƃ��Ă̓s�s�A�����Ē����W���I�ȏW�c�����ɏW���Ǝv���B
�l�Ԃ͍ŏ�����s�s�����A�W�c���������Ă����킯�ł͂Ȃ��B�A�t���J�̌���Ɏn�܂�l�ނ̏��͎��㐶���������B���ꂪ�n��ł̐����Ɉڂ�A�ړ����n�܂�A�S���E�ɎU����čs�����B�����Ă悤�₭��͂̂قƂ�ɍ������낵�A�s�s�����A�W�c�������n�߂�̂ł���B
�l�ނ����ォ��n��ւƐ����̏���ڂ����̂́A�n��ɐ�������C���p���A���[�A�[�u���A���C�I���A�L�����A�n�C�G�i�A�]�E�A�J�o�Ƃ������������ώ@���A���̐��Ԃ������ꂽ���̂Ǝv����B�l�ނ͌�������w�K�\�͂ɒ����Ă����B���̐����̐��Ԃ�������āA���g�̐����͈͂����L���Ă������̂ł���B�l�ނ̐��E�K�͂̑�ړ�������ԓn�蒹�A�C����V���鋛�����Ƀq���g�����̂Ǝv����B
�ł͓s�s�����A�W�c�����͉��Ƀq���g���̂��낤���B����͐��������I���a�̐��ԂɃq���g���̂ł͂Ȃ����Ǝv����B�I��a����镡�G�����͐l�Ԃ̑����s�s�Ǝ��Ă���B�܂������a������R�����A�����I������J�������B�����I�i�a�j�_�Ƃ����s���~�b�h�^�̎Љ�\���͂��̂܂ܐl�ނ������W���I�ȎЉ�\���ւƎp���ꂽ�B���ꂪ�W�c�����������ōł������I���u�������v�Ƃ��đ�����ꂽ�̂��낤�B
�����I��a�������Ă����c�Љ�̍\�}�����̂܂܁u���ʁv�Ƃ��Đl�ނ̎Љ�Ɏp���ꂽ�B�����炭���ꂪ���ʂ̌��_���Ǝv����B�Ȃ����̐��͂�҂҂̌Z�̃I���W�i���ł���A�ǂ̘_���A�w���ɂ��ڂ��Ă��Ȃ��B���␢�E�͍L���B�����悤�ȍl���������w�҂��ߋ����l���͂�����������Ȃ��B�}���K�`�b�N�œ˔�ȍl���������A�l�I�ɂ͌��\�u�v�͒ʂ��Ă���Ǝv���B
���L���V�^���e���A�����͓V���̑�p�f�i��҂҂̌Z�j
�L���X�g���̓`�����P�T�S�X�N�B�ȗ��T�O�O�N�߂��ɂȂ邪�A�v�����قǃL���X�g���̐M�҂͑����Ă��Ȃ��B�`���̎��オ�Ⴄ�Ƃ͌����A�_�ЂƂ�������̋�ʂ����Ȃ��قǍL�܂��������Ƃ͂��炢�Ⴂ���B��_���̍l�����Ȃ��܂Ȃ��Ƃ����̂����邩������Ȃ��B�������{���̗v���̓L���X�g���̕z�������̗��j�ɂ���̂ł͂Ȃ����낤���B
�L���X�g���͓`���ȗ��A�L�b�G�g�A���얋�{�Ȃǂ�����x�ƂȂ��������e�����Ă���B���̃L���V�^���ւ̍���̐��܂����͌㐢�Ɍ��p�����قǂł���B���{�̂悤�ɔ�r�I�@���Ɋ��e�ȍ��łȂ������܂ł̋��۔������N�����̂��낤���B�w�Z�̗��j�̎��Ƃł́u�����I�Ȑg�����x�̏�ɂ�����������Ă��������̌��͎҂��A�l�Ԃ̕���������L���X�g���̕z����K�v�ȏ�ɋ��ꂽ���߁v�Ƌ�������B
�m���ɂ����������ʂ͂�������������Ȃ��B���������R�͂��ꂾ�����낤���B�܂��l���Ȃ�������Ȃ��̂��L���X�g���̕z�������͓��{�����ōs���Ă����킯�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�L���X�g���̕z�������͑�q�C����̌㉟���������āA�S���E�I�K�͂ōs���Ă����B���������̕z�������͎�����Z�����̑�ʋs�E�A���D�A�����ȂǂƋ��ɍs���Ă����̂ł���B�k�ẴC���f�B�A���A��ẴC���f�B�I�A�I�[�X�g�����A�̃A�{���W�j�B�n��ɂ���Ă͉i�炭�h���Ă����Ñ㕶����鍑�����[���b�p�l�ɂ���Ėłڂ��ꂽ�Ƃ��������B�G�g�⓿�얋�{�����ꂽ�̂͂܂��ɃL���X�g���̕z�������Ƌ��ɍs���Ă������[���b�p�l�ɂ��s�E�y�т��̎x�z�ł������ƒf���ł���B���{�̗��j����ł͂Ȃ����L���V�^���e���ɐG��Ă��A���[���b�p�l�����E���ōs���Ă����s�E�s�ׂɂ͂��܂�G����Ă��Ȃ��B
�܂����얋�{�������ԍs���Ă����u�����v�ɂ��Ă��A�����̗��j�Ƃ͓��{�̕������֒����A���E�̒����Ɏ��c���ꂽ�����̂悤�ɔᔻ���Ă����B���������v���ɂ��́u�����v�̓��[���b�p�̐A���n�x�z���瓦��邽�߂����{�̖h�q�����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B���ۓ���R�O�O�N�B��x����Ƃ����[���b�p�̐A���n�x�z���Ă��Ȃ��B�C���h�⒆���Ƃ������l��͕�����S���Q�̃A�W�A�̑卑�����Ă̐A���n�x�z���Ă������Ƃ��l����A�u�����v�͉p�f�ƌĂԂׂ��{��ł������낤�ƍl����B�������A�����J�R��n�ɗ����Ă悤�₭�U�O�N�̕��a���ۂ���Ă��錻����{�ƈ���āA�ǂ��̍��ɂ����炸�A���������Ŗh�q������p���ł����̂͋����ɒl����B
���ėƐ�����͖̂����ېV�ȍ~�̂��ƂƎv��ꂪ�������A���̓L���X�g����e�������G�g�A���얋�{�̍����烈�[���b�p�Ƃ̐킢���n�܂��Ă����̂��B���Ƃ��Ĉ��҈��������A�G�g�A���얋�{�������{��N���҂��������̂��l�����Ƃ�����ʂ������Ă������Ƃ͎������낤�B
���u����̕����D�v�]�i�����G���j
�u�����D�v�����������낤���B
�����������珺�a�R�O�N��Ɏ���܂ŁA�u�����o�ŁE�W�����s�v������Ɏ�ɉ���̏����w�Z�ŗp����ꂽ���́B�w�Z�ŕ������g���ƁA���Ƃ��Ď�Ԃ牺��������ꂽ�؎D�̂��Ƃł���B�D�ɂ́u�������v���邢�́u�킽���͂ق�����������܂����@����������͂����܂���v�ȂǂƏ�����Ă���A�����ȉ��ꓯ������Ƃ��Ĉ��̏ے��Ƃ���Ă���̂��B
�Ƃ��낪�{���ɂ��A�����D�͖@�߂��ᓙ�Œ�߂�ꂽ���̂ł͂Ȃ��A����̋�������������u���̍��^���v�̂悤�Ɏn�߂��炵���B�D�����������k�͎��̈ᔽ�҂��o��܂ł����Ɖ����Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����Ŏq�������͓������̑��݁A�u�A�K�[�i�ɂ��j�v�Ƌ����ĎD��n���B�w�Z���o��Ε��������R���������A�D�������A���Ĉᔽ�҂�T���҂��B�t�ɂ킴�ƕ������g���A�D�������Ėڗ��Ƃ��Ƃ���q�������炵���A�����͂܂�ŃQ�[���̗l����悵���̂ł���B
������������ɂ͋������由�D���x�����݂��Ă����B�g���u���Ȃǂ��N�����Ƒ�l�����D��������������B���̎҂ɂ͔������ۂ����A���ꂪ���̉^�c�����ɂȂ��Ă����Ƃ����B���D�̏z�����������x���Ă����̂��B�����Ĕނ炪�W������w�Ԃ̂��A�{�y�Ƃ̓����ł͂Ȃ��A������̕W����i�m����j��b���㗬�K���ƑΓ��ɂȂ邽�߂������B�������������m��Ȃ��{�y�̕����l���A���������������ׂ��ȂǂƏ���ɋ��e�������Ƃ���A�����D�́u�����I�Ȑ��i��L���锱�D�v�Ɖ��߂����悤�ɂȂ����̂ł���B
���͂ӂƉ���̕ČR��n�߂��ɂ��������w�Z�̂��Ƃ��v���o�����B�u�������I�v�Ɩ{�y�}�X�R�~���J��Ԃ����A�q�������̊Ԃł͑������������ł��̐퓬�w���̋@��Ă�V�т����s���Ă����B�s����̒�܂�Ȃ���n�����ЂƂ̎D�̂悤�Ȃ��̂�������Ȃ��B
���l�ԋ@�B�_�i�����S�j�j
�M�҂͐l�ԂƃT���Ƃ̊ԂɌ���I�Ȃ������͂Ȃ��ƐM���Ă���B�T���̒��ɂ̓o�[�e���_�[�Ƃ��āA�b��̏���Ƃ��āA�l�Ԉȏ�̓��������Ă���G�˂�����B�l�Ԃ̒��ɂ̓T���ȉ��A����A�A�����R�Ƃ����̂���������B
�l�Ԃ̃J���������̒��ōł�������̂́u�l�Ԃ͈ӎu�������Ă���v�Ƃ������Ƃ��낤�B�l�Ԃ͎����̈ӎu�ɏ]���čs�����Ă���Ǝv���Ă��邪�A����͑�܂������A�l�Ԃ̍s���͂��ׂĕ����I�A���w�I�Ȕ����̏W�ςƂ��Ď����I�Ɍ��܂��Ă������̂ł����āA�ӎu�Ƃ����悤�Ȓ��ۓI�ȗ͂̂�����]�n�͂Ȃ��̂ł���B�s���̃p�^�[�����A�����ɂ��ӎu�������Ă���ƌ����邾���̂��ƂȂ̂��B������������ׂĂɋ��ʂ���B
���������������߂�͎̂q���̂��Ƃ��l���Ă���킯�ł����ł��Ȃ��B�����A�G�߂ƃz�������̊W�ŋ����M��������A������₵�Ă���ɂ����Ȃ��B���Ɠ����`����������ł��v���X�`�b�N�ł������̂ł���B����␅�ł������̂ł͂Ȃ����H�m���ɂ����ł���B�����������������B�������A����ł͎�̕ۑ��͕s�\�Ȃ̂Ő�ł����B���ŋ����₵���������������c�����̂ł���B���͑����炱�낰�o�������͌����������Ȃ��B�q���̂��Ƃ��l���Ă���킯�ł͂Ȃ�����ł���B
�q�i�ɉa�����Ƃ����s���ɂ��Ă��܂����������ŁA�F�Ɠ����������Ă���v�����f���ɂł��u���L�̃I���`���ɂł��a�����B�t�ɖ{���̃q�i�ł����Ă������炱�ڂꗎ������A����͂����P�Ȃ�S�~�Ȃ̂ł���B���ׂĂ͒P���ȕ����I�A���w�I�Ȕ����̏W�ςɂ������Ȃ��B
�A���ɂ��Ă��͓������B�I�⒱���Ђ������悤�Ƃ��ĐF�Ƃ�ǂ�̉Ԃ��炩���Ă���킯�ł͂Ȃ��B���������邾���ł���B���͋@�B���������B�r�k�͎����̈ӎu�ŁA�����ɗ�Ԃ������ς��đ����Ă���킯�ł͂Ȃ����A���{�b�g���l�Ԃ̂���������f���ē�������Ă���킯�ł��Ȃ��B
�v����ɁA�l�Ԃ��T�����A���������A�A�����@�B���A����y���A�_��������C���A���q�����q���N�H�[�N���݂�ȓ����ł���B������t�ɁA�l�ԂɈӎu�⊴�����ƔF�߂�Ȃ�T���ɂ͂������A���q��N�H�[�N�ɂ��ӎu�⊴���F�߂Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��̂ł���B
���u�i���Љ�v�Ɓu���v�i��҂҂̌Z�j
����\�����v�̌��ʐ������u�i���Љ�v�ɔᔻ���W�܂��Ă���B�u�i���Љ�v�͂��̎�����A�ǂ��̍��ł����邱�Ƃ����A�Ȃ������߂āu�i���Љ�v�����ɂȂ�̂��B�܂��͌��݂̓��{�ƍ��x�o�ϐ�������Ƃ̔�r���猟���Ă݂����B
���x�o�ϐ�������ɂ��u�i���v�͂������B���������݂́u�i���v�����Ђǂ������B���V���̉f��u�V���ƒn���v�i�P�X�U�R�N�j�A���c�f���̉f��u�Q��C���v�i�P�X�U�T�N�j������A���̂Ђǂ��͈�ڗđR�ł���B���������x�o�ϐ�������ɂ��u�i���v��������������u��]�v���������B�撣���Ďd��������Ε����Ƃ����Љ�̕��͋C���������B�����Ď����撣���Ďd���������҂͕���Ă������̂ł���B�Ȃ��Ȃ���{�͉E���オ��̌o�ϐ����𑱂��Ă�������ł���B
����������͂ǂ��ł��낤���B�����̂悤�Ɋ撣���Ďd��������Ε����̂��낤���B���������ɕn����̃X�^�[�g�̍��x�o�ϐ�������ƈ���āA����͑����ɐ��������̍����A�������ꂽ�Љ��̃X�^�[�g�ł���B���������{�͒����ɉE��������𑱂��Ă���B
���{�l�̐����̋��菊�ɂȂ��Ă���u��Ɓv�̎��Ԃ�����킩��₷���B���i�C���ǂ��Ȃ����A�ǂ��Ȃ����ƌ����Ă���B�ٗp���ȑO���͐ϋɓI�ɍs���悤�ɂȂ��Ă���B���������̎��Ԃ͂قƂ�ǂ��Ј��ł���A���Ј��̌ٗp���i�킯�ł͂Ȃ��B�܂��ȑO�̓X�|�[�c�`�[����X�|�[�c�I�����Ƃ̍L�����Ƃ��ĕ����邱�Ƃ������������A�i�C���������݂ł��X�|�[�c����̏k���͑����Ă���B���������o�u������ɂ̓��Z�i�i�|�p�x���j�Ƃ������Ƃ�����Ă����B���͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��낤���B�L������؋C�����B�e���r�ԑg�͋��̂������ĂȂ��悤�ȃg�[�N�ԑg���肾���A����̓X�|���T�[�ł���u��Ɓv���e���r�̍L���ɂ������������Ȃ��Ȃ��Ă���؋��ł���B
��Ƃ͐̂ɔ�ׂ�ƒ����ɂ��������Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B�̂̃T�����[�}���͊�Ƃ��o���o���蓖���ɉ��Ƃ��ł������A����ł́A�����ǂ��납�o���ɍۂ��Ď������悤�����邱�Ƃ�����B���̂悤�Ɏ���͉E��������ł���B�������E��������̒��Łu�i���v���L�����Ă���B�܂��ɂ����Ɍ���́u�i���Љ�v���ᔻ���W�߂�ő�̗v�������邩�Ǝv����B
�ł͂Ȃ����{�̊�Ƃɂ��������Ȃ��Ȃ����̂��B����ɂ͂܂��ꌩ�u�i���Љ�v���l���邤���ʼn��̊W���Ȃ��悤�Ɏv�����u���v�ɂ��čl���Ȃ��Ă͂����Ȃ��B���{�Ō������͂P�X�S�T�N�B�����m�푈���I�������N�ł���B�����m�푈���I���������_�ő���E��킪�I������̂�����A���E�̐����P�X�S�T�N�B���Ɠ��{�l�͎v���Ă���B�Ƃ��낪�P�X�S�T�N�̎��_�Ő����}�����͓̂��{�����ł���B���̑��̍��X�͑���E��킪�I��������Ƃ��A�V���Ȃ�푈�𑱂����̂ł���B�u���v�ł���B
���̗��̂������ő����̍��X�͌R���ʂɃG�l���M�[���₵�A�o�ς�敾�������B���Ƀ��[���b�p�͗��ɉ����A�Q�̐��E���̃_���[�W�A�A���n�̓Ɨ��������ċ}���ɐ������B�A�����J���x�g�i���푈�̔s�k�ő卬���B�\�A�Ɏ����Ă͖c��ȌR����Ɍo�ς����Ȃ��Ȃ��ĂƂ��Ƃ��Ԃ�Ă��܂����̂ł���B�������������œ��{�����͉ᒠ�̊O�ł��葱���A�o�ςW�����Ă������̂ł���B���ꂪ���x�o�ϐ����̐������B
���{�����Ɋ������܂�Ȃ������̂́A�x�g�i���A���N�A�h�C�c�̂悤�ɍ����Q�ɕ�������Ȃ��������ƂƁA�A�����J�R��n��u��������ɑ��Ȃ�Ȃ��B�A�����J�R��n�����邱�Ƃɂ���ă\�A�͗e�Ղɓ��{���U�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ������B���{�̕��a�͌��@�X���ł͂Ȃ��A�A�����J�R��n�ɂ���Ď���Ă����̂ł���B���{�͎�����u�s�����v�Ə̂��邱�Ƃɂ���āA�L���Ȍo�ςƔ����I�ȏ�ɂ킽�镽�a�����h�Ƃ��������w�͂Ȃ��ɋ��邱�Ƃ��ł������A�A�����J���k��������A�W�A�̋��Y���i�\�A�A�k���N�A�����A�x�g�i���A�J���{�W�A�j�̋��ЂɑR����̂ɁA���{�͌R����n��u�������Ŋi�D�̏ꏊ�ɂ������킯�ŁA�܂��ɗ��҂̗��Q����v���Ă����킯���B�����̓��{�̐����Ƃ͂��̓_�𗘗p���āA���Ȃ肤�܂�����������ƌ����Ă悢�B
���������̗����u�x�������̕Ǖ���v�i�P�X�W�X�N�j�u�\�A��́v�i�P�X�X�P�N�j�ŏI������B���ꂪ���E�i�ꕔ�������j�̎����������ɂȂ�B���E�̐�㕜���͂܂��ɂ�������n�܂�̂ł���B�A�����J�͂X�O�N��A�h�s�Ƌ��Z�r�W�l�X�ōD�i�C�ɕ������B���[���b�p�������V�������@�\�̉��U�A���[���b�p�����̂ɂ��ʉݓ����Ȃǂŕ����B�u���b�N�X�i�C���h�A�����A���V�A�A�u���W���j�Ȃ�V�����͂��䓪�B���E�o�ς͌����������̎���ɓ������̂��B
���������{�����͍��x�o�ϐ����̐����̌��������������܂܁A���E�̑傫�ȕω��ɂ��Ă����Ȃ������B�܂�ʼn����̂��Ȃ��ŋN�������`����n�k�̑�Ôg�����{�̉��ݕ��ɑ��Q�������炵���悤�ɁA�����̂��Ȃ��ŋN�������\�A����Ƃ�����Ôg���A���{�̒�����Ƃ⏬���ȏ��X�X���P���Ĉ��ݍ���ł��܂����̂ł���B���ꂪ�o�u������ȍ~�����������s�i�C�̐������B
�\�A�����Đ��̒������ƕς��A�������������Ȃ����B�\�A������O�͓��{�͋���������Ȃ��A�قƂ�ǓƂ菟���������B���ꂪ���{�̊�Ƃɑ����̂��������A�̂̃T�����[�}�����o���蓖���ɉ����R�B�\�A�����Ĉȍ~�͓��{�ȊO�ɂ�������̋������肪�ł��āA���{�̊�Ƃɂ��������Ȃ��Ȃ����B���ꂪ���̃T�����[�}���������ŏo������������Ȃ����R�B���邢�͒��тɋg��Ƃ̋�����P�O�O�~�}�b�N��H�킴������Ȃ����R�ł���B
���{�́u�i���Љ�v�̍L����͂܂��ɁA�X�O�N��ȍ~�̐��E�́u���v�Ɩ��ڂɌ��т��Ă���B���R�ɂ����{�́u�����v�̎n�܂�Ǝ��������Ă����Ƃ��낪�ʔ����B�u���a�v����u�����v�́A�Ђ���Ƃ���ƕ�������i�M���Љ�j���犙�q����i���ƎЉ�j�A�]�ˎ���i�n�������j���疾������i�����W���j�ȗ��̑�ϊv�������̂�������Ȃ��B���͂�u���a�v�̏펯�͒ʗp���Ȃ��B�u�i���Љ�v�̍L����͐V���ȎЉ�Ɉڍs���邤���ł̂ЂƂ̉ߒ��Ȃ̂�������Ȃ��B
�����{�͂Ȃ��푈�ɕ������̂��i��҂҂̌Z�j
���N�͏I��U�O���N�B�l�ԂŌ����Ίҗ�ɂ�����B�U�O�N�o���č��v�����Ƃ͓��{�̓A�����J�Ƃ̐푈�ɂȂ��������̂��Ƃ������Ƃ��B���܂ł��̂��Ƃɂ��Ă��܂茟����Ȃ������悤�Ɏv���B������Ă���A���h���A�����J�ɔC��������ɂ��āA���������a�������鍡�̌���͂Ȃ������悤�Ɏv���B�푈�����Ƃ����A���ʼn������悤�Ɂu�푈�̔ߎS���v�u�푈�̋������v�ł���B�����܂ł������m�푈�́u�߂���������������v�ɂƂǂ߂Ă��������悤���B�����炠���肪�푈�ɑ�����{�l�̎v�l��~�������Ă���悤�Ɏv����B
�s��͍��ʂ̕s���ȂǁA�R�����I�Ȏ��_����̌������邩�Ǝv���邪�A���g�͌R�����Ƃł͂Ȃ��̂ŁA�����ƕʂ̎��_����s��������Ă��������B
�}���K�Ƃ̐������邪���o�E������ɏ]�R���Ă������A�G�̏P���ɂ����ēP�ށB�O���̌�����㊯�ɕ����Ƃ����u�Ȃ����O�͐���Ď��ȂȂ������̂��I�v�Ə㊯�Ɉꊅ���ꂽ�Ƃ����B���݂̊��o���炢���ƁA���Ƃ����l�łȂ��̏㊯���Ǝv���Ă��܂����A�����͂��ꂪ������O�������̂��B�O�i���߂��o���ꂽ�������r�ɂԂ���A���̂܂ܒr�ɒ���œM�����������ł��A�M�����������͌R�l�̊ӂƂ��ď^����A�j���ŏ����������͓̂V�c�̋e�̖�̂����e��r�Ɏ̂Ă��Ƃ������ƂŌ����ɏ�����ꂽ�B���ł͐l���͒n�������d�����ƂɂȂ��Ă��邪�A�ނ����̐l���͈꒚�̏e�����y���������ƂɂȂ�B���̂悤�ȃ����^���e�B����S�O���n�A���e�O�E�m�A�_�����U���A��V�A�ʍӂɂȂ������̂��Ǝv���B
����A�����J�̕����́A�f��u�v���C�x�[�g�E���C�A���v�ɕ`����Ă����悤�ɁA�Z��̑唼���펀�B�c������l�̑��q�����ł���e�̂��ƂA�҂����悤�ƁA���������̋~�o���ɏo������Ƃ������Ƃ�����Ă����B�f�悾����`����Ă��邱�Ƃɂ͔��k��֒������邩������Ȃ��B�����������̓��{���̈������Ɣ�ׂ�ƁA�Ȃ�ƑΏƓI���Ǝv���Ă��܂��B
�܂��Q�O�O�P�N�X���ɋN�������ē��������e�������ŁA���q�@���ƃr���ɓ˂����e�����X�g���u�܂�ŕĊ͑��ɓ˂����ސ_�����U���̂悤���v�ƃ��f�B�A���]�������Ƃ͋L���ɐV�����B�l�I�ɂ����҂��C�X�������A���邢�͓V�c���i���Ɛ_���j�ɂ��@���I���C���ȂƎv���Ă������A�ŋ߂ɂȂ��ė��҂ɂ͌���I�ȈႢ������Ɗ�����悤�ɂȂ����B���̂��������ƂȂ����̂́A�����e�������钼�O�̃e�����X�g�̉f���������Ƃ��ł���B�e�����X�g�͐���i�W�n�[�h�j��킢�ʂ����Ƃɂ���āA�����ƁA�_�̌���Ƃ֍s���A�j�������ƐM�������Ă���B������\��͂��g�����X��Ԃɂ������B
�Ƃ��낪�_�����U���́u�V�c�̂��߂Ɏ��ʂ��Ƃ͓��{�l�Ƃ��čő�̊�сv�Ƌ������܂�Ă����ɂ��ւ�炸�A���U�̒��O�A�݂ȋ����Ă����̂��Ƃ����B�V�c�̂��߂Ɏ��ʂ��Ƃ��ő�̊�тł���Ȃ�A�Ȃ������̂��H���̂��Ƃ�������҂̊Ԃɂ͌���I�ȈႢ������Ɗ������̂��B
���_�������ƁA�@���I���C�Ƃ������͓��{�̕����I�w�i�B���Ȃ킿���{�l���g�����ʂ��Ƃɔ������������鍑��������Ƃ������Ƃɂ���Ǝv���B
�ؕ��Ƃ����l�����A�S�����̃u�[������A���̂悤�ɂς��ƎU��Ƃ������Ƃɔ�������������Ƃ���܂ŁB�ߔN���{�ł͎��E�҂̑��������ɂȂ��Ă��邪�A����͕s�i�C�Ƃ����������{�l�̂����������c�m�`�ɂ��Ƃ��낪�傫���̂ł͂Ǝv����B���ɂ����Ȃ���Γ�����悢�B�����������̓��{�l�͓����Ȃ������B�l�����C�Ɉ͂܂�Ă���Ƃ͂����A�x�g�i���푈�Ń{�[�g�s�[�v���Ə̂��āA�x�g�i���l�̑������C��n���č��O�ɒE�o�����̂Ƃ͂��炢�Ⴂ���B���{�l�̓��̒��ɍ��O�E�o�Ƃ����̂͂Ȃ������̂��낤�B
�����ЂƂ��{�l�ɂ�������Ƃ������Ƃɂ��������������鍑���ł���B�ŋ߂̘A��A�s�̋����n�u�n���E�����v���l�C�ɂȂ������ƂȂǂ͂��̂����Ⴞ�B�ア�҂���������u�����т����v�Ƃ������t�͌������ɒǂ��ēs���������`�o�ւ̓���炫�����́B�܂��u���ƕ���v�͖łт䂭���Ƃ���������������B���{�l�̃����^���e�B�͂Ȃ�Ɛ�N�ȏ�ς���Ă��Ȃ��̂��B����Ȃ畉����Ƃ킩���đ����m�푈������������̓��{�l�̊��o�������͗����ł���B�͂Ȃ��珟�Ƃ��Ƃ��Đ푈������Ă���킯�ł͂Ȃ��̂��B������͂��ł���B
�T�[�r�X�c�Ƃ���点�āA�T�����[�}�������g���A���̂����c�Ǝ��v�͏������オ��Ȃ����{��ƂƂǂ������Ă���B�T�[�r�X�c�Ƃ͎��v�̌���ł���Ă���킯�ł͂Ȃ��B�܂��Ă�J���̔����ł���Ă���킯�ł͂��炳��Ȃ��B�J���ɂ���ĂЂ����犾���A�ꂵ�ގp���������������Ă���̂��B���{�l���ꂵ�ނƂ������Ƃɂ��������������鍑���ł���B�u���a���L�v�ȂǂƂ����悤�ȁA���l���a�C�ŋꂵ��ł���p�����œǂނ悤�Ȑl��͓��{�l�����ł���B
���ʁA������A�ꂵ�ށA����ɉ����ĕs�K�A�n�����A�ʂ��E�E�E�B�������������������l�K�e�B�u�Ȃ��Ƃ���{�l�͔������Ɗ����Ă����B��������{�l�͑����m�푈�łR�O�O���l�����B����푈���������A�{�y����ɂȂ�����Ǝ��͂��ł���B�����������猴���ɂ���Ėł�ł�����������Ȃ��B�ʂɂ`����Ƃ������킯�ł��A�N���������킯�ł��Ȃ��B���{�l�͂��������������Ƃ������Ƃ��B
���x�푈�ɂȂ����ꍇ�A���{�l���ȏ�̂悤�Ȃ��Ƃ�F�����ĂȂ��ƁA���x�͕�����ǂ��납�łԊ댯��������B�Ȃ��Ȃ���{�l���g���łԂ��Ƃɔ������������鍑��������ł���B
�u�Ȃ�m��G��m��ΕS��낤���炸�v
���{�l�͐푈�ɏ��Ƃ��Ǝv������A�܂��������g��m��ׂ��ł���B
���O��̐_��i��҂҂̌Z�j
�O��̐_��ƌ����e���r�A�①�ɁA����@�B����{���͔��@���i�₽�̂����݁j�A�V�p�_���i���߂̂ނ炭���̂邬�j�A���������ʁi�₳���ɂ̂܂����܁j�̂��Ƃ��w���͂������A�Ɠd�Ŏg���Ĉȗ��A�L���s�R�̑�Ȃ��́t�Ƃ����Ӗ��Ŏg����悤�ɂȂ����B
�l�ނ̎O��̐_��Ƃ������u�@���E�����E�o�ρv���B��������̓x�����͏@�����������o�ς̏��ԂɂȂ��Ă���B�V�������Ă����o�V�����̂����Čo�ϖʂ������ʂ����g�b�v�ɂ��邱�Ƃ͂Ȃ��B�o�ς͂����̂����A�����͖��̂�����������̂ł���B�u���̎��ɑ�Ȃ��̂������v�Ƃ����l�������炷��A���R���̂��������鐭���̕����o�ς���ɂ���͓̂�����O���B
���̓��{�ɏZ��ł���ƁA����������������������̂Ƃ����̂͂��܂�s���Ƃ��Ȃ���������Ȃ��B���������j�����Ă݂�A�����ƂƂ����̂͂����Ă���ʎE�C�҂ł��邱�Ƃ��킩��B���}�L�̐M���A�G�g�A�ƍN�͌����ɋy���A�퍑�����A�����ېV�B���j��l�C�̂��鐭���Ƃ͕K���Ƃ����Ă����قǂ�������l���E���Ă���B���݂ł��C�O�̐����Ƃ͑�ʎE�C�҂ł���B�A�����J�̓C���N��A�t�K�j�X�^���ŁA���V�A�̓`�F�`�F���ŁA�����̓`�x�b�g�ŁB��������l���E���Ă���B�l���E���Ȃ����̓��{�̐����Ƃ͋ɂ߂ē���ȑ��݂��ƌ�����B
�������o�ςƂ����̂͂킩�����B���������̂����������̂��@���ƌ����̂͂��������ǂ�قǑ�Ȃ��̂Ȃ̂��B�V���ł͐����ʁA�o�ϖʂ͂����Ă��@���ʂ͂Ȃ��B����͐����V���Ȃǂ̏@���L��V�����̂����āA�V�����Ƃ����@���������͈̂ꑽ�����Ƃ��Ӗ�����B
�f��u�����̏�̃o�C�I�����e���v���ɂƂ�Ƃ킩��₷���B
�ƒ����̃e���B�G�ɂ͎O�l�̖������܂����B�O�l�̖��͔N���̔N��ɂȂ肨��������}���鎞���ɗ��܂����B�ނ����͕��e��������������߂Ă��܂������A�ߑ㉻�ɂ��A���͗����ɂ�錋����]�ނ悤�ɂȂ�܂����B�����͌o�ϓI�ɕn�������������I�т܂����B�ŏ����e�͓�F�������܂������A�����]�ނ̂Ȃ�Ƃ��̌����������܂����B�O���͐����^���ɐg�𓊂��邨�������I�т܂����B������ŏ����e�͓�F�������܂������A�����]�ނ̂Ȃ�Ƃ��̌����������܂����B�����͏@���̈Ⴄ�ً��k�̂��������I�т܂����B����ɂ͕��e�����{���A�Ƃ��Ƃ��Ō�܂Ō����������܂���ł����B
�u�@���A�����A�o�ρv�ɂ͋��ʓ_������B����͐l�Ԃ��킪�܂�����h�����Ă���Ƃ������Ƃ��B�o�ς͊�{�I�ɂ����育�Ƃ̉����ł���B���������Ƃ͎����ʼn�����������͂������A�l�Ԃ͂킪�܂܂Ȃ̂ł���𑼐l�ɂ�点�Ă��܂��B�����Ɍo�ς̔��W������킯���B�����͂Q�l�ȏ�̐l�Ԃ������ꍇ�̗��Q�����ł���B�킪�܂܂Ƃ킪�܂܂̂Ԃ��荇���B���̊Ԃ��A���⃀�`��p���Ȃ�������̂������ł���B�����ď@���͐l�Ԃ̍ő�̂킪�܂��u���ɂ����Ȃ��v�Ƃ����̂����ƂɂȂ��Ă���B�l�Ԃ́u���ɂ����Ȃ��v�Ǝv�����炱���A����������A�V��������A�։���A�ފ݂�����ƐM����̂��B�l�Ԃ����ɂ����Ȃ��Ǝv������A�@���͉i���Ȃ̂��B
�������̖�������̑�����́i���q�p�j
��䍎�l�͐�㐶�܂�ł͍ł����ڂ���Ă���o�ϊw�҂ł���B�ނ́w�ݕ��_�x�ŁA���̗�������܂�Ȃ������������悤�ɁA�ݕ��Ƃ͉����ɂ��čl�@����B�o�ϊw�̍����I�ȃe�[�}�̈�ł���B�����āA�����I�ł��邪�̂ɁA������o�ϖ��ɑa���l�ɂ��������ċ������N���e�[�}�ł���B
�ݕ��ɂ��ẮA���Ɍo�ϊw�̋��l�������������̋Ɛт��c���Ă���B�ݕ����ǂ�ȏ��i�Ƃł������ł������ȏ��i�����炾�B�ł́A���̉ݕ��̉��l�͂ǂ����痈��̂��B�ݕ��ƌ�������邳�܂��܂ȏ��i�ɉ��l�����邱�Ƃ͂킩��B����Ȃ�A���܂��܂ȏ��i�ƌ����ł������ȏ��i�ł���ݕ��́A���̂ɉ��l������̂��B����ɂ��āA���{��`�̖�����J���ҊK���̗��j�I�g���ɂ���ĉ������悤�Ƃ����}���N�X�́A�J�����l�_���������B�ݕ��ɂ́A���̌����`�Ԃł�����݁E��݂Ȃǂ̌����ł�����E����̌@�����H����̂ɕK�v�ȘJ�������߂��Ă���̂��A�ƁB
�������A���݁A�ܗL�������E��̉��i�Ɠ����z�ʂ̒ʉ݂͑��݂��Ȃ��B���݂��낤�Ƌ�݂��낤�ƁA�ꖇ�\�~�ɂȂ邩�Ȃ�Ȃ����̎������낤�ƁA�ݕ��Ƃ��Ẳ��l�͓����ł���B����ɂ́A�J�[�h�ȂǂɌ�����d�q�}�l�[�������g����悤�ɂȂ��Ă���B�����ɘJ�������߂��Ă���Ƃ͌����Ȃ��̂��B�ݕ��͂܂��������l�ɂ����Ȃ��̂ł���B
���l�ɂ����Ȃ��ݕ������ʂ���̂́A�����������l���A�ʂ̏��i�ƌ����ł��A����������͂���Ɏ��̐l�ɑ��Ă��A���̎��̐l�ɑ��Ă��A�����悤�Ɍ����ł��邩��ł���B�ł́A���̘A����������̈�ԍŌ�̐l�͒N���B���R�A�����̖����̐l�����Ƃ������ƂɂȂ�B��䍎�l�͂��������B
�u����Ȃ�ꖇ�̎��ꂪ�A�ݕ��Ƃ��Ďg���Ă���Ƃ������Ƃɂ���āA����Ƃ��Ẳ��l���͂邩�ɂ����Ă����ƂɂȂ�ꖜ�~�Ƃ������l�Ƃ́A�����̖����ɏZ�ސl�Ԃ��獡�����ɏZ�ސl�ԂւƑ����Ă����A�C�O�̂悢��������ɂق��Ȃ�Ȃ��v
���ɂ̒��ۓI���i�ł���ݕ��̕s�v�c�����悭�\������Ă���B�ݕ��͒��ۓI�ł��邩�炱�����R�ɗ��ʂ����{��`�����グ���B�܂����ۓI�ł��邩�炱���M�����u���ɍł��K�����q���ɂ��Ȃ����B�l�Ԃ͕s�v�c�Ȃ��̂̂ł���B
�������ƕ����w�i���q�p�j
�����̕s�v�c���Ƃ͉����B���낢��Ȃ��̂��l�����邾�낤���A�����ʂ�u�����Ă���v���Ƃ��ő�̕s�v�c���낤�B������V�����[�f�B���K�[���u���̃G���g���s�[�i�l�Q���g���s�[�j�v�Ƃ������t�Ő�������B
�����Ă��镨���Ǝ~�܂��Ă��镨�����r���Ă݂悤�B�����Ă��镨���̒��ɂ́A�K�������I�E���w�I�����������݂��Ă���B��̏ォ��ʂ�]�����A���፷�����邩�炻��͓]���藎����B�d�r�̓������ߋ�����̂́A�d�ʍ������邩�炾�B���̍��፷��d�ʍ����Ȃ��Ȃ����Ƃ��A�����Ă��������͎~�܂�B���Ȃ킿�A�����͕��t��ԂɂȂ����̂ł���B������G���g���s�[�ő����Ƃ����B
�Ƃ��낪�A�����̂����͑��̕����Ƃ͂������āA�e�Ղɂ͕��t��ԂɂȂ�Ȃ��B������Ñォ��_��I���������ƌĂ�ł����B�������A����̃G���g���s�[�i�����̂Ȃ����t��ԁj�Ƃ����l�����������A�����̂̓l�Q���g���s�[��ێ悵�A�G���g���s�[��r�o���鑶�݂Ƃ��Đ����ł���B�_���`�ɗ��邱�ƂȂ������w�̗��ꂩ�琶����_���邱�Ƃ͉\�Ȃ̂��B�������A�V�����[�f�B���K�[�̂��̍l���́A�����ɉȊw�I�Ȕނ̈Ӑ}���ď@����N�w�Ɋ�^����ʂ�����B
�����ׂ��d�����I���A���炩�ȘV��𑗂��Ă���l�̊�͂Ȃ����₩�Ȃ̂��A�����Ă܂��A���₩�Ȋ���̘V�l�ɂ͂Ȃ��G�l���M�b�V���Ȏd�����ł��Ȃ��̂��B�ނ̐S�̒��ɂ͗����͂Ȃ��A���t��ԂɂȂ��Ă��邩��ł���B���炬�Ǝd�����{���I�ɑΗ���������ł��邱�Ƃ��A���̌ÓT�I�����u�����Ƃ͉����v�͋����Ă����B
���n���P�[����Ђł����ɂȂ����č��̐l����i�ÐX�`�v�j
���܂̐��E�Łu�B��̃X�[�p�[�p���[�v�Ȃǂƕ]����Ă�������ŕx�T�ȍ��Ƃ̃A�����J����u�ɂ��Đ��E�̍ŕn���̂悤�ȎS����݂���Ƃ́A�V���b�L���O�������B�n���P�[���ɏP���A��K�͂Ȑ��Q���N���āA�A�����J�암�̊e�B�������ȗ��̗��j�ł��ň��̔�Q�����̂ł���B���т��������l���̑����ƁA����ȃr����Z��̔j��̐Ղ��݂�ƁA���̌����ƂȂ����n���P�[���Ɂu�J�g���[�i�v�ȂǂƏ����̖��O������A�����J�̊��s�������ɂ����_�o�ŕs���R�ɂ��v���Ă���B
���̃j���[�I�[�����Y�̔ߎS�ȏ̂Ȃ��ł��Ƃ��ɏՌ��I�Ȃ͈̂ꕔ�̎s�������ɂ�闪�D�̌��i�������B���̗l�q�̓e���r�ł��ӂ�ɉf���o����Ă����B�L��ȃX�[�p�[�}�[�P�b�g�ɐN�����āA�H���������Ђ͂�����J�[�g�ɓ�������ŁA���苎��N�A�h�A�̔j�ꂽ��ǂ�����i���R�̂悤�ɓ���ŃJ�S�ɉ����A���Z���̊X�H������Ă������N�����A�e���r��W�I�Ȃǂ̓d�C���i�����ɂ����œ����Ă������N�j���A�F�Ƃ�ǂ�̈ߗނ�r�����ς��ɕ����A�Ί���݂��A�����Ă��������A�Ȃɂ��̏��i����ꂽ������������A�ւ炵���ɕЎ�𒈂ɍ��X�Ɠ˂��o�����N�E�E�E�݂ȑ��l�̍��Y��D���A����ł���̂������B
���n����̕ɂ��ƁA���D�҂����̓t�H�[�N���t�g�܂Ŏg���āA�������X�̓�������Ԃ��āA���Ƌ�Ȃǂ𓐂�ł����B�e�C�X�ɐN�������ꖡ�̓��C�t����s�X�g���܂Ŏ����o���Ă����B�v������ЊQ�ɂ������s�������������̂��߂ɁA��ނɂ�܂ꂸ���l�̐H�Ƃ���肷��Ƃ�����ނ̍s�ׂł͂Ȃ��̂������B���Q�ŐH�ו��A���ݕ����Ȃ��Ȃ�A�߂��̏��X������H�����邽�߂ɒ��B����Ƃ������i�̍s���ł͂Ȃ��̂��B���ڂ̏��i���蓖���肵�����A�Ƃ��������ȗ��D�ł���A�ޓ��Ȃ̂ł���B��Q�҂����Q�ɑ����Ĕ����l�����ł��邱�Ƃ��l����A���̗����_���āA��Q�҂̍��Y��D���Ƃ����̂́A����߂Ĉ������Ƃ�����B�������X�S�̂ł���ȗ��D�s�ׂ��W�J����Ă���̂��B���{�ł͍l�����Ȃ����Ԃ��Ƃ����悤�B
���̗��D�ɂ͂���ɏd�v�ȓ������������B�����������D���l�Ԃ����̂ق�100�p�[�Z���g�����l�Ȃ̂ł���B�e���r�̉f����V���̎ʐ^�ł݂����A���D�҂݂͂ȃA�t���J�n�s���A�܂����l�������B���̎����͌��n����̑��̈ꕔ�̕ł����Â����Ă����B
���������Ȃ��݂����l�Ȃ̂��B
�암�̃j���[�I�[�����Y�s�͑��l��48���̂���67�p�[�Z���g�����l�ł���B������Z���̑����h�͍��l�Ȃ̂����A����ɂ��Ă����D�҂�100�p�[�Z���g���l�Ȃ̂ł���B�n���P�[���ɂ�鐅�Q�͎��R�����ً̋}���ԂƂ��Ďs���݂�Ȃɕ����ɏP�����������B��Q����\���͐l��▯���̑���ɂ�����炸�A�݂ȕ����ł���B�������Q�������Ƃ������Ƃ��ē��݂ɑ���Ȃ�A���D�҂̂Ȃ��ɔ��l��A�W�A�n�̎s���������ł������ق������R�ƂȂ�B�Ƃ��낪���ꂪ���Ȃ��̂��B
����������ɂ������낢���ƂɁA�j���[���[�N�E�^�C���Y�A���V���g���E�|�X�g�A�b�a�r�e���r�Ƃ��������}�X�R�~�͗��D�ɑ���Z�����������ł������悤�����l�ł��鎖����Ă��Ȃ��B���e���r�͉f���ō��l�̗��D�̌��i�𗬂��Ă��A����̂Ȃ��ł͂��̒P���Ȏ����ɂ͐G��悤�Ƃ��Ȃ��B���D���̂ɂ��Ă͕��_�]���R�̂悤�ɓ`���Ă��A���̍s�ׂ̎��s�҂������قڂ��ׂĒP��̐l��Ɍ����邱�Ƃ͓`���Ȃ��̂��B
�����������ۂɂ��ē�������}�X�R�~�̃��x�����Ό����_�ɔ���ێ�h�̘_�q���b�V���E�����{�E�����_�]���Ă����B
�u���}�X�R�~�͐l�퍷�ʎ�`���Ɣ���邱�Ƃ�����āA���D�҂��݂ȍ��l���Ƃ����d�v�Ȏ�����Ȃ��̂��B���x�����h�̐����Ƃ����͋t�Ɂw���l�͓�����}������Ă���̂ŁA�ً}���ɗ��D�����邱�Ƃ������ł���x�Ƃ����ԓx���Ƃ�B��������Ԉ�����Ή����v
�ǂ��l����ɂ���A���܂̃A�����J�Љ�Ȃ��l���K�w�̃M���b�v�Ƃ������G�Ő[���ȉۑ������Ă��邱�Ƃ������������ۂނ��Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�������Ƀj���[�I�[�����Y�Ȃǂ̓s�s�ł͍��l�̏����͕��ς������B�w�������l�͕��ς��Ⴍ�Ȃ�B���̌������Љ�S�̂̍��l�ɑ���Ό��⍷�ʂ��Ƃ������ɂ����͂��낤�B�Ƃ͂����Ό��⍷�ʂȂ�A�A�W�A�n�s�����ΏۂɂȂ镔��������B�����A�W�A�n�̗��D�҂��F���Ȃ̂��B�Ȃ����l�����Ȃ̂��B
���̓_�A�����{�E���͂т����肷��قǑ�_�ȍl�@������O���Ԃ��̎����̃��W�I�ԑg�ŏq�ׂĂ����B
�u�j���[�I�[�����Y�ł��������A�N�������Ƃ͐�����ɂ��킽���G���^�C�g�������g�i�Љ���̎����j�̎��s�̌��ۂȂ̂��B�����̓w�͂������{����̕����̎Ɉˑ�����S�����w���������͎Љ�Ōb�܂�Ȃ��w������A�Љ��{������ʂ̉��b���邱�Ƃ̂ł������������x�Ƃ������݈ӎ���ł��������Ȃ̂��v
�܂荕�l�����{�ւ̈ˑ����������āA�����Ƃ������Ԃɂ͑��҂̍��Y�������肵�Ă悢�Ƃ݂Ȃ��悤�ȓƓ��̐S��������������A�Ǝ������Ă���̂ł���B���̎����̔w��ɂ͎Љ�����g�債�Ă������x�����h�́u�傫�Ȑ��{�v�ւ̐h煂Ȕᔻ������B���l�̑����炷��A���ł��Ȃ����e�Ƃ������ƂɂȂ낤�B�������D�҂݂͂����l���Ƃ���������ے肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł���B�������ߋ��̓V�Ђ�\���̍ۂɑ�s�s�ŋN�������̑�K�͗��D���A���s�҂͂قڂ��ׂ����l�������Ƃ����̂������Ȃ̂��B
������͕\�ʂɏo�邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ����A�����J�Љ�̐l�킪��݂̃W�����}�����\�L�̑吅�Q�Ƃ�����펞�ɂ܂����̎p���݂����A�Ƃ������Ƃł��낤�B
���K�X�i�n�����j
���Ēn�k�̂Ƃ��̊�{�s���ƌ����A
�E�˂��J���ďo�����m�ۂ���
�E���̉��ɂ����荞�� �@
�E�e���r������� �@
�����Ă����ЂƂA �@
�E�K�X������ �@
��������̓K�X�����e�[�}�ł���B
���₷���Ə����₷���B�K�X�R�����̂܂݂͉�]���������܂��Ă���B�����v���œ_����悤�ɂȂ��Ă���B���������̕����͂ǂ��炩�Ƃ����ƁA����ň����̂ɓK���Ă���B���E�̎�͍\����A���ꂼ����������O���ɉ�]���₷���Ȃ��Ă���B�����甽���v���͍���ɗL���Ȃ̂��B�E��ŃR����������Ƃ��A�J���_�𖭂ɂ悶���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B����͎����ȏ���Ȃ��̂ŁA�g�����˂点�Ă���̂��B���̓_�A����Œ�����l�̓��N�Ȃ���ł���B�X�}�[�g�Ȏp���ʼn����邱�Ƃ��ł���B�Ƃ��낪�A�������C�t�����Ǝv�����A�K�X�R�����͂���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����Ƃ��͉�]���t�ɂȂ�̂ŁA�E��̕����X�}�[�g�ɏ�����B����ł͏����ɂ����̂��B��x�������x�����̂ŁA�͍̂��E�����ɂȂ�B���ǂ͍��E�����Ȃ̂ł́H�Ǝv�����肵�������B�Ƃ��낪���̒���������Ȃ��B
���E�̈Ⴂ�́A�ً}�x�̈Ⴂ�B�����̒n�k�����łȂ��A�i�x���ӂ����ڂ�Ă���Ƃ��ȂǁA�Ƃ����ɃK�X�R�����������Ȃ��Ɗ댯���B�����A�K�X�R�����̉E���i���v���j�����������ƌ��܂��Ă���̂́A�Ƃ����̏ꍇ�Ɂg�E��Łh�����₷���悤���Ȃ̂��B����Ƃ��������Ƃ��̂ق����ً}�x�������̂ł���B�����Ă��Ă܂Â����Ƃ��ȂǁA�Ƃ����ɍ��肪�o�Ă��܂��l�̏ꍇ�A�����ً}�̂Ƃ��ɂ́A�͂����Ăǂ���̎�ŃK�X�������̂��낤�H��͂荶�̂悤�ȋC������B����ł܂��܂����āA�ق�̈�u�̒x�ꂪ�ЊQ���܂˂���������Ȃ��B������l����Ƃ�����ƕs�����B���̂悤�����E�̈Ⴂ�͐����ɂ�����邱�Ƃ�����B�������̐l�����Ȗh�q��S������͕̂K�{�����A�K�X�@��������Ă��郁�[�J�[�������̓_�A�����ł��l�����Ă������������B
���ĂԂ���i�n�����j
�����A�Ŋ��̉w�܂Ŏ��]�ԂŒʂ��Ă���B�����̂Ŏ�܂͕K���i���B���āA������ӂƎv�������āA��܂��ǂ���̎肩��͂߂�̂��ƒ��ӂ���悤�ɂȂ����B�ӎ����Ď������ώ@���Ă݂�ƂP�O�O���E�肩��͂߂Ă����̂��B�ӎ����Ȃ��悤�ɂ��Ă��Ă��A�����čŏ��ɍ���p�̕�����Ɏ������Ƃ��Ă��A��͂�E�肩��͂߂�N�Z�����Ă����B�t����͂߂�ƈ�a��������B�Ȃ����낤�H
���߂��ɐg�߂ɂ���E�����̐l�ɂ�����Ă�������B����ƁA�ނ�͍��肩��͂߂�ł͂Ȃ����B����͗�����ɊW�����肻�������B���Ȃ݂ɂ͂����Ƃ��͂Ƃ����ƁA����͔��ɗ����葤����͂����悤�Ȃ̂��B�܂�u�ԓI�ɂ���A������̕�����܂����ĂȂ����Ԃ������Ƃ�����B�������̖l���E�肩���܂��͂߂�Ƃ������Ƃ́A������̎��R���Ԃ����Ă��������Ƃ������Ƃł͂Ȃ����낤���B
�Ƃ��ɉw�������Ƃ��́A�ؕ�������A������o������Ɨ�����ōׂ�����Ƃ�����@������B����ȂƂ��͗�����̎�܂��͂����āA�������o�����肷�邱�ƂɂȂ�B�������ʃR�[�q�[�̃����O�v�����J����Ƃ����A������̎�܂��͂������낤�B�����������X�̐��������܂��͂߂���͂������肷��Ƃ��̃N�Z�����܂ꂽ�Ɩl�͍l����B�܂������葤����蒷���Ԏ��R�ɂ��Ă��������Ƃ����̂́A��@����̖{�\���낤�Ƃ��v����B
�����炨���炭��܂�Е����Ƃ��Ƃ����A�����葤�̕����Ȃ��Ȃ�₷���n�Y�ł���B�����ƌ����ƁA�h���}�̌Y�����m�ȂǂŁA����ɕЕ��̎�܂������Ă����Ƃ��A����ɂ���ė����肪���ʂł����̂ł͂Ȃ����낤���B
���k�ЂƓ��{�l�i�͍����Y�j
��_�W�H��k�Ђ�葁�����\�N���o�����B���̊ԂɁA�V�����z�n�k���N���������A�ŋ߂͑�Ôg�ɂ���ăA�W�A�̍��X�͑�ЊQ���A�l�ԂɂƂ��Ă̓V�Ђ̋��낵�����A���炽�߂Ďv���m�炳�ꂽ�̂ł���B
���{�͒n�k���ŗ��j�����Ă��A���x����n�k�ɏP���Ă���B�����̍ЊQ�ɓ��{�l�͂ǂ��Ώ����Ă������B�����č���͂ǂ�����ׂ����ɂ��āA�M�҂͐��́u�S�v�̖��ɏœ_���i���čl���Ă݂����B
��_�W�H��k�Ђ̈�N�O�Ƀ��T���[���X�ߍx�ő�n�k���������B���̂��߂������āA�M�҂����Ă̗Տ��S���w�̗F�l�����Ƙb�������ƁA���̔�r���b��ɂȂ����B�����āA�����ɂ͎��ɖ��ĂȑΔ䂪�F�߂�ꂽ�B�܂��A�č��ł͑����ȗ��D��\�������������A���{�ɂ͂܂����������Ȃ������B���ꂾ���̍ЊQ����s��Ő����A���D��\�����ꌏ���Ȃ��̂́A�ނ���H�L�Ȃ��ƂŁA���{�l�͂�����ւ�ɂ��Ă������낤�B
���̓_��傢�ɏ^������ł���ƁA�u����ɔ����āv�Əo�Ă���̂��A���{���{�̑Ή��̒x���ł���B�č��哝�̂͐k�Ђ̗����Ɍ���ɗ��āA�����̂��߂̓��ʗ\�Z�ɂ��Č������Ă���B���{�̑����̑Ή��͂���ɔ䂵�Ă��܂�ɂ��x���A�Ƃ����̂ł���B
�����ŁA���{�̑�������Ă��Ӗ����Ȃ��B�ނ���A��ɏq�ׂ��č��Ɠ��{�̔�r�̖��Â̍��{�ɋ��ʍ������邱�Ƃ�F������ׂ����Ǝv���B����͒[�I�Ɍ����ƁA�l�Ԃ̐������ł���A�l�ԊW�݂̍���ł���B
���{�l�̏ꍇ�A�����m�炸�̐l�ɑ��Ă��K�v�ȂƂ��́A�S���ʂ������悤����̊���������B���̍ہA���܂茾��I�\����K�v�Ƃ��Ȃ��B���ꂪ���܂���p����ƁA�k�Ђ̂Ƃ��ɁA�����m�炸�̐l�����̊Ԃɂ��M���W�������₷���A�R�������̂���������A���ɑς����肵�āA����I������������̂�h�����ƂɂȂ�B
�Ƃ��낪�A���̂悤����̊��̔��f�Ƃ��āA�����ł���A����l���������茠�������Ƃ������̂ŁA���{�ł́u���v�Ɩ������Ă��A�����̏ꍇ�A�����̈ӎv�ɂ���Č���ł����A���ʓI�ɂ��W�c�̍��c�i����������Ԃɂ킽��j�ɂ��˂Ȃ�Ȃ��B��������̓ƑP��h���悳�������A��@��Ԃɂ����Ă̓}�C�i�X�ɂȂ�̂́A��̕č��哝�̂Ɠ��{�̑����̔�r������Ƃ킩��ł��낤�B���҂̌��茠�ɂ͑傫����������B
�����œ��{�̑�����哝�̂Ɠ����ɂ���A�ȂǂƂ����C�͂Ȃ��B����̂��Ƃ��l����Ƃ��A�����͂��̓�����܂��F�����ׂ��ł���B�܂�A���{�l�̂��l�ԊW�݂̍����ێ����A��@��Ԃɂ����ẮA�����j��A���[�_�[�̑��f�������\�ɂ�����@���l���Ă����B�����āA���{�Łu���v�ƂȂ����l�́A��@���������ꍇ�A�ʏ�̃p�^�[���ƈقȂ铮�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����o��ƐS�̏��������Ă����A�Ƃ������ƂɂȂ낤�B
�M�҂͓��{�l���悭���̎�����F�����A���m�Ɉӎ����ēw�͂���A���̂悤�Ȃ��Ƃ͉\�ł���ƍl���Ă���B����A�ЊQ�ɂ��čl����Ƃ��ɁA���{�l�S�̂���Ȃ��ƂƂ��ĔF�����ė~�����Ǝv���B
�����{�l�͂Ȃ��M���₷����߂₷���̂��i��҂҂̌Z�j
�Q�O�O�S�N�B���N�������ꎚ�ŕ\���Ɓu�Ёv���������B�V�����z�n�k�A�䕗��ʔB��������Ȃ�B�Q�Ԗڂ́u�v���������B�u�~�̃\�i�^�v�u�����l�v���B���N�̈�ʂƓ�ʂɂȂ����u�Ёv�Ɓu�v�B�ꌩ�Ȃ�̊W���Ȃ������ŁA���͐[���Ȃ��肪����B����͓��{�l���Ȃ��M���₷����߂₷�����Ƃ������Ƃ����茾�����ĂĂ��邩�炾�B�h���}�u�~�̃\�i�^�v�Ől�C�唚���ƂȂ����u�����l�v�B���c��`�ł��o�}�����������͂�ǂ��������|���ƂȂ��āA�����l���o��قǂ̉ߔM�Ԃ�B�u�~�\�i�c�A�[�v�Ɂu�؍��j���Ƃ̍��R���v�ƁA�����玟�ւƖO���������Ǝv������A���܂��̂��킳�ł́u�����O���Ă����v�Ȃ̂��������B�u�v�̐l�C�ɉ����Ă܂���N�Ƃ����ĂȂ��̂ɁA�܂��ɔM���₷����߂₷���̓T�^�B
�M���₷����߂₷���Ƃ����A������Ȃ��o�ꂷ��V���i�A�V���@�A�V�T�[�r�X�B�������ŋ߂͂R�����Ǝ����Ȃ��B�R���������Ȃ��ƌ����e���r�h���}�B�P�N���_���_���Ƃ��悤�ȑ�̓h���}�͂���тłȂ��B�厖�����N�����Ă���Ƒ��������Ǝv���A�l�̂��킳���V�T���B���̑厖���ւƔ�т��B�Ȃイ�ς��g�̑����B������A������B
�o�ς������ł͂Ȃ��B�����̐��E�ł����ŋ߂܂ő�����b�����낱��ƕς�����B�ꍑ�̃g�b�v������قǒZ���Ԃɂ��낱��ς��̂͒������̂ł͂Ȃ����B���������N����������b�ɂȂ����̂��B�N�C�Y�ɏo��ł���قǂ̂��肳�܂��B����̓o��ł���Ǝ��~�߂����������Ƃ��������B
�����Ɛ����̂͏@�����B�N���ɂȂ�ƃN���X�}�X�����i�L���X�g���j�A��A���ɂȂ�Ə���̏����i�����j�A�N��������Ɛ_�Ђɂ��Q��i�_���j�A�q���������߂��N�ʂ����i�j�B�ߑ��̂Ȃ��ۏo���B�������Ȃ��炻���ł��邩�炱�����a�ȓ��{�B���ꂪ�u�_���܂͂ЂƂv�̈�_�����x�z���Ă�����A�����댌�̉J�A�E�C�̉J���~���Ă��邱�Ƃ��낤�B�V�c���Ƃ�����_�����x�z���Ă��������m�푈������������͂����炩���B�ЂƂ̐_���܂ɂ������Ȃ��B�������ɐ_���܁A�������ɐ_���܁A���S���̐_�́A���{�l���M���₷����߂₷�����������炫�����̂��낤�B
�ł͓��{�l�͂Ȃ��M���₷����߂₷���̂��H����͍��N�̊����u�Ёv�ɐ[��������肪����̂ł͂ƌ��Ă���B
���N�̍ЊQ�f�������Ă���ƁA�������������Ԓz���グ�Ă������Y�i�Z��A�ƍ��j��艖�ɂ����Ĉ�ĂĂ����c����ƒ{���n�k��䕗�ɂ���Ĉ�u�ɂ��ĕ��Ă��܂��B����Ȃ��Ƃɑ���������l�́u���܂ł̓w�͂͂Ȃ����̂��I�v�Ǝv���̂����R�ł���B�����������������o���͍������߂Ăł͂Ȃ��B���{�l����c�×����炸���ƌo�����Ă������ƂȂ̂��B���̏؋��ɓ��{�ɂ͒������w���z�̋Z�p���炽�Ȃ������B���w���z�̋Z�p���炽�Ȃ������͓̂��{�l�ɋZ�p���Ȃ���������ł͂Ȃ��B���{�͐��E�ɋH�Ɍ���Z�p�卑�ł���B���������ƍ����S���B���{�ɂ́u�V�����v�A�t�����X�ɂ́u�s�f�u�v�����邪�A����炪���E�̈�A��̃X�s�[�h���ւ��Ă��邩��Ƃ����āA�����y�U�Ō���Ă͂����Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�u�s�f�u�v�͕��ՂȒn�`���I�ɉ��f���Ă��邩��ł���B����u�V�����v�͎R����J����̕��G�Ȓn�`���Ȃ������肭�˂����肵�Ė҃X�s�[�h�œ˂�����B������r���������ł������ɓ��{�̋Z�p�����݂͂���Ă��邩���킩��Ǝv���B
���̓��{���������w���z�̋Z�p���炽�Ȃ������ő�̗��R�́A�䕗�Ȃǂ̒��J�Œn�Ղ���邭�A�������n�k���������鍑����������ł���B���{���z���ؑ��Ȃ̂͌��z���ނƂȂ�X�т�������������A���x��������������Ƃ����̂����邪�A�䕗��n�k�łԂ�Ă��Č����₷�����������Ƃ����̂�����̂��낤�B���z���Ƃ����̂����Օi�������̂��B
����������������̂��n�k��䕗�ɂ����Ă�����Ă��܂��B�Ȃ�Ώ��Օi�ł��܂����B�����l����̂������I�ł���B��������{�l�͂������M���₷���A��߂₷���Ȃ����B���[���b�p�l�̂悤�ɉ��S�N�Ƃ������v���W�F�N�g�i���B�����́j�A���S�N�Ƃ��������z���i���Ƒ�����j�ȂǂȂ��B���ׂĖڐ�̂��Ƃ���B����ł����̂��A����ł����̂��B���{�������X�[���n�тɂ���A���{�̋ߊC�ɑ����m�v���[�g�����邩����B
���u�����P���W�v�i�����ޖ�j
���͎l�\�N�ȏト�[���b�p�̒����j���w��ł������A����̓��[���b�p���̂��̂ɊS�����������߂Ƃ������A�����ȍ~�̓��{�Ɍ���I�ȉe����^���Ă������[���b�p�̕����ɊS�����������߂ł���B����Ύ����̐�������T�邽�߂Ƀ��[���b�p��ΏۂƂ��Ă������ƂɂȂ�B
�͂��߂͒����j�ƃw���}���E�n�C���y���̌����̕��@�Ɏ䂩��A�ނ̌��������łȂ��A����Љ�̒��ł̃n�C���y�����g�̐������ɂ����ڂ��Ă����B�������A���̓h�C�c�ɗ��w���Ă���͈�n��̗��j�𒆐�������@�����v�܂ŕ`���A���̒n�̒����j�����d���Ȃ�����A�����̕��@�ł��̒n��̗��j���܂Ƃ߂Ă݂��B���ꂪ���̏�����ł������B���̒n��̋ߑ�j������h�C�c�j�Ƃ��`���A���̒n��̑S�j�͈ꉞ�������Ă���B���������ł̓n�C���y���̕��@�ɂ��A�����̒����n��j�̕��@�ɂ��������Ă��Ȃ��B
�Ƃ���œ��{�̋ߑ㎍�����[���b�p�ɑ��铲�ۂ�\�����Ă����B���������̐ڋߕ��@�͓��R�̂��ƂȂ�����j�Ƃ̏ꍇ�Ƃ͂��Ȃ�قȂ��Ă���B���������Y����q���t�݂͂����烈�[���b�p��̌����A���̑̌��̒�����Ώۂ�`���Ă���B���̂��߂ɗ��j�Ƃ̕`�����[���b�p�������ڎ������ɑi������̂ƂȂ��Ă���B
���j�Ƃ̓��[���b�p�̌����҂̕��@�����̂܂���A���̒n�̗��j���ɎQ������`�ŕ`���Ă��邽�߂ɓ��{�l�Ƃ��Ă̏��q�Ƃ��������͌����Ȃ��Ȃ��Ă���B����ŗǂ��Ƃ����l������B���������͂���ł͖����ł��Ȃ��B���[���b�p����{�l�̎��_�ő�����������ł���B
���̒��ł���ԑ傫�ȉۑ���l�̂�����ł���B���Đl�Ȃ�N�����F�߂�l�̂�����͂v�E�g�E�I�[�f���̎��ɕ\������Ă���Ƃ����B
�u���̕@��O�\�C���`�Ɂ@���̐l�i�̍őO��������B�@���̊Ԃ̖��k�̋�Ԃ͎��̓���A�����́@�������ɂ���l�ƌ��킷�e�����፷���Ō}���Ȃ�����@�ٖM�l��@���f�ł���������@�e�͂Ȃ��Ƃ�����f�������邱�Ƃ͂ł���̂��B�v
���{�l�ɂ͂��̂悤�Ȍl�̈ӎ��͎�����Ȃ����낤�B���������[���b�p�ɂ�����Ƃ͈قȂ����l�̈ӎ�������B����̓��C�i�[�E�}���A�E�����P�̎��Ɏ�����Ă���B���́w�Ⴋ���l�ւ̎莆�x���͂��߂Ƃ��Ē����ԃ����P��ǂ�ł������A�w�`�ێ��W�x�̒��̎��̎��������Ƃ���ې[���B
�u�⛌�͉J�̂悤���B����͊C����[�ł��߂��ݕӂɑł��グ�A�l���͂Ȃꂽ�L�삩�炢���⛌�̂��߂���ɂނ����ēo��B�������ċ�X�̏�ɍ~��B�@�����̎��Ԃ��A�J�ƂȂ��č~�肻�����B���ׂĂ̏��H�����_�̕��p�ɑ���Ƃ��B�@���҂𗠐�ꂽ��̓��̂��@���łƔ߈��Ƃ������Ȃ���͂Ȃ��Ƃ��A�@�������đ��ݍ����l�Ɛl�Ƃ��@�ЂƂ̐Q���ɖ���Ȃ���Ȃ�ʂƂ��A�@���̂Ƃ��⛌�͐�ƂȂ��ė���Ă䂭�E�E�E�v
�⛌�̌���̓A�C���U�[���J�C�g�ł���B������u�ЂƂ�ł��邱�Ɓv�Ƃ����Ӗ��ł���A�₵����ǓƂƂ͂��قȂ�B���������{�l�͂�����₵����ǓƂƎ�肪���ł���B�����P�́u��l�ł��邱�Ɓv���F���̌����Ƃ��Ď~�߂Ă���B�u��l�ł��邱�Ɓv�͐l�Ԃ̏����Ȏ₵���Ȃǂł͂Ȃ��A�����P�̎��ɂ���悤���C�ł���A���ł���A�J�ł���B�����ɂ̓��[���b�p�����̂����Ƃ��傫�Ȑ��ʂ�����B�����������[���b�p����w�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂͂��̗��j�Ƃ������A���̗��j���~�߂Ă������l���S�Ȃ̂ł���B
�����P�̓h�C�c�̎Ⴂ���l�B�����C�̂Ȃ������ɔ��R���Ď��R�̒��Ŏ����B�̋��n�낤�Ƃ��ďW�܂������H���v�X���F�[�f�̕��i�����Ă��̒n���ɖ�����Ă��܂�������N�O�̊C�̗l�q������������Ă����B�����̂���⏼�̌Öɖ����Ă��鑛�߂��͖����ꂽ�C�̑��߂��ƕ������Ă����B���̂悤�Ȋ����͎��l�����j�̐[�w�ɂ܂Ŏ������L���Ă��������ʐ��܂ꂽ���̂Ȃ̂ł���A���̎��͂��̂悤�Ȋ������w�ю�肽���Ɗ���Ă���B
���ڂ̍������ӎ����Ă݂�i�n�����j
�Ƃ����A�ʐ^���B��Ƃ��̃R�c��`�����悤�B����͗F�l�̃J�����}���ɋ������������ƃv�����ۂ����U���B�悭�Ƒ���F�l�ȂǂŋL�O�ʐ^���B�����肷�邪�A�����̊Ŕ̑O�ʼn����ɕ��Ԃ̂͂܂�Ȃ��B�܂�Ȃ��̂����A���Ƃ����ăV���E�g�ɂ����Ȃ�|�[�Y������ƌ����Ă��A�����ɂ͂ł��Ȃ����낤�B����ȂƂ��́A������i�J�����}���j���ړ�����̂ł���B�ړ��Ƃ����Ă����E�ł͂Ȃ��A�㉺���B�㉺�̃A���O���������ς��ĎB�e����B����ƁA�����Ƃ͈�����ʐ^���ł���̂ł���B�����ƈႤ�Ƃ������Ƃ́A�^�V�����V�N�Ȏʐ^�Ƃ������Ƃ��B���߂��ɖɓo������A�n�ʂɐQ�]�������肵�ĎB���Ă݂Ăق����B�g�����A���ꂢ���ˁI�h�Ƃ����ʐ^�������Ƃł���͂����B
�������Ƃ��c�Ƃ̏�ł�������B�ڂ̍�����ς��邾���ŁA����̉�������Ă���̂��B����͎��̎��̌��ŁA�Ȋw�I�����͑S���Ȃ����v�������Ă��Ȃ��̂ŁA�y���C�����œǂ�łق����B�ȑO�A���͋��l�L�����Ƃ邽�߂ɔ�э��݉c�Ƃ����Ă������Ƃ�����B�n�߂�����̃p�^�[���́A�u��Ђɔ�э��ށ���t�ɂ��������遨�f���遨�A��v���������A�g�ڂ̍�����ς���h���ӎ����Ďg���悤�ɂ���ƁA�u��Ђɔ�э��ށ���t�ɂ��������遨�b���Ă��炦��v�ɕς�����̂��B�܂��A�S�����S���ł͂Ȃ����A���Ȃ��Ƃ������ɒf���Ȃ��Ȃ����B���̋�̓I�ȓ��e�Ƃ́d�d
���������グ��悤�ɂ���B
������x�̋K�͂̉�Ђɂ́A��t������B�����ĂقƂ�ǂ��������B�����͈�ʓI�ɒj�������w���Ⴂ�B�܂�j���Ƙb���Ƃ��͓���I�����グ�����Ƃ������̂��B���ꂪ�����̕��ʂ̌��i�ł���B�����Ŏ��́A�����Ă��Ⴊ��ŁA�����Ɍ����낳��Ȃ���b�����Ă݂��B�����P�ɂ��Ⴊ�ݍ���ł��s���R�Ȃ̂ŁA�J�o�������ɒu���A�������玑�����o���t��������̂��B�������ꂾ���Ȃ̂����A����ɂƂ��Ă͐V�N�Ȋ��o�Ȃ̂��낤�B��������Ƙb���Ă��ꂽ�̂��B�ŏ��͋��R���Ⴊ��Řb�����̂����A���߂��ɂ��̌������Ă݂�Ƌ��R�Ƃ͎v���Ȃ����ʂ��������B�Ȃɂ���э��݉c�Ƃł͂Ȃ��Ă��A�����̌ڋq�Ƙb������Ƃ��ł��L�����B�C�Ђ������ђ����Ȃ���b��������̂��������낤�B�ȒP�Ȃ̂Ŏ����Ă݂Ăق����B
�t�ɏ����̏ꍇ�́A�j���������낵�Ă݂悤�B����͗����b�̂Ƃ��͂ނ��������̂ŁA�����Ă���Ƃ��Ɏg���B���݂��ɍ����Ă����ŁA�������������Ƃ��ȂǂɁA������Ɨ����オ��A�����ɂȂ��ĉ������������̂��B��ʂɂ���Ă͂ނ��������Ƃ������邪�A�ł����킹�̏�ň�x�ł���������ォ��b��������^�C�~���O�������Ă݂Ă������B������j���ɂƂ��Ă͐V�N�Ȃ̂ł���B����������ɂȂ�Ȃ����x�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����B�ӊO�Ȃ��Ƃ₢���ƈႤ���Ƃ����o����ƁA�l�͎v�����ȏ�ɔ������Ă����B���낢��Ȋp�x���玩���𖣂���H�v�����Ă݂Ă͂��������낤���B
���t�����X�v���Ƃ͉��������̂��i���q�p�j
�V���ɏo�Ă����f�p�[�g�̍L���ɂ́A�v�킸���Ă��܂����B�u�j�t�����X�v����S���N�A���C���ƗA���G�݃t�F�A�J�Áv�Ƃ����B�������ɂ��̎����̓t�����X�v����S���N�����A���C����n���h�o�b�O�⍁�����t�����X�v���Ɖ��̊W������̂��낤���B�����������̏\���͎x�ߊv���l�\���N�ł���B����܂��ǂ����̃f�p�[�g���E�[��������V���̃t�F�A�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�������A���̂悤�Ȃ��Ƃ́A����Ă��铖���҂��֏揤�@���Ɗ�����Ă���B�t�����X�v���Ɖ��̊W���Ȃ����Ƃ͂킩������ł̂��Ƃł���B��ߗ��Ă���͖̂��Ƃ������̂��낤�B
����Ɣ��Ȃ̂��A�֏�ȂǂƂ͉��������ȁu�ǎ�����v�V���R�����ł���B���N���߂̂P���P�V���t�������V���̘_���ψ��R�����u���v�ɂ́A�u�v����S�N�v�Ƒ肪�����Ă���B�����q���r���́A�t�����X�ł̋L�O�s�����Љ�A�u���ڂ������̂́A���Ղ葛������łȂ��A�v���̎Y���ł���w���R�A�����A�����x�Ƃ������O�������̎Љ�łǂ̂悤�ɋ������Ă��邩�A�Ƃ����c�_��������Ȃ��Ƃ��v�Əq�ׁA�u���j���瑽�����w�ԁv�u���j�ɂ������S���ɂ������v�ƌ���ł���B
����̓t�����X�v���֏�t�F�A��萔�{�߂��d���B���̗ǎ�����_���ψ��́A�֏揤�@���Ə��m���Č����Ă���̂ł͂Ȃ��B�{�C�ŗǂ����Ƃ������Ă������Ȃ̂��B���̘_���ψ��ɂ��A�t�����X�v���͋s�����ꂵ�߂�ꂽ���O���A���R�A�����A���������߂ė����オ�����������������I�Ȏ������Ƃ������ƂɂȂ�B�����A�ߔN�A�A�i�[���w�h�Ȃǂ̎Љ�j�A�����l�ފw�A�@���w�������ꂽ���������炩�ɂ�����t�����X�v���̎����́A����ȃ\�{�N�Ȋ��P�����̎����ł͂Ȃ��B�l�Ԃ̎��s�𗝐���t���������ɂȂ����ƌ����Ă����قǂ̕s���Ȏ����Ȃ̂ł���B��������̕֏�ł͂��邪�A���̂Ƃ�����{�ł����������t�����X�v���̐V�����̍D�����������o�Ă���B�ŐV�̂��̂��Љ�Ă������B
�܂��A���{�l�̎�ɂȂ闧��F��w�t�����X�v���ƍՂ�x�B����́A��N�o���l�E�I�Y�[�t�w�v���ՓT�x�̖�҂ł���B
�{�����͂́u�܌��̖v����n�܂�B���[���b�p�ɂ͌Â�����A���́A���A�Đ��̃V���{���Ƃ��Ė��������B�����~���I������t�A�L��̑傫�Ȗ̉��ŁA�l�X�͍Ղ�����A�܂����鎞�͈ٕ��q�������ɂ����B�������܂ށA���̍Ղ�̉�������Ƀt�����X�v��������B�t�����X�v�����Ղ�ƌ��鎋�_�́A��\�N�O�̃��t�F�[�u�����炠�������A�{���́A���{�l�������������ɁA��X�ɂ͂Ƃ����₷���������₷���B�v�����A�ǎ��l�̗\������s���^���̂���������ƋK�͂̑傫�Ȃ��̂ȂǂƂ͑S�������̈Ⴄ���̂��Ƃ킩��B��ʂɎ��^���ꂽ�ʼn��͎��}�����邾���ł������C���[�W�͈�V����邾�낤�B
��������́A�A�����J�̏������j�w�҃����E�n���g�́w�t�����X�v���̐��������x�ł���B�{���ŁA�n���g�́A�v���w��i�̂悤�Ȉ�̃e�N�X�g�ƌ���B�e�N�X�g�́A��҂̈Ӑ}�̒P���Ȕ��f���ł͂Ȃ��A�Ӑ}�̍��܂�ό`�����܂ސ������ł���B�v�����������鎞�A���`�̐����ȊO�̕�����Љ�ɖڂ������͓̂��R���낤�B�{���ł��A��ȏ@���I�M����тт�v���ՓT��v���V���{���̘b����������o�Ă���B����发�̂��߁A�Ƃ����͈������A�_���͐����ł���B
�{���̈Ӗ��Łu���j�ɂ������S�v������̂Ȃ�A�t�����X�v���Ƃ͉��������̂�����n�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���l�ނɂ����铮���̗��j�i�����u���j
�������́A�l�ނ͐����ł����Ƃ����F���ɂ����āA������l����ׂ��ł��邪�A���̏ꍇ�̐����Ƃ͉��ł��낤���B����͒P�Ɂu������L������́v�ƌ��Ȃ��A�����̖{�����^���p�N����j�_�̂�������ƋK�肵�Ă��A����͐l�Ԍ����ɂ͂Ȃ�̖��ɂ������Ȃ��B�ނ���A�����̏d�v�ȓ����́A�̈ێ����푰�ۑ��ɂ���Ƃ�����B�����̌`�ԂƋ@�\�Ɛ����Ƃ́A���̂��Ƃɂ���Ă��Ȃ�悭�������ꂤ��B�H�����͐����̊�{���ł��邪�A����͑O�L�̓������̋�̗�ł���ƂƂ��ɁA���㕶���̂����ł��A�����Ƃ������I�Ȑl�ԓI���ۂƂ����悤�B
���ɁA�l�ނ́u�����ł���v�Ƃ������Ƃ��ł��邪�A���̏ꍇ�̓����Ƃ��O�i�^���i���R���[�V�����j�̉\�Ȑ����ł���ƋK��ł���B�����Ƃ������{��̓A�j�}���̖��ł��邪�A���̓_�Ŏ��ɓI�m�ɓ����̓��������\���ł���B�����ł̑O�i�^���͋��ނɂ���ėV�j�Ƃ����O�i�^���`���Ŋ������ꂽ�B����́A�X�s�[�h��q�������̓_�ŁA����̃T����d�����̃u����}�O���ɂ����Ē��_�ɓ��B�����B���ނ̑̂́A�S�g����^����Ƃł�������悤�ɑ̊��̋ؓ������B�����B
���̌�A�������̊g��ɂƂ��Ȃ��A�����ނ���ނ��o�ꂷ��B���㐶�������ƂȂނ��߂ɁA�d�͂ɝh�R����̍\����L���邪�A�����ɋ��ނ̃��i�r���A�n���r���ɑΉ����āA�O���A�㎈���`�������B���̔��B�͕n��ł���A�����̒i�K�ł͎l���͙����̍ۂ̈�̂Ђ�������Ƃ��Ă̖����ʂ����ɂ����Ȃ��B�₪�āA�l���͑O�i�^����Ƃ��đQ���������A����ɂȂ�B�M���ނł͂���͂Ƃ��ɔ��B���A���s���y�₩�ɂȂ����łȂ��A�������\�ɂȂ�B�l���̑S�g�ɑ���䗦���傫���Ȃ�A�Ƃ��ɒ����𑝂��B�r�̂͂��т̋O�Ղ͔��~�`��悵�A�������邵���\���I�ɂȂ�B
�̊��͑O�i�^������������A���̂��ߔw���Ȃǂɂ�����ؓ��̗ʂ͂͂邩�ɏ��Ȃ��Ȃ�B���s���C�k�Ȃǂ͎���đ����������ӂ肩����]�T����ł���B���̂悤�ȉ^����̐i���̂��Ƃ͉��Ή��������i���琄�@�ł���B�̂̉~���ȉ^�����\�Ȃ炵�߂�ؓ��́A�i���ɂ�ĕ������Ă������Ƃ��A��r��U�w�I�ɒǐՂł���B
����A���ނ͔��ɂ����ꂽ�O�i�^�������s���铮���ł���A���̂قƂ�ǂ����Ăɗ���B�S�g�̌`�Ԃ����ׂĔ��ĂɓK�����A�O���͗��ƂȂ�A��ނ̗ɑ������ĉH�т��S�g�ɕ��z����B���͌y�ʋ��łȍ������琬��B���ׂĂ����ĂɓK����`�ԂƂȂ邽�߁A����ނɕ�����Ă��钹�ނ��A���̍��i�Ɋւ��Ă͕ψق̕�����r�I�����B���x�Ɋւ��Ĕ��Ă͔��ɂ����ꂽ�O�i�^���l���ł���B�����̐i���̗��j�A�Ƃ����Ғœ����̐i���̗��j�͑O�i�^���̗��j�ł��������邱�Ƃ��ł���B�����āA������n���̏d�͂ɍR���`�Ői��ł����Ƃ�����B���̓_�ł́A��ʂɁA���ނ̕����M���ނ�������z���Ă���悤�ł���B���ނ͐i���̓��́A��̋ɂɂ���Ƃ�������B
�������A���I���ʂ���݂�ƁA�����Ƃ������ꂽ�O�i�^���l���́A�l�ނ̗̍p���Ă����������s�ł��낤�B����͗쒷�ވ�ʂ̂��ƂȂގ��㐶���ɗR��������̂ŁA�O���ƌ㎈���������A�O�҂�p���Ď}����}�ւƈړ��������A�̊����������A�㎈�݂̂�p���ĕ��s�ł��邱�Ƃ��琶�������̂ł���B�ސl���i�K����l�ނւƉ�������Ă����ɂ�A�������s�͋@�\�I�ɂ��A�`�ԓI�ɂ���������Ă������B���̎�̑O�i�^���́A���x�����l�����s��A�Ƃ��ɔ��Ăɂ���ׂė�邪�A�㎈���������A����g�p���\�ɂȂ�Ƃ����傫�ȗ��_�݂������B���̂��Ƃ͔]�̔��B�Ƃ����܂��āA�l�ނ̕������W�������炷���̂ł���B
���l���y���͍��y�ʐςɐ���Ⴗ��i��҂҂̌Z�j
�����ŋN�����������u�[�C���O���ŁA��p�o�g�̋�������؎v�z�ɂ��Č���Ă����B
���{�ɑ��锽������A��p�ɑ���Њd�A�`�x�b�g�ɑ���@���e���A���`�ɑ��鍂���I�ԓx�B�����͑S�Ē��؎v�z�ɂ���ƁB���؎v�z�Ƃ͒����͈̑�Ȃ�A���{��؍��A��p�A���`�A�`�x�b�g�͒����̂����ׂȂ�Ƃ������������S��`�̂��Ƃ��w���B���̒��؎v�z�͑�����N�����A���̂��тɍ��y���g�債�Ă����������̗��j����|��ꂽ���́B�����炻�����������j���������͐l���y���̂c�m�`������B�|���m���ς������Ŏ��Y�ɂȂ����B�Ƃ������b�̂悤�Ȗ{���̘b������ȂƂ��납�痈�Ă���̂�������Ȃ��B
�Ό��s�m����������v�����͂��߂Ƃ��Ď����������ꂾ����ʂɋs�E�������͒��������Ƃ������Ă����B���Ƃ��Ƒ����̖�������荇�����悤�ȍ�������A�����Ⴆ�Ό��ꂪ�Ⴄ�B������Ⴄ���t��b���悻�̑��̐l�Ԃ͐l�ԂƂ͌��Ȃ���Ȃ������B�����畽�C�Ől���E���̂��Ƃ�����Ă����B
�Ƃ������y�ʐς��L���Ƃ������Ƃ͂��ꂾ�������A��������N�����A�l����������E���Ă����������B
�����悤�Ȃ��Ƃ̓��V�A�ɂ�������̂ł͂Ȃ����B���V�A�����̍L��ȍ��y���x�z���邽�߂ɂ�������̐l���E���Ă������j������͂����B���ꂪ���̐l���y���̂������ɂȂ����Ă���̂��낤�B�ŋ߂̎�������Ă��A�Ⴆ�e�����X�g�ɂ�錀��苒�A�w�Z�苒�����B�e�����X�g�Ƃ̏e����̖��A�l�������S�l����ł��Ȃ�̖��ɂ��Ȃ�Ȃ��B���������̂��߂ɂ͑����̋]���͂�ނ����Ȃ��B�Ƃ������Ƃ��납�B���ꂪ���{��������A���ꂾ���̎��҂��o�����~�o���̐�������Đ������|�ꂩ�˂Ȃ��B
���{�A�h�C�c�͐푈�ŕ��������߁A�싞��s�E�A�A�E�V���r�b�c�B�e�X�̔Ő��E������@����Ă͂��邪�A���̎�̔́A�����A���V�A�̗��j�ׂĂ݂��������̂ł͂Ȃ����B
�l���y���͍��y�ʐςɐ���Ⴗ��B
�i���͂��������Ȃ��B
���`���|�\�ɂ����銴��\��
�\�Ɖ̕���B�ǂ�������{���\����`���|�\�ł��邪�A���҂ɂ͖��炩�ɈقȂ�������������B����͊�̓����A���Ȃ킿�\��ł͂Ȃ����낤���B�\�ʓI�Ȉ�ۂ����Ă��邩��Ȃ̂��A�̕���̌G���Ɣ\�ʂ������悤�Ȃ��̂Ƃ��Ď��グ���邱�Ƃ�����B�������G���́A���҂̕\������A���̐��i�⊴����֒�������̂ł���B����ɑ��Ĕ\�ʂ́A���҂̊炪�\�ɏo�邱�Ƃ͂������ĂȂ��B�����܂Ŗʂ���Ȃ̂��B
�u�\�ʂ̂悤�Ȋ�v�Ƃ������t�ɏے������悤�ɁA�\�ʂ����\���̑㖼���Ƃ���Ă���B����͖{�����낤���B�����̕���ɂ����Ė��\��ł��邱�Ƃ́A�}�C�i�X�v���ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂��낤���B�ނ�ʌ��͔\�����ł͂Ȃ��B�����ɂ��A���̃A�W�A�̍��X�ɂ��Â����牼�ʌ��͑��݂��Ă���B�����������͊F�A�ߏ�Ǝv����قǓ��I�ɐU�镑�����ƂŁA��̌����Ȃ��}�C�i�X�������Ă���B
�ł́A�\�͂ǂ����B�ʂɂ�銴��̕\�����@�͒P���ŁA��{�͎��̎O�����Ȃ��B
�E�ʂ��Ƃ炷�\�킸���ɋ��i��т�\�킷�j
�E�ʂ�܂炷�\�킸���ɘ낭�i�߂��݂�\�킷�j
�E�ʂ��\�@��u�s���p�x��]����i�{��Ȃǂ̌����\���j
���ɐÓI�ł���B�Œ肳�ꂽ�\��ƌ���ꂽ�Z�@�ɂ��\���́A�ނ��뉉�Z���ŏ����ɂ��Ă����ۂ���^����B
����ł͖{���ɁA�\�͕\��̕\���ɂƂڂ����|�\���Ƃ����A�����́u�m�n�v�ł���B���ہA��̈�ۂقǂ��̂ǂ������Č�������̂͂Ȃ��B��̊p�x�ɂ���āA���邢�́A���̂������ɂ���āA��ۂ͂܂������ς���Ă��܂��B�܂�l����ʂ̋ؓ��̐L�k�݂̂ŕ\���F������̂ł͂Ȃ��A�O�E�̂��܂��܂ȗv�f�����܂߂āA���߂ĕ\��Ƃ��Ď���̂��B����Ɠ������Ƃ��\�ɂ��Ă�������B�ʂ��Ƃ炷�s�ׂ́A��Ɍ������ĂĖ��邢��ۂ�����A�t�ɖʂ�܂炷�͉̂e�������ĈÂ������������������߂��B�ꌩ�H�v�̂Ȃ������Ɍ�����\�����@���A���͔��ɗ��ɂ��Ȃ������̂ł��邱�Ƃ��킩��B
�܂��A������������B��ۂƂ͑����Ɏ葤�̎�ςɍ��E�������̂ł���B���Ƃ��A��l�̐l�Ԃ��������̂��Ɍ����Ƃ��Ă��A���ꂼ��̊������قȂ�Ό��ʂ͂������Ă��邾�낤�B
�\�Ɋւ��Ă��A���̂킸���Ȋ���\�������߂������A��������Ǝ�邩�́A�肵�����Ƃ������Ƃ��B���������\��Ȕ\�ʂɂ��A�����̕\������ĂƂ��͂��ł���B������������Œ肳�ꂽ�\�ʂ̊�́A���ׂĂ̕\��������A�������ꂽ����������Ȃ��B
 |
 |
���댯�̉���͊댯�Ƃ̋������h�i��҂҂̌Z�j
�����Ɋւ��ẮA��ҌZ�I�ɂ͐ϋɓI�Ɏ^�����������Ȃ��Ƃ�������B���낢�댾���Ă��邪�A�d�C�̋����ɃR�X�g�������肷������A�d�C�G�l���M�[�̋��������ɖ�肪����Ƃ���Ό����͂�߂�ׂ��B�������C�ɂȂ�̂́A�������Ƃ������Ă���A���́u�����͊댯������v��߂�ׂ��Ƃ��ʂ����Ă��邱�ƁB����͊댯�Ȃ��̂�r�����悤�Ƃ����_���B
���������ŋ߁A��]���͊댯������P�����悤�Ƃ��A�V��͊댯������P�����悤�Ƃ��A�R�n��͊댯�������߂悤�Ƃ��B�����Ɗ댯�Ȃ��͔̂r�����悤�Ƃ̕������܂���ʂ��Ă���B�������Ȃ���댯���A�댯���Ƃ����Đl�ԂɂƂ��ĉ����댯�����āA������l�Ԏ��g�ł͂Ȃ��̂��B�����������j��U��Ԃ��Ă݂Ă��l�Ԃ������̎��̂Ŏ����ƁA�l�Ԃ��l�Ԃɂ���ĎE���ꂽ���Ƃł́A��҂̕������|�I�ɑ����B���Ƃ���Ɗ댯�Ȃ��̂�r�����悤�Ƃ��čl���Ă݂��ꍇ�A�܂��l�Ԃ���r�����Ȃ��Ă͂����Ȃ��B�������^���Ƃ͂�����Ƃ����ǂ��l���Ă���̂��ȁB
���������l�Ԃ���������̂Ɉ��S�Ȃ��̂͂Ȃ��B��s�@�A�ԁA�S���A�D���B���̂��N����Γ��R���҂��o��B�����Ɠ������B�u�̂����K�͊댯�Ȃ��̂������v�͏�c�Ă̐��ł��邪�A���ꂩ����Ɠ�K���Ă̏Z��͂��납���w�r���Q�͂��ׂĊ댯�ł���B�P�����ׂ����낤�B��A�͂��݁A�J�b�^�[�i�C�t�A�V���[�v�y���V���A�h���C�o�[�B���ׂċ���ɂȂ�B��i���^�A��Ís�ׁB�g�̐����ɋy�Ԋ댯�ȍs�ׂ��B�@���A�x�@�A�ٔ��B��������ƙl�߂݁A�����̐l�̖������D�����˂Ȃ��B�댯�ł���B���悤�ɐl�ԎЉ�Ƃ͊댯�Ɨׂ肠�킹�Ő����Ă���킯�ŁA�댯��r�����悤�Ǝv������A�l�ԎЉ�͐��藧���Ȃ��B������l�ԂɂƂ��đ�Ȃ̂��댯���\���A�댯���R���g���[������\���Ȃ̂��B
�l�Ԃ͏�Ɋ댯�ɂ��炳��Ă����B�l�ނ̗��j�͊댯�Ƃ̐킢�������Ƃ����Ă������B��ɏ������悤�ɁA�l�Ԃ͐l�ԂɎE�����댯������B�܂����C�I����g���Ȃǂ̓��H�����ɐH�ׂ���댯���������B����ɓs�s�����i�ވȑO�̐l�Ԃ̐����́A���������R���̑O�ɂ��炳��Ă����B����Ƃ��͌��~�̒��œ����A�܂�����Ƃ��͏����̒��œ|��A�䕗������ΉƉ��͐�����сA�^���ɂ���ė�����A�����N����Β��͈��ɂ��ď������B�_�앨���s�ǂɂȂ�Ɠr�[�ɋQ��Ɍ������A�a�C����������ΐl�͂Ȃ����ׂ��Ȃ��|�ꎀ��ł������B�l�Ԃ͎����̐g�Ɋ댯���~�蒍�����тɁA���̒��Ŋ댯���\�͂�g�ɂ��A���S����ɂ��Ă������̂ł���B
���ꂪ�u�܂�肩��댯�Ȃ��̂�r�����悤�v�Ƃ������_�������������Ƃǂ��Ȃ邩�B�ԈႢ�Ȃ��댯���\�̗͂�����l�Ԃނ��ƂɂȂ�A�t�ɖ��ێ��ň�������҂��O���֕���o���悤�Ȋ댯��^�����˂Ȃ��B�C���N�Ől���ɂȂ����T�o�J�͌����ɋy���A�댯�����m�Œ��B�Ɏ��c����A�^���ɗ�����Ă������o�J�Ƒ����L���ɐV�����B���̂��N�����Đl������A�Ȃ�ł�����ł��s���̐ӔC�ɂ��₪��B���H�̋��Ԃɋ����Ă�����s���̐ӔC�B�r����ɍ�����Ă��Ȃ�������s���̐ӔC�B�̂̔_�Ƃ͊댯�Ƃ�������역�߂��˂���u���Ă����Ă�����O���������A����ł��l�͎x��Ȃ����������Ă����B
�����̉ԉՂ�̒��B�������ŏ����|���ƂȂ��Ď��S�������́B������s���̐ӔC���H���̓����̉f��������ƕ������̏͂����炩�Ɉُ�B��������Đe�����́u����ȁv�u��������n��̂͊댯���ȁv�Ǝv��Ȃ������̂��낤���H�q�ǂ������ӔC�͊댯���\�͂��ł��Ȃ������e�����ɂ�����̂ł͂Ȃ����H���������Ղ�Ől�����ʂ͓̂�����O�Ȃ̂��B�Ȃ��Ȃ�Ղ�͏W�c�I���C������ł���B�����������̒��ŁA�����≟���Ȃ̂�������܂イ�͏W�c�I���C�ȊO�̂Ȃɂ��̂ł��Ȃ��B�ݘa�c�̂���Ղ�A���I�̃J�[�j�o���B���N�̂悤�Ɏ��҂��o�Ă���B�t�����X�v���A����Ꝅ�A�֓���k�Ђ̒��N�l�s�E�B���ׂčՂ�ł���B�Ղ�͑�ʂ̎��҂��o�₷���B���̂��Ƃ̂��݂����ɂł�����Ă����A���邢�͎q�ǂ������̎��͉���ł�����������Ȃ��B�m����m�b���댯���\�͂̂ЂƂ����B
���悤�Ɋ댯���������A���S�ɕ邷�ɂ͏�Ɍ��݂̊댯��F�����A����ɑΏ����邱�Ƃ��K�v���B����͊댯��r�����邱�Ƃł͂Ȃ��A�댯�Ƌ������h���邮�炢�̐S�������K�v�Ȃ̂ł���B
�������Ɖ��y�i�����S�j�j
�J���S�}�A�w���V�[���A�V�����b�`�A�E�[���[�^�[�A�`�`���v�C�A�P���Q���R�[���A�A�u���J�_�u���A�i���T�b�_���}�I���_���M���[�A�I���}�j�p�h���t���A�V���U�[���A�Z������A�G���C���A�G�b�T�C�����͋��ߑi������E�E�E������������Ɣ����J���A�p�������A�ϐg���N����A�V�ϒn�ق������A���낪����ɕς�A����������A����������B�q���̍��͒N�ł������ɂ������ꂽ���̂ł���B�������A���������̌��ʂ������Ȃ����Ƃ����ƁA�₪�Ď����Ɍ�������ď펯�I�Ȃ��ƂȂ̐��E�ɁE�E�E�ǂ������A�����̈З͂͂���Ȃɂ��낢���̂ł͂Ȃ��B�������^�����������̂͂ނ��남�ƂȂɂȂ��Ă��炾�B�Ȃ�Ɠ��{�l�̐������x�z���Ă���͎̂����Ȃ̂ł���B
�����Ƃ͎�p���s�����ɏ����錾�t�A�܂��͌��t�ɏ�������̂ł���B��p���s���ɂ͎�X�̏������K�v�����A���ׂĂ̏������������Ƃ���ŁA��p���쓮������L�[���[�h�ƂȂ�̂������ł���B�Ւd��݂��A�����̑���u���A�\���˂��t���ɗ��āA�������[�\�N���Ė����̃X�[�v���ϋl�߂Ă݂Ă����ꂾ���ł͉����N����Ȃ��B�����������ď��߂Ď�p���쓮�J�n����̂ł���B������A�����̎�p�͏����Ȃ��Ŏ��������ŊԂɍ��킹��Ƃ����̂�����B
�������������Ă݂�Ɩʔ������Ƃ��킩��B���́A�����͈ꎞ��ȏ�O�̌��t���g���ׂ��Ƃ����������B����p��͕s�ł���B���Đl�̎����̓��e���ꂾ�B�Ñネ�[�}�l�̎����̓M���V���ꂾ�������A�C���h�l�̎����̓T���X�N���b�g�������B���{�l�̎����͍��Ȃ當��̂ł�������n�j�����A��O�̎����͊�����퍑����A��������̌��t�łȂ��ƌ��͂����Ȃ������B�����̌o���������̈��Ȃ̂ŁA�T���X�N���b�g��p�[����A������̂Ȃ܂������̂��g���Ă���B����ɂ��Ӗ��͂킩��Ȃ��̂����A����������Ƃ��Ă̗͂������B�A�r���E���P���\���J�A�I���i�{�L���[�x�[���V���m�[�A�i���J���^���m�g�����[���[�A�Ƃ���Ό��������ȋC������B�L���X�g���ł��u�����܂��̂��܂��傽��S�\�̐_��v�ƌĂт����Ȃ���_�����B�u�̂��炸�[���Ƃ����ł̃S�b�h�}�X�^�[�����v�ł͌����Ȃ��̂��B�A�b���[�E�A�N�o���B�N���o���A�N���o���B
�����̏������A�ꎚ��傽��Ƃ܂������Ă͂����Ȃ��A������O�コ���Ă������Ȃ��B�����������Ȃ��ꍇ�ׂĂ݂�ƁA�����Ă������i�K�Ń~�X�����������A�������������������Ă��Ȃ��������ł���B���{�_�b�̍����݂̏͂ł́A�C�U�i�~���u�A�i�j���V�A�G�I�g�R���v�����ăC�U�i�M���u�A�i�j���V�A�G�I�g�����v�Ǝ����������Ď��s���Ă���B�������t�������̂ł���B�J�����A�J���S���A�J�������S�A�ł͔��͊J���Ȃ��B
�����̌��p�A�V�ϒn�فA�ϐg�A���p�A�������A�������������͍̂��͐M����l�����Ȃ��B���\�͂⌌�t�^�肢��M����l�Ȃ�����ɂ��ϐg���M���邩������Ȃ����A�ӂ��̐l�͂܂��M���Ȃ��B����̎����̌��p�͂����ƕʂȂƂ���ɂ���B���ȈÎ��A�W�c�Ö��A������T�C�R�V���b�^�[�������B�����ɂ��O��������肱��ł��錾�t��v�l���V���b�g�A�E�g����������傫���B�X�������̎v�l���̂��̂𑼐l�̖ڂ��炩�����������傫���̂ł���B�i���}�C�_�A�i���~���[�z�[�����Q�L���[�A���������ă^�[�X�P�^�}�[�G�A��������悭�ł��������ł���B
�T�C�R�V���b�^�[�Ƃ��Ă̎����͎��ɍL�͈͂Ɍ�����B�����̍l����ǂ܂�Ȃ����߂ɁA���l�̍l�����͂˂��������邽�߂ɏ���������B���̓T�^�̓V���v���q�E�R�[�����B�Ȃ�ł����A����ł����Ƃ�����Ȃ��J�Ԃ��ď����Ă���ƎO�\������ꎞ�Ԃ��炢�Ō����ڂ�����Ă���B�Ԃ������Ă���Ί������B�w�����b�g�����Ԃ����A�����w�O�ł���Ă���u�����́A�����́A����ꂪ�A�����ɁE�E�E�v�Ƃ����������T�^�I�Ȏ����̈��ł���B�x�݂Ȃ����邱�ƁA����Ɍ����J�����Ȃ����ƁA����̌��t��v�l���V���b�g�A�E�g���邱�ƁB�����Ĕ��_���Ă͂����Ȃ��B�������邱�ƁA�����Ȃ����ƁA������邱�ƁB�����������٘_�p�́A���̓M���V������Ɋm�����Ă���̂����A�ĊO�m���Ă��Ȃ��悤���B������A�̂̓e���r���_��ȂǂŁA���̎�̌P�������w���Ƀ}�C�N�W���b�N����Ă���Ăӂ��߂����i���悭�������B�ŋ߂͂���������悪�Ȃ��Ȃ����̂ł܂�Ȃ��Ȃ����B�u����ꉮ����v�ɑR����͎̂��͋ɂ߂ėe�Ղł���B���ɐ������ă}���K�ł��ǂ�ł��邩�A���˂ނ�����Ă���悢�B�����Ƃ����ꂪ�ł���̂͑啨���Ƃ�����������B����ł����˂ނ�c���₢�˂ނ��b�����邪�A���h���Ǝv���B����̓��_�Ƃ����̂́A�؏����̂��܂��Ă����������ɂ����Ȃ��̂ŁA��ڋʂ������ĕ����Ă����̓o�J�Ȃ̂ł���B
�w��͂��ł��v�������ɂ������邱�Ƃ��o����悤�ɏo���Ă���B�����A���̕��͎����ł͎�������邱�Ƃ��o���Ȃ��悤�ɏo���Ă���B���̂��낤�x�i���c�ЕF�A�`�̎�j�B
�����Ŏ����ɂ���Ď�����邱�Ƃ��l���o�����킯���B���͕M�҂������p�̎����͎����Ă���B����������Ă���Ǝ��̈����������ɓ����Ă���̂�h�����Ƃ��ł���B���S������̂��Ƃł͂Ȃ��B�N�ł����ʂ肩�̎����p�̎����������Ă���͂��Ȃ̂��B�i���A�~�_�u�c�A�i���}�C�_�����̂ЂƂ����A���ɂ́u�`�L�V���[���v�Ƃ��u�R���j�����v�Ƃ��u�N�\�v�Ƃ��u�A���K�^���A�A���K�^���v�u�C���n�j�z�w�g�v�u�h�b�R�C�V���v�Ƃ��������̂�����B
����A�����グ���炫�肪�Ȃ��B�p�`���R���Ő₦�����̒��łԂԂ]���Ȃ���e���Ă���l�����邪�A����������ł���B�c�������G�`�����Ȃ���ԂԂ]���Ă�̂��������B�X�ɓO�ꂷ��ƁA�w�b�h�t�H���Ŏ����ӂ����Ȃ���ԂԂԂ₭�悤�ɂȂ�B�O�ꂵ���T�C�R�V���b�^�[�������B����̎����̓E�H�[�N�}���ł���A�a�f�l�ł���A�f�B�X�R�̍����ł���B���y���̂��̂������ł���B������ŋ߂̃|�b�v�X�̉̎��͔����s���āA�Ӗ��s���A�����������̂��B�����Ƃ��N���V�b�N�̉̎��ł��킩���ĕ����Ă���l�͂��Ȃ��B�킩�Ȃ����������B�킩��Ƃ��܂�ɂ��ᑭ�ȓ��e�ɂ������肵�Ă��܂��B�X�ɂ悭�l���Ă݂���A�Ñ�̉��y�͎�p�̈ꕔ�Ƃ��Ĕ����������̂������B���y�͕S���N�O���猻��܂ŁA��Ɏ����������̂��B�z���}�J�C�i�H
�������A�⌾�A�����A���_�f�����i�����S�j�j
����O�͏�Ɉ��|�I���o�J�ł���B
���M������̂͂��܂����B
�����ׂĂ̐푈�͏@���푈�ł���B
���l�͖ҏb�Ƃ��Đ��܂�A�A���Ƃ��Ď��ʁB
�������o���Ă���s������߂�B
��������m�����펯�ƌĂԁB
�����Ȃ��ɂ��邱�ƂƐ����Ă��邱�ƂƂ͂������B
�������ȊO�͑��l�ł���B
�������̖��\�Ԃ�ɋC�����Ă͂����Ȃ��B
���@�B���l����{�I�ɂ͓����ł���B����ɋC�t���Ă��Ȃ��̂��@�B�ł���B
�����O�ƊO�ς����g�����߂�B
�����͋����A�P�͎サ�B
���E�\�����j���l�͈̂����A���j��Ȃ��E�\�����l�͂����ƈ̂��B
�����`�Ƃ͉ߔ����̂��ƁB
���f���Ď咣��������邱�Ƃ��^���ƂȂ�B
���Ȃ��l�͂���ӂ�����A����l�͂Ȃ��ӂ������B�����Ђ܂��˔\���閧���B
�������W����߂�Ώ��̕��ʼn��������Ă���B
����i���ړI�ƂȂ邱�Ƃ������Ƃ����B
���ߒ����y���ނ��Ƃ���Ƃ����B
�������̂��Ƃ͑��l�����B
�����l�̂��Ƃ͎��������B
���������̑��q�͊v���ƂɂȂ�A�v���Ƃ̑��q�͋������ɂȂ�B
���ƍ߂̉e�ɏ@������B
���v���ɂ͔C�����Ȃ��B
���l�Ԃ͊炪���ł��B
����҂͕a�l�����A�ٌ�m�͔ƍߎ҂���Ă�B
���e�q�͑��l�̎n�܂�B
���킩��Ȃ����͒@���Ă݂�B
���������ڂ�����̃G���[�g�B
���N�ł����F�̓f���V�J�B
���܂͕@���̌����B
�����N�@���������k�߂�B
�����[���͕����x�����������B
���ɍ��̍��ɋɉE������B
���\�����E�����ł��Ȃ��ߌ��B
����͕ʂ�̎n�܂�i��҂҂̌Z�j
�C���^�[�l�b�g�́u�o��n�T�C�g�v�ɑ�\�����悤�ɁA���m��ʐl�Ƃ̏o����傫�ȃ����b�g�Ƃ���Ă���B�������Ȃ���u��͕ʂ�̎n�܂�v�Ƃ������Ă���B�C���^�[�l�b�g�̓E�B���X�T�Ŕ����I�ɕ��y���Ă���܂��P�O�N���炢�����o���ĂȂ��̂ŁA�u�o��v���肪��������u�ʂ�v�ɑ��Ă͂��܂����Ȃ��B
���݂g�o�̊Ǘ��҂͂S�O�A�R�O�A�Q�O�オ���S���B���ƂQ�O�N�A�R�O�N��B�g�o�̊Ǘ��҂��g�o�̉^�c�������Ƒ������ꍇ�A�g�o��Ɂu�ʂ��������v���������͂��ł���B�Ȃ��Ȃ牽�l���������K��邩��ł���B�g�o�̊Ǘ��҂����̗�O�ł͂Ȃ��B���̂g�o�����I�ɖK��Ă��闈�K�҂��Ǘ��҂Ƃ̕t��������������Q�O�N�A�R�O�N�ɂȂ�͂��ł���B���̏ꍇ�g�o��Ɂu�ʂ��������v�������������K�҂̑����́A�t��������������Β����قǁA�t���������[����ΐ[���قǁA�o�b�̑O�Ō��������܂���͂��ł���B���ƂQ�O�N�A�R�O�N�o�ĂA�o�b�̑O�ŗ��܂���l�X�̎p�͂قړ���Ɖ����B
�C���^�[�l�b�g���o�ꂷ��ȑO�͉Ƒ���e�ʂ��邢�͗F�l�A��Ђ̓����ȂǁB��قǎЌ𐫂̂���l�ȊO�́A�l�̎��ʂŗ��܂���͌���ꂽ���̂ƂȂ��Ă����B���������݉�X�͐l�ގj�㏉�߂Ăƌ����Ă������炢�A�l�̎��ʂƐڂ���@��̑����s���t�ɂȂ��Ă���B���܂͂�����ӎ����邱�Ƃ͂Ȃ��B�������Q�O�N�A�R�O�N�o�ĂA�l�͔ۉ������ɂ�����ӎ�����͂����B�������̎����̏�ʂɂȂ��Đl�͂Ȃ�ƌ�邾�낤�B�u����Ȃɏo��������Ď��̐l���͍K���������v�ƌ��̂��u�����玟�ւƂȂ��݂̂g�o�������ꂳ�т����v�ƌ��̂��B
������ɂ����X�͐l�ނ��������Čo���������Ƃ̂Ȃ��u�������̕ʂ�v��̌�����ŏ��̐����ɂȂ邱�Ƃ����͊ԈႢ�Ȃ��B
��������������Ȃ����߂Ɂi���q�p�j
�V����G����A���邢�͂�����Ƌ��{����C�ȉ�b�ȂǂŁA�����Ƃ������t�����������Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B�����Ƃ������t�́A���̂�����������O�Ɏg���Ă���̂ł���B�����A����ł͐����Ƃ͉����A�Ɩ����ƁA�����Ă���u�l�����ށB��₠���ĕԂ��Ă��铚���́A�����Ƃ͎v�����ł��傤�˂��A�Ƃ��A�����Ƃ̓}�S�R���ł���A�Ƃ��A�����Ƃ͎Q���ł��A�Ƃ����������̂ł���B�������A�����́A�����Ƃ���c�m�̗ϗ��Ƃ��Z���Q���Ƃ������A���Ƃ����퐶���Ɛړ_��������́A���������̈ꕔ�̂��Ƃɂ����Ȃ��B����Ȃ��̂��������̂��̂ł���Ƃ͎v���Ȃ��̂ł���B
�����A���ۂɂ́A�قƂ�ǒN���������Ƃ������̂��A�����������̂��ƍl����悤�ɂȂ��Ă���B�u�ӎ��̒Ⴂ�l�v�́A���݉��ł��т肿�т���������݂Ȃ����c�m�̕s����ᔻ���鐭���_�����A�u�ӎ��̍����l�v�́A�V���̘_�]������������p������ւ̏Z���ӎv�̔��f���咣����Ƃ��������_�����Ă���B��X�́A�����Ƃ������̂����������ӂ��ɍl����̂Ɋ���Ă��܂��Ă���B
�������A���̂悤�ɍl���Ă݂����A�������������̂Ƃ炦���ʼn������𖾂ł�����L�v�Ȓ��ł����肷�邾�낤���Ƃ����^�₪�N���B���Ȃ킿�A�\�A���U�ߍ���ł��ē��{���x�z�����ꍇ�A�Ƃ������Ƃ��B�����ōs���鐭���ɁA�v����萭���_��}�S�R�������_��Z���Q�������_�������Ӗ������ł��낤���B�܂������ہB���̈Ӗ��������Ȃ��B���Ƃ���A�\�A�̎x�z���P�O�O�N���Q�O�O�N���A����I����������̂��Ƃł��낤�B���̎��A�܂��l�X�́A�����Ƃ͎v�����ł��A�Ƃ��A�}�S�R���ł��A�Ƃ������o���ł��낤�B
�������A�\�A�������ɓ��{�ɍU�ߍ���ł�����x�z����\���͂قƂ�ǂȂ��̂ł���B�ނ���A�A�����J�̂ق����A���Ă͓��{�̈ꕔ�i����j���x�z���Ă����̂ł���i�k���̓y�́A�x�z�Ƃ�������̂ɋ߂��j�B�����ł́A�����́A�x�z�Ƃ����Ӗ��������ł������B���Ẳ���ł́A�����Ƃ����A�ČR�ɖ��W�ɂ͂��肦�Ȃ������̂��B
�����Ƃ������̂́A���̂悤�ɁA���́E�x�z�̖��Ȃ̂ł���A���̓���^���u�s���v�Ȃ̂ł���B��X�����炳��Ă���A�v������}�S�R����Z���Q���́A�s�������퐭���̂��̂܂��ꕔ���Ȃ̂ł���B
�ł́A�x�z�E�����Ƃ͉����B
����́A�l���l�����Ƃ������Ƃł���B�܂��A���_�A�S�C�A�S���A�H�Ɛ�L�Ƃ����������́B�����đ�͈����S����A���́A�Ƒ����̖��ߎw���Ƃ������A�l�����S���́B�����ɂ��A�l���l�������Ƃ̏W���`�ԁE���x�������ƌ��Ă������낤�B�����炱���A�G���Q���X�́A�����w�҂̒m�����̂����āA�Ƒ��⎄�L���Y�i���̃��m���N���ɑ�����Ƃ������Ƃ��N���A����𑼂̐l���F�߂�̂��A�Ƃ������Ɓj�⍑�Ƃ̋N���ɂ��Č��������̂ł���A�g�{�����́A�������z�i�N���ƒN���̊W�Ƃ������̂́A�����Ȃ�����ǁA�m���ɂ���A�Ƃ������Ɓj�ɂ��čl�@�����̂ł���B
�����ɂ��čl����A�Ƃ����ꍇ�A�����̂Ƃ�����l���Ȃ���A���́A�ӂ��͂�̂��������l������x�ɂ��������ɂ��čl���Ă��邱�ƂɂȂ�Ȃ��B�ނ��A�ӂ��͂�̂������ɂ��čl���邱�Ƃ͔��ɐ؎��Ȃ��Ƃł���B�����A������Ƃ����āA���ꂪ�������Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�����{�l�͍K�����i�͍����Y�j
���{���s����o�����Ă��甼���I�]��A���̊Ԃɓ��{�قǖڂ��܂������W���������͑��ɂȂ��ƌ����Ă������낤�B���݂̂����͂��đz�����ł��Ȃ������قǂ̖L���Ȑ��������Ă���B���̒n����ŁA�Q���ɋꂵ��ł���l��A�d�C���������Ȃ����������Ă���l���������邱�Ƃ��v���A�����̓��{�̔ɉh�́A�L������Ă������Ƃł��낤�B
�Ƃ���ŁA���̂悤�ȏ̂Ȃ��ŁA���{�l�͍K�����낤���B��������ƁA���ނ������ɈÂ�������Ă���l���������A�V�������Ă��A�Â��j���[�X�ɖ����Ă���B�����āA���{�̏�Ԃɂ��ĒQ���_�����A���������Ɍ��邱�Ƃ��ł���B���̂悤�ȓ_�ɒ��ڂ������A���{�l�S�̂��s�K�ɂȂ��Ă���悤�Ȋ���������̂ł���B����͂��������ǂ����Ă��낤���B
�������A������������s���̂����ɂ���l�͑����B���{���́u�NJ��v�Ȃǂɂ��Č��l�̂قƂ�ǂ́A�o�ϐ����̂䂫�Â܂�ɂ��Č��y����B�������A���������o�ς́u�����v��������҂���ԓx�ɍ��{�I�Ȗ�肪����̂ł͂Ȃ��낤���B�s���A�s���ƌ����A���{�l�͑��̍��X�̐l�ɔ�ׂ�ƁA����]��قǂ̂����������Ă���̂��B
�o�ς̂��Ƃ𗣂�āA�l�Ԃ݂̍���̖��Ƃ��čl���Ă݂悤�B���݂̔ɉh�������炵���L�͂ȕ���ɉȊw�E�Z�p�Ƃ������Ƃ�����B�{���A�Ȋw�ƋZ�p�͕����čl����ׂ��Ȃ̂����A���{�ł͉Ȋw�Z�p�Ƃ��ĂЂƂ̂��̂̂悤�ɍl����l�������B���̂Ƃ��̉Ȋw�̓��[���b�p�ߑ�ɋN�������ߑ�Ȋw��͂Ƃ��āA�����҂͂��̂��Ƃ��q�ϓI�ɁA�܂�A���̑ΏۂƖ��W�̗���ɗ����Č������A�����Ɉ��ʂ̖@�������o���B����ƋZ�p�����т��ƁA�����̓d�C�@�B�̂悤�ɁA�}�j���A���ɏ]���ă{�^���������ƁA�@�B���v���悤�ɑ��삳��A�]�܂������ʂ������邱�ƂɂȂ�B
����͑f���炵�����Ƃ��B�������A���ꂪ���܂�ɂ����܂��䂭�̂ŁA���{�̑����̐l���}�j���A���ɏ]���Ă����Ƃ��ƁA���ł��v���ǂ���ɂ��܂��䂭�A�Ǝv�����݂������̂ł͂Ȃ��낤���B�����A���̂��߂ɂ͏㓙�̋@�B��A�悢���@����ɓ����K�v�����邪�A�����͂����Ŕ������Ƃ��ł���B�܂�A������������Ή��ł��v���̂܂܂ɂł���\�\�K���ɂȂ�\�\�ƍl����B
���̂��Ƃ�[�I�Ɏ�����Ƃ��āA�q�ǂ��̕s�o�Z�ɔY��ł������e����A�u�Ȋw�����B���������A�{�^�������ɉ����ΐl�Ԃ͌��܂ōs���ċA���ė�����̂ɁA���q���w�Z�ɍs������{�^���͂Ȃ��̂ł����v�Ƌl�₳�ꂽ���Ƃ�����B�Ȋw�Z�p�́A���삷�鑤�Ƃ���鑤�ɊW���Ȃ��Ƃ��ɂ̂ݗL���ł���B���e�Ƒ��q�Ƃ����l�ԊW������Ƃ���ł́A����͖𗧂��Ȃ��B
���̂��Ƃ�Y��āA����l�͑��l�����ɑ��삵�Ď����̎v���ǂ���ɂ��邱�Ƃ��ł���ƍ��o���Ă���̂ł͂Ȃ��낤���B��肢�玙�@�ɏ]���Ď����̎q�ǂ����u�悢�q�v�Ɉ�Ă�Ƃ��A����҂ɑ���悢�u��v�������āA�ʓ|���Ȃ�����Ƃ��B�����āA���̌��ʁA�q�ǂ��⍂��҂͎������u�l�Ԉ����v���Ă���Ȃ��ƁA�Ȃ�ƂȂ������Ƃ��āA�]�v�Ɉ��������Ɍ������Ǝv����B
�u�l�ԊW�v�Ƃ����ƁA�b���}�Ɍ����Ȃ�B�e�q�̑Θb���ǂ����邩�ȂǂƂ����O�ɁA�ƒ�ł��F�l�ł��A�Ƃɂ����u�ꏏ�ɐ����Ă�����Łv�Ƃł����������悤������̋��L�Ƃ������Ƃ�����̂ł͂Ȃ��낤���B���̂悤�Ȋ���Ɏx�����Ă����A�l�Ԃ͎����͐����Ă���Ɗ�������̂ł���B
���̂��Ƃ�Y��āA���Ƃ����l���u����v������u�x�z�v�����肵�āA�����̗~�]�𐋂���̂��K�����Ǝv���B�����āA���̂��߂ɕK�v�ƍl���邨����}�j���A���T���ɔM�S�ɂȂ��Ă��邤���ɁA��ɏq�ׂ��悤�ȑ��l�Ƃ̊�������L����ԓx���キ�Ȃ��Ă��܂��B����ł́A�S�͈��肵�Ȃ����K���ɂȂ�Ȃ��̂����R�ł���B
�L���ȕ��ɑ������邾���̐S�̂Ȃ�����ɂ��邱�ƂɁA���������G�l���M�[���g���Ă͂ǂ����낤�B�����Ƃɂ����R�̉ʕ��̂��Ƃ�Y��A�����ɂȂ��Ă���ʕ�����荇�����邽�߂ɁA��ꏟ���ɍ����o�낤�Ƃ����݂����Ă���Q�O�B���{�l�͂���Ȏp�ɂȂ�ʂ悤�ɁA�܂��l�Ɛl�Ƃ��Ȃ����ĕ��������y���݂����o���ė~�����B
���u�@�֏e�̎Љ�j�v�]�i���q�p�j
�V�������オ�V�����Z�p�⓹��ށB�t�ɁA�V�����Z�p�⓹��V��������ށB���̓�̂��Ƃ͑��݂ɂ���݂����Ă���B���ꂪ���j�Ȃ̂ł���B���N�����Z�p�̔����A����Z�p�̉��ǁA����p�̔��B�E�E�E�B�ǂ���������B
�V��������̏o�����A����̗v���ł���A�����ɁA���̎���ޗ͂ɂ��Ȃ�B�S�C�̔����́A�푈�̗��j��傫���ς��A�l�X�̍l�������ς����B��\���I���̊j����̔����Ƃ��̓�x�̎g�p���A���̌�̐��E�̍s��������Â����B
�������A�ӊO�ɋC�Â��Ȃ��̂��A�@�֏e�̏o���Ƃ��̉e���ł���B�@�֏e�́A�P�Ȃ�֗��ɂȂ������e�ł͂Ȃ��B�m���ɁA�@�֏e�́A�P���e���A���e�ɉ��ǂ��ꂽ��������ɂ���悤�Ɍ�����B�ꔭ���ܔ��ɂȂ�A�\���ɂȂ�A�S���ɂȂ�A�甭�ɂȂ�A�ꖜ���ɂȂ��������ł͂���B�������A�����u�Ȃ��������v�͑傫�������B
�ߑ�̗�����͍����ł���B�܂�A�l�������قǂ̒����a���@��A�O�ɓy�X��ς�œG�̏e������g�����B��X�͂����O�̂悤�Ɏv���Ă��邯��ǁA����܂ł̐퓬�`�ԂƂ͑傫���قȂ��Ă���B�Ȃ��Ȃ�A��m�̎d���͂܂����@�肩��n�܂邩�炾�B�y���d��������m�̕K�{�̍�ƂȂ̂ł���B
����͂܂��m���̏o�g�K�w�̕ω��ɂ��Ή����Ă���B���悻�\�㐢�I�܂ŁA�m���͐��P�M���Ȃǖ��Ƃ̏o�g�҂����������B�ނ�͓`���I�Ń��}���`�b�N�Ȑ푈�ς������Ă����B�푈�ɂƂ��Ċ̗v�Ȃ͎̂m�C�ł���A�t�F�A�v���C�̐��_�ł���A�Ƃ����悤�ɁB�������A���ꂪ�͍���ɂ���ĕς���Ă䂭�B�u�푈�v���u��Ɓv�ɂȂ����B
�@�֏e�̔����ƍ̗p�̊Ԃɂ͐��\�N�̃^�C�����O������B���݂̂悤�ɐV���킪�����ɍ̗p����鎞�ォ�猩��Ί�Ȃ��Ƃ����A�e���̌R���͂��̐V����ɂ������ɒ��т����킯�ł͂Ȃ������B���̐��\�������̈Ӌ`����������Ȃ���������ł���B
�₪�āA�A���n�g�勣���̒��ŁA�@�֏e�͍L�����Ă䂭�B�A���n�ɂ�����Z���̖\�����������̂ɁA�@�֏e�͂����������̈З͂��������炾�B����́A�@�֏e���u�퓬�v�̓���ł͂Ȃ��A�u�E�C�v�̓����������ł���B
����ȕ��ɁA�ߑ�ɂ�����푈�̈Ӗ����A�@�֏e���L�[���[�h�ɂ��ė]���Ƃ���Ȃ��`���o�����̂��A�W�����E�G���X�u�@�֏e�̎Љ�j�v�ł���B
�푈�ƕ��킪����Ƃǂ�قǐ[�����т��Ă��邩�A�ϔO�I���a��`�҂ɂ͑z�����ł��Ȃ����낤�B�{���ɏ��������R���j�����Ƃd�E�b�E�G�[���́A����Ȃ��Ƃ������Ă���B�u�����́w���x�����ȁx���j�Ƃ��A�R���Z�p�Ƃ��ꂪ�����̐����ɋy�ڂ��e���̕��͂ɂ��育�݂��Ă����B�ނ�͂��̃e�[�}���s��������������ł���v�B���Ăł������炵���B���{�Ȃ�Ȃ��̂��ƁA�������낤�B�����푈�ɂ��Ă̒m�����}�j�A�ɓƐ肳���Ă����ׂ��ł͂Ȃ��B�\�N�O�ɖ|�o�ł��ꂽ���A�K���ɂ���łɂȂ邱�ƂȂ��A�ł��d�˂Ă���B�s�K�ɂ��A�������ǂ܂��ׂ��������Ă���悤�ȋC������B
���������d�ʎ�g�������S�o�i���O���@�t�����j
�ώ��ݕ�F�i�������ڂ��j
�ω��l��
�s�[�ʎ�g���������i���悤����͂�ɂ�͂�݂����j
�m�b�̍s�����Ă����Ƃ�
�ƌ����]�F���i���悤�����������j
���̐��̐��E�͎��̂��Ȃ��Ƃ������Ƃ��͂�����Ǝ�������
�x��؋���i�ǂ��������₭�j
�����Đ��̂��ׂĂ̋ꂵ�݂��Ђ���~��ꂽ
�ɗ��q�i����肵�j
�߉ނ̒�q��
�F�s�ً�@��s�ِF�i�����ӂ������@�����ӂ������j
�`������Ƃ������Ƃ͎��̂��Ȃ��@���̂��Ȃ��Ƃ������Ƃ͌`������
�F������@���F�i���������������@���������������j
�`�����邩�炱�����̂��Ȃ��@���̂��Ȃ����炱���`������
��z�s���@�����@���i���䂻�����悤�����@�₭�Ԃɂ悺�j
���o�A�L���A�ӎ��A�m���ɂ������Ă��@�܂��܂������̂��Ƃ�
�ɗ��q�i����肵�j
�߉ނ̒�q��
�����@���i������ق����������j
���̂������̌��ۂ͋�z�ł���
�s���s���i�ӂ��悤�ӂ߂j
���܂��Ƃ������Ƃ��Ȃ���Ύ��ʂƂ������Ƃ��Ȃ�
�s�C�s��@�s���s���i�ӂ��ӂ��悤�@�ӂ����ӂ���j
���ꂢ�Ƃ������Ƃ��Ȃ���Ή����Ƃ������Ƃ��Ȃ��@������Ƃ������Ƃ��Ȃ���Ό���Ƃ������Ƃ��Ȃ�
���̋@���F����z�s���i�����������䂤�@�ނ����ނ��䂻�����悤�����j
���̂��Ȃ��Ƃ������Ƃ̒��ɂ́@�`���Ȃ��܂����o�A�L���A�ӎ��A�m�����Ȃ�
���Ꭸ�@��g���i�ނ���ɂт����j
��A���A�@�A��A�́A�S���Ȃ����
���F�������G�@�i�ނ������悤�����݂����ق��j
�`�A���A���A���A�G�A�@���Ȃ�
����E�@�T�����ӎ��E�i�ނ����@�Ȃ����ނ����������j
��E���Ȃ���@�ӎ��E���Ȃ�
�������@���������s�i�ނނ݂悤�@�₭�ނނ݂悤����j
�������Ȃ��Ƃ������Ƃ́@�܂��܂��������Ȃ��Ƃ������Ƃɂ���
�T�����V���@�����V���s�i�Ȃ����ނ낤���@�₭�ނ낤������j
�V���⎀���Ȃ��Ƃ������Ƃ́@�܂��܂��V���⎀���Ȃ��Ƃ������Ƃɂ���
����W�œ��i�ނ����䂤�߂ǂ��j
�ꂵ�݂⎷�����Ȃ������@
���q�������@�Ȗ��������i�ނ��₭�ނƂ��@���ނ���Ƃ����j
�m���Ȃ���Γ����Ȃ��@�����Ă���䂦�ɂ��Ƃ��ƂȂ�
���F���@�˔ʎ�g���������i�ڂ��������@���͂�ɂ�͂�݂����j
���ׂĂ̐l�́@��邪�䂦�ɂق�Ƃ��̒m�b�̎��H�s��
�S�������G�i����ނ������j
�S�ɂ��܂������Ȃ�
�������G�́@���L���|�i�ނ��������@�ނ����Ӂj
���܂������Ȃ��䂦�Ɂ@���|���Ȃ�
������Ă�|���z�@���ퟸ���i����肢�����Ă�ǂ��ނ����@�����悤�˂͂�j
�����͂Ȃ�Ă��邷�ׂĂ̌�����l������@�i���̐Â��ȋ��n�ɓ��B����
�O�������@�˔ʎ�g���������i������Ԃ@���͂�ɂ�͂�݂����j
�ߋ��A���݁A�����̕��́@�m�b�̎��H�s�ɏ]���Ă邪�䂦��
�����ӑ����O�W�O����i�Ƃ����̂����炳��݂₭����ڂ����j
���̂����Ȃ��ō��̌���
�̒m�ʎ�g�������i�����͂�ɂ�͂�݂��j
�m�邪�䂦�ɒm�b�̎��H�s��
����_��@���喾���i����������@�������݂悤����j
���ꂱ���̑�Ȃ�^���̌��t�@���ꂱ�����̂��߂̐^��
�������@�����������i���ނ��悤����@���ނƂ��ǂ�����j
�ō��̐^���@���ꂱ����ׂ���̂̂Ȃ��^��
�\����؋�@�^���s���i�̂����悢�������@���ӂ��j
�ꂵ�݂͑S�Ď�菜�����@�^���ł��肤���ł͂Ȃ�
�̐��ʎ�g���������i�����͂�ɂ�͂�݂�����j
�䂦�ɒm�b�̎��H�s�Ƃ�
�������H�i�����������j
���Ȃ킿�����Ă��킭
㹒�@㹒��i����Ă��@����Ă��j
�����@������
�g��㹒��i�͂炬��Ă��j
�ފ݂ɉ�����
�g���m㹒��i�͂炻������Ă��j
���S�ɓ���������
���m��d�i�ڂ������킩�j
��肻�̂��̂ł���
�߂ł���
�ʎ�S�o�i�͂�ɂ₵�悤�j
�m�b�̎��H�̂��o
����K�i��c�āj
�����q���̂��������Ƃ́A�F���̏��Ƃł������B����́A�������łɁA�P�O�O�N�ȏ���������Â����̂ł������B�����̓�K�́A���Ƃ̂˂ŁA�V����͂��Ă��Ȃ��A�Ⴍ�ĈÂ����̂ł���B�c��͂�����u���v�܂��́u����K�v�Ƃ��ł����B���͒҂Ƃ��Ȃ��Ӗ��ŁA���Ƃ��Ƃ́A����ɍ����̈ӂł������낤�Ƃ����Ă���B�܂肻��́A�V����͂����悤�ȋ����Ƃ��Ă̓�K�������̂ł͂Ȃ��̂��B�ނ����̉Ƃ́u��K�v�Ƃ����̂́A�݂Ȃ����������̂������B�����ېV�̂���܂ŁA���{�̏����̏Z��ɂ́A�{��K�͂Ȃ��Ȃ������Ȃ������B
����ł́A���m�K���͓�K�������Ă������A�Ƃ����ƁA���͂����ł͂Ȃ��B���Ƃ��A�ӂ��̂���̓V��t�́A�O�w�A�ܑw�Ɨ��h�����A���̂Ȃ��̊K�i�͌X���}�ŁA�펞�����肨��ł��邵����̂ł͂Ȃ��B���́A�a���Ŏ���̊K�i�������肨�肷��Ƃ��A���������̂̐��܂Ȃ��悤�ɋ�J���邪�A�a���͕��ʂł̈ړ��͂Ƃ������A���̓I�ړ��ɂ͂ނ��Ă��Ȃ��B�K�i�̏��~�ɂ́A�����Ђ炢�Ă��܂��Ăǂ��ɂ��������������̂��B���m�Ƃ����ǂ��A�т̂ق��ɁA�����Ђ�����a�������������̂�����A���������������̈�������́A���܂肩��肪�Ȃ������͂��ł���B
�Ƃ���ŁA�ނ����̓V��t�̂Ȃ��̊K�i���݂�ƁA�㉺�̗��e���A���ɋ���ł�������������Ă��邪�A������������ɂ͂Ȃ��Ă����A�����ƂȂ���ł��A������͂����Đ��ė��Ƃ�����̂������B���Ƃ��ƓV��t�Ƃ������̂́A�펞�A�����Ől�����Z����悤�ȁu����v�Ƃ��������A�ً}�Ȃ����ɓ������ށu������v�ł������B������e�w�Ԃ̊K�i�͉��ݓI�Ȃ��̂ŁA���ł����ė��Ƃ��āA�G��h��ł���悤�ȍ\���ɂȂ��Ă���̂ł���B���m��������ʂɋ��Z���A��������Ƃ���́A�V��t�Ƃׂ͂̉��̂ق��ɂ���A���Ƃ��Ă̊e��̌����ł��邱�Ƃ������B
�����ł��������B�����ł͎��@�̓����̏�w�́A���̓W�]��Ƃ��Ē��]������A�Ƃ����v�f���悩�������A���{�ł́A����������݂����邽�߂����̂��̂ł������B���̂�����ے��I�Ȃ��̂́A�@�����̋����ł���B����͓��{�ł͂����Ƃ��Â����z���ł��邪�A�������͓�w�̓����ɂȂ��Ă���̂ɁA���������ɂ͓�K�̏����Ȃ��̂ł���B����ł͓�K���ĂƂ����Ă��A�����O���璭�߂邽�߂����̂��̂ł���B�����̊e��̓��ɂ������ẮA����͊��S�Ƀ��j�������g�A���̎��o�|�p�i�ł����āA�Ƃ��Ă��ォ��̒��]�����̂��肷�邵����̂ł͂Ȃ��B��r�I�������肵���K�i�����Ă��鋻�����̌d�̓��ł��A�����͂���ΊK�i�������ŋ����͂Ȃ��A��t���̓����ɂ������ẮA��ɂ�����K�i����Ȃ��B
�Ƃ���ƁA�Z��ɂ����炸�A���{���z�ɂ́A�̂��ɂׂ̂��A�O�̗�O���̂����āA�Z�ނɂ���������u��K�v�Ƃ������̂��Ȃ������̂ł���B�Ɍ�����A���{���z�́A���̔������疾���̂���܂ŁA�啔���A���Ƃ��Ă̌��z�\���ɏI�n���Ă����Ƃ����Ă����B����́A���܂ł������̐��E�̊ό��q�����߂�A�����ꂽ���z������Y�����������Ƃ��ẮA�܂��Ƃɕs�v�c�Ȍ��ۂł���A�Ƃ�����B
�ł́A���{�ȊO�̐��E�ł͂ǂ����낤���B���܂��炨�悻�O�A�l��N�܂��A���E�ŌÂ̖@���ł���o�r���j�A�́w�n�����r�@�T�x�ł́A��K�������Đl�������A���邢�͂��̉��~���ƂȂ��Ď葫��܂����Ƃ��ɂ́A���̉Ƃ����Ă���H�̎葫��܂�A�^�������̐l�����Ƃ��ɂ́A���̑�H�����Y����A�Ƃ����K�肪����B�Ƃ����Ƃ��납��݂�ƁA���̎���ɂ͂��łɈ�ʂɓ�K������A���������̓�K�͂����ւ�댯�Ȃ��̂ł��������Ƃ��킩��B�܂��A���[�}����ɂ��A�Ƃ��̐��{���A�������̍��w�A�p�[�g�̌��z�̋֗߂����������Ă���Ƃ�����݂�ƁA���w���͂��̂���ɂ����Ȃ肷����ł������A�������A���̉��E���w���́A���z�Z�p�����B���Ȃ��ނ����́A�댯���̂����Ȃ����̂ł������̂��낤�B��������ƁA�n�Ղ̈����A�������n�k�̑����킪���ł́A����͂����Ƃ��댯�ȍs�ׂł������ɂ������Ȃ��B�킪���ɓ�K�����B���Ȃ������̂��A����������������傫�������ł��낤�B
�������A�����܂ł��Ă��A�Ȃ����w���ɐl�тƂ���������̂́A���������Ȃ����낤���B����͂ӂ��A�s�s���������Ƃ�������B�o�r������[�}�̂悤�ɁA�ُ�ɐl�����c�������s�s�ł́A�l�͗��̓I�ɏZ�܂�������Ȃ������ɂ������Ȃ��B�����������ɂ́A�����ЂƂA�ׂ̗��R������悤���B����́u���Ɓv��`��`���Ƃ�����{���z�̗���̂Ȃ��ł��A��O�I�ɓ�K��������Ă��邻�̂����ꂩ���̂Ȃ��ɂ݂��������B
�����ȑO�̎���ɁA�����Ƃ��Ă̓�K��������Ă��鐔���Ȃ��������̃P�[�X�̂܂����ɁA��������ɋM�������Ă��O�t���z�Ƃ�����Z��������B���t�����t���́A�̂��Ɏ��ɂȂ������A���̑�\�I�Ȃ��̂��B�����������͏Z���Ƃ����Ă������ɂ��ʑ��ł���A�Ƃ��ɒ�߂邽�߂̖]�O�Ƃ��Ă��炦�����̂ł����āA���Ȃ炸��������N�����邷�܂��ł͂Ȃ������B�Â����y�E���R����ɐM���A�G�g�����Â�����s�́A��࣍��ȑ��w���{�a�ł��������A���̍ŏ��̂��̂ł������݂�ƁA��K�͕v�l�̋x�e���A�O�K�͒��ȁA�l�K�͖]�O�ƂȂ��Ă���B�܂肱��́A�����͂�����u�喼���v�̂��߂̈�咃���{�a�Ƃ��Ă���ꂽ���̂ł���B���ɍ]�ˎ���ɂ͂���ƁA���������Ă̗V����u���g����A�q�𔑂߂闷�Ă����B�����B�����ł͋q���K�ɂ����邪�A�������V�����h���ȂǂƂ����A���ʂȏꏊ�ɂ������Ă݂Ƃ߂�ꂽ���̂ł���B�����т̐��E�ł́A�g�������ɍS�D�����A��K����邳�ꂽ�Ƃ����̂͂������낢���Ƃł���B���Ă�ѐ������A�K�i�̏��~�ɕ֗��Ȃ悤�ɁA�����̂̐������炰�āA���̉��݂̂��������@�ق���������Ȃ���A���V�������ĊK�i���g���g���Ƃ������Ă��������̂��B���čŌ�̂��̂́A��͂�]�ˎ���̏��Ƃł���B�傫�Ȓ��ƂȂǂł́A��K�Ƃ������A�������u�ɂ�������A����l�̐Q�Ƃ܂肷��ւ�Ɏg�p���Ă����肷��B����������͂����܂ł���K�Ƃ������A�������A���m���ɂ����ƁA�A�`�b�N���Ȃ킿���K�ɑ���������̂Ȃ̂ł���B�Ƃ��낪�傫�ȏ��Ƃɂ͗�O���������B����͋����Ƃ�������̂ŁA���Ƃ̂����̑��̈�K�܂��͓�K�����~�ɂ������̂ł���B�����ł͕����҂ƂȂ������l�������A���捜���Ȃǂ��������Ă��āA����҂̂Ȃ��܂����߂ĉx�ɂ��鐢�E�ł���B�Ƃ��ɂ͎O�K�����������҂̂��������Ƃ��A���߂́w���{�i�㑠�x�ɂ݂��Ă���B
�ȏ�̃P�[�X���Ȃ��߂Ă݂�ƁA���{�̌Â�����ɑ��݂��������Ȃ���K�Ƃ����̂́A�ʑ��Ƃ����A�{�a�Ƃ����A�V����h��Ƃ����A����̐��E�Ƃ����悤�ɁA������̏ꍇ�ɂ�����N�����鐶����Ԃł͂Ȃ��A���܂������V���̐��E�ł��������Ƃ��킩��B�܂肻�����P�i����j�̐��E�ł͂Ȃ��A�n���̐��E�Ȃ̂��B��K�Ƃ����A�n�ʂ��瑫�̂͂Ȃꂽ���E�������т̐��E�ł��������Ƃ́A�����тƂ����s�ׂ̖{�������Ă���悤�ɂ�������B�����т͑�Ȃ菬�Ȃ茶�z�ɂЂ���s�ׂł��邩�炾�B�Ɠ����ɂ���́A����A��n�ɂ͂������Ă������������Ă���Ƃ��납��͂Ȃꂽ���Ƃ����A���_�I�~���ɂ��Ȃ�����̂ł������낤�B
�������A�����т̋�ԂƂ��ē�K������ꂽ�̂́A�����������_�I�Ȃ��̂����ł͂Ȃ��������B�����ɂ͂�͂�A����Ȃ�̕����I���R������̂ł���B���̂ЂƂ͂����܂ł��Ȃ��A�l�тƂɌ��z������т���������悤�ȍ��w��Ԃ�������]�̂悳�ł��낤�B���܂ł��z�e���ł́A�ŏ�K�ւ䂭�قǒl�i���������B���ɁA���Ƃ����̂悢���ƂŁA���C�̑������{�ł́A���Ƃ����͏d�v�Ȋ��̏����ł���B�����̓�K�ɏ��捜�������[����̂��A�厖�Ȍ|�p�i�⎼�C�⒎��������܂��낤�Ƃ���A�����̒m�b�ł������ɂ������Ȃ��B�����đ�O�ɁA��K���z������̂悢���Ƃ������˂Ȃ�܂��B
������܂��i�����S�j�j
�O����^��Ɏv���Ă������A�l�͎����Ɠ����悤�Ȑl�Ԃɂ͋��������ĂȂ��̂ł͂Ȃ����Ƃ������ƁB���ۓI�Ńs���Ƃ��Ȃ���������Ȃ����A���Ƃ��A�n�R�l�͊T���đ��̕n�R�l�ɑ��ė�W�ł���B����͖l���R�O�N�ȏ���n�R�l������Ă������Ƃ���̎����ł�����B�܂��A�a�l�͊T���đ��̕a�l�ɑ��ė�W�ł���B������l���g�̎������B�������͂邩�ɕn�R�Ȑl�ɑ��Ă͓���邪�A�����x�̕n�R�l�ɑ��Ắu���_���̎g����������A�I��������v�ƌ��������Ȃ��Ă��܂��B�����̑��q���Љ��`�҂ɂȂ�A�{�����e�B�A�ɂȂ�B�������͂邩�ɏd�ǂ̕a�l�ɑ��Ă͓���邪�A�����x�̕a�l�ɑ��Ắu�ȂA���̒��x�̂��ƂŃM���[�M���[�����ȁv�Ƃ����Ȃ߂����Ȃ��Ă��܂��B�l���g�A�����ŁA�����ł��Ȃ��Ȃ��āA����͂����܂����ȂƎv�������Ƃ����邭�炢�Ȃ̂ŁA���̒��x�̕a�l�ɂ͂��܂蓯��Ȃ��B�t�ɁA�����ƂЂǂ��A�ċz���~�܂��Ĉӎ��s�����R��������������ՓI�ɐ����Ԃ����Ƃ����������҂���u���Ȃy�������v�Ƃ����Ȃ߂�ꂽ���Ƃ�����B����Ă����̂͏�Ɍ��N�Ȑl�����������B
�����Ŋ�{�����������Ă����B�������͕n�R�l�ɓ���邪�A�n�R�l�͕n�R�l�ɂ͓���Ȃ��B���N�Ȑl�͕a�l�ɓ���邪�A�a�l�͕a�l�ɂ͓���Ȃ��B���̂悢�l�Ԃ͓��̈����l�Ԃɓ����B���ƂȂ͎q����V�l�ɓ���邪�A�q���͘V�l�ɓ���Ȃ����A�V�l�͎q���ɓ���Ȃ��B����͎q���ƘV�l�͑Γ������炾�낤�B�������A�V�l�͘V�l�ɓ���Ȃ��B�u�V�O���炢�ŘV�l�C��肷��ȁv�Ȃǂƌ������B�j�͏��ɓ���邪�A���͏��ɓ���Ȃ��B�����Ƃ��ŋ߂͋t�ŁA�����j�ɓ����悤�ɂȂ��Ă������ȁB�j����������������A���݂��ɓ���邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�킯�����B
���l�̓u�X�ɓ���邪�u�X�̓u�X�ɓ���Ȃ��B���̌������炷��ƁA���j�ƃu�X�A�����ƃu�I�g�R�̃J�b�v���������ł���B�����ғ��m�͂��܂������Ȃ��̂��B�����Ɠ����l�ԂƂ͗F�B�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�e�q�Z��͒��������B���������𓌐����k�ɕ�����ƍł����̈����W���ł��オ��B���{�l�����m�l�ɗ₽���̂��������肳���炾�낤�B����ł̓A�����J�̔��l�ƍ��l�͂Ȃ����������H����́A���l�ƍ��l�͌����̓��u�ł���A���̓���������Ƃ��������������Ƃ�����B���m�l�̓A�����J�l�ɂƂ��đ��l�Ȃ̂��B
���Ă̕n�R�����{�ɓ�����̂͐��E��̋������A�����J�������B��i���͓r�㍑�ɓ����B�O�H�̖����͋Q�얯���ɓ����B�������A�~���������A�������삦�Ă���Q�����̎�Ŕ��j����A�Ă��̂Ă��ĊD�ɂȂ�B�Q�얯�����m�ł͓���Ȃ��̂ł͂Ȃ����B����Ƃ����̂͗��Ԃ��������Ȃ̂��B���ʂ��Ȃ��Ȃ�Γ���Ȃ��Ȃ�B���{�͍����Ɋւ�����蓯��̂Ȃ����ɂȂ����B���ʂ��Ȃ��Ȃ�Ƃ����͖̂{���ɂ������ƂȂ̂��낤���B
�����̂͂₳�������Ƃ����A�y�������Ƃł�����B������������̂͂ǂ����B�����Ċ�Ԑl�����邪�A�t�ɕ��𗧂Ă�l�������B����Ƃ��D�z���̗��Ԃ��ł���A�N�ɂł�����ł��A�N����������Ȃ��Ƃ����̂����z��������Ȃ��B�ł�����Ȑl���A���̋t�̐l�����Ȃ��悤���B
���M����i�����S�j�j
�ꉭ�������K�������̂����\�Ȃ��Ƃ����A�悭�l���Č���Έꉭ���㗬�K���A���邢�͈ꉭ�����w�K���ƌ��������Ă݂Ă����e�͂܂������������Ƃ��B�v����ɊK�����Ȃ��Ƃ����̂��^���ŁA���������ĂƂ����Y���Ƃ��Ⴄ�Ƃ��낾�B���Ăɂ����Y���ɂ��M���K���A�܂��͂���ɏ�����K�������݂��Ă���B���{���������珺�a�Q�O�N�܂ł͋M���i�ؑ��j�������B�����ȑO�͌����Ƃ����̂������B�a�l�������B�M���͐l������悵�Ă��������ɗV�ѕ邵�Ă��������z�������̂��B�����Ƃ琶�܂�Ȃ���̐l���ŁA�M���Ƃ͉����Ȃ�����M���̐����Ȃ�Ă킩��Ȃ����A�M���ɂ������ʂ͂������Ǝv���B
�r�㍑�i�Ȃ�Ŗ��J���Ƃ����Ă͂����Ȃ��̂��j�̉���M���ɂ͈����̂�����B���ꂱ���l������悵�Ă��������̌���������A�n���������A�������ėV�сA�j����ɎE���B���ł�����ɋ߂�����M�������邱�Ƃ͎������B�������A��i���̋M���ɂ̓G���[�g�̖��ɂӂ��킵���l�Ԃ����������B�M���Ƃ͂Ђ܂Ƌ������ė]���Ă���h�p�̍����A���{�̖L���Ȑl��̂��Ƃł���B�P�Ȃ�y�n�������M���Ƃ͌ĂȂ��̂ł���B���������̋M����������������Ȃ����A�����̋M���̓G���[�g�Ƃ��Ă̎��o���������B�Ђ܂Ƌ����ǂ��g�����B�|�p�Ƃ̃p�g�����ɂȂ�B�Ƃ����̂���ʓI�����A�w�ҁA�����ƁA���z�ƁA�@���Ƃ̃p�g�����ɂȂ����̂�����B�s��Ȍ��z����뉀���c�����M���������B�M���̂����Ƃ���͎����̋������R�Ɏg���邱�Ƃ��B�����珎���Ƃ͖����̂��炵���|�p�i���c����B�����A���̋��������ɕ����ɕ����Ă��܂�����ǂ��Ȃ邩�B�܂������Ȃ��A�����c��Ȃ����낤�B
���̓��{�ɂ͋M�������Ȃ��B���E����ݐi�ې������������M���̑��݂������Ȃ��B���{�̋����͌|�p�Ƃ̃p�g�����ɂȂ�Ȃ��B����Ȃ��Ƃ����Ă�����q�����R�W�L�ɂȂ��Ă��܂��B�����̓}���V������A�p�[�g�����ĂāA�q���Ɏ؋����c���B���ꂪ��ԗL���Ȃ��������炾�B�Q�O���I�ɓ����Č|�p�͎��B���ɓ��{�ł͑S�ł����B
�M���̑��݂������Ȃ��Ƃ����̂́A�l�ޕ����̊�{���т���ł͐��������Ƃ����A�M���Ԃ��͍��z�̐ŋ��z���グ�Ƃ����`�ōs���Ă���B�z���グ��ꂽ�ŋ��������I�ȕ��ʂɎg���Ă��邩�Ƃ����ƃm�[�ł���B�ŋ��͌������̋��^��A�_���ƁA�s���Y�Ƃ̕⏕���Ɏg���Ă��邾�����B�͂����肢���ă��_�g���ł���B�Ƃɂ������ł�邱�Ƃ͂��ׂă��_�g���A�����d��������Ă��A���Ԃł��Ɣ��z�ɂȂ�B�M���̂悤�Ȍl�����Ƃ����ƈ����Ȃ�B�����A�|�p����Ă悤�Ǝv������A�ŋ������炵�āA�M���ɋ����������邱�Ƃ��B�o�b�n�����[�c�@���g���x�[�g�[�x�������[�O�i�[���A����M���x���̃o�b�N�A�b�v���Ȃ�������A�㐢�Ɏc��悤�Ȏd���͂ł��Ȃ������͂����B
�M�������A�M���|�p��ے肵�āA��O�����A�|�b�v�A�[�g��ŏo�����̂͊v�V�h�A�i���I�̒m���l�ł���B�M����̉��y��������V���X�^�R�[�r�`��J�o���t�X�L�[�͌���������A���Ȕᔻ������������Ȃ������B�|�b�v�A�[�g�͈��ō���A���Ńu�[���ɂȂ�A���ŏ���������B���F�g���̂Č|�p�ł���B�㐢�Ɏc����̂ȂNJF���ł���B����ʼn��̕s�s�����Ȃ��̂����A�����A�Q�O���I��U�Ԃ������A�|�p�I�ɂ͕s�т̎��ゾ�����A�ƕЕt������͖̂ڂɌ����Ă���B
���Y���̎Љ�j�i�����ޖ�j
�l�ɂ͐����̕c��������B���̕c���͖{�l����߂����̂łȂ��A���Ƃ͒m��ʌÂ��̂��猌�����̑����J�̂Ȃ��ō��ɓ`�����Ă���B�l�͕c���Ƃ����������j���J�ɂȂ��Ƃ߂��Ă���̂ł���B���{�̕c���̑����͂��Ă̋�̓I�ȈӖ��������A�P�Ȃ�L���ɋ߂�������^����܂łɑމ����Ă��܂��Ă���B
���[���b�p�ł�����͎����悤�Ȃ��̂ł��邪�A���[���b�p�̕c���̑������E�Ɩ��ł���Ƃ��납��P�Ȃ�L���Ƃ��Ċ���邱�Ƃ̂ł��Ȃ��c���������̂����Ă���B�}�b�N�X�E���F�[�o�[�̕c�����D���Ƃ����Ӗ��ł���Ƃ����Ă��A�G�[���b�q�E�V���~�b�g�̂��ꂪ�b�艮�Ƃ����Ӗ��ł���Ƃ����Ă��A���̐E�Ƃ̗��j�͂��̕c���̉������j�̔����̔ޕ��ɏ����Ă䂫�A�D���Ƃ��Ẵ��F�[�o�[�A�b�艮�Ƃ��ẴV���~�b�g���l����l�͂��Ȃ��B
�������u���Y���s�l�v�u�Y���v�Ƃ����c���������Đ��܂ꂽ�Ƃ�����ǂ����낤���B������ߋ��ɂ����Ă͎Љ�I�ɏd�v�ȐE�Ƃ̖��ł��邩��p����K�v�͑S���Ȃ��B���Ƃ��Y�����ߋ��ɂ������˖��ł����āA�Y���ɐG�ꂽ�҂��˖��̒n�ʂɂ����Ă��܂��قǁA�̎�����|���ꂽ���݂ł������Ƃ��Ă��A�\�㐢�I�ɂ��˖��Ƃ��Ă̒n�ʂ͏��ł��A�Y�����s�������l�����Ă���B�ߑ㖯���`�v�z�͐l�͐��܂�Ȃ���ɂ��ĕ����ł���A�Ƃ����������т��A�Y���Ƃ����c���������Ă����Ƃ��Ă����݂ł͌��I�ɂ����I�ɂ����[���b�p�ł͉����Q�i���ʁj�͂Ȃ��̂ł���B
�������ʂ��������łȂ��q�ǂ��̍��ɂ͂ǂ��������낤���B�c���̍��ɂ��̕c���̂��߂ɗV�їF�B���炩�炩���A�͂₵���Ă��A���ɂ����v�������Ȃ��������낤���B�c���Ƃ��ɂ͑S�������̂������肵��ʉ����̂��߂ɋꂵ�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ���������B����͎������̈�����悬���Ă䂭���j�̉e�Ȃ̂ł���B
�G���[�E�A���O�X�g�}���������̕c���̌�������o�����ČY���Ƃ������O�̗��j�I�E�n���I���z�ׁA���O���Y�����ǂ̂悤�ȖڂŒ��߂Ă����̂��𖾂炩�ɂ��悤�Ƃ����Ƃ��A�c�����̗��s�s�Ō��ɂ����̌������[���Ƃ���Ŕޏ��̌������x���Ă����̂ł͂Ȃ����ƁA���͂��z�����Ă��܂��B
���̂Ȃ�A���O�X�g�}���Ƃ����Y���s�l�Ƃ����Ӗ�������ł���B
�������A���O�X�g�}���͒P�Ɏ����̗c�����ւ̊������炱�̂悤�Ȍ������n�߂��̂ł͂Ȃ��B�ޏ����c�����ɂ������S�̏��͔ޏ���l�̂��̂ł͂Ȃ��A�����̓���̕c�������l�X�̑̌��ł��������ɈႢ�Ȃ��B��A�̌������I�����Ƃ��A�A���O�X�g�}���̖ڂ̑O�ɊJ���ꂽ���E�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂������낤���B���������l���l���ق��A�E���Ƃ������Ƃ͌���ɂ����Ă����l�����F���Ă���킯�ł͂Ȃ��B���Y��p�~�����������Ȃ��Ȃ��B�����������������\�㐢�I�ɂ�����܂Ń��[���b�p�ł͎��Y���s�l���劈������A�Y���͋��낵���g�̖т��悾�E�Ƃ̐l�ԂƂ�����ۂ��ʂ����Ȃ������B
�����ɂ����Ă������̉e���Ђ������Ă���Y���Ƃ����E�ƂƂ��̕c���̗��j��H���Ă䂭�Ƃ��A�������͒����������ߑ㏉���ɂ����ēs�s��_���ɂ����閯�O�̐����̂Ȃ��ŏ��Y���ǂ̂悤�Ȃ��̂Ƃ��Ă����Ƃ߂��Ă����̂���m�邱�Ƃ��ł���B����͓����ɒ����������ߑ�ɂ����ă��[���b�p�Љ�̂Ȃ��ł́A�l�ԂƐl�Ԃ̊W�̂����������̋ɂɂ����Ċώ@���邱�ƂɂȂ�B���̂Ȃ�l�ԂƐl�Ԃ̊W�̈���̋ɂɈ�������A���r�܂����邷���������̂���������锽�ʁA�����̋ɂɂ͐l���l���ق��A�E���Ƃ����W�����邩��ł���A���̗��ɂ̊Ԃł��̎���ɂ�����l�ԂƐl�Ԃ̊W���J������Ă��邩��ł���B
���āu���Y�v�͈�@�s�ׂɂ���ĎЉ�������Z�����S���Ŗ������߂̋V���ł����ċ��]���邢�͎�p�Ƃ��Ă̐��i�������Ă����B���ꂪ�\��A�O���I�ϖe���˖�����Y���ɂ���āu���Y�v���s����悤�ɂȂ����B�����Ĕƍ߂ɂ��Ă̍��{�I�ȍl���������̊Ԃɕω������B
���Ă͔ƍ߂̍s�ׂ����ł���A�ƍߎ҂̓��@�Ȃǂ͖��ł͂Ȃ������̂����A�V�����s�s�@�ɂ����Ă͔ƍ߂̍s�ׂ����ƍߎ҂̕��ɒ��ڂ�������ꂽ�̂ł���B�܂�ƍ߂̐ӔC�͌l�ɂ���Ƃ݂��A�ƍߎ҂͗ϗ��I�ɕ]������邱�ƂɂȂ����B�l�Ԃ͐V�����s�s��Ԃ̂Ȃ��Ō݂����J�������I�Ɍ������Ă䂫�A���Ă̎�p�I�E�_�b�I���E����������A�ƍ߂ɑ��Ă���p�ɂ��Љ�̏��̎�������l�̐ӔC�̋����ւƐi��ł������̂ł���B�����̂̒����ɔw���s�ׂ�Ƃ����҂͍���ϗ��I�����ɂ���Čl�Ƃ��āu��������v�悤�ɂȂ����B���̌o�߂͓����ɐl�Ԃ������̂̒��Ō������o�����ɕ邵�Ă����i�K����������o����ɂ����鎩��̊o���̉ߒ��ł��������B�l�Ԃ͂͂��߂Ė@�̑O�Ōl�Ƃ��ēo�ꂵ���̂ł���B
���̓_�ł��Ắu�Y���v�̂Ȃ����E����A�u�Y���v�����܂��\��A�O���I�Ƃ�������̓��[���b�p�Љ�j�Ǝv�z�j�A�����j�̂Ȃ��ő傫�ȉ���ł������B���Đl�Ɛl�����ԊW���J�͐_���Ȗ@�ł���A�Ƃ����������Ђ������Ă����B�������Ȃ���A�L���X�g���̐Z���Ɠs�s�̝����A�s�������̍������̂Ȃ��Ől�Ԃ̗����͐V�����ϗ��ނɂ��������B���Ђ��������Ɋ�Â��c�_���d����悤�ɂȂ����B�l�Ԃ͑P�����߂ēw�͂��ׂ����݂Ƃ���A���̌���Ŏ������s�����s�ׂɑ��Ă��ӔC�����ׂ����݂Ƃ��ꂽ�̂ł���B
���̂悤�ȌX���̂Ȃ��Ŗ@�͏\�I�ɂ͖����@�ƌY�@�Ƃɕ�����Ă䂭�B�\�I�ɂ͂��܂��u�Y�@�̒a���v�͋ߑ�Љ�̖G��������铮���̈�[�ł���A�l�Ԃ̎���A���̎��o�̈�̕\���ł��������B�l�Ԃ���̓I���݂ł��邱�Ƃ��������ꂽ�Ƃ��A���R�l�Ԃ͐ӔC�����̂Ƃ��ĂƂ炦���邱�ƂɂȂ邩��ł���B
�������ɔƍ߂������ӔC�Ƃ��Ĉӎ�����Ă�������ɂ͘A�����̂悤�ɔƐl�̈�@�s�ׂ̌��ʂ��Ƒ��S���ɋy�ԂƂ����s�����Ȗʂ��������B�Ɛl����̓I�l�ԂƂ��ĂƂ炦�A�l�ɔƍs�̐ӔC���Ƃ点��Ƃ����ߑ�I�Y�@�͂��̂悤�Ȉ����ɑ��ĉ���I�Ȉ�����ӂ݂������̂ł���B
�������Ȃ��瑽���̔ƍ߂͎Љ�I�ȍs�ׂł����āA���̐l�Ԃ⎞����Ƃ͑S�����W�ȁA���̌l�����̐ӔC�Ƃ��Ă̔ƍ߂Ƃ����̂��l���ɂ����B�ƍ߂Ƃ͔Ɛl�����̎����Љ���̂Ȃ��ő��̐l�X�⏔���x�Ƃ�������Đ����Ă����ߒ��Œ~�ς���Ă������s����s�����琶������̂Ȃ̂��낤�B�ƍ߂̌����͂��̎���̐l�Ɛl�Ƃ̊W�Ƃ����}��鏔���x�̂Ȃ��ň�܂��̂ł����āA���̌���Ŕƍ߂�������z�������ՓI�Ȏړx�Ōv�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����̐��ɂ���Ĕƍ߂̎�ނ�͈͈͂قȂ�A���鍑��W�c�ɂ����Ĕƍ߂Ƃ����s�ׂ����̍���W�c�ɂ����Ă͔ƍ߂ɓ���Ȃ��Ƃ�����͂����݂���B
�ƍ߂��Љ�I�ӔC�̖��ł���Ƃ������Ƃ́A�ЂƂ̔ƍ߂��������Ƃ��A���̔ƍ߂ɑ��Ă��̎Љ�̍\�����͑����ꏭ�Ȃ��ꉽ�炩�̐ӔC���Ă���Ƃ������Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��B�Ƃ��낪�\��A�O���I�ȍ~�ɂ�����Y�@�̓W�J�͔ƍ߂̐ӔC���l�̓��@�ƍs�ׂɋ��߁A�s�҂�f�߂��ď������铹���J�����B
����͂������ɍ����I�ȐR���ւ̓����J�����̂ł��������A����ȍ~���Ƃ��ЂƂ̎Љ�S�̘̂c����g�ɔw�������悤�Ȕƍߎ҂��������Ƃ��ł��A���̔ƍ߂͖{�l�̓��@�ƍs�ׂɂ���čق���A���̎Љ�S�̂��\������l�X�͉������炻�̍ٔ������]����݂̂ŁA���炩����邱�Ƃ͋H�ƂȂ����B�ЂƂ̎Љ�̘c�̕\���Ƃ��Ă̔ƍ߂̔Ɛl�͂�����̎Љ�̘c�̋]���҂Ȃ̂����A�ނ͈�l�ł��̎Љ�̘c�̑S�̂�w�����A�f�߂���A�Y��̘I�Ə����Ă��܂��B���̐l�X�͂��̂悤�ȕ�ڂɂ��Ă������Ƃ͂������Ȃ��o�����Ƃ��Ă�݁A���̓��̎d���ɖ��v���Ă䂭�B�����炭���݈ӎ��̒�ł͒����s�s�̎s�����ƍ߂������Ɩ��W�ł͂Ȃ����Ƃ�m���Ă����̂ɁA�S�̂��\���ĔƐl�����Y����Y���ɑ��Ă�������������A���̂����ꂪ�̎��ւƓb��ł������̂ł��낤�B
����_�\���I�I�[�f�B�I���A�i���O���R�[�h�͂P�O�O����������i��҂҂̌Z�j
�����͎���̕ω��̌��������X�������Ă���B����̕ω��́A���܂ł��������������Ƃ��Ă��A����قǂ̌������ω��͖ő��ɂȂ��������Ƃł͂Ȃ��̂��B���������������Ă����R�U�N�ԁB����ȂɎ���̕ω�����X���Ŋ����邱�Ƃ͂Ȃ������ƒf���ł���B����̕ω��́A�h�s�A�o�C�I�A�i�m�e�N�̂悤�ȐV�Y�Ƃ����X�Ɛ��ݏo���B���Ǝv������A����̕ω��Ɏ��c����A���O�̓��̂悤�ɏ������邩�Ǝv��ꂽ�Y�Ƃ��ˑR�������邱�Ƃ�����B�V���S�A���c���H�A�R�}�c�B���č��x��������̏I���Ƌ��ɖY�ꋎ���Ă�����Ƃ̊������㏸���Ă���B�����̍��x�o�ϐ����Ō������Ɓi���H�A�_���A��`�A�r���j�����������Ă��邩�炾�B�܂��Ɏ���̕ω����s����̕ω��Ɏ��c���ꂽ���̂��������t��\�I�ȗ�ł���B
���ɂ�����B�Ⴆ�g���b�N�̃X�s�[�h���~�b�^�[�K���B�X�O�L���ȏ�̑��x�������u���g���b�N�ɋ`���t�������̖@�����{�s����Ă���Q�����B�����̐��E�͌��I�ɕς�����B���܂Ŏ���̔g�Ɏ��c����Ă����D���A���A�i�q�ݕ��������̒����������n�߂��̂��B�i�q�ƃg���b�N�ɂ́A���͐[������������B�i�q���܂����S���������B�J�g�͌������X�g���J��Ԃ��Ă����B�����đS���K�͂ō��S�̃X�g�����Γ��{�̕����͖��ԂɂȂ�A�J�g�̗v���͂��₷���ʂ邾�낤�Ǝv��ꂽ�B��������͕ς���Ă����B�J�g�͎���̕ω��ɋC�t���Ă��Ȃ������B�����͂��łɉݕ���Ԃ���g���b�N�̎���Ɉڂ��Ă����̂��B�����ĘJ�g�͕������B����̕ω����ے��I�ɕ���鎖�������A���ꂪ���x�́u�g���b�N����i�q�ݕ��ցv�Ƃ���������̗��ꂪ�ł�����̂��������Șb�ł���B
�܂��A����܂�����̔g�Ɏ��c����Ă����Ǝv���Ă����u�����̑�z�v�B���ꂪ���ݕ���������B���R�͍���Љ�A���N�u���̍��܂�Ƃ��������̗���ł���B�����̑�z�̗��p���́A���̃f�t���Љ�̒��łނ��Ⴍ���ፂ���B�Ȃ�ƓX���Ŕ����l�i�̂Q.�T�{������̂��B����ł����v�����܂��Ă���Ƃ�������s�v�c�ł���B����҂͂����������Ă���A���邢�͎����̌��N�ɑ��Ă�����ɂ��܂Ȃ��Ƃ������Ƃ�����̂��낤�B
�����Ŗ{��̃I�[�f�B�I�ł���B�I�[�f�B�I�����Ă͍��x��������̉Ԍ`�Y�Ƃ̂ЂƂ������B���ꂪ����̕ω��Ɏ��c����A����}�j�A�̊ԂōׁX�Ɛ����Â��Ă��邾�����B�����I�[�f�B�I�ɖ����͂Ȃ��̂��낤���H�I�[�f�B�I�E�}�j�A�ɂ͔ߊϘ_�҂������̂ŁA�����������Â��������܂��܂��Â��Ȃ�B���������̌���������ω��ɂ����āA�I�[�f�B�I�Ɍ����ƂȂ���̂��������U�������B
���̂ЂƂ��u�X���[�t�[�h�v�̃u�[���ł���B����͉����Ӗ����邩�ƌ����ƁA���X���Ԃɒǂ��A�����������������𑗂��Ă�����{�l�́u���Ԃ����������Ɏg�������v�Ƃ����~���̕\��ł���ƌ��Ă悢�B�܂��G���u�o�����v�u�j�̉B��Ɓv�ȂǂɌ�����悤�ɁA�����̋�Ԃ��X�^�C���b�V���ɁA�����Ă�肺�������ɉ��o�������Ƃ����~�������܂��Ă���B�s���ԂƋ�Ԃ����������Ɏg�������t�B���̋M��������A���ꂪ�N�X���̌X���ɔ��Ԃ��������Ă���B�����Ă��̎��ԂƋ�Ԃ��Ɍ��ɂ܂ł��������Ɏg����u�I�[�f�B�I�v���V���Ȏs�����ĕ�������ƍl������B���ɃA�i���O���R�[�h�𒆐S�Ƃ����s���A�E�I�[�f�B�I�͂������B
���܂ł̓��{�l�̂��������́A���������B���邢�͕������������Ƃ������̂������B�����鐬����ł���B�u�����h�i���A�x���c���B���\�N�O�͓d�C���i�͖��̏��i�Ƃ��Ă����ߕ��ꂽ���Ƃ�����B�������Ȃ���O�q�����悤�ɁA���{�l�̎�͐��������M����ւƂ��傶��ɕς�����B������I�[�f�B�I�����܂ł̂悤�ȍ����ȃn�[�h���A�\�t�g���o�J�o�J�W�߂�Ƃ��������̂����荂�������ɃV�t�g������̂Ǝv����B
���������L�����n���Ă��A�I�[�f�B�I���������Ă����Ȃ�Ęb�͂Ƃ�ƕ�����Ȃ��̂������B����̓I�[�f�B�I�Ɏg�����ԂƋ�Ԃ̖��A�����Ă����ɂ����鑽�z�̂������I�[�f�B�I�����̂��܂����ɂȂ��Ă�����̂ƍl������B���������̖��̒��ŁA��ԂƂ����Ɋւ��Ă͂����ăn�[�h���͍����Ȃ��B
���ې��{���\�ɂ��ƂQ�O�O�U�N�����肩����{�̐l���͌���n�߂�Ƃ����B���{�̐l��������Ƃ������Ƃ́A��l������̋��Z��Ԃ�������Ƃ������Ƃł���A�����̃X�y�[�X��v�������I�[�f�B�I�ɂƂ��Ă͒ǂ����ł���B�܂����y��ʏȂ��v�悵�Ă����[�x�n����ʖԂȂǂŁA����ɍ�����l���̎g����X�y�[�X�����b�`�ɂȂ���̂ƍl������B
�����̖��́A���f�t���s�����ŋꂵ�����A���N�����Ȃ�ʒ��������œ��{�͍D�i�C�ɓ]�����������B���������́A�Q�O�O�W�N�k���I�����s�b�N�A�Q�O�P�O�N��C�����Ɍ������č��x�o�ϐ����܂�������B�U�O�N����{�Ə����Ă����B���������v�͂P�O���l������B���̗���ɏ��ʎ�͂���܂��B���̗���ɏ�肳������A���{�o�ς͂Q�O�P�O�N���܂ł͈��ׂ��B
����ăI�[�f�B�I�̕��������܂�����ő�̗v�����s���ԁt�ƂȂ����B���{�l�͂��Ǝ��ԂɊւ��ĕn�����ƌ����Ă���B����͓��{�̕����ɐ[���N�����Ă���Ǝv����B
���������B����Q�[����Ђ̘b���B���̃Q�[����Ђɂ͓��ނ̎Ј�������B�������o�Ђ��āA�{���d�����n�܂鎞�Ԃ܂łɁA�ԗ]���ɓ����Ј��B�����Ė{���̎d�����I��������ƁA�ԗ]���Ɏc�Ƃ���Ј��B�������ԕ������ĉ�Ђɍv���͂��Ă��邪�A�͂����ĉ�Ђŕ]�������Ј��͂ǂ������H�^�����Ȃ���҂̕��ł���B�Ȃ����H����͓����ԗ]���ɓ����Ј��ł��A�X�}�[�g�ɗv�̂悭�������͍̂D�܂�Ȃ�����ł���B��̌u���������������ƏƂ���钆�ŁA�������炵�āA�܂����鎞�ɂ͓D�ɂ܂݂�ē����p�����{�l�ɂ͍D�܂��̂ł���B������d���̐��ʈȏ�ɁA�u�������撣���Ă���Ȃ��v�Ǝv�킹�邱�Ƃ��̐S�Ȃ̂ł���B����͓��{�̕����ł���B���Ǝ��ʼn̂���u�u�̌��A���̐�v�B�Ƃ����̂��������B�b�q���ŁA�����������̒��Ŋ��܂݂�ɂȂ�A�J���~��ΓD�܂݂�ɂȂ鋅�������B�N���b�q�����h�[������ɂ��悤�ƌ���Ȃ��B����ȏ����Ƃ��낶�Ⴀ�k���̋��������͕s�����낤�B�s��������Ȃ����B�������������Ă��鋳�痝�O�Ɉᔽ���Ă����Ȃ����ƁB����Ȑ��_��f���Ă��A�Ȃ��b�q�����h�[������ɂ��Ȃ��B����͂Ƃ���Ȃ������A���܂݂�A�D�܂݂�̋����������������B����������犴�����邩��ł���B�����ɓ��{�̕����́A���������܂݂�A�D�܂݂�Ŕ|�����_�k�����̔��ӎ�������B�����炱�������s��̃T�[�r�X�c�ƁA�����ԘJ��������̂́A�������炫�Ă���Ǝv����B�P�Ɏd�����������炾�Ƃ��A�l����팸�����ŃT�[�r�X�c�ƁA�����ԘJ�����s����킯�ł͂Ȃ��̂ł���B���{�l�����Ԃɕn���������́A���{�×��̔_�k���������ɂ���ƌ����Ă悢�B
�Ƃ����킯�ŁA���̎��Ԃɂ��Ă̖��͌��\���[�����̂�����A������̂ł��邪�A������N���A����I�[�f�B�I�̕����͂P�O�O������Ƃ����ėǂ����낤�B
����Ձu���v�i��҂҂̌Z�j
����m�g�j����ŁA�V�Q�N�Ɉ�x�����s���Ȃ���錧�̊�Ձu���v�̓��W������Ă����B�ԑg�̒��łȂ��V�Q�N�Ɉ�x�Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��c�_�ɂȂ��Ă����B��������̂����A�ʔ����̂́A������C�l�i��������j���������V���Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ������ł���B
�C�l�Ƃ͉����H�Ñ�̊C�l�Ƃ͋����̂��Ƃł͂Ȃ��A����Ō����Ȃ炿�傤�ǗV�q���݂����Ȃ��̂ɂ�����B�D��Ŏ�ɐ��������A����ɂ��オ���Ă���B���Ƃ����łȂ��_�ƁA�ыƁA��H�ƂȂǂ��c�ށB�C�Ő�������l�Ԃ��Ȃ��ыƂȂ̂��H������D�����Ƃ��ɖ؍ނ��K�v�������ł���B
�C�l�͌Â�����q�C�p�ɒ����Ă����B���p��m�邽�߂ɂ́A���̓�����ǂ��ώ@���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�V���w�ł���B���͑��z�����邪�A���z�̓����ЂƂ����ł͕��p�͗ǂ�������Ȃ��B�����̂悤�ȍ��W�������������Ă������p���킩��̂ł���B�������q�s�Ƃ����͖̂�𒆐S�ɍs���Ă����B
���̐����ł��邪�A���͔N���o�߂���ɂ�āA�����Âp�x�������B�n���̎��]�̂Ԃꂪ�A���̂܂ܐ����̊p�x�̂���ɔ��f�����B���ꂪ�V�Q�N�ɂR�U�O���̂P�x�Â����̂��������B
�ŁA�Ղ�̂V�Q�N�ɂP�x�Ƃ����̂��A�������炫�Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����킯�B�^�U�̒��͂킩��Ȃ����A�Ȃ��Ȃ��ʔ����b�ł��ˁB
���]�Ă̂Q�P���i��҂҂̌Z�j
����m�g�j�Łu�]�Ă̂Q�P���v�Ƃ����ԑg������Ă����B������Q�O���N���炢�O�̔ԑg�ł���B�u�]�Ă̂Q�P���v�̓v���싅�j��ł����w�̖���ʂƌ�����قǗL���Ȃ��́B�ԑg�ł͂��̂Ƃ��̑I���ē̐S���A�@�m�@���A�_�ƂƂ�������悤�ȐE�l�|�����ׂ��ɏЉ�Ă����B���̔ԑg�͕��f�����A�싅�̉��[����`�������h�L�������^���[�Ƃ��đ�ςȔ������ĂсA�ς���̂ɐV�N�ȃV���b�N��^�����B�������߂Ă�ҌZ�̎��_�ł��̔ԑg������ƕʂ̈Ӗ��ŃV���b�N����B����́A�܂��싅���Â��Ƃ������Ƃł���B
���Ƃ����߂ɕ����]�Ă̕ω����B����͍��̃o�b�^�[�Ȃ�z�[�������ɂł��Ă���͂��ł���B��ʂɓo�ꂷ��]�Ăɑ���ߓS�̃o�b�^�[�͒N���ނ���͂ȃo�b�^�[����B������_����낤�Ǝv�����珬�H��������Ȃ��B���ہA�o���g�A�����|���̃T�C���B�����͍��ł��s���Ă��邱�Ƃł��邪�A�������Ȃ璷�ŗ͂���g���Ĉꔭ�t�]��_���ɂ���͂��ł���B
��������Ă킩��̂́A���ēɂ��ׂ������A���N�ɂ킽���ČP������Ă����E�l�|�Ƃ����̂́A�o�b�^�[�̒��ŗ͂̂Ȃ��ɂ���Ďx�����Ă������Ƃ��킩��B
���̃v���싅�Ɛ̂̃v���싅�A�����ς�������B����̓o�b�g���ς��A�����ǂ���Ԃ悤�ɂȂ�A�h�[������ɂ���ĕ��̉e�����Ȃ��Ȃ����B�܂��ؗ̓g���[�j���O�Œ��N���X�̑I��ł��z�[���������łĂ�悤�ɂȂ�A�o�b�e�B���O�}�V���ő������ɂ��Ή��ł���悤�ɂȂ����B����싅�͂��̂悤�Ƀn�C�e�N�����i�݁A�E�l�������Z�⓪�]�����������h���}�����S�ɏ��ł����B����ɏ��Ƃ��Ǝv������A�Z�⓪�]�����ɁA���ŗ͂̂���I�����ׂ�Ηǂ�����ł���B
����͌���̐푈�ɂ�������B�́A�푈�ɂ͋R�m���Ƃ������̂��������B�����Đ��ɂ̓h���}�����肻��́A���E�`�A�p�Y�k�Ƃ��Č㐢�Ɍ��p���ꂽ�B��������C���o�ꂵ�Ĉȗ��A�R�m���Ƃ����͖̂��Ӗ��ɂȂ����B���ł́A�j��͂����艓���֔����C���������ׂ邩���A���s��������d�v�ȗv�f�ɂȂ��Ă������B���������b��`�����u�p�Y����v�Ƃ����A�j��������B
����̐푈�ɂ��싅�ɂ����Ƃ������ʂ݂̂����߂���B�����ɂ͍������͂����Ă��A���}�����h���}�̓���]�n���Ȃ��B���ꂪ���݁i���܁j���܂�Ȃ����Ă���傫�ȗ��R���B�������Ȃ���ǂ�Ȃɏ��n�C�e�N�����悤�Ƃ��A�l�Ԃ̓��[�e�N�̂܂܂ł���B�����炢����l�Ԃ̓��[�e�N�ɉ�A����ł��낤�B�Ȃ��Ȃ�l���l�Ƃ��ĐS�h�蓮������邱�Ƃɂ͕ς�肪�Ȃ�����ł���B
���u�v�����v�y���܂���i���j
�y���܂��邪���̐��������Ă͂�R�N���B�P�Ɏ�҂ɐl�C���Q�̃^�����g�Ƃ��Ă����łȂ��A���W�I�E�g�[�N�̘b�@�����ꂩ��ς����v�����Ƃ��Ă̔ނ̖��͉i���ɋL������邾�낤�B
�u�F����A�����C�ł����v���u���A�F�A���C�����v�ɕς��A�I�}�G�A�����A�o�J�����[���e���݂����߂ĘA�����ꂽ�B�ނ͎��ɂƂ��Ă͗F�B�ł���A��y�ł���Z�M�ł���A�n�K�L�ɂ��R�~���j�P�[�V���������҂��ł����т��āA���Ԃ����̓Ɨ������R�~���j�e�B�[�𐬗��������B
�����̃p�[�\�i���e�B����ɑ����A�����̎�҂̂قƂ�ǂ��ׂĂ��u�[������v�̐�����邱�ƂɂȂ�B�w�i�ɂ������̂��g�у��W�I�̕��y�A�푈�̌����A�������̌����A�Ƃ��������̗���ł���A���̈Ӗ��ł��y���͐��Ɏ���̐\���q�������B�����č���W�I���e���r����l�����̔ԑg�ł����A�����ڂ̍������^�������W���ɂȂ����B�y�������������̋ǃA�i�Ƃ��ăf�r���[�����̂͂P�X�U�S�N�B���ォ��n�܂������̃��W�I�b�@�̕ϊv���c��̐���ȍ~�̓��{�l�̐��_��S���ɈӊO�ɑ傫���e����^�����̂ł͂Ȃ����ƕM�҂͐�������B
�����������悤�ł��Ď�C�A�������Ă���悤�ŌQ�ꂽ����A����Ɩ���̓����A����Ȑ�����̃��W�I����ĂĂ��܂����Ƃ�����E�E�E�H�U�X�N�Ɏn�܂������J�o���G�e�B�[�ԑg�u�y���܂���̃n���[�p�[�e�B�[�v��S�����āA�ނɉ�̂��y���݂ɖ������N���N���Ȃ���X�^�W�I�ɓ����Ă��������Ƃ��v���o���B
���̐l���̗ǂ��Ƒ��߂��鎀�ɐ��̖�����v�킸�ɂ͂����Ȃ��B
����q�i��c�āj
���{�l�́A�ǂ�ȕ��ł��A�k�������Ă��܂����Ƃ̓V�˂��B
���A�g�����W�X�^���W�I���A���{�̑㖼���̂悤�ɂ�����悤�ɂȂ������A�g�����W�X�^���W�I�����ɂ�����Ȃ��B�d�C����@�ł��A�①�ɂł��A���{�̕��݂͂ȏ������B�e���r�ł��A���^�A���^�Ƃ�܂��Ă��낢�날�邵�A�v�Z�@�ɂ������ẮA�����قǂ̑傫���̂��̂܂ł����ꂽ�B���̂ق��A�J�����A�����ԁA�D�ԂȂǂ���A������݁A�N���b�v�A�����s���Ƃ������g�̂܂��̕i���ɂ�����܂ŁA���{�̕��͈�l�ɏ��^�ɂł��Ă���B
���{�̂��܂��ł́A�Ƃ��ɁA�������^���A�k�����Ƃ������Ƃ������ɂ݂���B���Ƃ��A�ؒ��Ƃ�������̂́A�܂��ɂ��̎��̂Ƃ���A����������̏����Ȃ��̂ɁA�R�C�̕��i���݂��Ƃ̋Ïk���Ă��邵�A�܂��������z�ɂ́A�����ȂǂƂ��������ȋ�Ԃ�����B�����́A��������ɒ��l�̏Ђ������A�l�����Ƃ��������Ȃւ����ʉ������̂ɂ͂��܂�A���̒�q�̗��x�̑�ɂ������āA���ꂩ�炳��ɁA�O����ځA�O��A�����ځA���A�����ڂƁA�M���M���Ɍ��̃X�y�[�X�ɂ܂ŁA��Ԃ����k���Ă������B�������A�����Ɂu�y�n���v��u�Z����v�Ȃǂ��������킯�ł͂Ȃ��B�ŏ����ɂ���߂�ꂽ���܂���ԂɁA�u��сv�̐��E������Ƃ�����ꂽ����ł���B���ǁA���̒������z����A����Â��肪������A���ꂪ���܂��A���{�̏Z�����ʂ����{�I�ȃf�U�C���v�z�ƂȂ��Ă���̂ł��邩��A����Z��A�Ȃɂ��ɂ��āA���܂��������̂��ނ�͂Ȃ��̂�������Ȃ��B
���āA�����u�k�����v�Ɗ֘A���āA�����ЂƂA���{�̕��������̍\���I���F�Ƃ���������̂ɁA�u�y�ʉ��v������B�y�ʉ��͏k�����ƂȂ��ŁA�Ƃ��ɂ͂���ȏ�ɁA�������̐�����傫���K�肵�Ă���v�f�ł���B���̂��Ƃ����������悭��������̂́A�O���ւ������Ƃ��A���邢�͊O�����i�ɐڂ����Ƃ����B�O���̋�݂⓺�݁A�h�A�̌���c��A�R�[�q�[���q�A�֎q�A�x�b�g����o�X�^�I���ɂ�����܂ŁA��������ނ����̕�����ɂ���ƁA�Y�V���Əd�����G��������Ă��āA���������Ƃ܂ǂ��B����������́A�����悤�ɂ���ẮA���{�̕������ׂČy������Ƃ������Ƃł���B���̓T�^�͔����B�i�C�t��t�H�[�N�̂������̏d�ʊ��Ƃ������āA���{�̔��́A�݂Ȍy���B
���āA�H���ɂ�����y���̏ے������Ȃ�A�Z���ɂ����邻��́A����������q�ł���B���̎V�ɁA���Z�����͂�����q���A�悭�肢��̂䂫�Ƃǂ����~���́A�[���Q�A�R�~�����炢�̍a�̏���A�w��{�ŃX�[�b�Ƃ����A�ȂǂƂ������i�́A����܂��O�l�̖ڂ��݂͂�Ƃ���ł���B
���{�̘a���Z��̎����́A�����Ă����̏�q�≦�ł������Ă��āA������S���Ƃ��ς炤�ƁA�Ƃ��イ���u�ЂƂւ�v�̂��Ƃ���ԂɂȂ�A�Ƃ����̂��A�ЂƂ̑傫�ȓ��F�ł���B�ނ����A�Ƃ���ɂ���Ă͂��܂ł��A�c�̎��^�������_�Ƃł́A�������Ղ̂Ƃ��ɁA��q�≦���݂ȂƂ肳���āA�����̏�Ƃ��Ă����B�����������Ƃ��������킹��ƁA���{�̏Z��́A��{�I�ɂ��u�ꎺ�Z���v���Ƃ������Ƃ����������B�ꎺ�Z���̎������A��q�≦�Ƃ��������u�ڂ������v�ɂ��A�������̃R�[�i�[�ɂ������āA�Ƒ����������Ă���̂��B����͓��{�̏Z�܂��̋�ԕ����̑傫�ȓ����ł���B
�ǂ��̍��ł��A���܂��̍ŏ����u�ꎺ�v�ł������B���ꂪ���݂݂�悤�ɁA���G�ő傫�ȋ�ԂɂȂ����̂́A�ꎺ�����B�������͊g�債�Ă䂭�A����Ȃ�̘A���╪���̃V�X�e�����݂��Ă���������ł���B����K�̕ǂłł��Ă��郈�[���b�p�̏Z��ł́A�ꎺ�̑傫���ɂ́A�\���I���E������B�����ŁA�����̗v������A�����ƂЂ낢��Ԃ��K�v�ɂȂ��Ă����Ƃ��ɂ́A�V���������������ɂ����āA����ɂ������Ă䂭�����Ȃ��B���̂����̂����Ƃ����n�I�ȘA���̕��@�́A�Ñ�I���G���g��A�G�[�Q�C�̃g�����A�N���^���Ȃǂ̓s�s��Ղɂ݂����u���H�^�Z���v�̂悤�ɁA�ւ₪�����ɂ������Ă����āA���̊ԂɒʘH���Ȃɂ��Ȃ��A�e�ւ₪�����Ɂu�ʘH�v�����˂�A�Ƃ����V�X�e���̂��̂��B�P�W���I�ɐ����ɂł����x���T�C���{�a�̂悤�ȑ�K�͂ȋ{�a���z���A�����I�ɂ́A����ƋO����ɂ��Ă���B���ꂪ���[�}����ɂȂ�ƁA�z�[�����Ȃ킿�L�Ԃ�ʘH���S�Ƃ��A�e�ւ�͂��̂܂��ɂ������Ƃ����`���x�z�I�ƂȂ�B����ɍ��ł��쉢�ɂ䂭�ƃz�[�����p�e�I�Ƃ�������ɂ����A�e�ւ₪�A���̒���������ނ悤�ɔz�u�����R�[�g�E���[�h�E�n�E�X�Ƃ�����`���������݂���B�����̏Z�����{�I�ɂ́A���̒��뎮�����A�e�ւ₪�A�ꎺ�ň�˂̉ƂƂȂ�A���Ƒ��P�ʂɂ킩��ďZ��ł���̂����F�Ƃ�����B
�Ƃ��낪�A���{�̏Z��́A�����ɂ��ӂꂽ�悤�ɁA�����Ƃ́A����قȂ锭�W�̂������������B����́A�ꎺ��������Ȃ��傫���Ȃ��Ă䂭�Ƃ������̂��B���������p���Ƃ������z�l���́A���q����ɂ����ꂽ�c�̎��^�̕��ʂ������u���ƂÂ���v����������ł͂Ȃ��������Ƃ����A��������z�l���I�Ɋ��������Ă䂭����������u���@�Â���v�ɂȂ�ƁA�͂����肻�̌`����������B
����܂ł̎x�z�w�̏Z���́A��������ɐ��������u�Q�a�Â���v�ŁA����́A�����̋{�a���z��͕킵�����̂Ƃ����A�Q�a�Ƃ��鐳�a�̂ق��ɁA���A�����邢�͖k�ɑΉ��Ƃ����ʓ��̌������������āA������n�a�Ƃ����L���ŘA�������A����ΘA����̌`�̂��̂ł���B���̂����A�X�̂ւ�ɂ�����Q�a��Ή��́A�ꉮ�𒆐S�ɁA���̂܂����Ƃ�܂��݂Ƃ����u�����v����Ȃ铯�S�~�I���ʍ\���������A�ꉮ�Ɣ݂Ƃ̂������ɂ�����͂Ȃ��A�����肪����̂́A�݂ƊO���Ƃ̂������̎��˂�Ȍˁi�J�ˁj�Ȃǂł���B��������ƁA�����͈ꎺ��̌����A���Ȃ킿�u�ꎺ�Z���v�Ƃ������ƂɂȂ�B�����ł��̌�����傫�����悤�Ƃ������Ă��A�u���S�~�\���v�Ƃ�����Ԃ̐��i����A�����肪�łĂ���̂��B�v����ɁA�Q�a�Â���Ƃ����̂́A���{�×��̈ꎺ��̌����ł���~�����_�Ќ��z���A�������ɁA����Ƃ�܂��悤�ɍ��E�Ώ̂ɂ͂�߂��炵���A�Ƃ����邱�Ƃ̂ł�����̂ł��邩��A�X�̐_�Ќ��z������ȏ�ɑ傫���Ȃ肦�Ȃ��̂Ɠ��l�ɁA�Q�a�Â���̂��ꂼ��̐Q�a��Ή����A���܂�傫�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂��B
�Ƃ��낪�A���q�⎺������ɂ����ꂽ���m�̏Z���́A���̂悤�ȍ��E�Ώ̂̌��z�z�u�A���S�~�̎����\���Ƃ����A�����������͓��{�̌Ð��̓`����n�炷��M���̋������A�Ԃ���Ԃ��Ă��܂����B����������������z�Z�p�́A�p���̓o���ƁA���\��q�̔��B�ɂ���A�Ǝ��͂�����B
�p���̓o��Ƃ����ƁA����������ł��邪�A����܂ł̒��́A�ے��������ł������B�ЂƂɂ́A���z�H��̖����B�̗��R�ɂ��A�����ЂƂ́A�u�V�~�n���v�A�܂�V�͂܂邭�A�n�͎l�p�ł���A�Ƃ��������v�z�Ƃɂ��ƂÂ��Ă����B���͓V�ɂȂ�����̂Ƃ��āA�ے��łȂ���Ȃ�Ȃ������̂ł���B�������A�ӂƂ��ے��͍����ɂ��ĂȂ��Ȃ���ɂ͂���ɂ����B�����Ŗ����܂����������p�����ʎY����Ă���B
���āA�ے��̂Ƃ��ɂ́A�ꉮ�Ɣ݂̂������̒���ɂ́A������Ƃ��������{���A�����Ȃǂ��������̂���ʓI�ł��������A�p���ƂȂ�ƁA����Ɋ����ƕ~�����Ƃ����A�p�����˘g�Ƃ��āA�����ɂ������q���Ƃ���邱�Ƃ��ł���B���ꂪ���Ⴂ�ł���A�������߂���̂ɂ����ւ�ׂ�肾�B�����Ŗ��͂��̈��Ⴂ�ł���B����Ȃ���˂����Ȃ�A�ق��̍��ɂ��Ȃ��ł͂Ȃ����A�˂�Ȃ����A�l���Ȃ�ׂĈ��Ⴂ�ɂ���B�Ƃ���������̌`���́A�܂��������{�I�Ȃ��̂Ƃ����Ă悢�B���̈��Ⴂ�̏�q���A���{�ŕ��y�A���B�������̂́A�����u���v�̗͂����������đ傫�������̂ł���B
��q���̂��̂́A�ޗǎ���ɂȂ��A��������̐Q�a�Â���ɂȂ��Ă͂��߂ēo�ꂷ��B��������͕��nj˂Ƃ�������͂�����q�A���łɓ�����q�A�܂����ł���B����ɘa�����͂����������q�A����������q�����������ɂ����ŁA���{�̎�����Ԃ��A������Ȃ��c�����镨���I��b����������ꂽ�B���Ȃ킿�A�����q�́A���̌y���ɂ���Ď����̋�C���݂������ƂȂ��A�X���[�Y�ɂ������߂��邱�Ƃ��ł���Ɠ����ɁA���������̎����̂�����Ƃ��Ȃ�A����ɉ��̏�ɂƂ����ꂽ���Ԃ��q�̘a���́A�����̉��ӂ����܂ŁA�ˊO�����A���Ȃ킿�������������Ƃǂ��邱�Ƃ��ł���̂��B
���m�l�́A���{�̉Ƃ��Ǝ��łł��Ă���A�Ƃ����ƁA�ǂ�ȂɃ`���`�Ȃ��̂��Ƒz�����邪�A���������̎��ɂ���āA���\���~�A���S���~�Ƃ�����L�Ԃ��A�����Ȃ��ł䂭���@���z�̂悤�ȋ���ȁu�ꎺ��ԁv�ɐڂ���ƁA���ǂ낫�̐��������邾�낤�B�j���{�Ȃǂ́A���̓��{�́u�ꎺ��ԁv�����̍ō�����̂ЂƂł���B�����X�[���n�тɂ�������J�̍��ł���Ȃ���A���ꖇ�������āu�ǁv�ɂ�����A�Ƃ����Ȍ|�I�Ȕ��z�݂������Ƃ���ɁA���{���z�̂������낳�������A�Ƃ����Ă悢�B
���މ������i���̏ؖ��i�����S�j�j
�ߍ��̎Ⴂ�l�͔����������g���Ȃ��Ƃ����B�����ɂ͂Q�{�̔����S�{�̎w�Ŏ��̂����A�قƂ�ǂ̐l���Q�{���A���������R�{�̎w�Ŏ����āA�����ɂ��s���R�����Ɉ����Ă���B������ǂ������Ƃ����H�̂̐l�ɂł��āA���̐l�ɂł��Ȃ����Ƃ͐�����Ȃ�������B�̂̐l�͗����Ŗ�R���삯���A�ǂ�Ȗɂł����邷��Ƃ悶�o�����B�H�ׂ���A���A�H�ׂ��Ȃ��A�����ЂƖڂŌ��������B�[��A�P�L����̃��C�I���̓����������A�n�ׂ��Ɏ������ăl�Y�~�̑����܂ŕ����Ƃ�A�萻�̋|��Œ��₯���̂⋛�����Ƃ߁A�������荇�킹�ĉ��N���A�Ńi�C�t�����A���Œސj��������B����Ȃ��Ƃ͍��̐l�ɂ͂ł������Ȃ��B���́A���́A�k�o�͐̂̐l�̕����͂邩�ɗD��Ă����B�����łȂ���ΐ����c��Ȃ��������炾�B�������A�悭�l����ƁA���������\�͓͂����̕�����Ȃ̂ł���B
��O�̐l�ł����\���낢��ȗ͂������Ă����B�A�S����v�ŁA���̂����ޗ͂����������B�r����v�łP�O�L���Q�O�L�������͕̂��C�A�����ԗ��������Ă��A���̐l�̂悤�ɂ����|�ꂽ�肵�Ȃ������B�ނ�݂ɂ���Ȃ��������A�����ł����������܂ꂽ�肵�Ȃ������B�P�O���b�g�̓d���P�Ŋy�ɐV�����ǂ߂��B�w�悪��p�ŁA�n�����I�݂Ɏg�����Ȃ��A�����S�̔���ނ���A�G���s�c�����ꂢ�ɍ��A�M�Ŏ����������Ƃ��ł����B�����̎ϋ������ꂢ�ɐH�ׂ邱�Ƃ��ł����B�m�R�M���Ŗ��܂������ɐ�A�N�M���܂������ɑł����ނ��Ƃ��ł�����A�������Ɋ܂�Ŗ��𐁂����Ƃ��ł������A�o�P�c�̐����L���͈͂ɂނ�Ȃ��T�����Ƃ��ł����B�������Ŏ���|�����邱�Ƃ����ł����̂��B
�Q�O�N�O�̐l�����Ȃ�̂��̂������B�^�I�����i�邱�Ƃ��ł������A�Ђ������Ԃ��Ƃ��ł����B���Ђ����Ƃ����Ƃ��ł����B���N�M�Ŏ����������Ƃ��ł������A�������������B�Ȃ�ƃn���_�t�������ł����̂��B
���̐l�͂������������Ƃ͉��ЂƂł��Ȃ��B�ł̓_���l�ԂȂ̂��Ƃ����ƁA���͋t�ł���B�̂̐l���ł������Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�B������i���Ƃ����̂ł���B�����������Ă����\�͂������āA�ʂ̔\�͂��l�������̂��l�ނł���B�̂̐l�������Ă����\�͂������āA�ʂ̔\�͂��l�������̂�����l�A�V�l�ނł���B�\�͂Ƃ͐����̂т邽�߂ɕK�v�ȗ́B���ꂩ��̐l�͔����g���Ȃ��Ă��A�G���s�c�����Ȃ��Ă��A�Ђ������ׂȂ��Ă��A�N�M���łĂȂ��Ă��Ȃ�獷�x���͂Ȃ��̂ł���B�K�v�Ȃ̂̓p�\�R���A���[�v���A�V���Z�T�C�U�[�A�e�탍�{�b�g�A���C�J�[�h�A�J�[�A�r�f�I�A�t�@�b�V�����A���e�N�A�O����ւ̑Ή��A�e����A�m�I�ƍ߂ɑ���h�q�\�́A���X�ł���B�������������̂ɑΉ�����\�͂̂Ȃ����l�͖łт�B
���ꂩ��̐l�ނɂƂ��āA���l�̎����Ă������n�I�A���̓I�\�͕͂K�v�Ȃ��A�Ƃ������̂ĂȂ���Ȃ�Ȃ��B���l�̔\�͂��A����l�̔\�͂��A�����l�̔\�͂��A���ׂĐg�ɂ�����������ƂȂ������A�l�Ԃ̔\�͂ɂ͌��E�i�e�ʁj������̂ŁA�V�����\�͂��l�߂��ނɂ͌Â��\�͎͂̂ĂȂ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B�����������Ɨ~�����Ă��_���Ȃ̂��B
�މ����i���̏ؖ��Ƃ����̂͐V�����l�����ł͂Ȃ��B�_�[�E�B���̐i���_�͎��͑މ��_���Ƃ�������B�T���̖̑т��މ����A�K�����މ����A��r�̎w���މ������̂��l�Ԃł���B�މ��̒�������������Ԃׂ��ł���B
�����Y��p�~���A�w����������i���q�p�j
���Y�͔p�~���ׂ��ł���B�Ȃ��Ȃ�A���Y�͐l�Ԑ��ɔ�����s�����Ȑ��x������ł���B
����́A�ߑ�ɂ����鍑�Ƃ̐��x�Ƃ��Ă̐푈���A�قƂ�ǂ̏ꍇ�A����߂ĕs�����Ȃ��̂ł��邱�ƂƂ悭���Ă���B�����Ƃ���������i���A�n�������甲���o���A�E���Ƃ����������I��i�ɂ���Đ퓬�������W�߁A�����݂��Ȃ��ғ��m���E������B���̉A�S���B���̓J�}�g�g�Ԃ��Č��𗬂����Ƃ��A�S���ƌ����Ă���̂ł͂Ȃ��B�v�������Ē�R�^�������āA�����̎S���ł���B�ނ��A�����v�����\�͎�`�^�������邪�A��������łȂ����Ƃ͗��j���ؖ����Ă���B�����A�S���ƌ����̂͗������̂��̂̂��Ƃł͂Ȃ��B�l�Ԃ̈ӎu�⊴������ߑ㍑�ƂƂ������b���A�S�����\��ɐl�Ԃ����E����̂��A�S���A�ƌ����̂ł���B
�����ł��邩��A���̎��Y�p�~�_�́A���̂قƂ�ǂ̎��Y�p�~�_�҂̎咣�ƂP�W�O�x�����ł���B����������v����̂́A��R�̉\���̎w�E���炢���낤�B��R�ŌY�����ɂԂ����܂��̂����܂������̂ł͂Ȃ����A��ɖ��_�┅���������ł���B�������A���Y�ɂ͂��ꂪ���Ӗ����B������悭�Ȃ��B�����������̂��B��R�ɂ�鎀�Y���A��R�ɂ�钦�����A���\�{�����S�{���������Ƃ͓��R�ł���B���̂��߂ɂ��A���Y�͔p�~����Ă�����ׂ����낤�B�����A���̓_�ɂ��Ă͒N�ɂ��٘_�Ȃǂ���͂��Ȃ��B���Y�_�c�Ŗ{���ɖ��ɂȂ�̂́A��R����ɂ��肦�Ȃ��قǖ��X���X�ȋ��������̏ꍇ�ł���B�؋����ؐl�����@�����炩�Ȏc�s�ȎE�l�����ŁA��Q�҂̈⑰���߂��݂Ɠ{��ɑ̂��ӂ�킹�Ă���̂ɁA���Y�p�~��������̂��A�Ƃ������Ƃ��B
���͌����B����ł��A���Y��p�~���ׂ��ł���B����A���ꂾ���炱���A���Y��p�~���ׂ��ł���A�ƁB���Y��p�~���ĕ��Q��F�߂�ׂ����A�ƁB
��Ɏ��́A���Y�Ƃ������x�͉A�S�ł���ƌ������B���Y�Ɋւ��郋�|���^�[�W���ނ�ǂގ��A�����ӂ������v��������̂��A���̉A�S���ł���B���Q�����ȏ�A���肩�����܂ł��Ȃ����A�����Ȕƍߎ҂��E����邱�Ƃ��A�S�ƌ����Ă���̂ł͂Ȃ��B�����҂�N���҂��E�����̂��A���͉A�S���Ǝv��Ȃ��̂Ɠ����ł���B�����ӂ������قljA�S�ȋC�ɂȂ�̂́A���Y�����s�����Y�����̐S�����v������Ȃ̂ł���B
�Y�����ɂƂ��āA�ǂ������̌��ʼn��N�����O�ɋN�����E�l�������A�����������Ɗ�������悤�Ȃ��̂ł���͂����Ȃ��B�ނɂƂ��ẮA�V����e���r�Œm�������ۓI�Ȏ����ɂ����Ȃ��B�������A�ߋ��̂��ƂȂ̂��B�����ɂƂ��Ă͉��̊ւ����Ȃ��Ƃ��������Ă������낤�B�������A�ނ͐E���̖��ɂ����āA�����đ����݂��A�܂��ĎE�ӂ��������ɁA��l�̐l�Ԃ��E���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�e�E�Y���̗p���Ă��鍑�ł́A���Y�Ɏg�������̏e�̂����꒚�����͋�C�ł���Ƃ������A�i��Y�̏ꍇ�ł��A���ݔ𗎂Ƃ��X�C�b�`�͓����ɕ���������A���̂����̈�͓��ݔɘA�����ĂȂ��Ƃ����B���R���Ҍ���v���Ȃ��B
���̈���Ŕ�Q�҂̈⑰�́A���Ƃ����N�����Ă��A�Ɛl�ւ̂�����悤�ȓ{��Ƒ����݂̊��������Ă���B���ɂ��Ă�肽���Ƃ����C�������B���ɂ��Ĕ�Q�҂̐������Ԃ��ė�����̂��A�Ƃ�������͋��ł���B�Ԃ��ė��Ȃ����ƂȂǕ����肫���Ă��邩�炾�B��������������l�ɂ́A�������₵�����B���Q�͔�Q�҂��Ԃ炷���߂ɂ�����̂��ˁA�ƁB����ȕ��Q�́A�l�ގj�ソ���̈�x������͂��Ȃ������̂��B
���A���́A�l�ގj��ƌ������B���������{������B��ϒd�w���Q�Ɩ@���x�ł���B�����n�ߓ��{�ōŏ��̖@�w���m�ƂȂ�����ς��@���v�z�̕��y�̂��߂ɍu���������̂��A���̎���A�P�X�R�P�i���a�U�j�N�ɂ܂Ƃ߂����̂��B�ߔN�A��g���ɂł���y�ɓǂ߂�悤�ɂȂ����B
���̖{�́A�l�ނ̗��j�̒��ŁA�@�����x����������i�����Ă������Ƃ�����Ă���B��ς͌����B�����ł���A�ʂ肪����ɂ��������߂Ă��錢�����������Ċ��݂����Ƃ�����悤�ɁA�K�����Q������B�l�Ԃ������悤�ɁA������e���E�m�l�ɑ���U���ɑ��Ĕ�������B����́A�ł���A�x���ł���A�h�q�ł���B�u���̌��ۂ͐l�ނ̈�ʓI���ۂł���v�ƁB�����A�E������E���Ԃ��ł͎Љ���܂�Ȃ��Ȃ�B�����ŁA�������i������ɂ�A�����ғ��m�����K�ȂǂŌ��������鐧�x�����܂��B�������A����������łȂ�������A���܂��܂ȕs�s��������B�ߑ㍑�Ƃ��������镶���̍ŏI�i�K�ł́A���I�ȕ��Q�͈�ؔp����A���I�Ȗ@��������Ɏ���đ���̂��B�T���A���̂悤�ɐ�����Ă���B
���ʂ��猾���A�܂�́A�l�Ԃ����R��Ԃɂ����Ă͎����Ă������Q�����ߑ㍑�Ƃ��D�����̂ł���B�l����`�҂́A�����u���Ƃu�r�l���v�Ƃ����}���𗧂Ă�����B�������Ƃ���A�܂��ɐl�Ԃ̊�{�I�l���̈�ł��镜�Q�������ƌ��͂ɂ���ċ��D���ꂽ�̂����Y���x�̖{���Ȃ̂ł���B
���Q�����ߑ㍑�Ƃɂ���ė}������Ă��鍡�A�����ȎE�l�҂��Q�҂̈⑰���ˎE�����Ƃ��悤�B���̈⑰�͂ǂ��Ȃ邩�B�Y�����s���ł���B����̘b�ł͂Ȃ��B���ɁA���N���O�A���h�C�c�ł��������������������B�c�����������E�Q���ꂽ��e���A�@��ŔƐl���s�X�g���_�������̂��B���̋����E�l�Ɛl���l�߂ł��邨����͂܂��Ȃ��B�؋����ؐl������A�ƍߎ����̔F��ł͑����]�n�͂Ȃ������B�����A�ނ��A���̔Ɛl�͎��Y�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B���h�C�c�͎��Y�p�~��������ł���B�c�����̓G�Ƃ��Ƃ��ĕ��Q�����s�g������e�́A�����Ĕƍߎ҂ƂȂ����B
�ߑ㍑�Ƃ́A���̂��̗���ȕ�e��L�߂Ƃ����̂��B���Ƃ��E�l�҂̐����ł����Ă��A���������̂Ȃ�����������A���Ƃ��S�͂������Ă�������ׂ����A�ƍl���ł������̂��낤���B
�ہB
���Ƃ̐l���ւ̗D�z����Ƃ��҂����������̂��B�����̂悤�ɂ₳�����ߑ㍑�Ƃɋ^����������߂ɂ��A���Y�p�~�A�����ĕ��Q�����ׂ��B
���I�����C���E�V���b�s���O�̕s�U�͎x�����̈��S�����H�i�}�����j
���{�ɂ����炸�A�I�����C���E�V���b�s���O�́A�F�����Ȃ��B�Ȃ��F�����Ȃ����A���̗��R�Ƃ��āA���Ȃ炸��������̂́A�I�����C����̎x�����̈��S���ł���B�N���W�b�g�E�J�[�h�̃i���o�[������ɑ����Ĉ��p�����S�z���A�����Ύw�E����Ă���B
�ق�Ƃ��ɁA���ꂪ�����Ȃ̂��A�Ƃ����^�₪��o����Ă���B�I�����C���E�}�[�P�e�B���O��Ɓu�k�A�E�C���^�[�i�V���i���v�����s����I�����C���E�}�K�W���̍ŋߍ��ɂ��ƁA7��15������͂��܂��T�ԂŁA�A�����J�̃l�b�g���㑍�z��14���h�����������A���̂����̖�50�p�[�Z���g�ɂ�����7��100���h�������s�֘A�ł������Ƃ����B����́A�q�̃l�b�g�̔����唼���߂Ă���ƍl������B
�Ă̗��s�V�[�Y���ɂ������Ă��邱�Ƃ����邪�A�N�Ԃ�ʂ��Ă��A���s���i�́A���̂ǂ̕���������|���Ă���̂�����ł���B�����ŁA�u�k�A�v�̃��[���E�}�K�W���́A�����̂悤�ɏq�ׂĂ���B�uCD�Ƃ����Ђ����A�q�̂ق��������ƍ��z�̂͂����B�����x�����̈��S�ɕs��������Ȃ�A���10�h���̖{�̓I�����C���Ŕ����Ă��A300�h���̃`�P�b�g���͍̂T����ł��낤�B���ꂪ�t�ɂȂ��Ă���̂́A���������v
�������ɁA�����ł���B�x�����葱�����������邩�ǂ����ɕs������������A�傫�Ȕ������͂��Ȃ��B���ʂ̃V���b�s���O�ł��A�������̂قǁA�M���̂����鑊�肩�甃�����߂悤�Ƃ���ł��낤�B
�����ŁA�u�k�A�v�́A�l�X�̃V���b�s���O�K���̂Ȃ��ŁA�C���X�^���g�E�T�e�B�X�t�@�N�V����(�u�ԓI����)���A�傫�ȗv�f���߂Ă��邱�Ƃɒ��ڂ��Ă���B����͂܂�A�������̏u�ԂɁA����������Ƃ������Ƃł���B�Փ������͂������̂��ƁA�ӂ��ɏ��i��T�[�r�X����ɓ����ꍇ�ł��A�������A�����̂��̂ɂȂ����Ƃ��ɁA�����Ɏ��G���ꂽ��A�g�����肷�邱�Ƃ��A�傫�Ȋ�тƂȂ�B
�X���ł̔������́A�������V���b�s���O�E�Z���^�[�ł��낤�ƁA�l���X�ł��낤�ƁA���邢�͌����Ŏx�������ƃJ�[�h�ɂ��悤�ƁA�x�����ƌ����ɁA�����Ƃ����f���炵������̍��Ԃ肪����B�����Ă��ꂵ���̂ł���B���ꂪ�V���b�s���O�̑�햡�ł��낤�B
�l�b�g�E�V���b�s���O�ɂ́A���ꂪ�Ȃ��B�A�}�]���Ŗ{�𒍕����Ă��A�����������Ȃ̂͂������ɂ��ꂵ������ǁA3�����炢���Ȃ��ƁA�{���͂��Ȃ��B�҂������u�C���X�^���g�v�ɖ����ł��Ȃ��B�����ŁA������������y���݂��������Ă��܂��ɂ������Ȃ��B������A�Ȃ��Ȃ��l�b�g�Ŕ����C���N����Ȃ��B
����ł͂Ȃ��A�q�͂悭�����̂��B�y���y���̎��ꂾ����ł���B�Ȃ�̏�����Ȃ��B�Ƃ��ɏ㎿�̎����g���Ă���̂ł��Ȃ��B��G�肪�悢�Ƃ������Ƃ��Ȃ��B���Ȃ��m�ۂ������Ƃ��m�F���邾���̂��Ƃł���B�����́A���̃`�P�b�g�������āA��`�֍s���A�ǂ�����������s�@�ŁA�����̐Ȃɍ������Ƃ��ɁA����Ƃ��킶��Ƃ���Ă�����̂ł��낤�B�������u�Ԃɂ��ꂵ���Ȃ�l�����邾�낤���A���x���������Ă��邤���ɁA�����������Ƃ͂Ȃ��Ȃ�B
��������l�b�g�ŏ\���ł���B�Ƃ��ɃI�����C���Ŕ����Ί������������肷��B�z�e���̗\��������Ȃ�B�v���X�̗v�f����������ł͂Ȃ����B�������ɂ́A�u�ԓI�Ȗ������������̂��唼�ŁA�����łȂ����̂͏��Ȃ��B���ꂪ�A�I�����C���E�V���b�s���O�𑫓��݂����Ă��闝�R���ƁA�u�k�A�v�͕��͂��Ă���B�e�N�m���W�[�̐i���ɂ���āA�������������������ł����@�[�`�����ɓ�����悤�ɂȂ邩�ǂ����B���̂�����ɂ��A�l�b�g�Ŕ������̏������������Ă���ƌ����悤���B
���������������u���́v�Ɓu������v�i�͍����Y�j
���{�l�́A�u���́v���u������v���A����قNj�ʂ��Ȃ����������A�����ł���B��������q�ސl�Ɂu���̑��z�͐_���v�ƕ����ƁA�u����A���z�������͂����ƒm���Ă���v�Ɠ�����͂����B�u�ł́A�Ȃ��q�ނ̂��v�Ƃ���ɖ����A�ԓ��ɍ��邾�낤�B���{�l�͑��z��q�݂Ȃ���A�u������v�̒��ɐ����Ă��鉽�Ƃ������Ȃ��������ɂ��Ă����Ƃ�������B
�����[�I�Ɏ����̂��u���������Ȃ��v�Ƃ������t���B���ї�����Ƃ��Ă��u���������Ȃ�����E���ĐH�ׂȂ����v�B����́A���̈ꗱ�̒��ɁA�u������v���������Ă���Ǝv���Ă��邩��ł����āA���ї���厖�ɂ��Ă���̂��A�u������v��厖�ɂ��Ă���̂��A����������Ȃ��A����������������������B�u���������Ȃ��v�ƌ����Ă���̂́A�o�ς̖��ł͂Ȃ��A�u������v�̖��A���邢���@���̖���Ȃ̂��B
���̂悤�ɁA���퉽�C�Ȃ�����Ă��邱�Ƃ̒��ɁA�@���I�A�����I�Ȃ��̂������Ă���̂����{�l�̓��������A��X���g�A���̂��Ƃɂ��܂�C�t���ĂȂ��B����������ӎ����n�߂��̂́A�O���Ō������̐l�Ə@���ɂ��Ęb�������悤�ɂȂ��Ă��炾�����B�t�ɁA���{�ɂ���ė��ď��߂ė����ł����Ƃ����l������B
�Ⴆ�A��s��ł��������A�Y�ꕨ�������Əo�Ă���Ȃ�Ă����̂͐��E�łǂ��ɂ��Ȃ��B���̗F�B�́u�_�l���h���A����ɂ��s���Ă��鎄�������A�������Ȃ����{�l�̕����͂邩�ɓ����S�������v�Ƌ����Ă����B���́A�ǂ����s�v�c�ȏ@���S�A�����S�́A���퐶���ƌ��т������ŁA�e����q�ɂ����Ɠ`����Ă��Ă��邱�Ƃ��킩�����Ƃ������Ă����B
���������Ƃ��ꂵ���Ȃ�̂͊m�������A�u�߂���́A�����S������Ă��Ă���̂ł͂Ȃ����v�ƒQ���l�������B�������A���̎q���ɁA�Ⴆ�u���������Ȃ��v��������͔̂��ɓ���B�u���ї������������Ȃ��v�Ȃ�Ă����ƁA�q���́u�����ς�����̂Ɂv�ƌ������낤�B�̕��̋������͂ł��Ȃ��Ȃ��Ă���B
���̗��������A���e�Ƃ̊ԂŁu���Ƒ��q�Ƃ̑Θb�v�Ȃǂ������Ƃ͂Ȃ������B���e�Ƃ��Ă̖��߂́A����ŋF��l�߂��o�Ă���ƁA������Ƃ͂������Ď����ċA�邱�ƁA���ꂾ���B��X�q�������́A���e�̋A���҂��\���Ă��āA���ɂ悤�������Ă���A��e���Z��U�l�ɐ蕪���Ă��ꂽ�B���̔�������H�ׂȂ���A�u��������͈̂��v�Ǝv���Ă����킯���B
�ԒP�Ɍ����A�u���́v���Ȃ����́A��ϋ��炪���₷�������Ƃ������Ƃ��낤�B�u���́v��ʂ��āu������v���S���`��邩��A���e���u�����A�Θb���悤�v�Ƃ����K�v�͂Ȃ��B�܂�l�߂������ċA������A�����I���B���Ƃ́u�G�w���v�Ƃ������������Ă�����A���炪�ł��Ă����B
���{�l�̉ƒ닳��̌n�Ƃ������̂́A�u���́v���Ȃ��Ƃ������Ƃ��O��ɂȂ��Ă����B�������ɂ͈�̂����ɊF���W�܂��Ă���B�S�������邽�߂ɂ́A���荇�������Ȃ���Ύd�����Ȃ����A�F���W�܂�����A������Ɩʔ����b������B
�u���݂��Ɏ@�������āv�Ƃ��u���̂������āv�Ƃ��A�����������Ƃ��S���ł��Ă����̂́A�u���́v�����Ȃ����炾�����B�n�������ŁA�u���́v�Ɓu������v���ꏏ�ɂ��Ȃ��琶���Ă����������Ƃ����̂́A���{�l�͑�Ϗ�肾�����̂����A�}�ɖL���ɂȂ������ɂǂ��������炢���̂��������ɂ����Ȃ��Ă��܂�����Ȃ����Ǝv���B
���u�����o�҂̋����ׂ�����v�]�i�r�c���F�j
�����o�i�V�l�X�V�[�W�A�j�ƌ����Ă��A�قƂ�ǂ̐l�͉��̂��Ƃ��킩��Ȃ��ɈႢ�Ȃ��B���Ɍ`����������A���ɐF��`���������肷�邱�Ƃ��B���������Ă��A����ς艽�̂��Ƃ��킩��Ȃ���������Ȃ��B��̓I�Ɍ������B���Ƃ��A���Ȃ����X�p�Q�b�e�B��H�ׂ��Ƃ���B�X�p�Q�b�e�B�ɓ��L�Ȗ��Ɠ����ɁA��̂Ђ�ɂ��̋�������ł���悤�Ȋ��o�������Ƃ�����ǂ����낤�B�ˑR�A����Ȍo����������A�]�����������Ȃ������A�̂��ւ�ɂȂ����Ǝv�����낤�B
���܂�������o�������Ă���l������ƕ����Ă��A�ɂ킩�ɂ͐M�����Ȃ����낤�B���o�͎�ϓI�Ȃ��̂ő��l�ɂ͊ώ@�ł��Ȃ����炾�B�Ȋw�͎�ϓI�Ȃ��Ƃɂ͗�������Ȃ��ɂȂ��Ă���̂ŁA�����o�̖��͒����Ԗ�������Ă����B�{���̒��҂͂��̖��ɉȊw�I�ɃA�v���[�`�����قƂ�Ǎŏ��̐l�ŁA�{���͂��̋L�^�ł���B
�܂������o���̐_�o�Ȉゾ�������҂��A�ЂƂ�̋����o�҂ɏo����������b�͂͂��܂�B�����̋����o�҂́A�����������o�҂ł��邱�Ƃ���肽����Ȃ��Ƃ����B�N�ɂ���������Ȃ����炾�B�͂��߂ė������Ă����l�����������̋����o�҂͒��҂ƗF�l�ɂȂ�B�M�����Ȃ����Ƃɂ܂��Ȃ��Q�l�ڂ̋����o�҂�������B�ŏ��̐l�͖��Ɍ`�������邪�A�Q�Ԗڂ̐l�͍�������ɂ����ɐF��������Ƃ����B
�Q�l�̋����o�҂ɏo���������҂́A����𖾂��邽�߂Ɏ������J�n����B�����o�́A�����h���ɂقړ������o��������Ƃ����B�ӎu�ł͉���ł��Ȃ��s���ӂȂ��̂炵���B�ŋ߂̂͂��̃R�g�o���g���N�I���A�ł���B�����Ă��ɁA��]�V�玿���قƂ�NJ������~���A�Ӊ��n�݂̂������Ă��鎞�ɁA�����o���N�����Ă��邱�Ƃ����Ƃ߂�B�����͂P�X�X�R�N�Ƃ��Â����A�b��͂܂��{�ł���B
���p�u���b�N�E�h���C���Ƃ��Ắu�C�̃g���g���v�i��҂҂̌Z�j
���������ɗ�����قƂ�ǂ̕��́A�u�g���g���v��c������̑�Ȏv���o�Ƃ��A�̂悤�Ɏv���Ă���������唼���Ǝv���܂��B�ł������̏ꍇ���A���^�C���ł̋L�����قƂ�ǖ����i���Ă͂���̂����قƂ�NJo���Ė����j���ɂƂ��āu�g���g���v�͎Љ�I�ȕ�����Y���Ǝv���Ă��܂��̂ŁA��͂��i�_�A��Ƙ_�A�Z�p�_�A�n�����āA���j�I�ʒu�t���A���f�B�A�_�ƌ������l�X�Ȋp�x����́u�g���g���v�̈Ӌ`�t���͕K�v���Ǝv���Ă܂��B
�Ȃ�������������Ƃ��K�v���ƌ����ƁB
�Ⴆ�u�g���g���v�̂c�u�c�̔����E�E�E�B���ݔ������ꂽ�Ƃ��Ă��A���A���^�C���Ō������オ�܂������c���Ă���E�E�E�܂肠����x���グ�������߂�̂ŁA���i�Ƃ��āi���炭�̊Ԃ́j��������Ƃ͎v���܂��B����������������̐���ƂȂ�Ɓu�g���g���v�̑��݂���m��Ȃ����オ���S�ƂȂ�킯�ł�����A���グ�ƌ��������i���l�ƌ����̂́A�u�g���g���v�̏ꍇ��ׂ�͖̂ڂɌ����Ă���Ǝv���܂��B�A�j���Ɍ��炸�}���K�A�f��A�A���p�A���y�A�����Ȃ�ł������ł����A���i���l�������s�ꐫ�A�����������킯�ł͂���܂���B��͂肻���ɂ͕��ՓI���l�ƌ������̂�����킯�ł��B�N���V�b�N���y�▾�����w�A���邢�͖����f��ƌ������A���悻���i���l���قƂ�ǔF�߂��Ȃ��i�v����ɂɂقƂ�ǔ���Ȃ��j���̂ł��s��ɏo�Ă���̂́A���̕��ՓI���l���F�߂��Ă��邩�炱�����Ǝv���܂��B
������D���ȍ�i���D���ƌ����ꍇ�ɂ͗����◝�_�͊m���ɕs�v�ł����A���I�ȋ��L���Y�̐���ƌ����_�ɂ����Ă͗��_�t���͐�ΕK�v�B�܂��Ă⎄�̂悤�ȑf�l�Ȃǂɂ́u�g���g���v��_����ɂ͗l�X�ȖʂŌ��E������̂ŁA�v���̕]�_�Ƃ̑��݂͐�Εs���ƌ�����Ǝv���܂��B���z���������̌����@�ւ�m�g�j�̗l�Ȍ��������ȂǂŁA���{�̂s�u�A�j���_������Ă��炤�̂���ԁB���Ԃł��Ƃǂ����Ă����邱�Ƃ��ړI�ƂȂ�̂ŁA�Ȋw�I�ȗg�������i��F��z�Ȋw�ǖ{�j��A�������q���C���}�ӂ̂悤�ȃI�^�N�I���I�����Ɋׂ菟���ł��B
�y�����Ō��_�z
�P�A�g���g���̓t�@���X�̑z���o�ł���Ɠ����Ɍ����̋��L���Y�i�v����ɂ݂�Ȃ̂��́j�ł����邱�ƁB
�Q�A�㐢�ɓ`����A���Ր��̗L���ɂ��Ă͗��_�t�����K�v�B���Ɍ��I�@�ցi�m�g�j�Ȃǁj�ł̍�Ƃ��ł��]�܂����B
�g���g�����e���r����������Ă���R�O�N�o���܂����A���낻�낱�̗l�Ȉ���Ђ��������ƌ����̂��K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����H�Ǝv��������ł��E�E�E�������Ȃ��̂ł��傤���H
���s�u�A�j���u�C�̃g���g���v�]�i��҂҂̌Z�j
������߂ĊC�̃g���g����S�b�������Ă݂܂����B�g���g����S�b�ʂ��Č���̂͂��ꂪ�S�x�ڂ��ȁE�E�E���悻�P�O�N�Ԃ�ł��B
���߂Č������Ă��낢��Ȃ��ƂɋC�t�������̂ł����A�ł��������̂́A��揑�ɂ���u�ł��A�j���[�V�����炵���A�X�y�N�^�N���E�t�@���^�W�[�̐��E�𐬗������Ȃ�����A�C�ւ̏�M��w�i�Ƃ��āA�l���ɗ����������čs����l�̐N�̖`��杂�`���v�Ƃ����R���Z�v�g�Ƃ́A�܂�ňႤ��ۂ��������ƌ����_�ł��ˁB���̃A�j�����I���n���R���̒Z���������ɑP�Ȃ�j��s�ׂƂ���ɔ����ߌ���`�������̂��낤�Ǝv���܂��B���X�g�̂ǂ�ł�Ԃ��͈ȑO�������Ȃǂ́A�������˂Ȉ�ۂ��܂������A�������̐l�Ԃ⋛�B�ɂ₽��ƈ��l�A������������Ă���Ƃ����A�Ō�̔ߌ�����グ�邽�߂ɁA�㔼�g���g���ƌ𗬂���l�Ԃ�����₽��ƃo�^�o�^�Ǝ��ʂƂ���ȂǁA�ǂ�ł�Ԃ��̕����ɂȂ�悤�ȃv���b�g���U������܂��B
����S�̂����Ȃ�ߑs����Y�킹�Ă���̂����F�B�ŋ߂̃Q�[�����o�̐퓬�A�j���Ƃ͂��炢�Ⴂ�B�ȑO���݂��ق邳�w�E�������B�f��̉e���ł����A���l�^���X��n�[����㩂ɏo�Ă���[���Ȃǂ́A�����Ɂu�A���S�T�����̖`���v�ł��ˁB�㋐��Ȕ��~���o�Ă����̓G�C�n�u�D���ŗL���ȁu���~�v�B�C�̘S���́u�o�N�_�b�h�̓����v�A����C�J�́u�C��}�C���v���H�z���S�A�Z�C���[���A�H��D���~�b�N�X�������b������܂��B����̃L�����N�^�[�����\�o�Ă���̂��ڂɕt���B�o�L���[���͌���̃S�[�u�ł��ˁE�E�E�C�Ȃƌ����ݒ�܂œ����B
����O���̐l�ԂɈ�Ă�ꂽ�g���g���ƊC�m�����Ɉ�Ă�ꂽ�s�s�i���邢�̓g���g�����j�Ƃ��r�����X�g�[���[�\�����ʔ����B���p�͂̍����m�I�����Ԃ��I���n���R���̌���Ƃ��Ďg�p����ȂǁA�g���g����ʂ��Đ����w�I�Ȑl�Ԃ̓��F�i�U�����̍����A�j��{�\�ɂ���Ēm�I�i���╶����z���グ�Ă������ƂȂǁj���ǂ��\������Ă���B���ɑ�U�b�̃g���g���������ăs�s���|����V�[�����o�F�B
�Z�p�I�Ȓt�ق��⊩�P�����I�ȃX�g�[���[�W�J�Ɍ����Ă��܂����Ƃ��A�Ђ����ĈˑR��ʓI�ȕ]���i�t�@���̕]���͕ʂɂ��āj�Ⴂ�̂����A�����ڈȏ�ɓ��@�͂������d�w�I�ȓ��e��s�A�j�����ƌ�����Ǝv���B
�����x�ȓ��]�����ƍU�����i�����u���j
�l�̐S�����l�ޕ����ێ��̎�̂ł��낤�B�����ɂ��Ă̒�`�͐��X���邪�A�l�ނ̐����l���Ƃ��������l���邱�Ƃ��ł���B�����ĕ����Ƃ͓s�s�ɔ������āA�����̕������ʂ���̂ƍl������B��̍l���Ƃ��āA�����͐��_�I�Ȃ��̂ŁA�����͕����I�Ȃ��̂Ƃ��邪�A����͕�����s���Ɍy�����錩���ł���B������ɂ��Ă��A���㕶���̎x����̎�����S�ł��邪�A�l�ނ̐S�A���Ȃ킿���_�̓����͉��ł��낤���B�����ꂽ�m���A�ӎu�A������l�ނ̏��Y�ł��邪�A���́A���ɑ���S�A�����ăR�~���j�P�[�V�������l�ނ̑����ł��낤�B���ۓI�Ȏv�l�͐l�ނ݂̂ɋ����ꂽ���_�����ł���A���ꂪ���ߐ��ʓI�Ȕc�����\�ɂȂ�B�쒷�ނɂ����鎋�o�̔��B�������̍\���I�F���W�������Ƃ����悤�B�l�ނ̐��_�����͋��ɓI�ɂ͌|�p�A�Ȋw�A�����Ď�p�������͏@���ɂ܂ł�����B�����āA���̂��Ƃɂ���āA���̓����Ɗ��S�Ɉ�����悷��̂ł���B
�l�ނ͍��x�Ȑ��_�\�\���]������L���邪���ߔ��W���Ƃ��A�����̕����ɓ��B�����B�������A���܂�����̂́A�l�ނ͍��x�Ȑ��_��L���邪���ߖŖS�̊댯�������邱�Ƃł���B����́A���悢���̂����߁A����Ƃ��낪�Ȃ��B������~�]�͐��_�ɂȂ���B���̂Ȃ��ł��A���ׂĂ̓����ɂȂ�炩�̌`�ő��݂����U�����ɂ��Ē��ӂ��ׂ��ł��낤�B
�����������A���ɑ��ĂȂ�炩�̂͂��炫������Ƃ������Ǝ��g�A�U���������Ƃ݂邱�Ƃ��ł��悤�B�U�����͓����̐i���ƂƂ��ɔ��W���A���������ł���M���ނⒹ�ނł͎�X�̌`�Ŋώ@����Ă���B�Ȃ��ł��A����̂��̂ɑ����U�����͂������邵���A���X���l�����邽�߂̃I�X���m���U�����ɂ��Ă͕��Ⴊ�����B����Ԃ��U�����͐l�ނɂ����Ă����Ƃ������ł���A�푈�A�������ő�̎���Ƃ��Ĉ��������ɏo�����B�@���A�����̑��������l�Ɍ������A���̗�Ƃ��Ĉً��k�ɑ�����ْ[�҂ɑ���̕�����茵�������Ƃ͖��l�̔F�߂�Ƃ���ł���B���e�̊Ԃł͔ƍ߂͂�����ɂ������A�ЂƂ��т�����ƁA����͎c�E������߂�B
�U�����͒��ۓI�v�l�ƌ��Ԃ��Ƃ��������ߌ��ɂȂ�A���_�S�A�����~�A���K�~�A���~�Ȃnj���Ȃ����W����B��̓I�Ȃ��̂ƌ��т��ƓG���S�ƂȂ�B���j�ɂ݂���p�Y�k�͂����̘b�̏W�ςł���B����A�l�ނɂ����Ƃ��߉��ȓ����͗ސl���ł����āA������߉��̂��̂͐�ł��A�������݂��Ȃ��B���̂��Ƃ́A�g�߂Ȃ��̂ɑ��Ă�苭�������U�����̌������Ɖ��߂����B
�������p���Ɛ��_���i�����u���j
�啔���̗쒷�ނ͌Q����{�Ƃ���B�����ɂ͌̊Ԃ̈ӎu�̓`�B���K�v�ɂȂ��Ă��邪�A�g�Ԃ�A�\��A�����ɂ���đ��݂ɘA������B�j�z���U���ł͒Z�������A�S�̋N���̎w�W�ƂȂ��Ă��邪�A�ސl���ł͊�ʋ̕��������������ׂ��ɂȂ邽�߁A�����Ȃ��Ƃ���ŕ\������B�l�ނł́A�g�Ԃ��A��������ɂ���Č̊Ԃ̃R�~���j�P�[�V�����𑶕��ɐL�W�������B�g�Ԃ��͎��㎈�̍I���ȓ������Ȃ���Ƃ��Ă��������Ȃ������ł��낤�B����A�l�ނ��������邽�߂ɂ́A�����ꂽ�����_�o���K�{�ł��邪�A�����튯�Ƃ��āA�O��j�̊������K�v�ł������B�����͎Љ�̔��B�Ƃ����ڂɌ��т��āA�₪�č��x�ȃR�~���j�P�[�V�������\�Ȃ炵�߂��B
�l�ނ͌̂̑̍\���A�@�\�̗��ʂɂ��đ�z���Ă��邪�A����ɑ����̌̂����݂Ɋ֘A���邱�Ƃɂ���āA����߂č��x�Ȕ\�͂����Ă����B���̂悤�Ɍ̂������������̂����_�ł���A���̔����Ƃ��ẴR�~���j�P�[�V�������p�ɂƂȂ�B���̍����ƂȂ���̂������˂Ă����ƁA��͂蒼���p���̗̍p�ɂ����̂ڂ�B
����ɁA�����p�����U�����Ƃ͖��ڂȊW�ɂ���悤�ł���B�����̓����ɂ����āA�����Ƃ��U���I�Ȏp���͒����p���Ɏ���B�ӋC���V���铮���̐Ғ��͔w�����ɔ���A���͂҂�Əオ��B�l�Ԃ������͂�A�������т₩���B�ӋC�����̓����͐Ғ������ɋȂ��A�������܂�A�����҂̊Ԃɂ͂��ށB�l�Ԃ͌��𗎂Ƃ��A���ނ��B���̂��߁A�����Ȃ�����{���̂����V�͖������ȊO���l�ɂ��s�k�A�ꑮ�̎p���ƌ�������B�����p���͑����̓����ɂ����Ă����Ƃ��U���I�Ȏp���ł���B����͑O�����猩����̂ɂ͑傫��������p�ł���B���҂͐l�ނ������Ƃ��U���I�ȓ����ƍl���Ă��邽�߁A�l�ނ��U�����������p���̗p�Ƃ̊Ԃ̊֘A�ɔ[���ł���ؖ���~�����ƍl���Ă���B
�l�ނ̏��s���̂����ŁA���قȂ��̂Ƃ��Đ������̎p������������B�����鐳��ʁA���Ȃ킿�Ζʈʂ͐l�ވȊO�ł͂��܂�L�����ꂸ�A�������炳�ꂽ�ސl���ł����Ίώ@����Ă���B�Ζʈʂ͒����p�����Ƃ�˂Ζ����Ȏp���ł���A���̑O��ł�����i��������Ƃ�����B�����̎p���͒P�ɐ��I�~�]�̌��ʂłȂ��A����̐S�̗����ɂӂ��킵���\���Ƃ݂�ׂ��ł��낤�B
���̂悤�ɁA�����p���͒P�Ȃ�g�̏�̖��łȂ��A���Ȃ萸�_�I�v�f���������̂ł��낤�B�����Ƃ��������ꂽ�����p���Ƃ�������̂��A�����R�̕s���̎p���ł��낤�B�u�C�����v�̍��߂ƂƂ��ɏu�ԓI�ɋ�����ꂽ���̎p���́A���܂Ȃ����҂ɂ͕s���ȋL������т������B�������A�s���̎p���́A�{�l�ɍő�ْ̋������߂���̂ł���A�܂��A�������ɂ��̍s���ɂ����p���ł�����B���̎��������ʂ��A�u�C�����v�ɂ��肩�������āA��Ε��]�ƋK���Ƃ���点���R�l�����́A������ׂ��L�\�ȃG�\���W�X�g�������Ƃ����悤�B
������邢�ʂ�����B�����p���́A�̂̂����Ƃ����h�������ł��镠���𐳖ʂɂ��������p���ł���B��������Ęb���Ƃ������A���������Ɏ㏊�ł��镠�����������Ęb�����Ǝ��́A�������Ɋu�ӂȂ��Ƃ�����������̂��낤�B�S�Ȃ����A�����p���͋��������A�Ƃ��ɐ��_�I�ȋ������������ƂȂނ̂ɓK���Ă���Ƃ�������B�����A�l�ނ��l�������̂܂܂ł����Ƃ���A���_�I���������̖ʂł������̂悤�ȎЉ�͒z���Ȃ������ł��낤�B
�����o�����i�⍪�ޕv�j
�������ڂ̌�����ҁi����ҁj���A�ڂ̌����Ȃ��l�Ƃǂ�����ăC���[�W���������������Ƃ��ł��邩�Ƃ����̂́A�l�ԓ��m�̃R�~���j�P�[�V�����厖�ȃe�[�}�̂ЂƂ����A�ӂ���͂��Y���ꂪ���ɂȂ��Ă���B����̏����́A�����ς琰��҂̂��߂̎��o�I���ň��Ă��邽�߁A��������ɗ�����A�M��Ă��܂��āA�����܂ł͈ӎ����܂��Ȃ��̂ł���B����ǂ��납�A�������̎��o�ɂ��R�~���j�P�[�V�����ł����A���͂������̖ӓ_�����邱�Ƃ�Y�ꂪ���ŁA���o���������\�Ȃ悤�ȍ��o�Ɋׂ��Ă���B���܂��܁A���̎��o�̖ӓ_�Ȃ����Ă����̂́A����ɂ��Ă����͂��̎��o���A�Ȃɂ��̐܂ɁA�����ɂ��܂���Ă��܂��Ƃ��ł���B�ŋ߁A�|�p����V�т̐��E�ɂ܂ŁA���̎�̂��܂��G�A�������G���ӂ��Ă��āA�������̎��o��遂�ɋC�Â����Ă����@������Ȃ����̂��A����������ƁA�l�Ԃ̂���ȃA���o�����X�Ȓm�o�̔��B���A�������悤�Ƃ��鎩�R�̕⏞��p�̈�Ȃ̂�������Ȃ��B�|�p�̐��E�Ɍ���ė����X�[�p�[�E���A���Y���Ƃ����̂��A����Ȑl�Ԃ̖ӓ_���C�Â����Ă����i�D�̔��ʋ��t�ł���B
�����_�����𗘗p�����������G
�͂��߂ɂ���Ȃ������G�̈������������悤�B�ŋ߂̂������G�A���܂��G�́A����Ɏ肪����ł��āA���x�̋Z�I�����炵�����̂��ӂ��ė��Ă���B�\���A�����I�̃��[���b�p�ɂ́A�}�ƒn���A�����ɂ���ē��ꊷ��锽�]���ʂ𗘗p���āA�̎}�̊Ԃɐl�̊���������u�������G�v�����s�������A�ŋ߂ł́A�l�Ԃ̔��ɔ����Ȏ��o�̎��ʔ\�͂ɑi�������A�ŏ�������Ƃ݂������ł͑S���Ӗ��̂Ȃ��悤�Ɍ�����p�^�[���̂Ȃ�������A�����鋗���i���o�����j��ς��Č���ƃC���[�W�������o���Ă���A�Â�����i�܂Ō���ė��Ă���B������ȑO�A�������́u�V�т̔����فv�W�ɏo�i���ꂽ��i�̂ЂƂ����A�p���_���f�B��w�̐S���w�ҁA�j�R���X�E�E�F�C�h����������̂ł���B
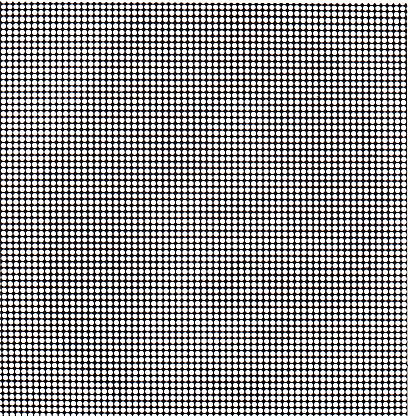
 |
 |
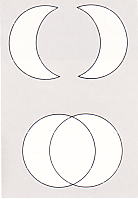

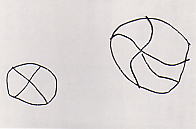

���u�_�b�v�Ɓu�Ȋw�v�i�͍����Y�j
�l�Ԃ����̐��ɐ����Ă䂭���߂ɂ́A���낢��Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���������܂����̂Ȃ��ŁA���܂������Ă䂭���߂ɂ́A���ɂ��đ����̂��Ƃ�m��A���̎d�g�݂�m��˂Ȃ�Ȃ��B���̂��߂ɁA���R�Ȋw�̒m���傫���������ʂ����B���R�Ȋw�̒m�邽�߂ɁA�l�Ԃ͎�����Ώۂ���藣���āA�q�̂��ώ@���A�����ɑ����̒m�����B���z���ώ@���āA���ꂪ�ܔM�̋��̂ł���A�����̏Z��ł���n���͎��]���A���̎�����܂���Ă��邱�Ƃ�m�����B���̂悤�Ȓm���ɂ��A�����͑��z�̉^�s������ł���B
���̂悤�����R�Ȋw�̒m�́A�u�����v��������藣���ē������̂ł��邩��A�N�ɑ��Ă����ՓI�ɒʗp�����_�ŁA�傫�����݂������Ă���B���R�Ȋw�̒m�͂ǂ��ł��ʗp����B�������A�����ł�������藣�����������A�S�̂̂Ȃ��ɓ���A�����Ƃ������݂Ƃ̂������ōl���Ă݂�Ƃǂ��Ȃ邩�B�Ȃ��A�����͂��̂悤�ȑ��z�̉^�s�Ɗ֘A����n���ɏZ��ł���̂��B�����͉��̂��߂ɐ����Ă���̂��A�Ȃǂƍl���͂��߂�Ƃ��A���R�Ȋw�̒m�͖��ɗ����Ȃ��B����́A�o���̍ŏ�����A�������ɂ��ē������̂Ȃ̂�����A���z�̓�����A�͂��炫�́A�����Ɩ��W�ɐ����ł���B�������A�ق��Ȃ�ʎ����Ƃ������݂ƁA���z�Ƃ́A�ǂ�������邩�B
���z�Ǝ����Ƃ̂������ɂ��āA�m����m�������Đ����Ă���l�����ɂ��āA�����O�͔ނ̎��`�̒��ŏq�ׂĂ���i�w�����O���`�x�j�B�����O���������ăv�G�u���E�C���f�B�A����K�˂Ă������Ƃ��̂��Ƃł���B�C���f�B�A�������́A�ނ�̏@���I�V����F��ɂ���āA���z���V����^�s����̂������Ă���ƌ����̂ł���B�u�����͐��E�̉����ɏZ��ł���l�ԂȂ̂��B�����͑��z�̑��q�����B�����Ă���̏@���ɂ���āA�����͖����A����̕����V��������`�������Ă���B����͂����̂��߂���łȂ��A�S���E�̂��߂Ȃv�ƃC���f�B�A���̈�l�͌�����B�ނ�͑S���E�̂��߁A���z�̑��q�Ƃ��Ă̋߂��ʂ����Ă���Ɗm�M���Ă���B����ɑ��āA�����O�͎��̂悤�Ɂw���`�x�̂Ȃ��ŏq�ׂĂ���B
�u���̂Ƃ��A���͈�l��l�̃C���f�B�A���Ɍ�����A�Â��Ȃ������܂����w�C�i�x�̂悤�Ȃ��̂����ɗR������̂������������B����͑��z�̑��q�Ƃ������Ƃ��琶���Ă���B�ނ̐������F���_�I�Ӗ���ттĂ���̂́A�ނ����Ȃ鑾�z�́A�܂萶���S�̂̕ی�҂́A�����̏o�v�������Ă��邩��ł���B�v
�C���f�B�A�������́A�ނ���u�_�b�̒m�v���邱�Ƃɂ���āA�����O���A�]���ւ����Ȃ��u�C�i�v�������Đ����Ă���B����ɑ��āA�ߑ�l�͉��Ƃ��������Ɛ����Ă��邱�Ƃ��B�ߑ�l�͖L���ȉȊw�̒m�ƁA����߂ĕn���Ȑ��_�Ƃ������Đ����Ă���B�����ŁA�C���f�B�A���������ނ�̐_�b�̒m���A���z�̉^�s�ɂ������u�����v�Ƃ��Ē�o����Ƃ��A�����͂��̗c�t���������̂ɂ��邱�Ƃ��ł���B�������A������A�����������ꂱ���E���A�ǂ��C���[�W����̂��Ƃ����A�R�X�����W�[�Ƃ��Ę_����Ƃ��A�����͏��Ă���͋����Ȃ��B
���R�Ȋw�̒m�����܂�ɗL���Ȃ̂ŁA�ߑ�l�͌���āA�R�X�����W�[�������ߑ�Ȋw�̒m�݂̂ɗ��낤�Ƃ������Ƃ��Ă��܂����̂ł͂Ȃ��낤���B���R�Ȋw�̒m�����̂܂����Ɂu�K�p�v���ăR�X�����W�[�����Ȃ�A�����̔ڏ����A�ƌ������͑��݉��l�̖����ɋC������������ł��낤�B�����������������������̂��u�v�ʉ\�v�Ȃ��̂ɂ���đ��肵�Ă݂�B�����Ȃ��Ƃ������Ǝv���l�ł��A�F���̍L���ɔ�ׂ�Ɩ��ɓ��������Ƃ�m�邾�낤�B���ɁA���̂��Ƃ��l����ƁA����͂܂��܂����Ӗ����𑝂��Ă���B
���̂�����̂��Ƃɂ��������C�Â��Ă���ƁA�����̑��݉��l�����o�����߂ɁA���Ղȁu�_�b�v�ł�����o�����d�����Ȃ��Ȃ��āA�u�Ⴂ�Ƃ��ɂ́v�����͂ǂ������A���������A�Ƃ����悤�Ȉ��Ղȁu�_�b�v������āA�ߏ����f�Ȃ��Ƃ�����B���邢�́A�@���ƂƂ����l�������A�R�X�����W�[�ɂ��Č����́A���Ղȓ��w�҂ɂȂ��Ă��܂��B�܂�A�u�悢���Ɓv���A����قǑ�R���Ă���A�Ƃ������炢�̂��Ƃ��ւ�Ƃ��Ȃ��ƁA�����̑��݉��l�������Ȃ��̂ł���B
�×����炠��_�b���A���ۂ́u�����v�ł���ƍl���A���J�̎���̎��R�Ȋw�̂悤�Ɍ���������߁A�_�b��̘b�Ȃǂ̉��l���ߑ�l�͂܂������ے肵�Ă��܂����B�m���Ɏ��R�Ȋw�ɂ���āA���R��������x�x�z�ł���悤�ɂȂ������A����Ɠ������@�ŁA�����Ɛ��E�Ƃ̂����������悤�Ƃ������߁A�ߑ�l�̓����O���w�E����悤�ɁA�n�����������A�Z�J�Z�J������������������Ȃ��Ȃ����̂ł���B
�������A������Ƃ����Ă����͂����ɁA�v�G�u���E�C���f�B�A���̃R�X�����W�[�����̂܂܂����������Ƃ͂ł��Ȃ��B�����͂��łɑ����̂��Ƃ�m�肷���Ă���B�����Ƃ��ẮA�����ɂӂ��킵���R�X�����W�[�����肠����ׂ��e�l���w�͂�����d�����Ȃ��̂ł���B�����́A�G�����x���K�[�̕\�������Ȃ�A�����̖��ӎ��̐_�b���Y�@�\�ɗ���˂Ȃ�Ȃ��B�������A���̂��Ƃ����邽�߂̈ꏕ�Ƃ��āA�×����炠��_�b��̘b���u��Ȋw�I�v�u���I�v�Ƃ������ƂŊȒP�ɔr�˂���̂ł͂Ȃ��A���̖{���̖ړI�ɉ������������ŁA���̈Ӌ`���������Ă݂邱�Ƃ��K�v�ł��낤�B
���}���K�Ɂu�f�b�T���v�͕K�v���H�i�|�F�����Y�j
���}���K�Ƃ̂����f�b�T���Ƃ͉����H
�u�f�b�T���v�Ƃ́A�{���͐��m�G��̉��G���Ӗ����錾�t�ł���B�����ɁA���m�ȕ��̌`�⎿���̕`�ʗ͂Ƃ������Ӗ��ɂ��g���Ă���A�u�f�b�T���́v�Ƃ����Ί�b�I�ȊG��Z�p�͂��w���B����ɂ��Ă��A�}���K�Ƃقlj����ɂ����u�f�b�T���v�����ɂ���l������Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�V�l�E�x�e�������킸�u�f�b�T���������Ă邩��p���������v�ƌ�������}���K�Ƃ͂��ɑ����B���̌��t���o��p�x�́A�������p�E��葽���Ǝv���B����������ˎ����ɂ��Ă��炪�A�������u�f�b�T���E�R���v���b�N�X�v�̎����傾�����B�����ȊG��C�s������Ȃ��Ńf�r���[������˂́A�w�V�x���\����̂P�X�S�V�N�A���c�[�O��V���V��Ƃ����������̑�䏊�Ƀf�b�T���͂̂Ȃ����w�E����āA���傰�����������Ƃ�����B
���̃}���K�Ƃ͖��G����{��Ȃǂ��u�{��v�ƌĂсA�}���K�̊�{���{��ɂ���Ƃ��ꂽ�B�����ȊG��C�s���o�����Ƃ��ނ�̌ւ�ł��������̂��B�����炱���A�f�l�̎��ȗ��ɂ����Ȃ�������˃}���K�̉X�����o��́A�ނ�̃v���C�h�����h�������̂ł͂Ȃ����낤���B�u�ד��v�Ƃ܂ł���ꂽ��˃}���K�����A�����������ɂ͂��ꂪ���}���K�E��Ȋ����Ă��܂����B��ˈȍ~�̃}���K�ƂŁA�����ȊG��̌P�������҂��͂����ĉ��l����Ƃ����̂��B����ł��ނ炪�}���K��`�������łȂ�̕s�s�����Ȃ��������A�\���Ƃ��Ă����h�ɐ��藧���Ă����̂��B�Ƃ������Ƃ́A���Ɛ��}���K�Ɋւ������A�}���K�̊G�ƃt�@�C���E�A�[�g�I�ȃf�b�T���̗͂L���Ƃ͂قƂ�NJW���Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B�Ȃ̂ɁA���݂Ɏ�����}���K�Ƃ������̂悤���u�f�b�T���v�����ɂ���̂͂ǂ������킯���낤�B�ނ�̂����u�f�b�T���v�Ƃ͂��������Ȃ�Ȃ̂��낤���B
���}���K���`���Ȃ��f�b�T���̓V��
�M�҂̔��p�\���Z����̗F�l�ŁA�����|��i�T�Ƃ����j������B�ނ͔��Q�̃f�b�T���͂������Ă��āA���т̓g�b�v�N���X�B�܂��ނ̓}���K���D�����������A�Ȃ����`�������Ƃ͂Ȃ������B�M�҂́A����̃}���K���T�Ɍ����A�u���O���`���v�Ɗ��߂����Ƃ�����B�T�́u�悵�v�Ƃ���ɂ��̋C�ɂȂ��ĕ`���͂��߂����A�ǂ��ɂ����ʂ̊G�̂悤�ɂ͂����Ȃ��B���炭����ꓬ���āA�Ƃ��Ƃ����M����蓊���Ă��܂����B�`�������̇T�̃}���K�����āA�䂪�ڂ��^�����B�����̃f�b�T���Ƃ͂قlj����A���낵�����ǂ��ǂ����G���������炾�ł���B��ۂɎc���Ă���͇̂T�̎��̌��t�ł���B�u�}���K�Ƃ��Ă��A�������Ȃ��ł悭�`�����Ȃ��v�B���ɂ��Ďv���Ƃ��̈ꌾ���A�M�҂��}���K�ƊG����u�f�b�T���v�̈Ⴂ�ɂ��čl���邫�������ƂȂ����悤�Ɏv���B
���}���K�́u�p�^�[���v��`�����̂ł���I
�T�̌����ʂ�A�}���K�Ƃ͊�{�I���u�������Ȃ��Łv���`������̂ł���B�������͂��߂ĕ`�����̂���ݐl���̎���G�A���A���Ȕw�i��`���Ƃ��ɂ͎ʐ^�Ȃǂ��Q�l�ɂ��邾�낤���A�ˋ�̃L�����N�^�[�Ȃǂ̓\���ŕ`���Ȃ���}���K�ƂƂ͂����Ȃ��B���������Ƃɂ����G�ł��A���x���`�������ɁA���Ȃ��Ă��`����悤�ɂȂ���̂ł���B�Ȃ����ꂪ�\���Ƃ����ƁA�}���K���u�p�^�[����`���v���̂����炾�B
�m��ɂ�����f�b�T���́A����Ƃ͍l�������܂������قȂ�B�p�f�b�T����l���f�b�T�����w�����鋳�t�́A���S�҂ɕK���u�Ώە����悭����v�Ƃ����B���S�҂͑Ώە������낭�Ɍ��Ȃ��ŁA���p�^�[���ŕ`���Ă��܂����炾�B��������߂錾�t�Ȃ̂ł���B����͕M�҂����w�f�b�T�������Ă���Ƃ����������A���f���̑�����`���Ă��āA�u�t����u���̐悪�T�{�Ɋ���Ă�Ǝv���Ă₪��v�ƌ���������ꂽ���Ƃ�����B���̂Ƃ��͉��������Ă�̂��悭�킩��Ȃ������B���̐�͎w���T�{������Ă���Ɍ��܂��Ă���ł͂Ȃ����B��������ɂȂ��čl����ƁA���̍u�t�́A�M�҂��u�ڂ̑O�̑��v�ł͂Ȃ��A�u�p�^�[���Ƃ��Ă̑��v��`���Ă������Ƃ�ᔻ���Ă����̂ł���B�ڂ̑O�ɂ���u���v�͐��E�ɂӂ��ƂȂ����݂ł���B��������{�I�ȍ\�����Ⴄ�킯�͂Ȃ����A���̑傫���⑾���A�����Ȏw�̂���i�H�j�͂��̐l�����̂��̂ł���B�����������E�ɂӂ��ƂȂ����̂��u���邪�܂܂ɕ`���v���Ƃ��A��b�`�ʌP���Ƃ��Ẵf�b�T���̖ړI�ł���B�܂�G��ɂ�����f�b�T���̖{���Ƃ��u�`���P���v�ł͂Ȃ��A�u����P���v�Ȃ̂��B����P���Ƃ̓p�^�[������r����P���Ƃ������Ƃł���B�ڂ̑O�ɂ���R�b�v�́A���Ƃ���ʐ��Y�i�ł���Ƃ��Ă��A�����Ɋώ@����ΐ��E�ɂӂ��ƂȂ��R�b�v�̂͂��ł���B���������Ă���u�Ԃ̊p�x�ƌ����̋�͌�ɂȂ������x�ƍČ��ł��Ȃ���Ԃɂ����Ċώ@���A���m�ɕ`�ʂ��邱�ƁB���ꂱ�����ߑ㐼�m�G��̊�{�v�z�Ȃ̂��B�}���K�Ƃ������u�f�b�T���v�Ƃ͂Ȃ�ƈَ��Ȃ��̂ł��낤�B
�}���K�Ƃ͖����́u�`�̃p�^�[���v�̈��o���������Ă���B�N�ł���������}���K�Ƃ��ЂƂ���܂��āA�����������^�����u�Ԃ�`���v�Ƃ�������A�P�O�O�l���P�O�O�l�u�ԂɌ�������́v��`�����낤�B�ӊO��������Ȃ����A�m��̃f�b�T���P�����݂�����ςl�Ԃɂ͋t�ɍ���Ȃ̂ł���B�������`����l�����邾�낤���A����͔ނ��f�b�T���̕�����������ł͂Ȃ��A�����̃}���K�ƂƓ��������̃p�^�[���F���\�͂��D��Ă���Ƃ����ׂ����B
���}���K�͈��̏����ł���I�H
�L�\�ȃ}���K�Ƃ́A�Ώە����������̐��Ńp�^�[���Ƃ��Ē��ۉ����A�������o�����X�Ɍ�����悤���ʂɒ蒅������B���̐����݂̃o�����X��R���|�W�V�����̔������������A�܂�̓}���K�Ƃ̂����u�f�b�T���v�̐��̂Ȃ̂��B����͊G��Ƃ������A�ނ��돑���̂���ɋ߂��B
�u�l�͑�́A���Ƃ��Ɖ悪�{�E����Ȃ����ˁA�f�b�T���Ȃ���������ƂȂ����A�܂������̎��ȗ��̉�ł���B������A����͕\���̎�i�Ƃ��ĂˁA���܂��܂��b�����铹��Ƃ��ĉ�炵�����͕̂`���Ă܂����ǁA�l�ɂƂ��Ă���͉悶��Ȃ���Ȃ����ƁA�{���ɍŋߎv����������ł��B���Ⴀ�������Ă����ƂˁA�ی`�����݂����Ȃ��̂���Ȃ����Ǝv���B�l�̉���Ă����̂́A�����Ɩڂ��܂邭�Ȃ邵�A�{��ƕK���q�Q�I���W�݂����ɖڂ̂Ƃ���ɃV������邵�A�炪��яo�����B�i�j�����A�p�^�[��������̂ˁB�܂�A�ЂƂ̋L���ȂƎv���B�v�i�k�^��ˎ����j
��˂̂��̔������u�G��R���v���b�N�X�̕\��v�Ȃǂ��⏬�����ĉ��߂���͓̂K�łȂ��Ǝv���B��˂ɂ͊m���Ɂu�{��R���v���b�N�X�v�����������A���̂��Ƃ��t�Ɏ���̕\����[���l�@����_�@�ƂȂ�A���ɂ̓}���K�\���̖{���ɋC�������Ƃ����ׂ����낤�B���ꂪ�����u�}���K���ی`�����v���Ƃ����킯���B�M�҂͂��̔����ɂł����Ėڂ���E���R���������C�������B��˂̂����ʂ�}���K�̊G���u�����v�ƍl����ƁA�}���K�\���ɂ܂�������₵������肪�A��������Ɖ������邩��ł���B�܂��A�敗�̗ގ��̖��B���Ƃ��Α�F���m�u�[���̍ہA�����ɏo�����������ɂ��Ă͋L���ɂ����炵�����낤�B�A�j���n�̃}���K�����J���Ă��A�����̂Ȃ��҂ɂƂ��ẮA�N���N���������������Ȃ��قǂ悭���Ă���B�p�^�[���̖����ȋ��L��������̂��B�������A������u�����v���ƍl����Εs�v�c�ł����ł��Ȃ��B�p�^�[���̋��L�Ȃ����ĕ����͈Ӗ����Ȃ��Ȃ�����ł���B�p�^�[�����Ƃ����Ɓu�����v�Ƃ������t���v�������ׂ�l�����邾�낤���A�����ł͂Ȃ��B������������l���Ă݂�悢�B�u�R�v�Ƃ��������̍��͈ꏏ�ł��A�P�O�O�l�����P�O�O�ʂ�̈Ⴄ�u�R�v���ł���͂�������ł���B�܂���˕��E��F���E�A�j�����Ƃ������敗�̍��ق́A�����ł����Ζ�����S�`�b�N�Ƃ������u���́v�ɑ�������Ƃ����邾�낤���B
���}���K�́u�G�v�͊G��ƋL���̒��ԁH
�������}���K���u�G�v����邤���Ŗ��Ȃ̂́A���ꂪ�����ɋ߂��L���\���ƋK��ł���Ƃ��Ă��A���ۂ̕����E�L���ނƔ�ׂ�Ίi�i�ɋ�ې��������Ƃ����Ƃ���ł���B���Ƀ}���K���u�G�v�͉��g�i�[���Ȃǁj�╶���i�Z���t�j�Ƒg�ݍ��킳��邽�߁A���ۂɂ͂قƂ���u�G��v�Ƃ��ĔF�������B���̓����Ƃ��Ė��炩���u�����E�L���v�̗v�f���������A��ۂƂ��Ă͂�͂��u�G��v�Ȃ̂��B���̃k�G�̂悤�ȓƓ��̐������A�}���K�\���̉��߂G�ɂ��Ă���B�]���̊G��_�I�ȃA�v���[�`��L���_�I�A�v���[�`���A�Ƃ��ɂ������肱�Ȃ��̂͂��̂��߂ł͂Ȃ����낤���B�{���͐V�ꂪ�~�����Ƃ��낾���A�������t��������Ȃ��̂ŁA�{���ł̓}���K�̃r�W���A���ȕ������w�����u�G�v�Ƃ����\�����g���Ă���B�������u�}���K�̊G�v�͂����܂ŊG�̂悤�Ɍ����邾���ŁA�{���͊G��ƕ����E�L���̒��ԗ̈�̕\�����Ƃ������Ƃɒ��ӂ��Ă������������B����Ӗ��Ń}���K�̃r�W���A���́A�ǂ��܂ł��u�}���K�v�Ƃ������t�ł�����肦�Ȃ����̂Ȃ̂�������Ȃ��B
�������f�B�̑r���i�����S�j�j
�����f�B�A���Y���A�n�[���j�[�����y�̎O�v�f�Ƃ���ꂽ�̂͏\�㐢�I�܂ł��B���ʁA���y���������ނƂ����J�Ő����Ƃ����ƁA�����f�B�����ł���B���̃����f�B�����ɂȂ��Ă����B�ǂ�ȃ����f�B������Ă����삾�Ƃ�����B�ÓT�I�ȉ��y�V�X�e���ł͐V���������f�B�͍��Ȃ��Ȃ����B�����œo�ꂵ���̂������ł���A�\�ł���A�������ł���B����ɉ��F�Ƃ��G�l���M�[�Ƃ������v�f����肱�ޓw�͂��s��ꂽ�B�������A������s���l�܂��Ă����B�����Ȃ�Ɣj�ꂩ�Ԃ�ł���B�����f�B�Ȃ��ʼn��y����낤�B���y�Ƃ͉����y���ނ��Ƃ��B�Ƃɂ����ǂ�ȉ��ł��o���Ă݂悤�A�Ƃ������ƂłЂƂ̃W�������Ƃ��đ������y�����܂��B���̒��ł����ɏd�v�Ȃ̂��l�̐������A������̂ł͂Ȃ��A�����ɑ��鑛���̂悤�Ȍ`�ŁA�Ƃ�ł��Ȃ������o���B���Ԃ����A�ԂԂ����Ă邾���̉��y������B������g�債�Ă����ƁA�G�X�j�b�N�E�|�b�v�X�A����ȁA�ǂ̐��E�ɂ����Ȃ�Â����炠�������Ƃ��킩��B���̘N�ǁA�Z�̘N�r�͂�����y�����A���������y�ł��邵�A�����A���@�����y���B�Nj��A�����A�����N�ǂ����y�ł���B���m�����A�̕���A�K�}�̖�����̌���A�w�O��f�p�[�g�̎����̔������y�ł���B�ŋߘb��ɂȂ����̂̓I�E���̐��@�����A����͌��t�̖��p�Ƀ~�j�}�����v���X�������̂ŁA�}�C���h�E�R���g���[���ɈЗ͂�����B
�Y��ĂȂ�Ȃ����̂Ƀ��b�v������B����̓����f�B�A�n�[���j�[���Ȃ��A���Y�������̉��y�Ƃ���Ă��邪�A���̃��Y�������ł����Ă��܂��Ζ{���̎����㉹�y�ɂȂ�B���ۂɂ���ɋ߂����b�v������B�肷���@���Ă����b�v�A���R�[�h�Ղ���œ������Ă����b�v���Ƃ������A�������������͔̂��t�ł����āA���b�v�̎���������낤�B�؋���@���Čo��ǂނ̂Ɠ����ł���B�i���A�~�_�u�c�A�i���~���[�z�[�����Q�L���[�̌J��Ԃ����~�j�}���E���b�v�ƌ��Ă悢�B
���H�[�J���ł̓��H�C�X�E�p�t�H�[�}�[�����Ă���B�̂ł��Ȃ��A�i���[�V�����ł��Ȃ������B���t�̎������̗v�f�A�A�N�Z���g�A�C���g�l�[�V�����A�����A�������A�����A����A���Z�A�ɋ}�A�g�����W�F���g�i�X�^�b�J�[�g�ƃ��K�[�g�j�A�ԁA���X���d�����āA�ꉹ�A�ꉹ�ɈӖ����������A�����g�ݍ��킹�邱�ƂŒ�����ɃC���[�W�����N����B���̎�̉��y�Ƃ̂ЂƂ�Ƃ��ăq�g���[������B�ނ̉����͂���ꂪ�����Ă���������Ƃ��낪����B�Ӗ����킩��Ȃ��Ă��`����Ă���̂ł���B���̌������炢���ƁA���t�͓��{��Ƃ��p��Ƃ��A���܂������̂łȂ��Ă����̂ŁA���ۂɉ���ł��Ȃ��A�Ӗ��̂Ȃ��n��̌��t�ʼn̂��p�t�H�[�}�[������B
��y�ɂ���A�������y�ɂ���A���H�C�X�E�p�t�H�[�}���X�ɂ���A�����f�B���y�Ƃǂ����Ⴄ���Ƃ����A���J�Ő����C�ɂȂ�Ȃ����y�Ƃ����������낤�B
���}���K�̌���w�I�E�L���_�I�l�@�i���q�p�j
�}���K�́A����A���y�A�f��ȂǂƓ����悤�ɁA�l�Ԃ̎v�l���L�^���`�B����L���̌n�ł���B����̏ꍇ�A���̋L���̌n�̒��ɂ��钁���̋K�������@�ƌĂ����̂����A�}���K�ɂ��A����ɂ����镶�@�Ɠ����悤�Ȃ��̂�����͂����B���́u�}���K�̕��@�v�ɂ��čl���Ă݂�̂��{���̈Ӑ}�ł���B
�O���ŏq�ׂ��}���K�̒�`�ɂ��āA�}���K�̕��@�̎��_����A������x�l���Ă݂悤�B�}���K�̒�`�́A�u�R�}���\���P�ʂƂ��镨��i�s�̂���G�v�Ƃ������̂ł������B������A�L���_�̗p����g���Č���������Ă݂�ƁA�u�������Ɛ��𐫂Ƃ�����������A�̊G�v�Ƃ��邱�Ƃ��ł���B
���̗p��ɂ��ĊȒP�Ȑ��������Ă������B�u�������v�Ƃ́A��ʊG���ʐ^�Ȃǂ̏ꍇ�̂悤�ɁA�����ɕ\�����ꂽ���̂��A��]�őS�̓I�ɂ��߂鐫���ł���B�ނ��A����ȕlj��Q�O���ʂ����ʐ^�Ȃǂ́A�u�S�̓I�ɂ��ށv�̂Ɋ����������ē����������Ȃ��Ă͂Ȃ炸�A�u��]�Łv���A�����I�Ȉ�u���Ӗ����Ă͂��Ȃ��B�������A�ӏ҂̈ӎ��̒��ł́A�����܂ł���]�Ȃ̂ł���B����ɑ����u���𐫁v�Ƃ́A�ӏ҂��\�����̕�����H��Ȃ��炻����W�ς��邱�Ƃɂ���āA�S�̂���̗���Ƃ��Ă��ނ��Ƃ��ł��鐫���ł���B���𐫂����L���̌n�̑�\�Ƃ��ẮA�܂����ꂪ��������B�}���K�́A�R�}�̓����ɂ����Č��������ώ@����A�R�}�̂Ȃ���ɂ����Đ��𐫂��ώ@�����B
�����������������́A���̕�����`������{���I�ȗv�f�Ȃ̂����A����ł����삲�Ƃ̂����������{����\���̑O�ɗ����ǂ���ǂ��Ɗ����A�ǂ�˔j���悤�Ƃ������݂͗��j�I�Ɋ��l���̕\���҂ɂ���ĂȂ���Ă����B���𐫂�����߂ċ�������\���Ƃ�������ɂ����Ă��A������ς��Ď��o�ɑi����H�v���A���������܂��蕶���g�p������{��ł͕p�ɂɍs����B�����Ɏ����ẮA���𐫂�茻�����������قƂ�Lj�ʊG��Ɠ����ɂȂ�B��ʊG��̍�҂����̊Ԃɂ��A���𐫂��l���������Ƃ�����]�͂���A�����I���߂̖����h�̉�Ƃ����͕������̑������{���`�����肵���B�������A����͎����̈���o���A���̈���Ȋ�]�͌��s�̃}���K�̒��Ɏ�������邱�ƂɂȂ�B
�}���K�Ƃ���ɗאڂ���G�����C���X�g���[�V�����Ƃ̔�r�́A���̂悤�ɂȂ邾�낤�B�G����̓}���K�ɔ䂵�āA�G�ƕ��͂̕������傫���A�G�͌������݂̂�S���Ă���B�C���X�g���[�V�����́A�����̑}���G�́A��ʊG��ƕς�炸�A���������������A�����̂��̂́A��R�}�}���K�����̓��݂�����𐫂ɏ]���ĕ����\�Ȃ悤�ɁA���𐫂���݂����Ă��邱�Ƃ������B
�A�j���[�V�����Ƃ̔�r�ł́A���̌�������S�����̂��R�}�ł��邩�J�b�g�ł��邩�Ƃ��������������邱�Ƃ��ł���B�����āA�}���K�ɂ����ẮA�R�}�͒P�Ɍ�������S�������łȂ��A���𐫂��S���A����̂ɂ���ɍׂ����������\�Ȃ悤�ɁA�A�j���[�V�����ɂ����Ă��A�J�b�g�͌����������𐫂��S���A�������\�ł���B�A�j���[�V�����̏ꍇ�A��̃J�b�g���̐��𐫂́A���R�A���̃J�b�g�̎��ԁA���Ȃ킿�R�O�b�Ȃ�R�O�b�Ƃ������钷���Ƃ��Č�����B�}���K�̏ꍇ�A�J�b�g�ɑ�������R�}�́A��ɒP�ʂƂ��Ă͈�ł���B����Ȃ̂ɁA�ǂ����ĕ����\�Ȃ̂ł���A���𐫂�S�����Ƃ��ł���̂��낤���B
�����ۏ���̂��t���[���Ȃ̂ł���B�t���[���Z�p�́A��Ƃ�앗�ɂ���Ĉ�l�ł͂Ȃ����A�Ⴆ�Α傫�ȃR�}�Ƃ������̃R�}�ł́A���̒��ɕ���i�s���Ȃ킿���𐫂��傫���`�����B�܂��A��l�̐l���̉�b����R�}�ɕ`����邱�Ƃ�����B���̏ꍇ�́A�傫���łȂ��A��l�̐l���̔z�u���l�����t���[���̍H�v���Ȃ����B���������R�}���A��R�}�̒��ɕ`�������𐫂͑傫���B
�܂��A�����}���K�ɓƓ��̃t���[�����g���邱�Ƃ͂悭�m���Ă��邪�A����́A�����}���K���X�^�C����ɋ߂�������L���A����������������ł���B�����}���K�ł́A�Ɠ��̃t���[���g�p���A�R�}�ƃR�}�Ƃ̐���I�Ȃ���������p�����Ă���B
���̂悤�ɁA�t���[�������́A���̑傫����`�Ԃ�ς��邱�Ƃɂ���āA�����������𐫂����R�ɕ\��������}���K���@�̓����̖������ʂ�������߂ďd�v�Ȃ��̂Ȃ̂ł���B
���ꂾ���ł͂Ȃ��B�}���K���t���[���Ƃ����������u���k�ɔ��B���������ƂƁA���Ȃ�ʓ��{���}���K��i���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ̊Ԃɂ́A�����֘A�������o�����Ƃ��ł���B
���{��́A���m�̂悤�ɁA����̌`�ԕ��ނ�����A�A���^�C������܂��P����ɑ�����B����́A��ɑ�\�������܌ꂪ���p����ω��ɂ���ĒP�ꂪ�Ȃ�������A�x�ߌ�ɑ�\�����Ǘ��ꂪ��`�ω����Ȃ��ꏇ�ɂ���ĕ��͂����������肷��̂ƈقȂ�A�����A���������P���S�������ĕ��͂��`���B�܂��A���{��́A���������܂��蕶�Ƃ����A�������̋����\�ӕ����E���𐫂̋����\�������̍��p�V�X�e���ł�����B���̓�̂��Ƃ́A�}���K�̕��@�Ƌ����ގ����������Ă���B
���f��͑����|�p���i��҂҂̌Z�j
�f��͑����|�p�ł���B���Ȃ킿���p�I�v�f�i�f���j�A���w�I�v�f�i�X�g�[���[�j�A���y�I�v�f�i�f�批�y�j�̎O��v�f�ɉ��������I�v�f�A����ɂ̓~���[�W�J���Ƃ��Ȃ�ƕ����I�v�f�������B�͉̂f������̂悤�ɂƂ炦�A���̂悤�Ɋӏ܂��Ă����B�������f��̃��[���}�K�W���s���Ĉȗ��A���L���W�������̉f���i�ɐG���悤�ɂȂ��Ă���l�����ς���Ă����B
�f�悪�����|�p�ł��邩�ǂ��������O�ɁA�܂��f�悪�ǂ̂悤�ɂ��Ēa�����A�ǂ̂悤�ɔ��W���Ă��������l���Ă݂�K�v������B�܂��f�悪�a������ȑO�̉f��O�j�B�h�C�c�f��u�t�B�����E�r�t�H�[�E�t�B�����v�ł͉f�悪�a�����錹����u���v���u�����G�v�Ƃɕ����A�f��Z�p�̃q���g�ƂȂ����l�X�Ȏ��o�I�u�W�F�i�e�G�A�p�Y���G�A�����A�̂������炭��A�����ՂȂǁj���Љ��B�������l�Ԃ̎��o�̎c���Ȃǂ����p�����g���b�N���f����`�������ŋɂ߂ďd�v�ȗv�f�ł��������Ƃ��������̂ł���B
�܂��f�悪�a�������P�W�X�T�N�B�����~�G�[���Z��ɂ���Č��J���ꂽ�l�ގj�㏉�̉f��́A�]�ƈ����H�ꂩ��o���ʂ��B�e�������̂ŁA�����ɂ��X�g�[���[�����y���Ȃ������B�f��͂��炭�ʐ^�Ɠ����u�f���̋L�^�v�Ƃ��Ă̖����������A�₪�đ�O�̌������ւƔ��W���Ă����B���̑�\�I�Ȃ��̂͊�p�t�����G�X���l�X�ȉf���g���b�N����g���č�������B�f���A��|����ȃZ�b�g��g��ŎB�e���ꂽ�j���A���Ă��邾���ŕ�����P�������ȃh�^�o�^�쌀�Ȃǂł���B
�₪�Ė����f�扩������ɂȂ�ƁA���̐V���W�������̌|�p�s�f��t�ɁA�V���Ȍ|�p�̉\�������o�������̕���̌|�p�ƒB�����X�Q�����n�߂�B���̑����͋ߑ���p�^���A���Ȃ킿�A�_�_�C�Y���A�h�C�c�\����`�A�V���[�����A���Y���A���V�A�\����`�ȂǂŊ����l�����ł���B�����̋ߑ���p�^���Ɖf������т���ړ_�͂�͂莩�R�Ȋw�̔��B�A���ɕ����w���B��̓I�ɂ̓o�E�n�E�X�̃��z���E�i�M�������u���Ɖ^���v�B����͉f��̖{�����̂��̂ł���A�����̍Ő�[�̌|�p�ƒB�����̕\���̏ꏊ���f��ɋ��߂��̂����ȂÂ���B
�₪�ĉf��͂���Ȃ�Z�p�v�V�̎���Ɉڂ�A�f���ɉ����t���悤�ɂȂ����B�g�[�L�[�̒a���ł���B����ɂ��~���[�W�J���≹�y�f��ƌ������V�����W�������̉f�悪�a�����邫�������ɂ͂Ȃ������A�t�ɉf���̐i�����~�߂Ă��܂������ɂ��Ȃ����B�P�X�Q�V�N�̃g�[�L�[���O��̉f�������ׂ�����̕t���O�̉f��̕����A���̕t������̉f����V����������B����͉f���Z���X�ɕq���Ȑl�ł������قǂ���������͂����B�܂������̉f��̃v�����g�[�L�[���x��Ă���Ήf��͂����Ɛi�����Ă������낤�ƌ��𑵂��邱�Ƃ������ł���B
���̂悤�ɂ��Č��Ă����Ɖf��̗��j�͉f���\���̔��B�̗��j�ł���A�f���\�����̂��̂��f��̎���ł������Ƃ�������̂ł���B���������Ď��g�̉f�������ڂ����̂��Ɓs�f���t�𒆐S�Ɍ���悤�ɂȂ�A�X�g�[���[�A�f�批�y�A���҂̉��Z�͕t�������ɂ����Ȃ��Ǝv���悤�ɂȂ����B
���݁A�����Ȃ�����A�F�̐������炵���肵����c�Ԃ�̂悤�ȉf�������Ă������Ƃ�����B�ނ�͌��݂̂悤�ȃX�s�[�f�B�[�ȕҏW�A�d�ቹ���܂����炷�����A�l��������炷���߂Ɏg����b�f�ȂǂɌ��E�������Ă���悤���B�f��͉f���\���ł���B���̌��_�ɗ����Ԃ邱�Ƃɂ���āA�܂��V���Ȍ��삪���܂ꂻ�����B
�����ɂ䂭�ߒ��̌ܒi�K���i�G���U�x�X�E�L���[�u���E���X�j
�L���[�u���E���X�́A���̙ˑ�ȗՎ����҂̃C���^�r���[�̌��ɂ��Ƃ����A�����̋߂�����\�����A���邢�͐鍐���ꂽ�l�́A���̌ܒi�K���������ǂ��čŏI�I�Ɏ��̎�e�ɂ�����Əq�ׂĂ���B
�����i�K�@�۔F
�������v���I�����ɜ��A�����ɂ���ƌ������Ƃ�m�炳���ƁA�����̐l���܂������������u����Ȃ͂��͂Ȃ��v�Ƃ����۔F�ł���B�۔F�͗\�����Ȃ��Ռ��I�ȃj���[�X�����ꂽ�Ƃ��̊ɏՑ��u�Ƃ��Ă͂��炫�A���̊ԂɁA�ʂ̎��Ȗh�q�@���ƂƂ̂��Ă������Ƃ��ł���B���̈Ӗ��Ō��N�Ȕ����ł���B
�����i�K�@�{��
���Ԃ��A���͂�ے�ł��Ȃ��ƒm��ƁA���̔����́A�{��A�A��݁A���݁A�Ȃǂ̊���o�Ă���B�u�Ȃ��A���ɂ���Ă��̂킽�����A����ȖڂɁE�E�E�v�Ɖ^���̕s�����Ȃ���A���N�Ȑl�ւ̑A�]�≅�݂��\�ʉ�����B�{��́A�ߐe�҂͂�������t�E�Ō�w�ȂLj�ÃX�^�b�t�ɂ��������邪�A���h����A��������A���b������āA���������l����l�ԂƂ��ċ�����Ă��邱�Ƃ�m�銳�҂́A�₪�ē{���Â߂Ă����B
����O�i�K�@������
�_�A���邢�͉^���Ɖ��炩�̎��������ł���A����������ƁA���̎��Ԃ�������։������Ƃ��ł��邩������Ȃ��ƍl����B�u���̉^����邱�Ƃ��ł���Ȃ�A������x�Ɛl�苑�₵���肵�܂���v�E�E�E�܂艽�炩�̋]�������ƁA�悢�U�镑�������邱�Ƃɂ���āA���߂Ă�����x���������A���q�̍���ɏo�Ȃ������A�Ȃǂ̖]�݂����������Ǝv���B
����l�i�K�@�悭�T
�a�[�������A�����������Ă���ƁA�l�͂��͂�a�C�̎��Ԃ��A�P�Ȃ钥��ł���Ƃ��A�ꎞ�I�Ȉ����ł���Ƃ������������ł͂��܂���Ȃ��Ȃ��Ă���B�����āA�[���Ȃ悭�T��Ԃɂ�������B�悭�T�ɂ́A
�@�����悭�T
�A���E�Ƃ̌��ʂ��o�傷�邽�߂Ɍo�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������I�悭�T
�̓������A���҂͂܂������قȂ鈵�����K�v�B�Ƃ��ɑ��̃^�C�v�ɂ��Ă͗�܂������A�ނ���߂��݂��ꎩ�̂̕\���𑣐i���邱�Ƃ��K�v�ł���B
����ܒi�K�@��e
�����R���̎����͏I���A�Ō�ɐl�͎����̉^��������Ă����B�������Ƃ�܂��l�тƂ�ꏊ�Ɖi�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��߂��݂̍�Ƃ��A���łɂȂ����������܂܁A������x�Â��Ȋ��҂������āA�߂Â��I�����݂ߑ҂��Ƃ��ł���B�n���̎��Ԃ��ӂ��A�S�̕��͂��܂��Ă����B�Ȃ��ɂ͍Ō�܂œ����A��]�����Ƃ��Ƃ������A���̎�e�̒i�K�ɒB���邱�Ƃ̂ł��Ȃ��l�����邪�A���������l�������A�₪�Ă͐킢����߂��������B
���E���̃n�C�Z���X�i�����S�j�j
�l�Ԃ͎E�����D���Ȃ̂ł���B��߂�����̂͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B���낢��Ȑl�Ɉ�ԍ��{�I�Ȏ�����Ԃ��Ă݂��B�u�E���͂Ȃ������Ȃ��̂ł����v�B�[���̂������������Ă��ꂽ�l�͂��Ȃ������B�M�҂ɂ��������Ȃ��B�u�@�����֎~���Ă��邩��v�ł͓����ɂ��Ȃ�ɂ��Ȃ�Ȃ��B�u�_�l���ւ��Ă����܂��v�B������i���Z���X���B�_���܂̐��͂ǂ̂��炢���邩�킩��Ȃ��B�C���h�̂���@���ł͐_�̐��͉��\�����Ƃ����Ă���B�E�������サ�Ă���_���܂����Ȃ��Ȃ��B���̑�\�̓J�[���[�����B
�u�������E�����̂͂���ł��傤�B������l���E���Ă͂����Ȃ��̂ł��v�Ƃ��������͍ł��i���Z���X���B�u����͎������E�����̂������Ƃ��|���Ȃ��B�v�Ƃ����E�l�҂���������B�܂��u�������E�����̂͂��₾���A�l���E���͍̂D�����v�Ƃ����������_���I�Ŕ��_�̗]�n���Ȃ��B�u���Ȃ��͕�����̂�����ł��傤�B������l�����Ă������܂���v�u�͂��A�����ł����v�Ƃ����ď\�ܓ��ԍ����𑱂��鑊�o��肪���邩�ˁB
�l����̑��݂Ƃ��ĎЉ�Ƃ������̂��l���A�Љ����邽�߂ɎE�l���֎~�����̂��A�Ƃ����������邪�A����́u�Ȃ������Ȃ��̂��v�̓����ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�ⓚ���p�ŋ֎~����Ƃ��������ł���B�Ƃ������Ƃ͎Љ�ς��ǂ��Ȃ邩�킩��Ȃ��Ƃ������ƁB�]�ˎ���ɂ͎Љ����邽�߂̂Ɂu�Ԉ����v�Ƃ������̎E�l��u���Ύ̂āv�Ƃ������̎E�l���A�قƂ�nj��F�ɋ߂��`�ŖٔF����Ă����B��\�ꐢ�I�ɂ͂��̃V�X�e������������ƍl���Ă��関���w�҂͑����B
�E���͂Ȃ������Ȃ��̂��A�Ƃ�������ɑ��铚���͍��̂Ƃ���Ȃ��B�ł͋t�ɍl���āA�l�Ԃ͂Ȃ��E�����D���Ȃ̂��A�Ƃ�������B���͂���ɑ��铚���͏o�Ă���̂ł���B����͐l�ޒa���̔閧�ɐ[���ւ���Ă���̂��B�l�ނ͂ǂ̂悤�ɂ��Ēa���������A���ɏЉ��̂́A���͒������ł���B�Ƃ͂����Ă��M�҂̊��S�ȓƑn�ł͂Ȃ��B��\�p�[�Z���g�͊C�O�̐l�ފw�҂̐��ł���B�M�҂͂����K���ɃA�����W���āA������҂薡�t�������������B�Ȃ��A���{�̐l�ފw�҂ɂ͂��������l���������Ă���l�͂ЂƂ�����Ȃ��B�݂�ȃ}�W���ȃs���[���^���Ȃ̂��B
�������l�ސi���_�B��l�S���N�O�ɐl�ނ̑c��炵���������a�������B�i���͒x�X�Ƃ��Đi�܂Ȃ��������A���S���N�ɁA���̐��������H���������H�����ɕ����ꂽ�B���H�n�͉a���������ĐH�ׂ�Ƃ��������̐����ł��������߁A�i���͒�~�A���ω��ւ̑Ή��������A�₪�Đ�ŁA���H�n�̒��Ŋ��ω��ɓK���i�i���Ƃ͌���Ȃ��j���Ďc���Ă��������̂��T���ɂȂ����B
���H�n�̂��̂������{�\�A�E�C�{�\����A����ɂ͎E�l�{�\�܂ł����B���A��̕K�v�ォ��m�\�����B���A�i�����Ă����B���ꂩ��S���N�A�܂荡����S���N�O�ɁA���H�n����A�G�H�n���}�����ꂵ���B���H�n�͏��O���[�v�ɕ�����Đ������A�����{�\�A�E�C�{�\�݂̂����B���A�O���[�v�Ԃ̎E�l�������A�����̔��B���x��A�l�����������Ȃ������B�G�H�n�͗Z�ʂ������A���̍L�����������ł���̂ŁA�m�\�����B���A���������܂�A�O���[�v���傫���Ȃ�B�{�������Ă��������{�\�A�E�C�{�\�A�E�l�{�\�̈ꕔ�͏����ăQ�[����|�p�ƂȂ�B�\���N���܂łɂ͏����H�n�͖łтāA�G�H�n�̐l�Ԃ����͂��̂��n�߂�B���̒�����܂�������������čŌ�ɐ����c�����̂����l���B�����������ˑR�Ƃ��ē����{�\�A�E�C�{�\�A�E�l�{�\�͎c���Ă���B������K�v�ȏ�ɋ����c���Ă���B���ꂪ���̖ҏb��T���Ƃ͌���I�ɈقȂ�_���B���C�I���͐H�p�ȊO�ɓ������E�����Ƃ͂Ȃ��B�l�R�̒��ɂ͐H���C���Ȃ��̂ɃJ�G���⏬�������܂��ėV��ł���悤�Ɍ�������̂����邪�A����͐l�ԂɎ����ĐH���ɕs���R���Ȃ��Ȃ������߁A�{�\���c�߂��ďo�Ă������̂ƍl������B
�l�Ԃ͓����ƎE���̃e�N�j�b�N�A�����h���e�N�j�b�N�����Ƃ��Đi�����A�����B�����Ă����B���E�͂ЂƂA�l�ނ݂͂ȌZ��A�Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��̂ł���B���̌Z�킾���ĎE�������̂��l�ނ̓����ł���A�푈�͉i�v�ɂȂ��Ȃ�Ȃ��B���Ƃ��Ɛ푈�̂��тɕ����͔���I�ɐi�����Ă������̂ł���B�������E�����炷�ׂĂ̐푈���Ȃ����Ă��܂����Ǝv������A�ǂ����Ă�����ɑ����K�͂ȎE�C�Q�[���A�E�l�Q�[�����K�v�ɂȂ邾�낤�B�Ƃɂ����l�Ԃ͎E�����D���Ȃ̂��B
���u���Ǝ���v�]�i�؉����V�j
���̎R����킹�Ă���u���{����W�v�i�������������فj�̉��ɑ����^�ԂƁA�G�⒤���ɍ������Ĕ����g�̓������U��W������Ă��邱�ƂɋC�����B���邢�́A�l�E���̓�����p�i�ƕЂ���ׂĂ��邱�ƂɌ�������������������邩������Ȃ��B
�������A���Ƃ������ɂ͐_��������A�Ƃ��Ĉ����Ă�����j�ȗ��̒������j������B������̌��㕗�̈����������ق̓W���ɂق��Ȃ�Ȃ��B
���͒P�Ȃ镐��ł͂Ȃ��B�����炱���A���͓�������ł��鑄��S�C���͂邩�ɑ����c�����̂��Ƃ��钘�҂́A�|���āA�ł͓��Ƃ͂ǂ̂悤�ȕ���ł������̂��Ɩ₤�B���ւ̕t�����l��������{�̕���̑�\�̂悤�Ɍ��������Ă������A���ł̓��̎��Ԃ͑��O�m���ĂȂ����炾�B
���ł́A�G�Ƃł�����藣��Đ킨���Ƃ��鉓��u���������B���������āA�����Ƃ��d�v�ȕ���͒����|���ł���A�����S�C�ƂȂ����B���ꂪ�����~�T�C���ɑ������ƍl����Δ[���������B���Ɠ��œn�荇���A�قڊԈႢ�Ȃ��������B����ł͂Ƃ��Ă����͎���ɂȂꂻ���ɂȂ��B
����𗠕t���邽�߂ɁA���҂͐퍑����̌R����i����ؖ����j����펀�ҁA�폝�҂��ǂ���r�������ׁA���r�A�S�C�r�A���r�������ɒB����̂ɑ��A���r�A���r���ꊄ�ɂ������Ȃ��Ƃ��������𖾂炩�ɂ����B����ɂ�������炸�����K�v�Ƃ��ꂽ�̂́A�G�̎�����˂Ȃ�Ȃ��������炾�B
�����������̌�����Y��āA����ʊi�̕���ɍՂ�グ�Ă��܂����Ƃ��A���҂́u�`�����o�����z�v�ƌĂԁB�R�L����A�R�k�A�u�߁A�߂��̓`�����o���f��ɂ���Č��z�͖ϑz�ւƂӂ���B���̍ł�������̂́A���{���R�̏��Z�����ɓ��{�����Ԃ炳���Ă������Ƃ��낤�B�����܂ł��Ȃ��푈����������A�푈�̃��A���Y���͎�����B�{���́A�����I�O�ɏI������푈���A����ꂪ�����������Ă������̂��Ƃ���邱�Ƃւ̌x���̏��Ƃ��Ȃ肦�Ă���B
�����I�̈��@�I�Ɠd���T�C�N���@�ɂ��Ă�҂҂̌Z�͂����l����i��҂҂̌Z�j
�Ɠd���T�C�N���@���Q�O�O�P�N�S���P���Ɏ{�s�����B�①�ɂȂǂS�i�ڂ̓d�C���i�ɂ��ĉ^������܂߂����T�C�N����p������҂ɕ��S������ƌ������́B�����̂ɂ���Ă͂��̔�p���P���~�߂��ɂȂ���̂�����炵���B�e���r��①�ɂȂǂ͏��^�̂��̂����P���~�ȉ��̂��̂�����̂Ő��i���i�ȏ�̔�p�S��������\��������ƌ����B�s���̂�邱�Ƃ̓A�z�Ȃ��Ƃ������Ƃ͌�������قǂЂǂ��@���͂Ȃ��ƌ�����B
�܂����ɕs�@�����������邱�Ƃ͖ڂɌ����Ă���B���������ꂪ�������Ă��Ȃ��炻��ɑ���Ή���┱���K�苭�����������Ă��Ȃ��̂����狰�����B�������S�~���炯�ɂ���C���I���̃A�z�I
���T�C�N���ɍm��I�Ȑl�ł����ꂾ�����z�ȕ��S����������Ƃ��ꂩ��̊��s���ɑ傫�ȋ^�O�������ƂɂȂ邾�낤�B���͒ʐM�A�o�C�I�A���{�b�g�Ƌ��ɂQ�P���I�̏d��ȃL�[���[�h�̂ЂƂȂ̂�����吨�̐l�ɍD�ӓI�Ɏ~�߂���悤�ɂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
���̖@�������܂��@�\���Ȃ��ƒf���ł���̂��l�̑P�ӂɗ����_�ɂ��邩�炾�B���������l�̑P�ӂĂɂ��Ă��܂����������߂����Ȃ��̂��I���̏؋��Ɍ���������I�N�X�̌��ł��錌�t�̗ʂ������Ă��Ă���B�l�̑P�ӂ��L���Ȃ�ΔN�X�����Ȃ�����������ł͂Ȃ����B���ꂪ�����Q�O�O�����̌��t�̍̎���Q���~�����ƂȂ�ΐl�͍s�������Č����ɗ�ނ��낤�B��������҂҂̌Z�����ŎQ�����邼�B�l�͖Ŏ�����I�Ȋ��o�ł͂Ȃ��Ȃ������Ȃ����̂Ȃ̂ł���B
�����ł�҂҂̌Z�̒B���T�C�N���ɏo���Ə���҂��ׂ����V�X�e��������Ă͂ǂ����H�ƌ������ƁB�Ⴆ���܂��P���~�Ŕ����Ă��e���r���P�O���~�ƌ����l�i������B������ď���҂����T�C�N���ɏo�����W���~���Ԃ��Ă���ƌ����V�X�e�������B�P���~�̓��[�J�[�̂������B�����P���~�̓��T�C�N����p���B�����ĕs�@���������y�͖߂��Ă���͂����W���~�����T�C�N�������ڂ������߂��W���~������d�g�݂ɂȂ�B����ŕs�@�������S�������Ȃ�킯�ł͂Ȃ����啝�Ɍ���̂͊ԈႢ�Ȃ��B�܂��s�@�������������Ƃ��Ă��������W���~���g���ă��T�C�N����������Ηǂ��B
�ǂ����ȁH�Ȃ��Ȃ��̃O�b�h�E�A�C�f�A�ł��傤�H�f�l�ł����̂��炢�̂��Ƃ͍l����̂�����@�����l����l�͂����ƒm�b���i��ƌ��������ȁI
���u�|�p�̋t���@�ߑ���w�̐����v�]�i���萭�j�j
�����Ă�Ă����u�|�p�v�Ƃ��u�A�[�g�v�Ƃ͂������������B���邢�́A�u�|�p�Ɓv�u��i�v�u�Ƒn���v�Ƃ́B�������͔��R�Ƃ����̊T�O�́A�����n����Đl�ނɋ��ʂ̂��̂��Ǝv���Ă���B�������{�����u�|�p�v���Ƃ����T�O���A�����\�����I���[���b�p�ɂ����ď��߂Đ����������̂ł������Ƃ������ɘ_����B
�������͋C�y�ɃM���V���u�|�p�v�Ƃ����l�T���X�u�|�p�v�ƌ��ɂ��邪�A������ߑ�Ɋm�����ꂽ�T�O���ߋ��ւƓ��e���Ă���ɂ����Ȃ��B�{���͏]���̔��z�ɑ傫�ȕϗe�𔗂��u�|�p�v�̊T�O�j�ł���A���̎咣�̏Ռ��́A����A�[�g�Ɋւ��l�ɂƂ��Ă����Ԃ�傫�����̂��B
�u���R�ȋZ�p�i���x�����A�[�c�j�v�i���R�w�|�j�Ɓu�@�B�I�Z�p�i���J�j�J���A�[�c�j�v�Ƃ����`���I�ɁA�\�����I���t�ɁA�V���Ɂu�������Z�p�i�{�[�U�[���j�v�����荞��ł������ƂŁA�Z�p�i�A�[�c�j�̐��E�̍ĕҐ����N����B�����ŏ��߂ĉ��y�A���A�G��A�����A���x����Ȃ�̈�A�܂��u�|�p�v�Ƃ����V���ȗ̈悪���������B���̍ĕ҂Ő������O���삪�A�����̐l���n�w��A�Ȋw�Z�p�A�|�p�ƂȂ��Ă����킯���B
�|�p�Ƃ��u�n������v��̂ł���A�n�����������|�p�Ƃ̖{�����Ǝ������͍l���邪�A�\�����I�܂ł̃L���X�g���I�`���ɂ����ẮA�u�n������v�̂͂����_�݂̂��u�l�Ԃ͑n������͂������Ȃ��v�B�Ƒn���i�I���W�i���e�B�[�j�ɂ���A�I���W�i���Ƃ͌��X�u�N���E����v�̎��ł���A�Ƒn�I�Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ������B����͌|�p�Ƃ̉c�݂ɐ旧���č݂�K�͂��w���Ă���A������\�����I�����ɁA�|�p�Ǝ��g�̓����ɋA�[����Ă����B
���Ƃ����ɂ��ƁA�{���̂��߂ɏ\�N�̍Ό����₵���Ƃ���B���킽����������ɂ����āA���̂悤�Ȓn���Ȍ����̉c�݂��A�������L���ŗL�v�Ȏv���ݏo���Ă��邱�Ƃ͑傫�Ȋ�тł���B
���u�B���Ȑ��ԂƎ��v������i�����ޖ�j
�ӊO�ƒm���ĂȂ������ł����A�����ȑO�̓��{�G��ɂ́A���摜�̗��j������܂���ł����B�������p�w�Z�i���݂̓����|��j�̑��Ɛ���ɉۂ���ꂽ�̂��A�͂��܂�Ȃ̂ł��B����͒������{�l���A�u�����v�𑼐l�Ƌ�ʂ��Ē�������K�v���Ȃ���������ł͂Ȃ����B���͂���ǂ������邩�A�������d�v�������̂ł��B
���ہA�u�l�v�Ƃ������t���A�����P�V�N�܂ő��݂��Ȃ������B���͂��̓��{�l�Ɠ��́A�W�c�ƌl�̊W��\���̂��A�u���ԁv�Ƃ������t���ƍl���Ă��܂��B
���̓��{�̂�������ɂ��A�u���ԁv������̂������Ă���B���Ƃ��Ε����n���̎��Ȍ������A�e�^�҂̕v�ł��锻���ɑ{������R�炵�������B�i�@�Ɍg���ނ�͓����u���ԁv���Ă��邩��A�߈������Ȃ������B�u���ԁv�Ƃ́A���Q�W�����L����W�c�Ȃ̂ł��B
�܂��O���@������ł��A���炭�O���Ȃ̐E���͂قƂ�ǂ��A�����������̍s�ׂɋC�����Ă����͂��ł��B�������A�����u���ԁv�ɑ����鎩���ɉ̕����ӂ肩����̂�����A���Č��ʂӂ�������B��A�̌x�@�s�ˎ��Ƃ��̂��ݏ����ɂ��܂������������Ƃ������܂��B
�������������������}�X�R�~�́A�u���������@�v�u�����ւ̔w�M�v�Ƃ������A�ߑ�s���Љ�̌��t�Œf�߂��邾���ŁA�u���ԁv�̑��݂�f�ʂ肷��B����̓C���e�����܂��A�u���ԁv�̈��������ł��B
�����u���ԁv�̈�Ԗ��ȂƂ���́A������l�Ԃɂ��A���ꂪ���o����Ȃ��_�ł��B���{�l�͒N�����A�ߑ㉻���ꂽ�����I�u�Љ�v�ƁA�`���l��ɏے������`���I�u���ԁv���_�u���X�^���_�[�h��m�炸�����Ă���B
���̓T�^�������Ƃł��B�����i����j�ł͋ߑ�Љ�̌��t���g�����A�n���̑I����ł͂����Ȃ��u���ԁv�̌��t�ɖ߂�B�����Ƃ́A�u���ԁv�̌��t���A�Љ�I�ȏ�Ń|�����Əo�Ă��܂��̂��w���B�v����ɁA�X�͐����߂���̂ł��B�����ɂ��l�Ԑ��������炳�܂ɂ��A�������Đl�C�������Ƃ������B�X�̐l�C�̂Ȃ��̂́A�����Ŕނ̐l�i�������Ă��܂��A���]���邩��ł��B
�X�́A�u�����������������v�ӔC���Ƃ��Ď��߂邱�ƂɂȂ�悤�ł����A���̐ӔC�Ƃ́A�����S�̂ɑ��Ăł͂Ȃ��A�����܂Ŏ����}�Ƃ����u���ԁv�Ɍ��������̂Ȃ̂ł��B������A�O����͂܂���������s�\�ɂȂ�B��s���ׂ�Ă��ӔC�҂���������Ȃ�����ŁA���[�̎Ј����N�������l�I�s�ˎ��Łu���Ԃ𑛂������v����ƁA��Ƃ̃g�b�v���Ӎ߂���B�����т��u���ԁv�̒��ŁA��l��l�̌l�̈ʒu�����m�Ɏ�����ĂȂ�����ł��B�ɂ�������炸�A�����Ȋw�ȂȂǂ������d������������s���ƌ����Ă���͖̂������r�������A��_�ɉ߂��܂���B
���[���b�p�ł́A�L���X�g����_�Ƃ��钆���Љ��A�s���v�����o�āA�u�l�v�̋����̂ł���ߑ�Љ�m������܂ŁA�Z�S�N���������B���{�ł́A�v�����N�������Ƃ͈�x����ƂĂȂ��B�剻�̉��V�A�����ېV�A�s���̕ϊv�A���ׂ��u�O���v�ɂ��N���Ă���B
�������A�����ŋ����������̂́A���́u��������{�l�̓_���Ȃv�ƌ�������͂������ĂȂ����Ƃł��B�ނ���]�����j�w�҂������A���{�𐼉��Љ�Ɣ�r���A�u�x��āv���邩�̂悤�Ɉ����Ă����Q���͂���߂đ傫���l���Ă��܂��B���ʂƂ��ē��{�l�̖����o���u���ԁv�ƁA�u�Љ�v�̃_�u���X�^���_�[�h���������Ă��܂�������ł��B���������w�҂����A�u���ԁv�i�w��j�̏Z�l�ł��邱�Ƃɂ����C�����Ă��܂���B
�ł́A�s���l�܂������{���u���ԁv���A�ǂ��Ŕj�����炢�����H��ؓ�ł͂����Ȃ��B���������́A������l��l�̒��ɂ����u���ԁv�Ɨ�ÂɌ��������A���Ή����邵���Ȃ��Ǝv���܂��B�u���ԁv�������ɕς��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ă��A�u���ԁv�Ɛ܂荇�������A����ɏ��z���邱�Ƃ͂ł���͂��ł��B
���{�l���^�̎��摜��`����悤�ɂȂ�Ȃ�����A��\�ꐢ�I�̖閾���͖K��Ȃ��B